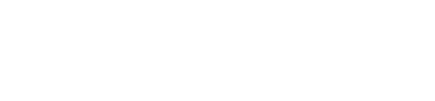運動方針 | 平和フォーラム
2024年05月04日
平和フォーラム2024年度運動方針
はじめに
1999年10月に設立された平和フォーラムは、今年設立から25年を迎えます。
世界規模での大戦、イデオロギーによる社会分裂、地球環境破壊の20世紀から、平和と共存、多元的価値と文化の共生、地球環境と調和する「新しい世紀」をめざして設立されましたが、残念ながら世界の現実は私たちがめざす方向とはまったく逆にすすんでいます。
ロシアのウクライナ侵攻を契機としたウクライナ戦争は泥沼化したまま3年目に入り、パレスチナのガザ地区ではイスラエルの激しい攻撃のもと、不条理ともいえる大量虐殺が続いています。2つの戦争を巡っても各国の対応は一致せず、むしろ対立を強めるばかりです。そのほかにも緊張が高まる朝鮮半島や中国と台湾の関係、そして大統領選を控える米国内の激しい党派対立は、国際社会の大きく深い分断と対立の冷戦構造にとどまらず、世界大戦につながりかねない極めて危険なリスクをはらんでいます。
依然として、ウクライナの各地でロシア軍とウクライナ軍が戦闘を続けていて、大勢の市民が国外へ避難しています。ウクライナ空軍は8日、ロシア軍が無人機やミサイルを使って各地を攻撃したと発表し、南部オデーサ州では、無人機による攻撃で物流や輸送のインフラ施設などが被害を受けたとして、緊張が続いています。
ウクライナのゼレンスキー大統領も3月下旬に放送されたアメリカのテレビ局のインタビューで、「ロシアは反撃の準備をしていて、5月末か6月はじめになる可能性がある」という見方を示しています。
戦争の長期化によって穀物を含めた食糧の供給不足、原油や天然ガスなどのエネルギー問題の深刻さが増しています。こうした問題は長期化すればするほど大きな影響が出ることが懸念されます。日本でもこうした影響を強く受けながら記録的な円安や物価高騰、実質賃金の低下が続き、コロナ禍による疲弊と相まって市民生活の苦しさは増しています。
日本政府は、軍事支援として3700万ドル(約53億円)を北大西洋条約機構(NATO)に拠出することを伝えましたが、こうした軍事的手段で国際紛争が解決できないことは明白であり、平和的外交手段をもって即時停戦を働きかけることこそが日本の取るべき立場です。
パレスチナ自治区ガザで続くイスラエル軍とイスラム武装組織ハマスによる戦闘は、4月7日で半年となりました。ガザ側の死者は3万3千人を超え、飢餓で命を落とす子ども達が後を絶たず、国際法違反といえる人道危機は著しく悪化するばかりです。
レバノンのシーア派組織ヒズボラとイスラエルの戦闘も激化し、4月1日にシリアのイラン公館が空爆されたことに対し、イスラエルは空爆を否定せず、緊張は中東全域に広がっています。イスラエルは国際司法裁判所の暫定命令や国連安全保障理事会の一時停戦決議も顧みず、国際法違反を重ねるばかりです。イスラエルの無法をこれ以上放置すれば国際秩序の崩壊は避けられず、国際社会はこうしたイスラエルの姿勢に強く抗議し、即時停戦を実行に移すことが求められています。何十年にわたってパレスチナ人への抑圧と迫害を見て見ぬふりをしてきた国際社会にも大きな責任があります。最も重要なことはイスラエルによる大量虐殺を一刻も早く止めさせることです。
平和フォーラムは、「パレスチナに平和を!緊急行動実行委員会」への結集をはかりながら、一日も早い停戦を訴える世論喚起のとりくみをはかってきました。
バイデン米大統領は4日、イスラエルのネタニヤフ首相と約30分にわたり電話会談を行い、即時停戦が人道状況の安定や改善、民間人の保護に不可欠と強調し、支援団体や民間人の安全確保に向け即時行動を取るよう要請したと伝えられていますが、イスラエルのネタニヤフ首相は、ガザの南部ラファにイスラエル軍が侵攻する日程は決定していると発表するなど、強硬な姿勢は崩していません。アメリカは自らの責任が極めて重いことを自覚し、イスラエルへの支援を打ち切って停戦実現に向けて力を尽くすべきです。
こうした大きく揺れ動く世界情勢を理由として、国内では短絡的に危機が煽られ、2022年12月には国会での審議も経ずに国会閉会中の時期を狙いすましたかのように、国のかたちを大きく変える安保3文書が閣議決定されました。少子化対策や社会保障、物価高騰への対応といった市民生活に直結する政策は後まわしにされ、空前絶後の防衛費増強から戦争する国づくりにひた走るのが今の日本であり、岸田政権です。
2024年通常国会では、3月26日に防衛装備移転三原則の運用指針が改定され、日本がイギリス・イタリアと共同開発する次期戦闘機について、第三国への輸出を加納とする方針を閣議決定しました。
日本は現行憲法の下、「武器輸出三原則」を確立し、武器輸出を制限してきました。制限は段階的に緩和され、安倍内閣が2014年に閣議決定した「防衛装備移転三原則」で武器輸出に道を開きましたが、運用指針で救難、輸送、警戒、監視、掃海の五類型に限り、国際共同開発・生産を除いて殺傷武器の輸出を実質的に禁じてきました。しかし、政府は使用目的が五類型に該当すれば、現行制度下でも殺傷武器を搭載した装備品を輸出できるとの見解を示すなど、都合よく解釈を変更してきました。
敵基地攻撃能力の保有や防衛予算倍増に加え、武器輸出の拡大で防衛産業の成長も促す姿勢や際限のない軍備拡大偏重主義は、現行憲法の平和主義や専守防衛に反するものです。殺傷武器の輸出は国際紛争を助長しかねず、平和国家の歩みに対する国際的な信頼も失いかねません。
その他にも秘密保護の範囲を経済安全保障に関わる情報にも広げる「重要経済安保情報保護法案」は、国民の知る権利や表現・言論の自由を侵害することが懸念されます。適性評価制度の法制化は、企業の労働者や大学を含む研究機関の研究者などが幅広く対象になり、プライバシーが侵害され、断った場合には不利益を被る人権侵害にさらされる恐れがあります。
また「地方自治法の一部改正」は、大規模災害や感染症のまん延に対する国としての迅速な対応が法案の根拠とされていますが、個別法で国の指示権は規定されるもので、立法根拠が不明確です。地方の自治事務に対する国の不当な介入を誘発する恐れがあります。現在、憲法審査会では大規模災害や感染症まん延への対応として、緊急事態条項の憲法への創設や議員任期の延長が議論されていますが、緊急事態条項の創設は、極度の権力集中による政府の権力濫用の危険性を高めるものです。今回の地方自治法の一部改正は、改憲ではなく法制定により、有事の際の自治体の権限を奪い、政府の権力濫用を強めるものです。引き続き、個人の権利侵害や地方自治への不当な介入を許さないとりくみが求められています。
この間の憲法審査会では、戦争する国づくりの総仕上げと言わんばかりに、「改憲ありき」の議論が一部野党を含む改憲5会派(自民、公明、維新、国民、有志の会)から声高に主張されています。とりわけ衆院憲法審査会では、改憲5会派から改憲発議に向けた条文案作成のための作業部会の設置が提起されるなど、緊急事態条項の創設や議員任期の延長を足がかりに、改憲発議をめざす動きが強まるものと思われます。改憲勢力が衆参において3分の2以上を占める中、改憲発議を許さないたたかいに傾注する必要があります。
国内政治では、自民党派閥のパーティー券裏金事件にどう決着をつけるのか、能登半島地震の被災者の生活再建に向けてどう取り組むのか、政治課題は山積しています。
自民党は、派閥の政治資金パーティー券裏金事件に関係した議員ら39人の処分を決めましたが、政治資金収支報告書へ不記載とした理由や経緯、裏金を何に使ったかなど全容は明らかになっていません。自民党は処分をもって事件の幕引きをはかりたいのでしょうが、過去には離党勧告を受けた議員が後に復党して党の要職を務めた例もあり、事件の深刻さに見合う処分なのか疑問です。説明責任や政治責任が果たされないままの幕引きは断じて許されません。
4月28日は、衆議院の補欠選挙が東京15区と島根1区、長崎3区で行われる予定です。結果次第で裏金問題で揺れる岸田首相の政権運営にさらなる影響を及ぼすことになります。9月には岸田首相が自民党総裁としての任期満了を迎えます。衆議院の解散・総選挙が自民党総裁選挙の前か後なのか、内閣支持率が回復して解散を打てる状況になるのか、岸田首相が描く解散戦略に関心が集まることは必至の情勢です。
元日に能登半島を中心に発生した巨大地震により、志賀原子力発電所は電源設備などのトラブルが相次ぎ、火災の発生や津波情報をめぐる発表の訂正が繰り返されるなどの混乱に陥りました。
原子力災害は、今回のような地震や津波が引き金となる複合災害として発生する危険性が高く、道路の寸断や通信の途絶といった状況でも、安全対策が機能するかは極めて重要です。世界の地震の2割が日本で起きると言われる地震大国・日本の原子力政策の危険性が改めて浮き彫りになりました。
9月27日、長崎県対馬市の比田勝市長は、核のごみの最終処分場建設に向けた文献調査を受け入れないことを表明しました。北海道の寿都町と神恵内村では文献調査まで進んでいますが、北海道知事は最終処分場建設に反対の立場を明言しています。
山口県上関町の原発建設計画は、2011年の福島第一原発事故を受け工事は中断している状態ですが、昨年8月、上関町の西町長は、使用済み核燃料中間貯蔵施設の建設調査受入れを表明しました。再び対立と分断の不幸が繰り返されるのではと、上関町は今なお原発に翻弄され続けられています。
青森県六ヶ所村の再処理工場は数十年にわたって「建設中」のままであり、完成の目途もたっていません。核燃料リサイクルを担うはずだった「もんじゅ」は1兆円以上の国費を費やした末に、何ら成果を出せないまま廃炉となりました。核燃料リサイクル政策は既に破綻しています。原発を稼働し続ける限り、行き場のない使用済み核燃料がたまり続けることになります。
東電福島第一原発の汚染水の海洋放出は、多くの反対の声を無視して強行されました。問題となっているトリチウムで汚染された水は、使用済み核燃料の再処理後にも発生するもので、六ヶ所村の再処理工場から海洋放出されることが核燃料リサイクル事業の当初からの計画にあるといわれています。こうした点からも、原発推進政策を進めることは許されません。
原発の長期運転を可能にしたGX法は、極めて罪深いものです。原発の運転期間の上限の根拠が不明確であるばかりか、原子炉が老朽化によってどのような影響を受けるか、圧力容器がいつ限界を迎えるかの予測は、現在の科学技術では難しいといわれています。
いま世界各国では、安全かつクリーンな発電技術の実用化に向けて開発競争が起こっています。政府が進めるべきは再生可能エネルギーを最優先させる政策への転換です。原子力に頼らない安全でクリーンな発電に向けた技術開発にこそ傾注すべきです。
政治課題は、地震への対応や「政治とカネ」にとどまりません。物価高の中で国民の暮らしをどう守るのか、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中でどう対応するのかなど、多岐にわたります。あらゆる課題に対して、岸田首相が「丁寧に説明する」と繰り返すばかりでは納得できません。
岸田首相は自らの脆弱な政治基盤を補うためにあらゆる政治勢力におもねり、防衛政策やエネルギー政策の進め方はアメリカ追従、与党内の権力構造優先であり、閣議決定で重要なことを決める手法は、国会軽視、国民軽視、政治の私物化以外の何物でもありません。このような状況の中で、私たちは戦争法の廃止と立憲主義の回復、憲法改悪を阻止するための多数派形成が求められています。市民と立憲野党の共闘を強める中で立憲主義、民主主義を取り戻すとりくみを進めていく必要があります。
1.憲法理念を実現するとりくみ
(1)憲法理念の実現にむけて
日本国憲法は、大きな犠牲を払った悲惨な戦争の反省から、平和と民主主義の願いの下に生み出されました。どんな理由があろうとも二度と戦争はしないと誓った憲法第9条は、戦後の混乱と絶望の時代から今日まで、人々に大きな希望と生きる勇気、平和の大切さを与え続けてきました。平和フォーラムの基本的立場は、憲法理念の擁護と実現をめざすとともに、人権や民主主義の国際的なとりくみの到達点に立って、さらに発展させることです。平和フォーラムはこの間、東北アジアの平和に向けたとりくみや、人びとの生命の尊厳を最重視した「人間の安全保障」の具体化をめざしてきました。子どもたちの未来と世界の平和、地球環境と人権を守るために、「基本的人権の尊重」、「平和主義」、「国民主権」という日本国憲法の最も大切な三原則の理念をいかさなければなりません。
安倍政権による集団的自衛権行使容認と戦争法の制定により、日本は米国の思惑に追従し、防衛装備品の爆買いや特定秘密保護法や共謀罪法、重要土地調査法など軍事優先の法制度の創設、米軍との軍事演習強化をすすめ、日米統合軍構想へと軍拡と同盟強化の路線を歩み続けてきました。
そして岸田政権に代わっても、国会審議を無視して「安保関連3文書」が閣議決定され、市民生活に直結する政策は後まわしにされ、空前絶後の防衛費増強から戦争する国づくりにひた走っています。武力及び軍事同盟に依存しない姿勢を日本政府は内外に示し、憲法前文と第9条が掲げている理念を実現していくことがなによりも重要です。
(2)岸田政権の暴走を許さないとりくみ
岸田首相は、1月30日の施政方針演説で、憲法改正について「あえて自民党総裁として申し上げれば(9月までの)任期中に実現したい」と明言しました。内閣支持率の低迷を踏まえ、保守層にアピールする狙いがあるものと思われます。
岸田首相は改憲を「先送りできない課題」の一つと位置付け、任期中の実現に向け「議論を前進させるべく最大限努力したい」、「条文案の具体化を進め党派を超えた議論を加速していく」と繰り返してきました。昨年10月の所信表明演説では「条文案の具体化など、これまで以上に積極的な議論が行われることを期待する」と話すなど、国会での議論を促す程度にとどめてきましたが、今回の施政方針演説で自民党総裁の立場を強調するのは極めて異例であると同時に、権力者を縛る憲法について首相が国会で改正を訴える行為は、国務大臣らの憲法尊重擁護義務を定めた憲法第99条に反するもので許すことはできません。「国のかたち」である憲法秩序を根本的に変えることができるのは、主権者である国民のみのはずです。こうしたことを顧みることなくなぜ改憲が必要なのか、理由や改憲の内容にはまったく触れず、ただただ改憲に向けた決意を口にするなど立憲主義国家において決して許されるものではありません。
加えて岸田政権は、「台湾有事」を名目に南西諸島への自衛隊配備強化、軍事費GDP2%への増大を打ち出すなど、安倍・菅政権以上に改憲・軍拡路線を鮮明にしています。また、防衛予算を安易に増税により賄おうとする姿勢は、物価高への対応などに追われている国民感情から大きくかけ離れたものです。
国民の理解も得られないまま大軍拡路線をひた走り、日本の安全保障政策を変容させるのではなく、まずは徹底した外交努力を行うべきであり、粘り強い対話を通して近隣諸国との関係改善をはかることが先決です。そのためにも私たちは、岸田政権に対峙し暴走を許さないとりくみの強化が求められています。
(3)憲法審査会をめぐる状況と改憲を許さないとりくみ
これまで衆議院憲法審査会では、新型感染症の拡大や災害などの非常時、混迷する世界情勢を口実に、緊急事態に備えた緊急事態条項を憲法に創設することの是非などが議論されてきました。自民党が憲法に創設すべきと主張する緊急事態条項は、内閣が大災害等で緊急と判断した場合には、国会の権能(立法権)を当該内閣が実質的に兼ねることができ、衆議院議員の任期を延長することができるとするものです。
自民、公明、維新、国民、有志の会は、「緊急事態における議員任期の延長が必要」と主張していますが、立憲民主党や社民党は、「任期延長は議員を固定し内閣の独裁を生む恐れがある」と反論、参議院の緊急集会で緊急事態への対応は可能であるとして、緊急事態条項の創設を理由とした改憲に反対の姿勢をとっています。
憲法は主権が国民に存することを宣言しています。選挙権は国民の国政への参加を保障する極めて重要な権利です。緊急事態における議員任期の延長は、政権与党の延命のために濫用的に利用されるおそれが否定できず、立憲主義の観点から重大な疑義があると言わざるを得ません。議員の任期延長という国民主権に反する制度を改憲により創設するのではなく、確実に選挙ができる制度構築とそのための法改正こそ実現すべきです。
参院憲法審査会は、昨年10月の最高裁判決が合区対象県の投票率低下などの問題点に言及したことを踏まえ、参院選で隣接県を一つの選挙区とする「合区」の問題を中心に議論がされています。自民党は合区解消に向けた憲法改正を実現すべきと主張していますが、立憲民主党は改憲による合区解消に対し、投票価値の平等を「地方の声を国政に反映させる」という主張で押しつぶすことは、基本的人権の尊重との関係で問題があると指摘するなど、衆院と参院の議論内容の違いも顕著となっています。
岸田首相は、4日の年頭会見で「総裁任期中に改正を実現したい思いに変わりはなく、議論を前進させるべく最大限努力したい。今年は条文案の具体化を進め、党派を超えた議論を加速していく」と強調しました。内閣支持率が上がらず、このままでは選挙を戦えないという声が党内に広がっていることから、自民党の党是である改憲への本気度を示し、党内求心力の回復と保守層をつなぎ留めることを意図したものと思われます。
昨年12月の衆院憲法審査会で自民党は、緊急事態時の国会議員任期延長や衆院解散禁止などの改憲条文案を作成するための作業機関を、今年1月召集の通常国会で設置するよう提案しました。自民党の改項目には、大災害時に移動の自由など個人の権利を制限する緊急事態条項などが盛り込まれています。緊急事態条項は東日本大震災の経験もあり、参院の憲法審査会でも改憲が必要な根拠として、自然災害時における対応のための緊急事態条項の必要性が改憲派議員から主張されています。議員任期の延長は国民の基本的権利である参政権を否定するもので、憲法違反とする最高裁の判示もあります。すべての国会議員の任期延長が果たして必要なのか、大災害時だからこそ冷静に、かつ十分な警戒をもって国会の動向を注視する必要があります。
憲法とは、そもそも権力の濫用や暴走に歯止めをかけるものです。時の政権が憲法を都合の良いように解釈し、憲法の理念が生かされているかの検証をすることもなく、改憲議論を押しすすめる改憲派勢力の姿勢を容認することはできません。
平和フォーラムは、改憲発議阻止、軍拡反対を基本に立憲民主党をはじめ改憲・軍拡に反対する政党、国会議員、法律家団体などと連携しながら、衆参の憲法審査会の傍聴行動など必要な国会対策をはかります。憲法審査会の議論経過や論点などをまとめた「憲法審査会レポート」の作成を継続するなど、国会の審議動向や問題点を市民団体や労働組合を通じ広く発信し、改憲・軍拡を許さない機運を高めていきます。
(4)広範な市民の結集に向けたとりくみ
これまでの憲法審査会での議論を広く共有し、国会議員の任期延長を含む緊急事態条項の憲法への創設のための改憲や、平和憲法の理念を大きく逸脱する防衛政策の大転換の危険性を広く訴えていくなど、政啓活動においても憲法改正を視野に入れたとりくみが必要となります。
これまで平和フォーラムは衆参の憲法審査会の傍聴を継続し、その都度「憲法審査会レポート」の発行を通じて審査会の議論内容を発信してきました。また、安保法制(戦争法)の廃止を求めて毎月19日に行われる「19日」行動では、1000人委員会としてその運営を主体的に担い、憲法理念を脅かす動向に対しては「声明」を発信するなど、一貫して改憲を許さないとりくみを進めてきました。
精緻な憲法・法律論の展開と憲法審査会の議論の推移の発信、広範な市民の結集、立憲民主党をはじめ改憲・軍拡に反対する政党や国会議員、有識者や法律家団体などと緊密に連携しながら、改憲ありきの拙速な議論に歯止めをかけなければなりません。
平和フォーラムは、5月3日に東京・有明防災公園で開催される「武力で平和はつくれない!とりもどそう憲法いかす政治を 2024憲法大集会」の成功をめざすとともに、改憲・軍拡阻止の機運を広く訴えるとりくみを進めます。
(5)護憲大会のとりくみ
平和フォーラムはこれまでの政府の姿勢や憲法審査会の問題点を広く共有することを目的に、昨年11月11日~13日の日程で「憲法理念の実現をめざす第60回大会」(護憲大会)を開催しました。地元・新潟実行委員会のご尽力もあり、開会総会からシンポジウム、分科会、ひろば、まとめ総会を成功裡に終了することができました。
メイン企画のシンポジウムは、憲法審査会委員の衆議院議員の新垣邦男さん(社民)、吉田はるみさん(立憲)、参議院議員の杉尾秀哉さん(立憲)、打越さく良さん(立憲)の4人の国会議員にパネラーとして登壇いただき、名古屋学院大学教授の飯島滋明さん(憲法学)をコーディネーターにシンポジウムを実施しました。4人の国会議員と飯島さんの発言を踏まえ、憲法をいかし改悪を阻止するために、私たち一人ひとりが主権者としての意識を向上させ、積極的に政治に参画するなどで、生活者の立場に立った政策・制度の実現や、平和憲法の堅持につなげる必要があります。憲法理念がますます軽視され、憲法改悪に向けた動きが現実的になっていることから、「改憲発議阻止、軍備増強を許さない」たたかいを中心に据え、全国で運動の広がりと盛り上がりをつくっていくことの重要性を共有することができました。
「憲法理念の実現をめざす第61回大会」(護憲大会)については、11月24日から26日にかけて、岡山県・岡山市で開催を予定しています。今後、開催地との具体的な協議をすすめ、護憲大会実行委員会において、大会の骨子案をまとめていくことになっています。
【とりくみ】
①「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」、「9条改憲NO!全国市民アクション」主催の共同行動にとりくむとともに、「戦争をさせない1000人委員会」独自の集会・行動、宣伝活動を展開します。
②戦争法の廃止・憲法改悪の阻止のとりくみをすすめます。また「安保関連3文書」の閣議決定、大軍拡・増税路線の撤回を求めます。
③自民党をはじめとする改憲勢力に対抗するため、立憲フォーラムと協力し、院内外での学習会などを行います。中央での学習会開催に加え、ブロック段階での開催を奨励し協力します。
④機関紙「ニュースペーパー」はじめ、情宣チラシ「どうかんがえる?」シリーズを適宜発行し、情報の発信に努めます。あわせて引き続き、ホームページの活用を推進します。
⑤軍拡路線の流れを止めるための、安全保障のあり方や、アメリカや東アジア諸国との新たな友好関係を追求するための大衆的議論をまきおこすとりくみを引き続きすすめます。
⑥5月3日に開催される「武力で平和はつくれない!とりもどそう憲法をいかす政治を!2024憲法大集会」をとおして、現行憲法の持つ平和理念を広くアピールします。あわせて、全国各地で開催される憲法集会のとりくみを推進します。
⑦衆参の憲法審査会の審議動向を注視するとともに、改憲勢力による改憲・軍拡の流れに警戒を強めます。そのための国会対策を立憲フォーラムと連携してすすめます。
⑧「憲法理念の実現をめざす第61回大会」(護憲大会)については、11月24~26日に岡山県・岡山市で開催します。今後、具体的な準備を地元実行委員会、護憲大会実行委員会ですすめます。
⑨安保法制違憲訴訟を支える会と連携し、安保法制の違憲判決を求める諸行動にとりくみます。
2.日本の防衛政策に対するとりくみ
(1)安保3文書の撤回、命とくらしを犠牲にしない社会を
第2次安倍政権が発足した2012年以降、特定秘密保護法(2013年12月)、集団的自衛権の行使容認閣議決定(2014年7月)、米国との防衛協力指針(日米ガイドライン)の再改定(2015年4月)、安保法制(戦争法、2015年9月)、組織犯罪処罰法改正(共謀罪法、2017年6月)などの悪法等を成立させ、米軍の武力行使との一体化への道を拓いて、自衛隊の行動範囲を世界に広げてきました。そして、私たちの「知る権利」を脅かし、権力による「予防弾圧」をも可能にする国内の治安を引き締める体制をつくりあげてきました。
さらに「安倍政治」を引き継ぐ岸田政権は2022年12月、安保3文書(「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」、「防衛力整備計画」)を閣議決定し、「専守防衛」すらかなぐり捨てる「反撃能力」という名の先制攻撃能力を持つことを宣言するに至っています。そして2023年は、安保3文書に基づいて、さらなる軍事拡大のため、防衛産業強化法(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律)や防衛力強化資金法(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法)を矢継ぎ早に成立させたほか、兵器や軍事技術の輸出を緩和する防衛移転三原則の運用指針を改定する閣議決定を行いました。
アメリカの対中国戦略を補完する役割を果たすこうした軍事拡大路線は、北東アジアの非核・平和を実現することなく、かえって軍拡競争や偶発的な衝突の危険性を増大させ、私たちそしてアジアの人びとの命を脅かし、くらしに犠牲を強いることになります。日本国憲法前文の理念と第9条を実現するとりくみを引き続き進めていくことが大切です。
(2)米軍とともに戦争をする体制を許さないとりくみ
ⅰ)NATOなど軍事同盟との連携、日米安保の強化を許さない
軍事同盟であるNATO(北大西洋条約機構)と日本の関係は、2018年にNATO日本政府代表部を欧州に開設して以降、関係を深め、NATO諸国と軍事演習を頻繁に行い、日本に連絡事務所を開設することも検討されています。
また、陸海空自衛隊を一元的に指揮する常設組織「統合作戦司令部」を2024年度中に発足させるため、防衛省設置法の改正案が提出されました。2023年1月の「日米安全保障協議委員会(2プラス2)」で米国は、日本の「統合司令部」設置を歓迎するとともに、日米共同文書で「相互運用性と即応性を高めるため、同盟におけるより効果的な指揮・統制関係を検討する」と確認しています。戦争のための日米統合司令部が事実上進むことにも警戒が必要です。
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は明白な国際法違反ですが、ここに至った背景の一部にロシアを取り巻くNATOの拡大があったことも事実です。軍事同盟の強化と拡大は戦争を防止する抑止にはなりません。
日米安保を変質させて日米軍事一体化を強化し、NATOなど多国間安保(軍事同盟)をすすめていく日本の防衛施策を転換させなくてはなりません。
ⅱ)在日米軍基地の縮小・撤去を求める闘い
辺野古新基地建設をめぐっては、軟弱地盤改良工事に伴う設計変更を承認しなかった沖縄県に対し、国は代執行裁判を提訴し福岡高裁での判決を得たうえで2024年1月10日、大浦湾側の工事に着手しました。
この代執行裁判の判決は、玉城県知事が公有水面埋立法に基づいて行った設計変更不承認が違法かどうかの判断をせず、国と県の対話による解決を認めず、普天間基地が常に危険にさらされていることを判断しないなど、代執行の三要件を充足しない全く不当なものでした。本来対等・平等である地方分権改革以降の国と地方自治体との関係をないがしろにし、地方自治の精神を踏みにじる国の強権発動は断じて許されません。
90メートルにもなる軟弱地盤を埋め立てることは困難視されており、防衛省が当初見積もった総工費3500億円の約3倍の9300億円が試算されていますが、さらに不足することが指摘されています。また米軍当局は、辺野古新基地の完成を早くて2037年と見積もっており、軟弱地盤の影響による滑走路の沈下や普天間基地よりも滑走路の長さが短くなることに懸念を持っています。今後も難工事によって長期にわたり普天間基地の危険性が放置されるばかりか、新基地完成後も米軍にとっては利便性を重視して普天間基地の継続運用がされないとは限りません。
沖縄戦犠牲者の遺骨を含む土砂の投入や莫大な税金を工事につぎ込むことなく、辺野古新基地建設計画を撤回すべきですし、普天間基地の運用停止に向けた議論を日本政府は進めるべきです。
アメリカの対中国戦略は、自衛隊を巻き込んでこれを「矛」とし、米軍は分散・配置して対応する戦略に進んでいます。米海兵隊は2023年11月に「海兵沿岸連隊」を当初予定より前倒しで発足させ、米空軍も同様に航空戦力の部隊を分散させる計画を明らかにしています。しかしこの動きは決して在日米軍基地の役割を低減させものではなく、自衛隊基地と在日米軍基地の相互利用、日米共同およびNATO諸国との軍事演習の増加、外来機の飛来の増加などで基地機能が強化されていることに注意を向ける必要があります。
基地周辺では爆音被害やPFOS、PFOAなど有機フッ素化合物の検出が確認されています。しかし地方自治体による基地内の調査が十分に行えず、米軍による情報公開も極めて限定的になっているのは、日米地位協定があるからこそであり、同協定の抜本的な改定が必要です。
ⅲ)軍事費拡大と増税を許さないとりくみ
2024年度政府予算が成立し、防衛費の当初予算は、7兆9496億円と2023年度当初予算から1兆1277億円増え、第2次安倍政権下の2013年度以降12年連続で過去最大を更新しました。一方軍事ローンである後年度負担(新規分と既定分の合計)は、14兆1926億円にものぼり、2023年度の10兆7174億円から大幅に増加させました。
また防衛省が計上する補正予算も見逃せません。2023年度の補正予算額は8130億円と過去最大になりました。そもそも補正予算は財政法29条に基づき、当初予期できなかった大規模災害など特に緊要になった経費の支出としてあるべきです。防衛費を聖域のように扱って予算編成することは断じて許されません。
防衛力の強化のために安定的な財源を確保するとして岸田政権は、防衛力強化資金を創設して決算剰余金や税外収入を活用するとしているほか、法人税、所得税及びたばこ税などから財源を確保する方針です。そしてそのための税制措置は複数年かけて段階的に実施していくとしています。GDP2%の軍事費支出ではなく、少子高齢化社会で社会保障給付額が増加する状況及び逆ピラミッドの人口構成を改善していくための施策にこそ使うべきです。
ⅳ)南西諸島・九州地域の軍事強化に反対するとりくみ
安保3文書は、中国、朝鮮、ロシアを念頭に置いて軍事力の抜本的な強化を行うとうたい、日米同盟の抑止力・対処力の強化及びNATO諸国やオーストラリア、韓国などとの連携を強化し、敵地攻撃能力(「反撃能力」)の保有などを明記しました。また南西諸島・九州地域の補給拠点、長距離ミサイル基地の整備、情報集能力の向上、司令部の地下化など駐屯地・基地の強靭化を図ることが盛り込まれています。
そして安保3文書に基づいて、民間の空港や港湾施設を米軍とともに使用することを目的として、10道県の38か所が「特定利用空港・港湾」として候補に挙げられたほか、2033年までに全国で130棟余りの弾薬庫を新たに整備する方針を政府は示しています。
2010年の防衛大綱・中期防衛力整備計画で、南西諸島・九州地域の防衛力強化を防衛省が打ち出して以降、沖縄県では与那国駐屯地(2016年)、宮古島駐屯地(2019年)、石垣島駐屯地(2023年)を開設し、鹿児島県では奄美大島に駐屯地・分屯地(2019年)を開設し、西之表市馬毛島では、米軍空母艦載機陸上離着訓練(FCLP)及び自衛隊の補給拠点としての新基地建設が2023年から始まりました。長崎県では2018年に日本版海兵隊ともいえる水陸機動団を相浦駐屯地に新たに配備(2018年)し、佐賀県では佐賀空港への陸上自衛隊のオスプレイ配備のため、2023年6月に造成工事に着手しました。
政府は、抑止力・対処力を高めるとともに「国民保護」にも言及していますが、軍事施設があるからこそ攻撃を受ける可能性が高まり、ましてや有事の際の避難誘導など全く現実的ではありません。自衛隊基地の増強、新設には断固反対の姿勢を貫いていきます。
また、自衛隊の強化の一方で、自衛隊内でのいじめ、女性自衛官に対するセクハラやパワハラなどの問題があとをたちません。自衛隊の任務拡大のなかで増大していることから、これら問題に引き続き関心を寄せていきます。
ⅴ)オスプレイの運用を許さない、日米地位協定の抜本的改定を
米軍機オスプレイについては、2023年7月に公表された事故報告書で、初めて事故の原因が機体にあることを認めました。しかも不具合の根本的原因は不明であるとしています。その後11月末には鹿児島県屋久島沖で米空軍オスプレイの墜落事故が起き、すべての米軍オスプレイと自衛隊のオスプレイが飛行を停止しました。
欠陥機オスプレイの配備は撤回させ、オスプレイの運用にかかわる定期機体整備、佐賀空港新設工事などの事業中止を求めていく必要があります。
また、オスプレイに限らず米軍機の墜落事故が世界で頻繁に起こっているほか、日本国内における市街地上空で、空中給油訓練や低空飛行など危険な飛行を繰り返しています。日本での米軍機の飛行訓練等は、指定された空域以外でも可能であるため大変危険です。米軍機の飛行に特権を与えている日米地位協定の抜本的な改定、航空法の適用除外規定の見直しを求めていかなくてはなりません。また、2023年7月に日米合同委員会で合意された米海兵隊オスプレイの超低空飛行訓練(高度500フィート未満200フィートまで)の撤回を求めるほか、議事録すら公表されない日米合同委員会についても批判していくことが重要です。
(3)市民社会の軍事化を許さないとりくみ
ⅰ)秘密保護の強化と監視社会化に反対する
2022年9月に全面施行した土地等監視・利用規制法(「重要土地等調査規制法」)では、重要施設がある注視区域及び特別注視区域に指定された区域内の住民や物件所有者について、政府が情報を調査・収集することができ、さらにそれらの関係者に至るまで調査や情報提供を求めることができます。また、重要施設の機能を阻害する「おそれ」がある行為について規制、禁止させることができるとしています。
情報や調査の具体的項目、機能阻害行為とはなんであるかなど法文では明らかではなく、閣議決定で基本方針を決めていくことになっており、恣意的な運用のおそれがあります。
指定区域はこれまで、自衛隊施設、在日米軍施設、原子力発電関連施設などの周辺区域が指定されていることから、反戦平和運動、反原発運動などへの規制につながりかねません。財産権など私権の制限するものともいえる同法の廃止を求めていく必要があります。
ⅱ)科学技術の軍事転用、日本が死の商人になることを許さない
政府は、「防衛生産と技術基盤の強化」のため軍事産業の育成・保護に力を入れています。2022年5月に経済安全保障推進法が制定され、軍事技術に転用できる先端的重要技術の開発支援を制度化しました。さらに2023年6月には防衛産業強化法を成立させ、軍事生産と技術の保護育成のための基盤を固めています。
さらに政府は、2024年1月に開会した通常国会に経済安全保障推進法の改正案を提出しました。この改正案は、2013年に強行採決された秘密保護法で外交、防衛、テロリズムの防止、特定有害活動の防止にかかわる4分野に続いて、経済情報も「秘密」に加え、情報にかかわるものの身辺調査の強化(セキュリティークリアランスの強化)と重罰を科す制度です。
先端技術研究・開発を軍事研究・開発へと向かわせ、秘密の保護の強化と個人のプライバシー侵害を進める危険性をはらむ法律は撤回以外にあり得ません。「軍事目的のための科学研究を行わない」とする声明を出していた日本学術会議に対する政府の介入などの動きと共に、今後の動向を注視していく必要があります。
政府は2023年12月、殺傷兵器を輸出できるように「防衛装備移転三原則」の改定を閣議決定しました。紛争当事国には輸出しないとしていますが、ウクライナ支援で在庫が枯渇している米国にパトリオットミサイルを輸出することは、紛争当事国に武器供与する補完的な役割を果たしていることになります。国際紛争を助長しかねないとして武器輸出を制限してきた政府方針の大転換を国会での審議もなく自公政権内での手続きで進めたことは断じて許されません。
今後政府は次期戦闘機の日英伊共同開発で、完成した戦闘機を第三国に輸出することや英防衛大手BAEシステムズからライセンスを受けて日本製鋼社が製造している155ミリ榴弾砲(FH70)の輸出も検討しています。武器輸出の拡大を許さず、日本が死の商人への道を歩まぬよう政府の動向を引き続き監視をしていきます。
【とりくみ】
①憲法前文理念および憲法9条に反する集団的自衛権の行使の閣議決定、安保法制(戦争法)の廃止、安保3文書の撤回を求めるために、戦争をさせない1000人委員会とともに戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会のとりくみに協力していきます。
②米軍基地や自衛隊基地の機能強化、日米軍事一体化に反対する各都道府県運動組織・各地域ブロックおよび全国基地問題ネットワークのとりくみを支援していきます。また各都道府県組織・各地域ブロックが行うとりくみ等の情報を全国で共有できるようにし、反対運動の強化に努めます。
●自衛隊と米軍等との共同軍事訓練の動きを監視し、情報発信します。
●情報が得られた各都道府県組織のとりくみをまとめ、運動すすめるための資料として活用できるようにします。
●5.15平和行進実行委員会が主催する「2024 5.15平和行進」に協力します。
全国結団式:5月17日(金)15時~16時 琉球新報ホール
平和行進:5月18日(土)8時30分出発式・9時行進スタート 宜野湾市役所
県民大会:5月18日(土)12時~13時 宜野湾市立グラウンド
③日米安保条約に基づく日米地位協定や日米合同委員会にかかわる課題、とりわけ米軍機の飛行問題、基地由来の環境汚染や爆音問題について、全国基地問題ネットワークおよびオスプレイと低空飛行に反対する東日本連絡会と連携して、学習会、教宣用資料の発行、対政府要請行動にとりくみます。
④土地等監視・利用規制法や経済安全保障推進法および特定秘密保護法の適用拡大による市民生活や経済活動への影響について、原水禁や全国基地問題ネットワークと連携し、学習会、教宣用資料の発行を追及します。
⑤軍事生産や技術開発の動きを監視、検証し、攻撃型兵器や技術の導入に反対するととともに、軍事研究や武器輸出の動向を注視していきます。
⑥超党派の国会議員で構成されている沖縄等米軍基地問題議員懇談会の政府ヒアリング等の活動を注視していくとともに、政府要請の窓口として協力関係を保持していきます。
3.東アジアの非核・平和のとりくみ
(1)成果なく終わったG7首脳国会議
2023年5月19日から22日にかけて、岸田文雄首相の選挙区広島において日本が議長国としてG7首脳会議が開催しました。岸田首相は、「ゼレンスキー大統領を招き、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の重要性を確認し、守り抜く決意を新たにするとのメッセージを、世界に向けて力強く示せたことは意義深い」と成果を強調しました。19日には「ウクライナに関するG7首脳声明」同じく「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン」が、20日には「G7広島首脳コミュニケ」が、採択されています。コミュニケは「ロシアのウクライナに対する侵略戦争を、改めて可能な限り最も強い言葉で非難する。必要とされる限りの揺るぎないウクライナへの支持を再確認する」とするもので、全体としてロシア、中国、朝鮮民主主義人民共和国への非難に終始するもので、現状の問題を克服する具体的表明はありませんでした。
首脳会議には、招待国として中国やロシアと関係の深い「グローバル・サウス」から、インド(G20議長国)・ブラジルなどが招待されました。グローバル・サウス諸国の、親中国・親ロシア政策へのくさびを打つ目的もあったと考えますが、インドモディ首相やブラジルルーラ大統領は、中国・ロシアへの親近感を否定することはなく、中国・ロシアへの牽制・抑止を基本にしたG7各国の姿勢に対してグローバル・サウス諸国の支持を集めることができませんでした。
中国政府は、「G7は中国側の重大な懸念をかえりみず、中国を中傷、攻撃し、中国の内政に乱暴に干渉した。これに強烈な不満と断固反対を表明する」と、きびしい言葉を用いて反発しています。ロシアは、中国を中心としたBRICS諸国への依存度を高め、中国やインドがロシア産原油を買い支える状況となっています。中国の対ロ輸出も増加し過去最高を記録する中、李強首相は「中国はロシアとの経済交流を拡大させたい」とも述べています。ロシアのウクライナ侵攻が、世界の分断を誘発しているならば、G7各国はロシアとウクライナの停戦への交渉・協議の間に立ち、分断を阻止する情勢を作らなくてはなりません。G7諸国の世界経済への影響力の低下もあって、今回のG7首脳会議は、中国・ロシアを攻撃対象として新たな分断を呼び込み、多極化する世界情勢を反映したものとなりました。
平和フォーラム・原水禁は、G7が被爆地広島で開催されることから、広島原水禁と協力し5月17日に広島YMCA国際文化ホールにおいて「『ヒロシマ』のおもい、核兵器廃絶のおもいを世界へ5.17原水禁集会」(参加200人)を開催し、日本政府に対して核の先制不使用宣言を求めると共にウクライナ戦争終結の外交努力を求めました。しかし、G7で採択された「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン」は、「核抑止力」の肯定を基本に据え、先制不使用宣言や核兵器禁止条約に触れることのない核兵器保有国の主張に沿ったものとなっています。カナダ在住の広島での被爆者サーロー節子さんは、「広島まで来てこれだけしか書けないかと思うと胸がつぶれるような思いがしました。大変な失敗だったと思います」と述べています。
(2)日米軍事同盟強化は戦争への道
4月8日から6日間にわたり岸田首相が訪米しました。バイデン大統領は「日米同盟は歴史上かつてないほど強固」として、今回の合意が「同盟発足以来最も重要な進展」と評価しました。岸田首相は「日本は常に米国と共にある」と語り、日米同盟の更なる強化を示唆しました。
会談後の共同声明では、「台湾海峡の平和と安定の重要性」を強調し、米英豪によるAUKUS(オーカス)への軍事技術開発への協力や自衛隊と在日米軍の指揮統制のあり方(日米統合軍構想)の見直し、防衛装備品の共同開発・生産など、一層の軍事連携・協力強化を打ち出しています。
これに対して中国外務省は、「中国への中傷・攻撃」と反発し「強い不満と断固とした反対」を表明しました。国内議論など民主的手続きを欠いた日米同盟強化の方針は、東アジア情勢へ大きな懸念となるものです。経済的関係が強まる中国の反発は、日本にとって決してプラスになるものではなく、台湾や朝鮮半島有事を強調して脅威を煽り、日米同盟強化と防衛力増強に走る岸田政権の姿勢は、日本社会の市民生活を一層きびしいものにするに違いありません。
声明で語られた「核を含むあらゆる能力を用いた日本防衛に対する米国の揺るぎないコミットメント」は、5月にも予定される日米安全保障協議会(2プラス2)で「突っ込んだ議論」を行うとされています。核兵器による抑止と通常兵器による抑止を合わせた「拡大抑止」の議論は、戦争被爆国であり平和憲法を持つ日本において、踏み込んでいいものではありません。平和フォーラム・原水禁は、様々なとりくみを通じて今回の日米共同声明に表現される「戦争国家」への道を阻止していかなくてはなりません。
(3)進まない日中間の政治交流
2023年6月18・19日のブリンケン米国務長官の訪中の後、米国務省は、米台関係の「ファクトシート」を更新し、削除していた「台湾の独立を支持しない」との文言を復活させています。ブリンケン長官も、「台湾政策に変更はなく『一つの中国』政策を維持するなら『台湾の独立』を支持しない」と述べています。
2023年11月16日には、1年ぶりとなる米国バイデン大統領と中国習近平国家主席との首脳会談がサンフランシスコで行われ、国防相会談の再開や軍司令官による軍の演習や展開での対話再開を合意したとされています。バイデン大統領の中国の台湾総統選への介入停止の求めに習主席は、「アメリカは中国の平和的統一を支持すべき」「米国では中国の軍事作戦が取り沙汰されているが、そのような計画はない」と強く反論したとされています。中国は、「他国の介入がない以上、ことは平和裏に進む」とアピールする狙いがあったものと考えられます。米中の対立が、世界情勢に大きな影響を与えている今日、米中対話と双方の歩み寄りが期待されます。
1月13日、台湾総統選挙の投開票が行われました。中国と対立し、対米関係を重視する与党・民主進歩党(民進党)の頼清徳候補の勝利が確定しています。対中融和路線の最大野党・国民党と親米路線を選択する民進党を軸に主要3党で争われたものの、いずれの党も、台湾の「現状維持」に努めると主張し、多少の意見の相違はあるものの台湾の正式な独立も中国との統一もない現在の中途半端な状態を肯定することとなっていました。同時に行われた立法委員(国会議員)選挙では、国民党51議席、民衆党8議席で民進党50議席を野党が上回ることとなりました。今後の政局は混沌としており、頼清徳候補を「戦争リスクをもたらすトラブルメーカーだ」として批判する中国側がどのように対応するかが注目されます。麻生副総理の度重なる「台湾有事」への発言などに象徴される中国を脅威とする日本政府の態度は、台湾市民の感覚からは大きく乖離し、東アジア情勢の不安定要素となっています。
この間、平和フォーラムは中国との関係を重視し、中国人民平和軍縮協会との交流を重ねてきました。コロナ禍で途絶えていた軍縮協会の原水禁大会への参加も昨年再開し、今後の交流が期待されます。2023年は日中平和友好条約締結45周年であり、中国大使館主催の式典にも参加し、かつ中国大使館とは日常的交流を重ねてきました。東アジアの平和にとって、日中関係の深化は重要であり、今後も関係強化にとりくんでいきます。
(4)混迷の朝鮮半島と日本
G7に岸田首相は、ユン韓国大統領を招待し、二人して「韓国人原爆犠牲者慰霊碑」に献花しました。両首脳がお互いを褒め称え合う両国首脳によるこの演出は、現在進行する米韓日の東シナ海から日本海への軍事展開の一層の強化を示唆するもので、韓日両国が米国の東アジアでのプレゼンスを補完し、対朝鮮、対中国・ロシアに共同して対応する意思を示したものに他なりません。ウクライナへの対応においても、両国ともにNATO首脳会議に出席するなど、その立場は明確です。日韓両国の米国との同盟強化政策は、東アジアの平和への障害となるものと言わざるを得ません。
平和フォーラムは、この間、朝鮮への一方的な敵視政策をあらため、朝鮮戦争の停戦協定を平和協定へ進化させることを基本に、米韓合同軍事演習の中止を求めて、全国9カ所で、米国および韓国の大使館・領事館へ申し入れ行動にとりくんできました。2023年は、朝鮮戦争の停戦合意から70年目の節目の年で、7月22日に韓国ソウルで開催された「停戦協定70周年平和集会」へ、各県組織も含めて7人が参加しました。先立つ7月14日には、平和フォーラムが事務局を担う「東アジア市民連帯」の主催で、連合会館大会議室において「朝鮮戦争停戦70年 国際シンポジウム-戦争危機から平和へ、転換の道しるべ」を、韓国ゲストも交えて開催しました。現在、停戦状態の朝鮮戦争を終結し、米国を中心とした当時国間で平和協定を締結し、南北間の、日朝及び米朝間の国交を正常化する事が、東北アジアの平和にとって重要です。
ところが、韓国ユン政権と米国バイデン政権は、2024年3月4日から14日にかけて、3隻の空母(ロナルド・レーガン、カール・ビンソン、セオドア・ルーズベルト)を朝鮮半島近海に展開し、大規模軍事演習「フリーダム・シールド(自由の盾)」を実施しました。今後も5月20日に予定される台湾総督就任式にあわせて、エイブラハム・リンカーン、ジョージ・ワシントンを含め計5隻の空母を展開させる予定と言われ、8月には「核作戦シナリオを含めた訓練」を中心とした「乙支(ウルチ)フリーダム・シールド(自由の盾)」を実施するとされています。前政権下では中断されていた米韓合同軍事演習の質・規模・期間を含めた強化は、朝鮮の反発を生み、朝鮮をしてロシアとの同盟強化と韓国との対決姿勢に転換させています。
4月10日の韓国の総選挙では、比例区のみで闘ったチョ・グク(曺国)元法相の率いる「祖国革新党」が12議席を獲得、連携する最大野党の「共に民主党」も175議席を獲得しました。ユン大統領の与党「国民の力」は108議席に留まり、いわゆる「ねじれ国会」は継続され、選挙結果が明らかになった段階で、ユン大統領は「国民の意思を謙虚に受け止め、国政を刷新する」と述べています。野党の議席が政権与党をこれほどに圧倒したのは大統領直接選挙制度の導入後初めてとされます。このような中で、ユン政権が、親米路線や対北政策、対日政策を大きく変更するとは考えられませんが、しかし、野党勢力が足並みをそろえてユン政権に対抗する中、政権のレームダック状態は免れず、徐々に外交政策など政治路線を変更する事も考えられます。平和フォーラムは、野党圧勝を作り出した韓国の平和団体などともに、東北アジアの平和へのとりくみを強化していきます。
2023年12月30日まで5日間開催された朝鮮労働党中央委員会総会は、今後の朝鮮の外交・安保の方針を米国との対話からロシアとの同盟強化へと明確に変更しています。2024年1月5日から翌日にかけて、朝鮮軍は延坪島北西の公海上の軍事境界線付近で砲撃を行い、朝鮮が2023年11月に表明した、2018年に「平壌(ピョンヤン)南北首脳会談」で交わされた「9.19南北軍事合意」の破棄を実行に移しました。また、米韓の同盟深化の下、朝鮮への制裁と圧力の外交へと転換した韓国ユン・ソンヨル大統領に対して、キム・ジョンウン朝鮮国務委員長は、「南朝鮮(韓国)は『主敵』」と発言するなど、南北情勢はきわめて深刻な事態となっています。このような情勢の中、米国内においても、「米立法府が朝鮮との平和条約締結を優先的に進めるべき」などと朝鮮との和平を求める声が上がっています。
南北対話、米朝対話の再開こそが朝鮮半島の平和への道であり、38度線をめぐっての朝・中・ロと韓・米・日の対立は決して相互の利益にならないことを自覚すべきです。現在、米中露対立の中に飛び込もうとする勢力はなく、対立は世界を巻き込んで深刻化しています。日本は日朝国交回復をめざし、また米朝間の橋渡し役を演じ、朝鮮戦争の終結への話し合いを進め、緊張緩和の情勢を醸成していくべきと考えます。東北アジアの軍事的対立を深めていくことは得策ではありません。
2023年の日韓でのとりくみから、キム・ジョンミン監督による映画「WARmericaの運命」が生まれました。日本語字幕版を作成し、2023年2月20日には連合会館大会議室で上映会を開催しました。朝鮮半島に我が物顔で君臨する米国のこれまでを描いたドキュメンタリー映画は、今後の朝鮮半島のあり方を示唆しています。全国での上映会開催を進めるとともに、自衛隊の参加も含めた米韓共同軍事演習に反対し、朝鮮半島を中心とした東北アジアの平和へのとりくみを強化していきます。
(5)ゆがんだ日韓関係
日韓両政府の米国との同盟強化の方針を受けて、ユン・ソンヨル(尹錫悦)韓国大統領は、2023年3月に日韓の懸案事項であった元徴用工問題で、韓国行政安全省傘下の「日帝強制動員被害者支援財団」が遅延利子を含む賠償金相当額を原告側に支払うとする内容で、関係改善に動きました。これは、日本企業には負担させずに韓国側が肩代わりするもので、韓国社会の反発が予想されます。対米追従と日本の戦後補償を棚上げする関係改善の外交姿勢は、ユン政権の支持率低下を招いています。ユン政権は、韓国国内において南北対立を煽ることでゆがんだ日韓融和への市民の反発を薄めるべく、躍起となっています。朝鮮との友好団体などへの弾圧を強めています。一方で、日本の入管は韓国の平和団体活動家の入国を拒否する暴挙にでています。このような、韓国・日本政府ともに連携した国家による平和運動への弾圧に対しては、きびしい姿勢でとりくんでいかなくてはなりません。
2018年以来5年ぶりに、韓国大法院(最高裁)は2023年12月21日、韓国人の元徴用工ら11人が、日本企業を相手に損害賠償を求めた2件の訴訟で、日本企業の上告を棄却し、原告勝訴で確定しました。大法院は、戦時中の動員が「日本の不法な植民地支配と直結する反人道的な不法行為」であり、被害者らの慰謝料請求権は日韓請求権協定の対象外だと判断しています。
また、2023年11月23日には、ソウル高等法院が元日本軍慰安婦らによる賠償請求について、ソウル地裁判決を破棄し原告勝訴の逆転判決を下しました。国際法上の「主権免除」を主張し日本政府は、裁判に出席せず上告もしなかったため判決は確定しました。ソウル高裁は、「国際慣習法上、韓国の裁判所での裁判権を認めるのが妥当だ。朝鮮半島で原告を動員する過程での不法も認められ、慰謝料を支払わなければならない」と指摘し、「主権免除」の原則は認められないとしました。国際社会の新しい流れとして「主権免除」を認めない状況が生まれています。
朝鮮敵視政策を打ち出すユン・ソンヨル政権は、日韓関係のゆがんだ是正策を打ち出しています。しかし、韓国市民社会は、過去の植民地政策を総括せず歴史歪曲に進む日本政府の姿勢を許すことはないでしょう。平和フォーラムは、朝鮮半島との歴史的和解は、過去に日本政府が行った植民地支配の過ちを真に認めることから始まるものと確信し、そのためのとりくみを積極的にすすめていきます。
(6)関東大震災100年朝鮮人虐殺犠牲者追悼と責任追及の行動
2023年9月1日は、1923年9月1日の関東大震災朝鮮人虐殺事件から100年を迎えました。さまざまな団体が追悼の式典を開催しています。平和フォーラムも、これまで共に差別と闘ってきた仲間と「関東大震災朝鮮人虐殺100年-朝鮮人虐殺犠牲者の追悼と責任追及の行動」のための実行委員会を組織し、建国記念の日を考える集会を含めて朝鮮人虐殺の問題を学ぶために4回の学習会、院内学習会、フィールドワークを開催してきました。それぞれ多くの方々に参加をいただきました。また、大震災当日の9月1日には、銀座ブロッサムを会場に在日朝鮮人や日本人の大学生・高校生の協力もいただき、「追悼と責任追及の集会」(約800人)を、翌2日には連合会館大会議室において「国際シンポジウム」(約350人)を開催しました。韓国や米国などからも市民団体22人、韓国の仏教者団体35人など、海外からも参加をいただきました。
このとりくみの中で、関東大震災時の朝鮮人虐殺が、①植民地出身者に対するジェノサイドであったこと、②日本政府は、事件当時からこれまで真相解明はおろか犠牲者および犠牲者数の正確な調査も、謝罪すらも行わずに来たこと、③小池百合子東京都知事の追悼集会へのメッセージ送付拒否に象徴されるように歴史歪曲の動きも見られるなど、いまだ問題解決に至らないことが明らかになっています。
日本国内でのマスコミによる積極的な報道と追悼集会での日韓連携強化の中で、韓国共に民主党や与党の一部議員など100人が「関東大震災時の虐殺事件に関する特別法案」を提出、2023年12月に来日した韓国のキム・ジンピョ(金振杓)国会議長は27日、首相官邸で岸田文雄首相と会談し、韓国国会が日本側に要請している関東大震災時の朝鮮人虐殺事件の真相究明と遺骨返還への積極的な協力を要請しました。日韓の歴史的和解も含めた新しい関係の構築には、差別の撤廃と植民地主義の克服が需要であると考えます。
戦後の日本社会における植民地支配への反省の欠如が、多文化・多民族共生を謳いながらも、在日朝鮮人や外国人への人権侵害を繰り返す根本原因となっています。平和フォーラムは、集会で採択した「政府要請文」をもって、日本政府の責任を追求し謝罪を以て植民地主義の払拭をめざそうと考え、10月16日、国家公安委員会と警察庁へ「政府要請文」を提出し受理するよう求めました。当初、日時も参加者も決定したにもかかわらず、急遽受け取ることはできない旨の連絡が来ました。最終的に、内閣府請願課への提出となりましたが、新聞報道で明らかになった当時の神奈川県知事から内務省警保局長宛の報告書などが警察庁ないし警視庁に存在すること、政府が「政府内に文書が見当たらない」と回答していることなどから、要請交渉を嫌って拒否したと考えられます。
実行委員会に参加していただいた仲間は、敗戦後も温存してきた植民地主義、そこから派生する朝鮮人差別、外国人差別を払拭するとりくみを、今後もすすめていくことを確認しています。平和フォーラムは、今後も多くの仲間と共に世論喚起と政府の植民地政策による朝鮮人虐殺の責任を追及していきます。
【とりくみ】
①東アジア市民連帯として参加する国際平和機構「コリア国際平和フォーラム」との国際的な連携の強化に努めます。
②韓国のNGO「アジアの平和と歴史教育連帯」と連携し、歴史認識の一致をめざしてとりくみます。また、歴史教科書の採択や記述に関する問題にとりくみます。
③日中関係の重要性を考え、「中国人民平和軍縮協会」との関係を強化します。
④植民地支配責任・戦後責任問題の解決のために、日韓連帯を基本に、「強制動員問題解決と過去清算のための共同行動」とともにとりくみます。また、正しい歴史認識のもと、「明治日本の産業革命遺産」や「佐渡金山」などの世界遺産、韓国徴用工や日本軍慰安婦などの課題にとりくみます。
⑤東アジア市民連帯を中心に、日韓・日朝問題にとりくんでいるさまざまな組織とともに、朝鮮半島との連携強化を基本に、課題の解決にとりくみます。
⑥「関東大震災朝鮮人虐殺100年-虐殺犠牲者の追悼と責任追及の行動」の実行委員会に参加した組織の連帯を基本に、植民地主義の払拭をめざします。
⑦韓国平和団体作成の映画「WARmericaの運命」上映会の成功と朝鮮半島に関わる問題の情宣に努めます。
4.さまざまな人権課題へのとりくみ
(1)朝鮮学園をめぐる課題へのとりくみ
2010年度から実施された高校授業料無償化措置(2014年から「高等学校等就学支援金制度」)において、外国人学校の中で朝鮮学校だけが適用されないまま、2013年に文部科学省令が改正され、朝鮮高校は適用の申請すらできないようにされました。2019年10月1日からの幼保無償化においては、朝鮮幼稚園だけの排除でなく、ブラジル学校などの各種学校である外国人幼稚園がまとめて排除されました。また、コロナ対策の一環である「学生支援緊急給付金」の制度からも朝鮮大学校が排除されました。この間、平和フォーラムでは署名や集会によって不当な差別を止めるよう訴えてきました。
幼保無償化については、様ざまな批判と要求から、2021年度、文科省が「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援」の制度を設けました。これは幼保無償化制度から排除された幼児教育施設を対象にしようというものです。しかし、居住する市区町村が必要と認めなければ支給対象とならないことから同じ施設(例えば同じ朝鮮幼稚園)に通う子どもでも居住地により支援の対象にならないという制度設計自体が不平等で問題の多い制度です。
今年は幼保無償化制度に関する「少子化社会対策大綱」にあった「5年後[2024年]を目処に見直し」にあたり、幼保無償化制度の抜本的な改正を求めていく必要があります。
この間、全国5ヶ所の裁判の原告も含まれる朝鮮大学生が2013年5月31日から始めた「金曜行動」は、全員寄宿制の朝大生が、夏冬の長期休暇には帰省し、「金曜行動」も休みとなりっていたので、2015年7月17日から朝大生の長期休暇中には支援者たちが「朝大生に続く勝手に金曜行動」として、金曜行動を継続するようになりました。朝大生による金曜行動は2020年2月21日の(朝大生主催だけでの)第200回で、コロナの影響もあり、いったん休止となりましたが、支援者たちによる「勝手に金曜行動」として継続し、12月15日に第500回を迎えてしまいました。
2023年4月1日から「こども基本法」が施行されました。この法律は、こどもに関する施策について「全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。」を求めています。一日も早く朝鮮学校への高校・幼保無償化を実現しなければなりません。
国際社会では、4月18日から21日、朝鮮学校を支援するアメリカ、ドイツ、オーストラリア、韓国等の団体が集まり、「第1回朝鮮学校差別反対国際連帯ハンマダン」を開催、平和フォーラムからも参加し、「朝鮮学校の差別中断を国際社会に訴える!」という共同声明が発表されました。
日本政府の朝鮮学園に対する不当な差別は、朝鮮学校への「ミサイル発射を止めさせろ」などの嫌がらせの電話、赤羽駅構内での「朝鮮人コロス会」などの落書き(22年9月)に見られるヘイトスピーチ、ヘイトクライムを引き起こす要因となり、日本社会に求められる「多文化・多民族共生社会」構築に大きな障害となっています。自民党の杉田水脈衆院議員は、アイヌ民族や在日コリアンに関するブログへの投稿内容を昨年秋に法務局から「人権侵犯」と認定されています。東北アジアの平和にむけて、日朝国交正常化にむけても、国内における差別撤廃と植民地支配から引き起こされてきた差別意識の払拭が求められます。
【とりくみ】
①「朝鮮学園を支援する全国ネットワーク」、「日朝学術教育交流協会」、「朝鮮学校「無償化」排除に反対する連絡会」や当事者団体などと連帯し、幼保無償化、高校就学支援金制度、また、コロナウイルス対策を目的としたさまざまな支援制度からの在日朝鮮人社会の除外を許さず、すべての制度の適用を求めてとりくみを強化します。
②実効性あるヘイトスピーチ解消のための条例を求めて、とりくみを強化します。
すべての子どもに学ぶ権利の実現を!研修・交流会実行委員会が行なう「こども基本法に則り朝鮮人・外国人学校の子どもの学ぶ権利の保障を求める署名」に協力します。
(2)部落差別解消に向けたとりくみ
1922年3月3日に「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と高らかに人間の尊厳と平等をうたい上げた全国水平社が創立されて以降、部落差別解消に向けたたたかいは被差別部落だけでなく様々な人権団体や労働組合も自らの課題として参画しながら、部落差別をはじめ、あらゆる差別を許さないとりくみとしてすすめられてきました。
2016年12月には、差別の解消に向けた国等の取組を定めた「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。この法律は、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である」と示すとともに、部落差別の解消に関し、基本理念、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、相談体制の充実、教育及び啓発、部落差別の実態に係る調査といった具体的施策について定めています。
しかし法的措置は実現したものの、人権侵害からの救済や人権保障を促進するための国内人権機関は設置されておらず、この問題があらゆる差別を助長させている大きな要因となっています。裁判所とは別に構成、予算、活動のすべてにおいて政府から独立し、人権侵害からの救済をおこなうのが国内人権機関であり、現在世界120か国で設置されています。国際機関からの再三の勧告にもかかわらず自公政権は、「(国際的な勧告には)法的拘束力がない」「人権の定義が曖昧である」「逆差別の恐れがある」などとして、人権機関の設置を真っ向から否定しており、この状況を変えていくとりくみが重要です。
1963年5月1日に起きた狭山事件で石川一雄さんが不当に逮捕されて61年、狭山第3次再審を請求してから18年が経過しました。弁護団はこれまで出た新証拠を提出し、有罪判決に合理的疑いが生じていることを明らかにしたうえで再審を開始するように求めています。あらためて鑑定人尋問、インク資料の鑑定の実施を求める署名活動や、新証拠の学習と教宣活動を強化していくことが必要です。
「全国部落調査」復刻版出版事件(鳥取ループ事件)の控訴審判決が2023年6月28日に東京高裁で出され、被告の行為が「差別されない権利」を侵害していることを認め、出版差し止め範囲を一審の25都府県から31都府県に拡大するとともに、賠償額も一審の約489万円から約550万円に増額するとなりました。「差別されない権利」が認められたことの意義は大きく、今後の様々なとりくみに生かしていくことが重要です。
平和フォーラムは、部落解放同盟と連携しつつ、部落差別を含めたあらゆる差別を解消するとりくみをすすめていきます。
【とりくみ】
①人権侵害からの救済や人権保障を促進するための国内人権機関の設置の実現に向けたとりくみを求めます。
②狭山事件の再審勝利をめざしたとりくみをすすめていきます。
(3)水俣病問題の早期解決に向けたとりくみ
1956年5月1日に熊本水俣病の発生が公式に確認され、1965年6月12日には新潟水俣病が公表されました。以来、被害者の救済を求め加害企業、国、県に対する裁判闘争をはじめとしたさまざまなとりくみが熊本、新潟両平和運動センターなどを中心に進められてきました。
政府・環境省は、最高裁が2004年と2013年の二度にわたって国の認定基準で棄却された被害者を水俣病と認める判決を言いわたしているにもかかわらず、「77年判断条件を変えないまま、総合判断による認定について、メチル水銀のばく露歴を具体的に明記することによって現実には厳しい認定基準を維持(2014年3月7日付環境省通知)」として、認定基準を見直していません。認定をめぐる裁判では、2018年3月の新潟水俣病第3次訴訟高裁判決は原告の上告棄却、2020年3月の熊本互助会第2世代訴訟福岡高裁判決も原告の上告棄却、2022年3月の熊本互助会同認定義務付け訴訟熊本地裁判決は原告敗訴と、きびしい結果が続いてきました。
しかし2023年9月27日、ノーモア・ミナマタ第2次訴訟の近畿訴訟において大阪地裁は原告128人全員を水俣病と認め、国、熊本県、チッソらに総額3億5200万円の支払いを命じる原告全面勝訴の判決を示しました。判決はこれまでの国や熊本県の施策の誤りを明確に断罪し、従来の被害者救済策の根本的な転換を迫る画期的なものでした。しかしその後国、熊本県などは大阪高裁に控訴し、原告および支援者の期待を大きく裏切り、問題解決は再び先延ばしにされる事態となりました。一方熊本訴訟において熊本地裁は、3月22日に、原告144人全員の請求を棄却、うち25人を水俣病と認定するも除斥期間を適用して賠償を認めないという近畿訴訟とは真逆の不当な判決を出しました。ただしこの判決で水俣病と認定された人には特措法が定める対象地域外で被害を受けた人も多く含まれており、国の認定行政の問題点を指摘する内容も含まれています。原告団は直ちに控訴を表明し、たたかい続けることを確認しています。(なお新潟訴訟判決は4月18日であり、総会では口頭で補強します)
被害者全員の救済に向けては、裁判において勝利するだけでなく、国や県が救済に向けて真摯に取り組まざるを得ない状況を作り出すことが必要で、市民の関心の高まりと、救済を求める声の拡大が重要です。この間平和フォーラムは、「ノーモア・ミナマタ第2次訴訟公正な判決を求める要請署名」や「同団体署名」をはじめ、判決報告集会などにとりくんできました。原告の平均年齢は高齢化しており、一刻も早い全面解決が求められます。平和フォーラムは、引き続き熊本、新潟両平和運動センターと連携し、補償を受けられずに取り残されている被害者救済のとりくみを進めます。
【とりくみ】
①原告団、弁護団のとりくみに協力し、水俣病の実相と責任追及、被害者救済の必要性を広めるとりくみに努めます。
②NPO法人水俣フォーラムが主催する「第20回水俣病記念講演会」に協賛します。
●第20回水俣病記念講演会
日時:4月29日(月)14時30分~18時
場所:有楽町マリオン朝日ホール
(4)外国人の人権確立に向けたとりくみ
2023年8月、国連人権理事会「ビジネスと人権」作業部会が訪日調査後に発表したミッション終了声明において、日本は外国人労働者など脆弱な対象への不平等と差別の完全な解体が緊急に必要であると指摘されているとおり、日本における外国人の人権問題は深刻な状況です。
2023年6月9日には反対の声を押し切り「出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)が成立しました。人の命にかかわる問題を数の力で強行採決することは許されません。日本の入管行政は、国連人権理事会からは、「無期限の入管収容が国際法、自由権規約と適合しない、収容が行政官吏(主任審査官)裁量であることは問題、入国管理において収容は最終的な手段であるべきだがそれが保障されていない、非拘束措置導入においてその監督措置制度はプライバシーや経済上の不公平問題を招く、子どもの保護措置の欠如」など厳重な指摘がされています。しかし日本政府は、国際人権規約を批准しているにもかかわらず、この指摘に反発し抗議をする状態です。
平和フォーラムは入管法の改悪が明らかにされて以降、移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)と連携し、入管法改悪反対アクションとして、署名活動、国会前シットインなどを展開し、非正規滞在者に対する人道的な在留特別許可を求める声明の拡散などにとりくんできました。
2024年の通常国会においては、政府は「永住者」の在留資格を持つ外国籍住民が税や社会保険料を納めない場合等に永住許可を取消せるような入管法の改悪をしようとしています。軽微な違反によって重要な生活基盤を奪う制度は、外国籍住民の尊厳を軽視し、当該者を不安に陥れる差別的な制度であり、断じて認められません。
永住許可取り消し制度の創設に反対するとともに、引き続き改悪された入管法の再改正と移住者の人権を尊重する制度の構築を求めていかねばなりません。
国際貢献を名目に、実際には労働力確保の手段となり人権侵害の温床となってきた「技能実習制度」は2022年12月から「特定技能制度」とあわせて見直す有識者会議が開催され、2023年11月に最終報告書がまとめられました。そして2024年2月9日の関係閣僚会議では技能実習制度を廃止し、「育成就労制度」を設ける方針を示し今国会で関連法案を提出するとしています。しかし、「特定技能1号」も含めて国際人権基準からかけ離れており、労働者の権利に制約があるままです。地域社会や産業を支える移住者に対し、基本的な人権をまもる制度でなければなりません。
移住連と連携し、日本を終の棲家ときめた外国人が安定、安心して暮らせるよう、「永住者」資格の取り消しの導入の撤廃を求めるとともに、基本的な権利と労使対等の原則に基づいた人権保障がされた制度の創設を求めます。
そして日本に定住・滞在する外国人が安心して生活を送ることができる、多文化共生の社会の実現をめざしとりくみます。
【とりくみ】
①改悪された入管法の再改正と移住者の人権を尊重する入管制度の構築を求め、移住連と連携し、とりくみます。
②収容施設、仮放免措置における処遇の改善、在留資格がない外国人の人権を侵さない制度の確立を求め移住連や関連組織と連携し署名や集会などのとりくみを行います。
③日本で就労する外国人が基本的な権利と労使対等の原則に基づいた人権保障がされた制度の創設を求め移住連と連携しとりくみます。
④日本に在留する外国人への差別、偏見を克服するため、集会や学習会など多文化共生と人権確立のためのとりくみを行います。
(5)ミャンマー民主化支援のとりくみ
2021年2月の軍事クーデターから3年が経ち、ミャンマーでは国軍による抵抗する市民への拷問、虐殺、民主派・少数民族武装勢力と国軍との抗争、さらには厳しい状況下、将来を支えるべき人材が海外へ流出、貿易の激減などで経済活動も衰退、農業など伝統的な産業も途絶えかねない状態です。最近では拘束された市民の子供たちが学校に行かずに働く児童労働も増えており教育も衰退しているとみられています。
民主派・少数民族武装勢力の激しい抵抗で国軍は劣勢に立たされ、勢力の強化を図るべく2024年2月10日から、それまでは志願制であった徴兵制を義務化しました。年間約5万人が徴兵されると推定され、自分の親族に銃を向ける任務にあたりかねず国外脱出を図る若者も急増しています。国際的にも孤立する国軍は停戦調停にあたり、インド洋へのルートとしてミャンマーとの関係を重視していた中国に仲介協力を求め、中国が仲介に乗り出しているとみられていますが先行きはまだ見えていません。
2024年2月5日時点で、国内避難民は235万人、近隣諸国への避難民は55110万人にのぼるとされています。避難地域では避難者は劣悪な環境におかれているとの報告もあがっています。ASEANも支援策を探っているものの連携が取れず、また国軍に阻まれ支援も市民へ届いていません。国連ではミャンマー問題に関する特別チームを立ち上げ、高官ら専門家による現地視察や国軍との交渉を試みていますが成果が見られません。昨年は、総がかり行動実行委員会の呼びかけるミャンマー支援へのカンパ活動にとりくみ、110万円をミャンマー現地での支援グループと連携する在日ビルマ市民労働組合に送りました。
日本は2023年のASEAN友好協力50周年特別首脳会議においてASEAN各国と協力してミャンマー情勢にとりくむことを表明しました。日本政府が、人道危機を克服するという国際世論を造成すること、ミャンマーの民主化を支援する態度を示し行動すること、具体的な支援策を迅速かつ効果的に提案し実行すべきです。支援を必要とする人たちに支援が届き、平和に暮らせる日が早く戻るよう、ミャンマー市民を支援する組織や支援者の方たちとともに集会やカンパ活動を実施するとともに日本政府に対し積極的な行動を求めていかなければなりません。
【とりくみ】
①在日ビルマ人コミュニティなどミャンマー市民の支援組織につながる組織と協力し、集会、カンパ活動などを行い、ミャンマーの支援にとりくみます。
②日本政府に対し、平和的解決のための具体的な行動をとることを求めていきます。
(6)アイヌ民族の権利獲得に向けたとりくみ
2007年に国連総会において「先住民族の権利に関する国連宣言」が採択され、先住民族には、①精神的及び宗教的な伝統、慣習及び儀式を表現し、実践し、発展させ、及び教育する権利、②宗教的及び文化的な場所を維持し、保護し及び干渉を受けることなく立ち入る権利、③儀式用具の使用及び管理の権利並びにその遺体及び遺骨の返還に対する権利が保障されること、そして、国は、関係する先住民族と協力して設けた公正で透明かつ効果的な措置によって、国が保有する儀式用具並びにその遺体及び遺骨へのアクセス並びに返還を可能にするよう努めなければならない」と決められています。もちろん日本政府も批准しており、その規定を守らなくてはならない義務が発生しています。
平和フォーラムは、憲法理念の実現をめざす函館大会で提起して以来、「先住民族アイヌの声実現!実行委員会」(以下実行委員会)に参加し、アイヌ民族の仲間とともに、盗掘された遺骨の返還、アイヌ語など文化の教育、アイヌ民族への経済支援、また、杉田水脈元総務政務官によるアイヌ差別問題などアイヌ民族の権利回復のため、省庁を横断的に結んでチャランケ(政府交渉)にとりくんできました。
自民党杉田水脈衆議院議員のアイヌ民族に対する差別発言に関しても、チャランケの中できびしく追及してきました。中央省庁が差別実態認めることに消極的な中、実行委員会の多原代表が札幌法務局に人権救済の申立をした結果、同法務局は一連の杉田議員の発言を「人権侵犯」と認定しました。杉田議員は「国会答弁の中で謝罪し、ブログも削除した」として改めて話すことはないとし、「アイヌの方を侮辱したとか、差別したという認識はあるか」との記者の問いにも、「全くない」と答えています。このような発言が許されることはなく、実行委員会は、①内閣官房アイヌ総合政策室はヘイトスピーチを差別と認めること、②アイヌ施策推進法第4条のアイヌ差別禁止条項に、差別禁止を国と自治体の責務と位置づける、③罰則規定などを位置づけること、④人権侵犯の救済制度に代理人制を位置づけ、認定を短期間で速やかに行うこと、⑤さまざま出されてきた国連勧告に基づき、パリ原則に則った国内人権機関を設置することなど、チャランケの中で要請しています。
2019年に施行された「アイヌ施策推進法」(アイヌ新法)は、2024年には見直しの年となるため、実行委員会は、アイヌ施策を見直しへのチャランケとともに、「アイヌ政策見直しを求める請願署名」にとりくむこととしました。平和フォーラムは、実行委員会の要請に基づき署名のとりくみを提起してきました。
3月28日、実行委員会は、講師に辛淑玉さんを招き「ヘイトスピーチ・複合差別を許さない、アイヌ民族の先住権を認めろ!3.28院内集会」(衆議院第2議院会館多目的室)を開催するとともに、平和フォーラムを中心に全国から集めた衆参両院議長への請願署名提出(9万3180筆)を行いました。
また、平和フォーラムとして2月12日、「『建国記念の日』を考える集会-差別を許さない!植民地主義とアイヌ民族」を連合会館大会議室で開催し(参加150人)、アイヌ問題の学習を進めました。
【とりくみ】
①「先住民族の権利に関する国際連合宣言」に基づき、アイヌ民族など先住民の権利確立にとりくみます。
②本年に予定されている「アイヌ施策推進法」の見直しに向けて、議論を進め、政府とのチャランケにとりくんでいきます。
③各県運動組織におけるアイヌ民族問題の学習機会の設定にとりくみます。
(7)性差別を許さず、女性の社会進出、地位向上をはかるとりくみ
上川外務大臣が国連やG7関連の国際会議で、日本が「女性・平和・安全保障(WPS)」において主導的役割を果たすと述べていますが、政府の施策は全く追いついていないのが現状です。2023年度の「ジェンダーギャップ報告書」でも、男女格差はアジアで最下位、世界でも下位にあります。日本政府は重大な権利侵害が生じた場合に通報し救済申し立てができる個人通報制度や、重大な権利侵害に対して調査し勧告する国連の女性差別撤廃条約の「選択議定書」も批准していません。男女格差の問題解決のためにあるはずの司法においても、女性の最高裁判事が15人中2人のみです。
家父長制は戦後の民法改正で法的には廃止されましたが、自民党など保守勢力は、妻は夫の扶養のもとにあるという固定観念や性別役割分業意識が存在する社会の状況を、憲法の男女平等の理念に基づいて根本的に変革するどころか、温存しようとしてきました。その結果女性の社会進出がいまだに妨げられています。女性の人権確立に焦点を置き、社会の意識を変えていくためには、私たち自身が真摯に学ぶだけでなく、様々な社会制度を改革、実行していかなければなりません。政府は大企業に対し男女の賃金格差の開示の義務付けをするなどの策を打ち出していますが、このことを通じて当該企業に男女賃金差の改革をせまり、すべての事業所に波及させていくとともに、税制や社会保障制度の改正などにも連動させていかなければなりません。
今年4月には「困難な問題を抱える女性の支援に関する法律(支援新法)」が施行されます。DVや性暴力被害など苦境や困難に直面した女性に最適な支援を届けることを国・公共団体の責務と定め、行政機関に地域と民間団体が協同し当事者の立場になって柔軟に対応することを目的とした画期的な法律です。しかしいまだに周知がされていない、施行に向けて各地域の基本計画が未整備といった課題が指摘されています。法に基づき継続的で安定した支援を実現するために、自治体に正規雇用の女性相談員をおく、複合的な相談に対応できるようスキルアップを図るなどが重要であり、国の十分な財政支援が不可欠です。2023年11月の護憲大会の分科会では、「ジェンダー平等」をテーマに専門家を招き、100人を超える参加者とともに支援新法についての課題を提示し、実際に女性問題の相談にあたる機関をヒアリングした状況を共有しながらとりくむべきことを探りました。
選択的夫婦別姓制度を望む人は増えているにも関わらず、自民党をはじめ保守的な勢力が反対し進展が見られません。戦前の慣習や右翼的な家族観に固執した概念を打破し、憲法の理念にのっとりすべての人のアイデンティティーを尊重する社会を実現するため、とりくみを強めます。
【とりくみ】
①男女格差解消のために、女性の低賃金構造を生んでいる税制や社会保障制度を「家族単位」ではなく個人単位の制度に変えていくことを求めます。
②選択的夫婦別姓制度の法制化を求めます。
③国際基準に則った女性の権利とジェンダー平等を実現するために、国連の女性差別撤廃条約の「選択議定書」を、日本政府が早急に批准することを求めます。
④支援新法の周知、および施行に際しての各地域の体制整備の徹底を、政府、公共団体に求めます。
⑤男女が平等に暮らせる社会が実現できるよう、関係団体などと連携しながら、学習会や集会にとりくみます。
(8)多様な性のありかたを受け入れられる社会の実現にむけたとりくみ
「多様性、人権及び尊厳が尊重され、促進され、守られ、あらゆる人びとが性自認、性表現あるいは性的思考に関係なく、暴力や差別を受けることなく生き生きとした人生を享受することができる社会を実現する」ことが世界的にも明確な基準となる中、日本政府は2023年のG7サミット開催国として対応を迫られる事態となりました。しかし「外圧」を受けて昨年6月に施行された「LGBT理解増進法」は自民党保守派の頑強な抵抗により実効性がない、むしろ差別解消を遅らせる内容のまま成立してしまいました。
さまざまな市民団体や経済団体からもLGBTQへの暴力や差別をなくすために国が制度を整えるべきとする要請が続いています。同性のカップルが結婚できないことに関する裁判では、これまでの6つの地裁の判決のうち5つが違憲または違憲状態、1つが合憲としながらも将来的に違憲となる可能性を示唆しました。
3月14日には札幌高裁が、婚姻について「両性の合意のみに基づいて成立する」と定めた憲法24条1項について「両性という文言だけでなく目的も踏まえ解釈すべき、人と人の自由な結びつきとしての婚姻を定めている」として高裁判断として初めて違憲と判断しました。3月26日には、最高裁が、同性パートナーが犯罪被害者等給付金支給法に基づく遺族給付金を受けられるかが争われた訴訟において、同性パートナーも支給対象になりうるとの判決を示しました。
また2024年3月1日現在、全国の397自治体がパートナーシップ制度を導入し、同性カップルが限定的ながら自治体や民間のサービスを受けられるとりくみも行われています。企業でも同性婚の法制化への賛同を募るキャンペーンが展開され3月7日時点で477企業・団体が賛同、利厚生の配偶者に同性カップルを含むとするなど企業ごとに対応を進めています。しかし自治体、企業ごとに内容は異なり、基本的な民法上の権利は保障されていません。
本来、国が法整備による根本的な解決と、差別を克服するための諸制度の拡充をすべきところ、自公政権はとりくみに極めて消極的であるために、自治体や企業の努力に頼らざるを得ない状況になっています。広範な民意や司法の判断を無視し続け、差別を助長するような言動すら散見される政権与党の姿勢を厳しく批判し、差別の無い、だれもが生きやすい社会を実現するためのとりくみをすすめます。
【とりくみ】
①政府が同性婚の法制化を早急に進めること、LGBTQへの差別や偏見に対し厳格な処分を行うための実効性ある制度を整えるよう求めていきます。
②LGBTQへの差別と偏見を解消するための集会やとりくみに、関係団体と協力しながら参画していきます。
(9)働く者の権利破壊を許さないとりくみ
平和フォーラムはこの間、「関西生コン事件」は国家権力と生コン業界が一体となって仕組んだ労働組合つぶし事件だとして、関西生コンを支援する会(支援する会)と連携し、①大阪広域生コンクリート協同組合(大阪広域協組)の責任明確化、②組合員が不当逮捕・起訴された刑事裁判における無罪判決の獲得、などを求めて6年間余り活動してきました。
刑事事件とされたのは、ストライキやビラまきなど正当な組合活動で、憲法28条の労働基本権を不当に侵害するものであり、労働組合全体の問題として共通認識をもつ必要があります。
事件の本質についての認識と支援が広がるなかで、刑事裁判においては、検察官が不当逮捕された組合員に対する取り調べと称して組合脱退勧奨をくりかえしていた事実があきらかにされる一方、さらに、2023年に2件の無罪判決が大阪高裁で確定したのに続き、2024年2月にもビラまきが威力業務妨害だとされた事件で7人の組合員に大津地裁で無罪判決が出されたのち検察の控訴断念で早々と無罪が確定しました。「関西生コン事件」の本質が、業界・警察・検察が一体となった組合つぶし事件であったこと、検察の捜査と起訴がいかに恣意的なものであったかが明らかとなりました。
ところが、この流れに逆行して、中央労働委員会は、2023年大阪広域協組による一連の労働組合排除指示を肯定すると同時に、旭生コン事件(2023年4月)、三和商事事件(同年8月)、寝屋川コンクリート事件(同年9月)において、大阪地労委の判断を覆す命令を相次いで出しました。労働者と労働組合の団結権救済機関としての使命を放棄して、大阪広域協組の組合つぶし攻撃に加担しているような姿勢は許されるものではありません。
組合側は、中労委の不当な命令取り消しを求める行政訴訟を2023年11月に東京地裁に提訴しており、支援する会と連携して、引き続き中労委対策をすすめます。
また、全日建は警察・検察・裁判所による違法な捜査、逮捕令状発付と起訴、長期勾留、そして、組合活動を禁止する憲法違反の保釈条件などについて、国(検察と裁判所)と滋賀、和歌山、京都の各府県(警察)を相手取って提訴した国家賠償請求訴訟は、争点整理が終わりつつあり、夏以降に証人尋問が開始される見込みです。
一方で、フェイク動画等の影響で事件の真相が理解されていない現状があることから、映像を通し事件の真実を広く訴えようと、2022年秋に全日建が制作したドキュメンタリー映画「ここから『関西生コン事件』と私たち」を、平和フォーラム加盟組織や各地方組織の協力も得て、各地で上映してきました。2023年10月には韓国語版も完成し、韓国においても上映運動が始まっています。引き続き、関西生コン事件の真実が広く社会的に理解されるよう、各地の支援する会などが開催する上映会のとりくみに協力していきます。
平和フォーラムは、引き続き支援する会と連携し、裁判闘争や労働委員会闘争の支援をするとともに、関西生コン事件の真相を明らかにするための「ここから」の上映活動と連動させた、各地で開催される学習会やオルグ活動にも協力していきます。
【とりくみ】
①関西生コン事件の本質が、生コン業界と警察・検察による組合つぶしであることを広め、支援する会と連携し権力による不当弾圧を許さないとりくみをすすめます。
②裁判闘争や労働委員会闘争の動向を注視します。とりわけ、中労委対策を強化し団体署名の実施など必要な対策を強化します。また、刑事裁判においてひとつでも多くの無罪判決を勝ち取るべく、「陪審員裁判」を模した集会や再現ドラマを企画するなど、理解と共感を広げる活動をすすめます。
③各県組織や各都道府県組織がとりくむ、映画「ここから『関西生コン事件』と私たち」の上映会を通して、権力による不当弾圧の実態を広範な人びとに伝えるとりくみを推進します。
④関西生コンを支援する会の会員拡大に努めます。
5.民主教育を進めるとりくみ
(1)教科書に対するとりくみ
2024年度から文科省は、全国の小学5年から中学3年までの外国語教科書を従来までの紙と合わせて、デジタル教科書で配付しています。今後、算数・数学の教科書を順次デジタル教科書にしていく構想です。急速にデジタル化が進む学校現場において、子どもたちの主たる教材である教科書が紙ではなくなることによる、教育効果の検証が十分行われているとは言い難い状況にあります。最も大切な観点は、デジタル化が子どもの豊かな学びにつながるか、だと考えます。視力への影響も懸念される部分があり、身体的影響の検証も追いついていません。デジタル化が学校現場の実態を踏まえた導入となるよう、広く社会的な課題として捉えていく必要があります。
子どもたちの主たる教材である教科書は、各教科書会社が作成したものを「教科用図書検定委員会」が検定し、合格した教科書の中から、実際には各採択地区で検討されたのちに採択をされ、決定します。特に2000年代以降、「教育に対する国家統制」とも言われるように、記述内容について「政府見解を必ず載せる」といった通知文が発出されるなど、政治とは無関係であるはずの「教育の独立性」が脅かされる事態が相次いでいます。
中学校の教科書の新しい検定結果が公表されましたが、申請された教科書のうち歴史の2点について、公表前に検定内容が外部に漏れていたとして、合否が決定しない「未了」となる前代未聞の事態となっています。文科省は検定手続きを精査し、後日、結果を公表するとしています。記述内容について外交問題に発展することも想定されることから、どういった結果になるのかについては注視していく必要があります。
この新たな検定を経た教科書の採択が今夏、各採択地区で行われます。平和フォーラムは、全国各地で開催される教科書展示会への参加を呼びかけるとともに、各教科書の特徴を整理した資料を作成する予定です。
戦争被害の歴史はもちろんのこと、戦争加害の歴史についてもしっかり向き合うことが重要だとする観点から、過去の歴史を歪曲化しようとする「歴史修正主義」の教科書の問題点を明らかにする必要があります。
子どもの豊かな学びを支える教育環境に、大きな影響を与えることになる教科書。広範な市民の意見と学校現場の考えを基に、今夏の各採択地区での教科書採択が正しく実施されるよう、注視していく必要があります。
(2)道徳教育課題に対するとりくみ
平和フォーラムは道徳研究会と協力して、人権を大切にした教育実践例を紹介する「道徳教科書/もうひとつの指導案―ここが問題・こうしてみたら?」とするホームページを運営しています。年間数回にわたる研究会を開催し、教科書を一面的につかうだけではない「もうひとつの指導案」の例示を中心に、内面を評価することや道徳的価値を押し付けることにならないよう配慮した実践を紹介しています。
今後も、多忙を極める学校教育現場の一助となるよう、実態を基にした実践紹介などを中心に一層の充実に努めていきます。
【とりくみ】
①政権の意図に偏った恣意的な教科書検定の実態を明確にし、全国の市民団体および韓国のNGO「アジアの平和と歴史教育連帯」とともに、バランスのとれた教科書の記述内容を求めてとりくみをすすめます。
②憲法改悪反対のとりくみと連動し、「修身」などの復活を許さず、復古的家族主義、国家主義的教育を許さないとりくみを展開します。
③人に優しい社会へのとりくみをさまざまな方向から強化し、貧困格差を許さない方向からも、教育の無償化へのとりくみを強化します。
④歴史教育課題・道徳教育課題に対応するため、問題・課題を共有し授業実践の還流を目的としたホームページを市民等の協力のもと、人権を大切にする道徳教育研究会に協力して「道徳教科書/もうひとつの指導案―ここが問題・こうしてみたら?」(https://www.doutoku.info)を運営していきます。
6.核兵器廃絶にむけたとりくみ
(1)核廃絶の実現に向けて
ⅰ)原水禁運動の基本として
原水禁は広島・長崎での被爆の実相を出発点として、「核と人類は共存できない」を基本理念に据え、加害と被害の歴史にそれぞれ向き合いながら、国内外の市民、諸団体と連帯し核廃絶に向けたとりくみをすすめてきました。
広島・長崎に次ぐ三度目の核兵器使用には至っていませんが、これまで何度も人類は核戦争直前の危機に直面してきました。また、繰り返されてきた核開発と核実験によって世界各地に多くの核被害を生み出しました。核廃絶と世界平和の実現は世界の人びとにとって切実な願いであり、20世紀中期以降、国際的反核運動のうねりとして現れ、原水禁もその一翼を担ってきました。
しかしながら、いまなお核廃絶は実現しておらず、日本においても核抑止論の壁を打ち崩すことはできていません。2024年は被爆から79年目を迎えることになります。被爆者もいっそう高齢化しつつあるいま、あらためて原水禁として核廃絶に向けた決意を打ち固め、いかに運動をすすめていくのかが問われています。
冷戦期をピークとして核兵器の保有数自体は減少してはいますが、この間、保有国においては兵器の小型化と技術の向上がさかんに行われていることから、核軍縮に向かっているとは到底言うことができません。この間、アメリカは核兵器の「近代化」を積極的に推し進めてきました。中国は核弾頭数を増強しています。また、インド・パキスタン・朝鮮がすでに公然と核兵器保有に至り、イスラエルも核兵器保有が確実視されています。さらにイランの核開発に向けた動きが注視されています。
こうしたなかで核兵器禁止条約(TPNW)と核拡散防止条約(NPT)が、核軍縮・廃絶をめぐる国際的な動向の中心的な軸となっています。
核戦争の危険性が現実性を帯びる緊迫した情勢にありますが、だからこそ核保有国を正当化するような核抑止の論理がつくりだした現状として捉え、ウクライナをめぐる欧米とロシアの対立軸のとなっている北大西洋条約機構(NATO)も含めて、全面的な批判・検証が必要です。そして、これらに対抗する国際的な世論形成をもって核軍拡への道を阻みつつ、「核なき世界」へと踏み出す人類史的な契機とすべきです。
ⅱ)核兵器をめぐる世界の動き
2022年2月に開始されたロシアによるウクライナ侵攻は、平和を願う多くの人びとにたいへんな衝撃を与えました。とりわけ、そのなかで行われている核兵器使用の威嚇や原発への攻撃・占拠は、この間、核軍縮に向けた積み重ねを踏みにじる暴挙です。
軍事同盟であるNATOの拡大や、ウクライナ東部のロシア系住民に対する迫害を口実にしていますが、いかなる理由があろうとも、断じて許すことができない蛮行であり、抗議の声をあげ続けていかなくてはなりません。
さらに、泥沼化する戦況のなかでロシアによるベラルーシへの戦術核の搬入がすすめられているとされ、また、ザポリージャ原発などをめぐっては占拠のみならず直接攻撃の対象ともなり、深刻な事態が続いています。
アメリカとの対立姿勢を強めるロシアは、11月2日、包括的核実験禁止条約(CTBT)の批准を撤回しました。ロシアは発効要件国のひとつであり、これまで署名・批准した国の中で最大の核兵器保有国でした。そのロシアがCTBTの批准を撤回したことは、核軍縮へ向けたこれまでの国際的な積み重ねを揺るがすものです。
2023年10月から始まったイスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区への軍事侵攻はいっそう深刻化しつつあり、すでに多くの一般市民を殺害したうえ、多くの市民が避難している地域への集中攻撃に手を染め、もはや「ジェノサイド」というべき域に至っています。
パレスチナ市民の生存自体を否定するような軍事展開がすすむなか、11月6日、イスラエルのアミハイ・エリヤフ エルサレム問題・遺産相がガザ地区への核兵器使用を「それも一つの選択肢だ」と発言しました。
これには批判が集中し、職務停止処分となりましたが、イスラエルは事実上の核保有国であり、この間のロシアと同様、戦争のエスカレートが、歯止めなく核兵器使用へと進みうるという現実性を示しています。
原水禁は11月14日に声明「ロシアのCTBT批准撤回とイスラエルの閣僚による原爆投下容認発言 どちらも許さず、改めて核廃絶を強く訴える」を発表し、こうしたロシア・イスラエルの動きを批判しています。
アメリカの「核態勢の見直し(NPR)」をめぐっては、バイデン大統領は「米国の核兵器使用は、核攻撃の抑止と、米国や同盟国への核攻撃に対する報復に限られるべき」という立場だとされていますが、この間トーンダウンしているのは同盟国、つまり日本政府が抑止力の低下を懸念して働きかけを行っているからとみられます。
いっぽう、中国はアメリカとの対抗関係が強まるなかで、運用可能な核弾頭を約500発へと増強したとされています(2023年10月、アメリカ国防総省発表による)。また、朝鮮は米韓との対決姿勢を強め、大陸間弾道ミサイル(ICBM)発射実験などを繰り返したほか、水中核兵器システム実験に着手し、核による攻撃能力保持をアピールしています。
核と戦争をめぐる危機的状況を反映し、科学誌「原子力科学者会報(BAS)」は、いわゆる「終末時計」の針が人類滅亡まで「残り90秒」まですすんだと発表しています。これは2023年に引き続き最短の残り時間です。
核兵器をめぐる世界情勢は、たいへん厳しいものがありますが、そうしたなかで発効から3年を迎えた核兵器禁止条約(TPNW)への期待がより高まっている状況があります。
2017年7月に採択されTPNWは、人道的立場からNPTを補完するものとして2021年1月に発効しました。2024年1月現在、署名国は93か国(地域)、批准国は70か国(地域)となり、参加が拡がり続けています。
ⅲ)日本政府は戦争被爆国として役割を果たせ
2023年5月下旬、広島でG7サミットが開催されました。これは岸田首相の肝煎りによるものでしたが、ロシア・ウクライナ戦争の継続という世界情勢下にあって、そして被爆地広島において、核保有国と「核の傘」の下にある各国によって、いったいどのような内容が議論されるのが問われることになりました。
しかし、G7の日程のなかでは原爆資料館見学と被爆者との面会あわせて40分程度行ったにとどまり、発表された「核軍縮に関する広島ビジョン」についても「核抑止論」肯定を前提としたもので、核の先制不使用宣言やTPNWについてはいっさい触れることなく、具体的な核廃絶への道筋を示すものではありませんでした。
日本はこの間も核保有国と非保有国の「橋渡し役」を自称しながら、一貫してTPNWへの不参加の態度を変えることがありませんでした。しかしすでに発効し締結国会議も開催されているいま、早急に方針転換することが必須です。
原水禁はこの間、広島原水禁ととともに岸田首相に対する要請行動にとりくみ、TPNW批准と核保有国の先制不使用宣言に向け役割を果たすべきと訴えてきました。
また、G7直前の5月17日には広島市・広島YMCA国際文化ホールにおいて、「『ヒロシマ』のおもい、核兵器廃絶のおもいを世界へ5.17原水禁集会」を開催し約200人が参加、核の先制不使用宣言とロシア・ウクライナ戦争を終わらせるための外交努力を求めました。
9月19日、岸田首相は核兵器用核分裂性物質の生産を禁止するカットオフ条約(FMCT)の記念行事でFMCT早期交渉開始やNPT体制の「堅持と前進」を主張、また国連総会の一般討論演説では30億円を拠出して「核兵器のない世界に向けたジャパン・チェア」を設置するなどと発言したものの、あいかわらずTPNWについては触れていません。
11月27日~12月1日、アメリカ・ニューヨークで開催されたTPNW第2回締約国会議には、日本は前回同様、オブザーバー参加すらしませんでした。
12月8・9日には長崎市内で「国際賢人会議第3回会合」を開催、岸田首相はここでも「核兵器のない世界」に向け、「強いリーダーシップを発揮していく決意」を表明しています。
2024年1月30日の施政方針演説においても岸田首相は「核兵器のない世界」であるとか「ヒロシマ・アクション・プラン」に触れたものの、相変わらずTPNWには言及しませんでした。
3月18日、国連安全保障理事会は「核軍縮・不拡散」をテーマに閣僚級会合を開催しました。ここではアメリカがロシアの核による威嚇や中国の核弾頭増強を非難し、それに対してロシア、中国が反論する展開になりました。
このなかで、日本の上川陽子外相は、兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT、カットオフ条約とも)の交渉開始に向け、賛同国12か国による「FMCTフレンズ」の設立を表明しています。これは昨年8月の核拡散防止条約(NPT)再検討会議で岸田首相が提唱した「ヒロシマ・アクション・プラン」のもとで核軍縮をすすめようという日本政府の態度をあらためて示したかたちです。
アメリカ共和党のティム・ウォルバーグ下院議員が、3月25日、地元ミシガン州での演説で、パレスチナ自治区ガザ地区の戦争について「手っ取り早く終わらせるため、長崎や広島のような」爆弾を投下すべきだと発言したことに批判が拡がっています。ところが、4月3日の外務委員会での質問に対し、上川外相は、「ウォルバーグ議員が25日に核兵器使用を容認するかの発言を行い、メディアを通じて拡散していること」をたいへん憂慮しているが、釈明動画を出したことを理解し、政府として抗議することが必要な状況ではないと答弁しています。
ここまで見てきたように、岸田首相はことあるごとに被爆地広島の選出議員であることをアピールしながらも、戦争被爆国の政府首脳として果たすべき役割、すなわち核抑止論に立ち向かい、核兵器廃絶に向けた具体的な行動に踏み出すことは、終ぞありませんでした。
岸田首相は単に決意表明を繰り返すのではなく、まずはTPNWへの積極的な関与の表明など、日本政府自身が核廃絶に向けた具体的なステップをすすめるべきです。そして、核保有国に対しては先制不使用宣言を求めるなどの外交努力を果たすべきです。
ⅳ)世界の市民と連帯して原水禁運動をすすめよう
元・高校生平和大使(第24代)の大内由紀子さんを中心に結成された「Connect Hiroshima」が呼びかけた署名「核兵器禁止条約第2回締約国会議へのオブザーバー参加を求めます」には原水禁としても協力してきました。10月31日には外務省に対し計43288筆を提出し、日本政府としての積極的な行動を求めました。
原水禁も参加する「核兵器廃絶日本NGO連絡会」は日常的な諸団体・個人の情報交換をすすめるいっぽう、連絡会を窓口とした外務省との交渉や「ICAN」事務局長との意見交換、あるいはイベント活動などを行ってきました。連絡会が主体となった「核兵器をなくす日本キャンペーン」展開にも協力しています。
また、原水禁・連合・KAKKINの3者の枠組みで、核保有国に対する要請書提出行動を、2023年度には以下の日程で行ってきました。
フランス大使館(7月26日)/アメリカ大使館(8月31日)/中国大使館(9月22日)
/ロシア大使館(9月25日)/イギリス大使館(9月26日)
引き続き日本政府や各国政府に対する要請などを行うとともに、「核兵器廃絶日本NGO連絡会」をはじめとする諸団体・個人と協力しながら、核兵器廃絶を求める世界的なうねりをつくりだすためにとりくんでいきます。
2023年11月27日から12月1日にかけ、アメリカ・ニューヨークで開催されたTPNW第2回締約国会議が開催されました。日本は不参加でしたが、そのいっぽうでNATO加盟国で「核の傘」の下にあるドイツ、ノルウェー、ベルギーがオブザーバー参加したことには注目されます。
採択された政治宣言では、いかなる核兵器の使用や威嚇も国際人道法に違反するものとし、この間みられた非核兵器国に核兵器を設置しようとする動きを批判しました。そして核抑止が核不拡散に反し核軍縮を妨害しているとも指摘、核兵器の非正当化と汚名化を進める決意を、前回に引き続き表明しました。
また、核抑止論に非人道性やリスクに関する科学的論拠に基づいて対抗していくことを次回(2025年3月開催予定)に向けた課題として確認しています。
原水禁はこの締約国会議にあわせ、谷事務局長を中心に代表団をニューヨークへ派遣しました。同行したメンバーは高校生・大学生という若い世代で構成され、現地の市民団体とも協力しながら、核兵器廃絶を訴える諸行動にとりくみました。
原水禁としてはワーキングペーパーを提出したほか、今回は締約国会議のなかで市民社会からの発言枠を獲得し、同行した高校生・大学生がスピーチすることができました。また、国連周辺での市民集会などにも参加、発言を行いました。これらの高校生・大学生の活動は注目を集め、多くのマスコミ報道がありました。なお、派遣期間中は現地から日々活動報告を原水禁ウェブサイトに掲載し、情報発信に努めました。
原水禁としては、国際会議などのへの代表団派遣にとどまらず、国際社会への発信や諸団体・個人とのさまざまなレベルでの交流を、引き続き追求していきます。
(2)高校生平和大使の活動
8月19日から26日にかけ、第26代高校生平和大使22人をはじめとした派遣団は、スイス・ジュネーブの国連軍縮部訪問と核廃絶を求める署名提出を中心とした諸行動にとりくみました。
4年ぶりとなる欧州派遣であり、手探りのなかでの実施ではありましたが、高校生たち一人ひとりのがんばりのなかで、英語でのスピーチや交流を成功させました。そして、4年分の署名62万4939筆分の目録を手渡すことができました。また、国連軍縮会議傍聴の際には、各国代表の発言のなかで複数の好意的言及も受けました。
26日の長崎での帰国報告会には支援者のほかマスコミ各社も参加し、今回のとりくみについての報道は全国に配信されています。困難な国際情勢のなかですが、被爆国の若者が活動を継続することへの期待と注目は、いっそう増しています。
この成果を踏まえつつ、2023年12月17~19日、一昨年に続いて「東京行動」を実施しました。各国大使館や国会議員訪問などをとりくんだほか、核兵器をめぐる国内外の情勢の学習と第五福竜丸展示館の見学を行いました。
こうした高校生平和大使としての集団的なとりくみだけではなく、それぞれの地域で、地域選出の高校生平和大使と高校生1万人署名活動メンバーによるとりくみも行われています。定例的な署名活動や学習会、さまざまな集会での核廃絶を求めるアピール活動は多くの市民に好意的に受け止められています。
原水禁は、今後も「高校生平和大使を支援する全国連絡会」を通じ、若者のとりくみ、被爆体験の継承課題にかかわるとりくみをすすめていきます。とくに、OPのネットワークづくりに着手しつつあり、その一環として原水禁広島大会の「子どものひろば」の企画運営を大学生・高校生に協力してもらい、長崎大会では開会行事での報告や署名活動、若者行事「ピースブリッジ」開催などを行いました。
(3)「原水爆禁止世界大会」と「3.1ビキニ・デー」の開催について
原水禁世界大会はこの間、福島・広島・長崎の現地に、全国から結集するかたちで行われてきました。開会・閉会総会や分科会、フィールドワークを通して被爆の実相を学び、議論するなかで反核平和に向けた思いを共有し、次代へと継承するうえで大きな役割を果たしてきました。
この間、コロナ禍のなかで規模縮小をやむなくされてきましたが、2023年については現地実行委員会の皆さんと協議しながら従来規模での開催を追求し、準備を行ってきました。
そのうえで「被爆78周年原水爆禁止世界大会」は、7月30日福島大会、8月4・5・6日広島大会、7・8日長崎大会の日程で開催し、福島・約550人(全体集会)、広島・約2100人(開会総会)、長崎・約800人(開会行事)の参加がありました。国際シンポジウムについては広島では「核兵器廃絶に向けた道筋をえがく」を、長崎では「放射能汚染水の海洋放出に反対する」をテーマにそれぞれ開催しました。
長崎大会では台風接近により9日の閉会総会や平和行進をとりやめる苦渋の決断を行いましたが、そのほかはおおむね予定通りの開催でやりぬくことができました。
全体として、核兵器をめぐる世界情勢や汚染水放出などの国内状況を大会内容にしっかり反映することができました。また、各大会ともに多くの初参加者がいることを踏まえた分科会運営を心がけ、この間の課題として据えてきた「被爆の実相の継承」「運動の熱の共有」に向け実りのあるものとなったと考えます。また、育児スペース確保や、高校生をはじめとした若い世代の企画への参加・協力など、この間指摘・要望を受けてきた課題へのとりくみにも着手しました。
被爆者の高齢化がすすむなか、「被爆の実相」を継承していくことは喫緊の課題です。また、核廃絶に向けた決意を共有していくうえで、原水禁大会の果たすべき役割は重要なものとなっています。この間とりくんできた映像配信やSNSなども活用しながら、とくに若い世代の参加をいっそう拡大していくことをめざしていきます。
いっぽうで、物価高騰と旅行需要の高まりのなかで宿泊費が急騰し、また予約が取りづらい状況が続いています。各大会に参加するにあたっての負担の増大が顕著になっています。各大会がこれまで果たしてきた役割と果たすべき役割についてしっかり議論しながら、多くの市民が参加しやすい大会運営の追求、とりわけ今後の開催日程や内容についての検討をすすめる必要があります。
このことをあらためて確認しながら、被爆79周年となる2024年の大会開催に向け、準備をすすめていきます。2025年には被爆80周年を迎えることも見据えながら、国際・国内情勢に対応した内容をつくっていきたいと考えます。
1954年3月1日、ビキニ環礁でのアメリカによる水爆実験によって、「第五福竜丸」をはじめとする日本の漁船が被爆しました。このことをきっかけに日本における原水爆禁止運動が大きく拡がりました。私たちはこの被害の実相を継承し、核廃絶の決意を確認するため、毎年3月1日に静岡での集会を行ってきました。
2024年3月1日、静岡市・静岡商工会議所静岡事務所会館ホールで「被災70周年3.1ビキニ・デー全国集会」を開催し、全国から約180人が参加しました。
中村桂子さん(長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)准教授)から「核兵器廃絶に向けた世界の動きと私たちの課題」と題した講演を受けたほか、大内由紀子さん( Connect Hiroshima )からTPNW第2回締約国会議派遣報告、ビキニ市民ネット焼津・かまぼこ屋根の会による地域での市民のとりくみ報告、静岡選出の高校生平和大使からはマーシャルの若者との交流をはじめとした発動報告がありました。70年の節目の年にあってビキニにおける被爆の実相を風化させず継承することの重要性と、さまざまなかたちで核廃絶に向けたとりくみをいっそう強化していくことを確認し合うことができました。
なお、翌2日には焼津市・弘徳院で、第五福竜丸の乗組員で被爆後亡くなった故・久保山愛吉さんの墓前祭を執り行い、あらためて核廃絶を誓ったほか、焼津市歴史民俗資料館のビキニ事件関連展示を見学し、ビキニ事件がもたらした被害についての学習を深めました。
【とりくみ】
①核兵器廃絶にとりくむ国内外のNGO・市民団体との国際的な連携強化をはかり、日本国内の核兵器廃絶にむけた機運を高めるため、核兵器廃絶にむけたとりくみを進めます。
②米国の中距離核ミサイル再配備に反対し、「非核三原則」の法制化を含めたとりくみを強化します。
③原水禁・連合・KAKKIN3団体での核兵器廃絶にむけた運動の強化をはかります。NPT再検討会議をはじめ、核保有国大使館への要請行動などに協力してとりくみます。
④東北アジア非核地帯化構想の実現のために、日本政府やNGOへの働きかけを強化し、具体的な行動にとりくみます。さらにアメリカや中国、韓国などのNGOとの協議を深めます。
⑤非核自治体決議を促進します。自治体の非核政策の充実を求めます。さらに非核宣言自治体協議会や平和首長会議への加盟・参加の拡大を促進させます。
⑥政府・政党への核軍縮にむけた働きかけを強化します。そのためにも核軍縮・不拡散議員連盟(PNND)や国会議員と連携したとりくみをすすめます。
⑦日本政府に対し、「核兵器禁止条約」への署名・批准を求め、被爆国として核兵器廃絶にむけた積極的な役割を果たすよう追求します。
⑧日本のプルトニウム増産への国際的警戒感が高まる中、再処理問題は核拡散・核兵器課題として、プルトニウム削減へのとりくみをすすめます。
⑨「高校生平和大使を支援する全国連絡会」を通して、高校生平和大使、高校生1万人署名活動のサポートなど、運動の強化をはかります。また、SNSなどを使い若者へむけた情報発信を強めます。
⑩核軍縮具体策としての核役割低減、先制不使用、警戒態勢解除、核物質最小化等の内容を広く情報発信します。
7.原発再稼働を許さず、脱原発を実現するとりくみ
(1)能登半島地震と志賀原発
今年1月1日に発生した震度7の能登半島地震によって、北陸電力・志賀原発敷地内外で施設被害が発生し、1・2号機の変圧器(3機あるうちの)2機が破損し、(3系統ある)電源の2系統が使えなくなるという事態が発生しました。現在かろうじて残る1系統の電源で燃料プールを冷却する状況にあり、一歩間違えば重大事故の可能性すらありました。変圧器の破損によって絶縁油が漏出、一部は海にまで流出しました。さらに地震の揺れで、建屋上部にある核燃料冷却プールも大きく揺れ、周囲を囲っている1メートルほどのフェンス(壁)から冷却水が外に1万数千リットルもあふれ出ました。また志賀原発にも3メートルの津波が到達していたことも明らかになりました。
モニタリングポストも18か所が故障し、測定できなくなりました。放射性物質の敷地外の漏洩監視という重要な機能が失われることは深刻な問題です。今回の地震では1号機地下で震度5強を観測したとされていますが、一部の機器で加速度が設計の想定を上回ったことも報告されています。福島原発事故以降、基準地震動を600ガルから1000ガルに引き上げ耐震対策を講じましたが、今回、志賀町内で2828ガルを観測した地域もあり、志賀原発の耐震対策が十分であったかも問題にしなければなりません。
今回の地震によって能登半島各地の道路で寸断、土砂崩れ、隆起・陥没などが発生し、救援活動に大きな障害をきたしています。漁港も隆起や陥没により使用できなくなり、一部では海上からの救援活動も困難になりました。
原発の放射能漏れなどが起きなかったことは幸いでしたが、万が一起きた場合は、避難や救援がさらに困難になることは明らかで、避難計画を根本から見直すことが必要です。原子力規制委員会は、1月17日に「屋内退避」などの指針見直しを表明しており、今後の議論を注視する必要があります。
しかし屋内退避すべき建屋そのものが倒壊や防災拠点の損傷が相次ぐ中で、屋内退避することができない状況が明らかになりました。車両の通行も不可能になり、孤立する集落も現れるなど、原発事故との複合災害になれば、被害はさらに拡大していくことは明らかです。
志賀原発2号機は、2025年度中の再稼働を目指していますが、複数の断層が集中する能登半島で、避難や復旧が容易でないことが明らかになり、再稼働より「廃炉」が必要なことを示しています。
2月29日、石川県平和運動センターなどと共同で、志賀原発の廃炉を求め、政府や経済産業省、原子力規制委員会への要請行動を行いました。特に地震の影響で家屋の倒壊、道路の寸断などによって避難が困難となる実態が明らかになり、原発事故などが重なる複合災害への対応を考えると原発の再稼働は許されないと訴えました。また、北陸電力は、志賀原発の被災状況を小出しにしており、情報の全面公開と視察等を受け入れるよう要請しました。
その結果、3月18日には志賀原発の視察に入ることができました。発生から2ヶ月以上が経過していたこともあり、「不都合な状況」が見受けられないよう一定の整理をした上で視察を受け入れたことは、透明性のある情報公開とは到底言えません。
今後も原水禁として、地元と協力し廃炉に向けたとりくみを強化していきます。
(2)山積する福島第一原発をめぐる課題へのとりくみ
ⅰ)困難な廃炉作業と汚染水の海洋放出
8月24日から始まった放射能汚染水の放出は、今年3月17日に4回目の放出で2023年度の放出を終えました。今年度は、タンク約30基分にあたる約3万トン分を4回に分けて放出しました。含まれるトリチウムの総量は約5兆ベクレルでした。これは年間放出量の上限の22兆ベクレルの2割余りでしたが、来年度は約5万4600トンを7回に分けて放出するとしていますが、今後もこの放出が30年間も繰り返し行われることになっています。
10月25日、汚染水を処理する多核種除去設備(ALPS)の配管洗浄作業中にホースが外れ、作業員5人が放射性物質を含む洗浄水を浴びて2人が入院する事故が発生しました。入院した2人の作業員は、着用が義務づけられていたカッパを着けていなかったことが明らかになりました。当初100ミリリットル程度と説明されていた飛散が数リットル飛散と訂正し、入院した作業員を1次下請け説明していましたが、3次下請けであることがわかるなど、緊張感の欠如と管理体制の不備が露わとなりました。これには、11月1日の原子力規制委員会の定例会合で石渡明委員が「説明が変わるたびに数字が大きくなる」と不信感をあらわにしました。
また東京電力は、今年に入っても2月7日に汚染水の浄化装置から汚染水が屋外に漏れるトラブルを起こしました。東京電力は、装置内の配管の弁が開いたままになっているのを作業員が見落としたまま、水を通す作業を行ったことが原因だとしています。しかし、原子力規制庁は、東電内で弁の開閉を管理する部署が明確でなく、作業前に弁の状態が管理できていなかったなどとして、作業ルールや安全対策を定めた「実施計画」の違反であると指摘しています。放出から1年も経たないうちにトラブルが続出することは、今後長期にわたり安心・安全な作業を果たしていけるのかが極めて疑問です。
東京電力は、廃炉完了の目標とする2051年までに処理水の放出を終える方針ですが、デブリ(溶融核燃料)が残る限り汚染水は発生し続けます。政府と東電は2041~51年までにデブリを取り出し、廃炉を完成させる計画でしたが、先行している2号機での核燃料デブリの試験的な取り出しについて、作業が難航していることから、目標としていた今年度中の開始を断念し、改めて今年10月までの開始を目指すことを1月下旬に発表しました。取り出し開始の延期は3回目で、廃炉の難しさが改めて浮き彫りになっています。
日本原子力学会で廃炉の問題を検討する委員会のトップを務める宮野廣さんは、朝日新聞のインタビューで「廃炉の本丸はこれから」と指摘し、51年までの「廃炉完了」は技術的に「あり得ない」と述べています。完了30年先の道筋が見えない中で、長期に渡っての作業を、緊張感を持ってやり続けることができるのか、今回の事故であらためて課題となりました。
長期に渡る海洋放出は、海洋の生態系にどんな影響を与えるのかは未知数です。現に長期に渡る環境影響評価はなされていません。燃料デブリを通過する汚染水には、トリチウムだけでなく60種を超える核種があり、中には半減期の長いものも含まれ、通常の原発からの放出と異なっています。
そのような現状の中で、安易に「30年」で終了するかのような幻想を振りまき、海洋放出を正当化するのはあまりにも無責任です。
この間、汚染水放出に対して原水禁や原子力資料情報室などと「ミライノウミプロジェクト」を8月30日に立ち上げ、インターネットを使っての動画配信等のとりくみを通じて問題点を明らかにしています。また、「『ALPS処理水』の海洋放出を直ちに停止することを求める署名」を展開し、全国に協力を求めてきました。この署名は、4月24日に国に提出する予定にしています。「さようなら原発1000万人アクション実行委員会」は放出が強行された8月24日にちなみ、この間、毎月24日に抗議行動を行ってきました。9月~11月は首相官邸前での抗議行動(各回参加者40人~50人)、12月24日には、銀座デモ(参加者約100人)、1月24日は官邸前での抗議集会(19人)を行ってきました。なお、放出開始から1年にあたる8月まで、首相官邸前などでの抗議行動を行う予定です。
また、事故から13年にあたる今年の「原発のない福島を!県民大集会」を、3月16日に福島市でひらかれました。当日は、全国各地から1100人があつまり、福島の様々な現状報告や能登半島地震と志賀原発の問題などが報告されました。
また、この集会から3月20日のさようなら原発全国集会までを期間として「フクシマ連帯キャラバン」にもとりくみました。福島県浪江町対馬地区のみなさんとの交流、東海第二原発のUPZ圏内(30キロ圏内)の市町村への申し入れなどを行い、あらためて「フクシマを忘れない」「脱原発の実現を!」と力強く声をあげました。
ⅱ)避難生活に対する政府支援の打ち切りを許さないとりくみ
2022年12月現在で、福島県内に6392人、県外に2万1392人、避難先不明5人の合計2万7789人が、今なお避難生活を余儀なくされています。さらにこの数字に含まれない自主避難者なども多数おり、福島県・復興庁の調査では十分に実態が把握されていないのが現状です。
避難解除された地域では、復興拠点を中心に町の再生が進められていますが、商店街や医療施設などのインフラの整備が進まず、就労する産業も進んでおらず、帰還者は、元の人口の1~2割程度に留まっています。長期に渡る避難で、生活の場が移ったことも大きく、復興・再生には多くの課題が残っています。
一方で、避難指示解除に合わせて住宅支援などの補償が打ち切られ(県内の災害公営住宅からの退去など)、避難者は生活の基盤が失われる状況に追い込まれています。また自主避難した被害者に対する住宅支援打ち切りと追い出しが強制的に行われ、この問題については裁判も行われています。被害者に寄り添う保障の実現に向けてとりくみを進めていきます。
ⅲ)国や東電の加害者としての責任を明確化するとりくみ
福島原発事故に対する東京電力旧経営陣3人に対する刑事責任を訴えた「福島原発刑事訴訟」について東京高裁は、1月18日に旧経営陣を「無罪」とする判決を出しました。裁判では、政府の地震調査研究推進本部が公表した「長期評価」の信頼性と、巨大津波が原発を襲う可能性が争点となりましたが、高裁は東京地裁に続きこれを認めませんでした。
しかし「福島原発刑事訴訟」結審後に判決が示された東京地裁での旧経営陣に賠償を求める「東電株主代表訴訟」の民事裁判では、上記「長期評価」の信頼性を認め、旧経営陣4人が対応を怠ったとして、過去最高額の13兆円余りの賠償を命じました。刑事訴訟も民事訴訟も重要な証拠や論点はほぼ同じでしたが、結果は逆のものとなりました。
「刑事訴訟」では、東京高裁に対して原告側が、裁判長の現場検証とあらたな証人尋問および結審後に出た「東電株主代表訴訟判決」の証拠採用と弁論再開を求めてきました。しかしこれらはことごとく採用されなかったことから、刑事訴訟の「無罪」判決は、とうてい納得できるものではありません。
刑事訴訟は原発事故の最終的な責任を「誰が」取るのかを問うものでしたが、そのことに対する判断は示されず、「想定外」の災害であれば、国も事業者も免罪され、市民に被害だけが押し付けられるということになります。原発が存在するかぎり、政府・事業者のありかた、責任の所在について引き続き追及をしていくことが重要です。
この間原水禁は、「さようなら原発1000万人アクション」とともに福島原発刑事告訴団に協力、支援を行ってきました。現在、指定弁護人が上告し、最高裁での争いとなり、引き続き支援を継続していきます。
ⅳ)子どもや住民の「いのち」を守るとりくみ
県民健康調査は、事故から13年が経過し、「甲状腺検査」以外の検査は事実上終了してしまいました。福島県内での甲状腺がんを発症した子どもの数は、2023年12月時点で新たに12人増えて338人になりました。発症者数は、増え続けている現状にありますが、政府や東電は、過剰検査などを理由として原発事故との因果関係を頑に認めていません。しかし、原発事故によって大量の放射性物質が広範囲に降り注ぎ、多くの住民が放射能に晒されたことは確実であり、不安を抱える住民も少なくありません。政府や県は被曝した住民が多数いるという事実に基づいて、住民の命を守るとりくみを進めるべきです。
甲状腺がんを発症した事故当時6~16歳の6人(その後1人が追加提訴)が、東京電力を相手に東京地裁で損害賠償請求訴訟を提訴し、裁判が2022年5月26日に始まり、その後9回の口頭弁論が開かれてきました。政府や東電は事故によって肉体的にも、精神的にも追い詰められている被害者の健康被害を認め、その補償に責任を果たすべきです。
また、「避難指示解除」によって、国は事故後進めてきた「医療・介護保険料及び医療費の減免措置」を2023年度から切り捨てをはじめ、2027年度までにすべてを終えようとしています。しかしこの措置は、放射能汚染が続く中での困難な生活再建や、放射線被曝を含む心身への負荷による健康悪化を強いられてきた原発事故被害者に対する重要な支援でした。国策で進めてきた原発が起こした健康被害でもあり、国が行うべき最低限の「補償」であり被害者の当然の権利でもあります。減免措置の見直しを求めることが重要です。
原水禁は、「さようなら原発1000万人アクション」とともに裁判支援をすすめます。さらに「減免措置の見直し」を地元福島の市民団体などと共にとりくみをすすめていきます。
(3)核燃料サイクルに対するとりくみ
日本原燃は、2023年8月に、遅れている六ヶ所再処理工場の完工が、26回目の延期となることを発表し、12月26日には「2024年度のできるだけ早期」に完工をすると発表しました。しかし現実は、「27回目の完工延期の見通し」と報道され、建設完了から稼働への道筋が見えていないのが現状です。
日本は、「余剰のプルトニウムを持たない」ことを国際公約していることで、世界からプルトニウム削減が求められています。六ヶ所再処理工場で作り出されるプルトニウムは、プルサーマル燃料の需要に合わせて再処理されることとなっており、プルサーマル発電の進展によって操業が左右され極めて不安定と言わざるを得ません。作り出されるプルサーマル燃料(MOX燃料)も試算では燃料1トン当たり37億円で、通常のウラン燃料の16倍に当たり、電力自由化が進む中で、高額な燃料を使うことは、経済的合理性を欠くものです。
一方で、プルサーマル発電をしていた玄海原発3号機(佐賀県)で使用していた「MOX燃料」は、フランスに再処理とMOX燃料の加工を依頼していましたが、九州電力分のプルトニウムの在庫が尽き、プルサーマル発電を停止せざるを得ない状況になりました(2月2日に通常の発電に切り替わりました)。四国電力伊方原発3号機(愛媛県)も同様の理由でプルサーマル発電を今年7月に一時停止すると言われています。イギリスにも使用済核燃料の再処理を委託しプルトニウムを取り出していますが、MOX燃料への加工はできず、宙に浮いたままです。MOX燃料利用政策も混迷しています。
また、茨城県にある日本原子力研究開発機構の東海再処理工場は、原子炉から出た核燃料をリサイクルする日本初の再処理工場で、原子力発電の廃炉に当たる廃止措置に入っています。これまで再処理を行った過程で発生した高レベル放射性廃液を、2028年までにガラス固化作業を終了する予定でしたが、相次ぐトラブルで固化処理停止を余儀なくされました。2028年11月までに60本のガラス固化体を製造する予定でしたが、これまで25本を製造した段階で溶融炉内に堆積物がたまり、ガラスを取り除く作業が必要になり、2022年10月5日にガラス固化処理を停止しました。
当初2024年末に再開する予定でしたが、機器の不具合や追加作業などが発生し、2026年度にずれ込むと公表しました。そして終了時期も10年先送りとしました。ガラス固化作業は困難を極め、これまでの想定の甘さが露呈しました。
当然それは廃止措置費用の高騰に結びつき、これまで機構側は正式廃止措置費用について発表はしていませんが、2017年10月に新聞各紙に報道された情報では、2003年の時点での除染・解体費は1600億円とし、輸送に870億円、および廃止措置の最初にかかる費用の2170億円、放射性廃棄物の埋設に3300億円とされ総額8000億円と報道されました。しかし今から20年ほど前の試算で、その後の原材料費や人件費、輸送費などの高騰の中で、決して8000億円などという安易な想定はできません。それを国民的議論もないままに、負担だけが押し付けようとすることは許せません。いまだ全体像が示されないまま、なし崩し的に事業が進められていくことは許せません。
六ヶ所再処理工場は、東海再処理工場のガラス固化技術を採用し、試験段階で度々トラブルをおこしています。核燃料サイクル政策が破綻する中で建設を強引に推し進めてきましたが、大量の高レベル放射性廃液をガラス固化できない可能性があり、そのことは後世代に危険なツケを残すことになります。六ヶ所再処理工場を、東海再処理工場の二の舞にさせてはなりません。建設の中止と核燃料サイクル政策からの撤退を求めていかなければなりません。
再処理を中心とする核燃料サイクルの破綻は明らかであり、計画そのものの断念を強く求めるとりくみが極めて重要です。地元の運動を支えるとともに、計画断念の訴えを広めていきます。4月6日の「4・9反核燃の日行動」はその一環として現地青森で声を上げました(参加者500人)。
(4)原発再稼働に反対するとりくみ
ⅰ)GX方針に反対するとりくみ
岸田政権は、脱炭素の加速化やロシアのウクライナ侵攻によって生じたエネルギー問題を理由に、2022年にGX(グリーントランスフォーメーション)実行会議を立ち上げました。会議は福島第一原発事故以来、「原発の依存度を低減」とするこれまでの方針を転換し、原子力の最大限の活用、原発再稼働の推進と新増設、運転期間制限(現行原則40年、特別に60年まで)の撤廃、高速炉や小型原発、核融合炉の開発推進などを掲げ、岸田政権は原発積極推進に大きく舵を切りました。国会や市民にはかることなく、原発推進派の有識者を集めて、4か月ほどの議論で重要な基本方針を転換しました。その後のパブリックコメントに寄せられた多数の反対意見も尊重することなく、昨年2月に「GX脱炭素電源法案」(原子力基本法、原子炉等規制法、電気事業法、再処理法、再エネ特措法の5つの改正案を束ねたもの)が閣議決定されました。その後、「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(GX脱炭素電源法)と「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(GX推進法)として成立が強行されました。
中でも規制委員会の所管する原子炉等規制法から原発の運転期間に関わる規定を削除し、経済産業省の管轄する電気事業法に移行し、原発の停止期間を除外し、60年超の原発の稼働を可能にしようとする法改正は、原子力規制委員会の委員から「安全側への改変とはいえない」と反対意見が出るなど問題の多い内容です。
そもそもGX方針は、原発の新増設やリプレース、小型原発の建設など、いまの電力業界の要望ですらないものが含まれ、核融合にいたっては実現できる見通しがなく、多くの項目に具体性や実現可能性がありません。GX会議の真の目的は既存原発の再稼働と運転期間の延長です。一方で廃炉や廃棄物処理、核燃料サイクル、避難計画といった積み残した重要課題を先送りするものに他ならず、無責任といわざるを得ません。
ⅱ)各地の再稼働問題への対応
岸田首相は、2024年夏以降に最大で17基の原発の再稼働や再稼働認可をさせるとしていますが、実現には地元合意のとりつけや実効性ある避難計画の作成、耐震性の基準クリアなど多くの課題が山積しています。さらに、事業者の不手際やデータ改ざん、コンプライアンスの欠如などが目立っています。事業者としての適格性が問題となっています。
直近では、能登半島地震による活断層の問題や志賀原発からの避難の困難性、さらに原子力施設内での陥没や機器の損傷など大きな問題が露わになりました。
女川原発は東日本大震災で被災し、1号機は廃炉になりましたが、2号機は2020年2月に原子力規制委員会の審査に合格、同年11月に宮城県知事が再稼働の同意を表明、2024年9月の再稼働をめざすとしています。
2021年5月に石巻市民が、仙台地裁に重大事故時の避難計画に不備があると再稼働を差し止める裁判を提訴しましたが、2023年5月24日、原告側が事故の危険性を具体的に立証しておらず、請求の前提を欠くとして差し止めを認めませんでした。その中で原告が求めていた避難計画の実効性の判断については踏み込みませんでした。避難計画の実効性は、住民の命を守る重要な要求です。すべての再稼働に対して、避難計画の実効性を訴えることが重要です。この間現地では、地元紙を中心に意見広告運動を進め、この問題を広めてきました。さらに3月23日には、「さようなら女川原発全国集会」(仙台市内、約1000人参加)を開催し、再稼働をさせず廃炉に向けた動きをさらに強めています。原水禁としても、引き続き現地の運動を支え協力していきます。
柏崎刈羽原発では、2021年、外部からの侵入を検知する機器の不備や中央制御室への不正入室などテロ対策の重大な問題が発覚し、原子力規制委員会は、2021年4月に事実上の運転禁止の行政処分を出し、再稼働へ向けた手続きは中断しました。しかし12月27日、原子力規制委員会は自律的な改善が見込める状態であることが確認できたとして命令を解除、再稼働に向けた手続きが再開されました。これを受け東京電力は3月28日、再稼働に必要な検査の一環として、7号機の原子炉に早ければ4月中旬に核燃料を入れることを、原子力規制委員会に申請する方針を固めたと報道されました。
この間現地では、7月16日、「中越沖地震から16年 福島を忘れない!県民集会@柏崎」がとりくまれ、原水禁としても協力してきました。
東海第二原発(茨城県東海村)では、現在建設中の防潮堤の欠陥(不備)が10月17日に報道され明らかになりました。現在工事は停止していますが、事業者の日本原電は、それでも来年9月の工事終了のスケジュールは崩していません。一方東京高裁では差止訴訟の控訴審が行われています。2021年3月に水戸地裁で画期的な「差止」判決を勝ち取り、その後、原告(訴えが認められなかった原告も含め再度控訴し争うことに)と被告の日本原子力発電の双方が控訴し、再度「運転差止」の審理が進められています。水戸地裁に続き「避難の問題」が大きな焦点となります。
今後も原告団と共に裁判勝利に向けて支援を強化していくことが重要です。そのためにも老朽化する東海第二原発のさまざまな問題点を訴え、再稼働を阻止し、廃炉を求めていかなければなりません。
一方で、地元東海村は、11月27日の防災会議で「原子力災害に備えた東海村住民避難計画」を決定しました。山田修村長は、「計画策定で目標を一つ達成できた」と述べましたが、避難場所や移動手段の確保、人員の確保などの実効性のないもので、再稼働ありきの机上の空論となっています。能登での地震・津波の被害をみれば、村民約3万8000人の避難や避難解除の目安と指針など具体的なものとなっていません。
さらに半径30キロ圏内には、14市町村、約91万人超が住んでいますが、県の避難想定では約17万人と試算されました。試算では、避難する範囲を5キロ圏内としていますが、過小評価と言わざるを得ません。東海村には、東海第二原発の他にもさまざまな原子力施設が集中し、福島の例を見ても放射能影響が5キロを超えないということは考えられません。事故の想定を軽く見積もっては住民の命は守ることはできません。避難先、移動手段、マンパワーなど、福島だけでなく能登の事態を真摯に学ぶことが必要です。
関西電力は、運転開始から40年を超え、この間定期検査をしていた美浜3号機を、1月18日に再稼働しました。美浜原発3号機の運転再開で、福井県内で稼働する原発は、大飯原発3・4号機、高浜原発1・2・号機と併せて6基となっています。若狭湾に集中する老朽原発の再稼働は、事故や地震による被害などが特に懸念されます。
一方で関西電力は「使用済み核燃料の中間貯蔵地を2023年末までに福井県外に探す。探せなければ老朽原発を停止する」と約束していましたが、「保有する使用済み核燃料のわずか5%のフランスへの搬出」や「上関での中間貯蔵地建設調査」などの小手先の奇策と詭弁を弄し、約束を反古にしました。
その中間貯蔵施設については、関西電力と中国電力が、上関町の建設予定地で、建設可否を判断する現地ボーリング調査に向けた森林伐採が行われています。十分な住民説明もないまま、既成事実を積み上げていることは許せません。現地の上関原発建設中止を求める運動と連携しながら、中間貯蔵施設建設の中止を求めていきます。
同じく福井県にある日本原子力発電(原電)敦賀原発2号機は、これまで再稼働に必要な審査資料で誤り(1000ヵ所以上の審査資料の記載不備など)が繰り返され、審査が中断されてきました。しかし8月31日に、審査申請書補正書を申請するなど、再稼働へ向けた動きがふたたび出てきています。関電と福井県に当初の約束を履行させ、若狭の全ての老朽原発を廃炉に追い込まなければなりません。
昨年9月11日に中国電力は、島根原発2号機を今年8月に再稼働させるとの発表をしました。島根原発は、島根半島に立地し、福島第一原発と同系の沸騰水型炉(BWR)で、全国で唯一、県庁所在地にあります。避難計画の策定に必要な30キロ圏内には、島根、鳥取両県に約45万人が居住しており、安全に避難できるのかが大きな課題となっています。能登半島地震に見るように、家屋の倒壊や道路の寸断などで、住民の避難計画が「絵に描いた餅」であることが浮き彫りになりました。現在、1号機は廃炉作業中で、3号機は新規稼働に向けた規制委員会の審査中となっています。多くの市民が暮らし、避難がスムーズに行えないことは、すでに福島第一原発事故や能登半島地震でも証明されています。市民の命を危険に晒す原発の再稼働に強く反対していきます。
今後も被災原発や長期運転停止の原発などの再稼働は、GX方針のもと次々と出てきます。事故の危険性や実効性のない避難計画の問題点、60年延長による原発の老朽化の問題点などを訴えながら再稼働阻止に向けた運動を強め、各地の運動と連携して行くことが必要です。
1月1日の能登半島地震で発生したM7の地震と連動した津波による被害は、あらためて半島での避難や救援の困難性をまざまざと示しました。これに原発事故が重なればさらにその困難性は倍加していくことは明らかです。能登半島と同じように半島に原子力施設がある積丹半島(北海道・泊原発)、下北半島(青森県・大間原発、東通原発、六ヶ所核燃料サイクル施設など)、牡鹿半島(宮城県・女川原発)、佐多岬半島(愛媛県・伊方原発)などは同じような問題を抱えていると言えます。そのような地での原発稼働は問題で、避難の実効性を大きな争点としなければなりません。
原発再稼働に対しては、原発立地地域の運動と連携を図り、再稼働の阻止や稼働中の原発の停止に向けた運動を進めていきます。そのことを通じてGX基本方針の政策見直しを求めていきます。
現在原水禁は、「さようなら原発1000万人アクション」に協力して、「原発回帰を許さず、再生可能エネルギーの促進を求める全国署名」にとりくんでいます。国会においては立憲野党と協力しながら問題点を追及します。
(5)高レベル放射性廃棄物の処分場誘致問題に対するとりくみ
原子力発電環境整備機構(NUMO)は2月13日、北海道の寿都町と神恵内村において、原発の運転によって生じる高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場の選定に向けた、文献調査報告書の原案を公表しまし、活断層や活動の恐れのある火山など明らかな不適地は少ないと判断し、概要調査に進む候補地域として、神恵内村は村内の積丹岳から「15キロ以内の範囲を除いた範囲」を、寿都町は「町全域およびその沿岸海底下全域」を示しました。
今後地元の同意や核抜き条例を持つ北海道知事の意向が一つの焦点になります。今後「概要調査」へ移行をさせないためのとりくみを進めなければなりません。また寿都町・神恵内村に続いて処分場の候補地に手をあげる自治体を作らせないとりくみもあわせて進めていくことが必要です。
政府は高レベル放射性廃棄物の最終処分を「政府の責任でとりくんでいく」との方針を明確にしたうえで、「原子力と関係が深い自治体との協議の場を設定し、課題の議論・検討を進める」、「複数の地域での(協議の)実施を目指す」とし、政府が主導して全国100以上の自治体を訪問するとしています。今後、各地でも同様の動きが出てくる可能性があります。このような動きに対しては早い段階で現地の運動と連携し、課題の全国化を図ることが重要となっています。さらに、原水禁として「原発のごみ」の問題点を明らかにした「どうする?原発のごみ」シリーズ化したパンフレット(1号~5号)を作成し、問題点理解の促進を図っていきます。
(6)エネルギー政策の転換を求めるとりくみ
脱炭素を名目に原子力回帰をめぐる国際的動向を奇貨として、日本国内においても原発をクリーンなエネルギーとして再度拡大しようとする動きが強まっています。ロシア・ウクライナ戦争による世界的なエネルギー価格高騰の状況なども利用しながら、「原子力」や「火力」の再稼働や新増設の必要性をここぞとばかりに喧伝しています。
じっさい、岸田政権は脱炭素の加速化やエネルギー供給の安定化を名目に「GX推進法」ならびに「GX電源法」を強行採決し、原発回帰路線をいっそう強めています。
原子力ではなく、省エネや再生可能エネルギー技術の進展を見据えたエネルギー戦略に舵を切り、一刻も早く再生可能エネルギー100%の電源構成計画を実現すべきです。その際、メガソーラーや風力発電等で環境に影響を及ぼさないような規制とともに、原発温存を念頭にした旧大手電力に有利な電力市場構造が再生可能エネルギーの普及を阻害していることをふまえた制度整備が必要です。
2023年11月30日から12月13日にかけ、国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)がアラブ首長国連邦・ドバイで開催されました。採択された成果文書は「化石燃料から脱却する」「2030年までに再生可能エネルギー容量を世界全体で3倍に拡大する」とするいっぽう、「ゼロ排出・低排出技術」の一つとして原発を追加しています。さらにアメリカ・フランス・日本など20か国以上が温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「ネットゼロ」達成のために2050年までに世界の原発の発電容量を3倍に増やすとする宣言を行いました。
私たちは脱炭素だけではなく脱原発を同時に推進することを以てのみ持続可能で公平な社会がつくられるのだということを基本において、原子力回帰を目論む反動的な動きに対抗し、運動を展開しなくてはなりません。こうした立場を共有する市民団体・NGO・市民と連携しとりくみをすすめていきます。
この間、3月と9月に「さようなら原発」の大規模集会を行ってきましたが、上述の情勢を踏まえ、2023年9月は気候変動や脱炭素にとりくむ人びとと共同して「ワタシのミライ ~No Nukes & No Fossil~ 再エネ100%と公正な社会をめざして」(9月18日・代々木公園)として開催しました。引き続きこうした幅広い人びととの共同のありかたを模索していきます。
(7)重要性を増す「さようなら原発1000万人アクション」のとりくみ
2023年8月の放射能汚染水の放出の動きに対して、地元の「これ以上海を汚すな!市民会議」などと共に、抗議行動や全国一斉スタンディングなどを呼びかけて、官邸前や各地でのとりくみをすすめていきました。7月17日には、いわき市で「海の日アクション2023 汚染水を海に流すな!~海といのちを守るパレード~」を行ってきました。 その後、8月24日の強行放出に抗議し、9月以降、向こう1年間にわたり毎月24日に首相官邸前の抗議行動や銀座デモをおこなうこととし、9月~12月にかけて行動を行ってきました。今後も行動を継続し、汚染水放出の停止を求めていきます。
また、9月18日には東京・代々木公園での脱原発や気候危機・エネルギー問題等での大きなイベント「ワタシのミライ ~No Nukes & No Fossil~ 再エネ100%と公正な社会をめざして」を開催し8000人を集めました。今回、原発問題と関連が深い気候危機やエネルギー問題、環境問題に関わるグループに「さようなら原発」から声をかけて初めて共催することができました。これらの課題には、多くの若者が参加しています。それぞれの経験や運動スタイルの違いはありましたが、それでも初めてのとりくみの中で、お互い多くのものを学びました。集会へは、若手の参加者が多く、この経験を今後の運動へ活かし、参加継続と拡大が求められています。
また、ロシアのウクライナ侵攻からまる2年にあたる2月24日、東京・青山公園において総がかり行動と共催で「ウクライナに平和を!2・24青山集会&デモ」を行い、600人を集めました。ロシアのウクライナ侵攻により原発への攻撃・占拠が行われていることに対して、さようなら原発の運動として抗議の声をあげました。戦火の中にある原発の危険性を訴え続けていくことが必要です。
福島原発事故から13年目となる3月20日、に東京・代々木公園で「さようなら原発全国集会」を開催しました。集会には全国各地から6000人が集まり、福島の汚染水や刑事告訴の訴え、能登半島地震と志賀原発の問題などが訴えられました。
引き続き福島の課題や各地の再稼働の動きに対して連帯し、原水禁・平和フォーラムとして運動の中心を担いとりくみをすすめていきます。
なお、「さようなら原発全国集会」を9月16日、東京・代々木公園で開催する予定です。
【とりくみ】
①福島原発事故に関するさまざまな課題について、現地と協力しながら運動を進め、政府や行政への要請や交渉を進めます。特に、汚染水の海洋放出に反対していきます。
②原発の再稼働阻止にむけて、現地と協力しながら、課題を全国化していきます。合わせて自治体や政府への交渉を進めます。
③能登半島地震による避難計画の問題点を明らかにし、各地の原発避難計画の実効性や計画の見直しを求めていきます。
④老朽原発の危険性を訴え、廃炉に向けた運動を進めます。
⑤核燃料サイクル政策の破綻を明らかにし、計画の断念と六ヶ所再処理工場などの建設中止を求めます。
⑥大間原発や上関原発などの新規原発や中間貯蔵施設の建設中止を求めていきます。
⑦高レベル放射性廃棄物の地層処分に反対し、北海道平和運動フォーラムと協力しながら寿都町や神恵内村の「概要調査」に進ませない動きを作り出します。さらに全国に広がる高レベル放射性廃棄物処分場誘致の動き対して、地元の運動との連携を強化していきます。
⑧原水禁エネルギープロジェクトがとりくんできたエネルギーの提言を活用し、再生可能エネルギー100%を実現させるようなとりくみを行います。
⑨「さようなら原発1000万人アクション実行委員会」の運動に協力し、事務局の中心を担い、とりくみの強化をはかります。また、ウクライナ問題についても引き続き原発問題を課題として、運動を進めます。この間年に2回開催していた全国集会については、9月16日(月・休)は気候問題に取り組む団体との共催、2025年3月上旬は福島課題での集会開催を追求します。
8.ヒバクシャ援護・連帯にむけてのとりくみ
(1)急がれる被爆者課題の解決
広島・長崎への原爆の投下から78年が過ぎ、被爆者健康手帳を持つ全国の被爆者は2023年3月末で11万3649人となり、その平均年齢は85.01歳となりました。年々確実に高齢化が進み、医療や介護の支援拡充が喫緊の課題となっています。原爆症認定訴訟、被爆体験者、在外被爆者、被爆二世・三世など課題の解決も急がれています。
被爆者がこれまで被爆の実相を各国で語ってきたことにより、世界ではヒロシマ・ナガサキ以降、核兵器が使われない歴史を紡いできました。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻やイスラエルによるガザ地区での圧倒的な武力攻撃など、国際情勢が不安定になるにつれ、核兵器使用のリスクが高まっています。被爆者の一番の願いは核兵器の廃絶にあります。その実現にむけ、国内においては被爆者援護法を国家補償にしていくことが、戦争責任を明確にすることになり、戦争を抑止することにつながります。被爆者の課題を解決していくことが、戦争による核兵器使用を抑止することにつながるという観点からも、原水禁は引き続き、被爆者の残された課題解決にむけとりくみます。
(2)在外被爆者への差別を許さず援護を実現するとりくみ
戦後、祖国へ帰還した在外被爆者への援護は、日本の戦争責任・戦後責任と重なる重要な課題です。原水禁・平和フォーラムは、在外被爆者自身の裁判闘争を支援し、「被爆者はどこにいても被爆者」であるとして、差別のない援護の実現にむけてとりくんできました。在外被爆者の権利を制限していた厚生労働省公衆衛生局長の402号通達(被爆者手帳を交付されていても、外国に出国や居住した場合は、健康管理手当の受給権が失効する)は、その違法性が最高裁でも認められ、制度上の不平等は大幅に改善しました。
しかし、長い年月の経過の中で、在外被爆者が本人の被爆を証明する証人を見つけることが困難となり、被爆者援護を受けられないケースが出ています。また、在朝被爆者は個人としての救援が受けられず、あくまでも朝鮮は国単位での支援しか認めないとしていることから、被爆者援護法の主旨である「個人補償」が実現していません。
在朝被爆者を個人として補償しない状況が続くことは、人道的にも、日本の戦争責任・戦後責任の視点からも問題です。在朝被爆者の実態把握と人道的援護などを求め、政府・厚労省との交渉や国会で議論を促進することが必要です。
(3)「被爆体験者」に援護法の適用を求めるとりくみ
長崎では、爆心地から12キロ圏内において、放射能を含んだ雨(黒い雨)や粉塵を浴びたり、放射能で汚染された空気や水、食物を体内に摂取したりした結果、被爆した人たちが多数存在しますが、旧長崎市内ではないことを理由に、被爆者援護法の枠外に置かれ、「被爆体験者」と位置づけられています。
広島の「黒い雨」訴訟では、広島高裁判決において原告全員を被爆者と認定しました。同じ「黒い雨」を浴びながら、広島と長崎で違いが生じることは極めて不合理です。
長崎県・市が国に対して、「黒い雨」について再調査を求めた件について、厚労省は昨年11月、当初調査期間が1年程度必要としていたものの、その期間が短くなる見込みであることを明らかにしました。3月26日には「被爆者問題議員懇談会」が開催され、その中で厚労省は「黒い雨」の再調査の進捗について明らかにしました。厚労省によると、追悼祈念館の体験記3744件に「目を通し終えた」とし、今後その記述についての「精査・分析」を行うとしています。しかし、「何をもとに、誰が認定するか」といった基準も定まっていないことが明らかになったことからも、厚労省がこの再調査を「被爆者の救済」の観点から実施しているかについては疑問が残ります。
4月1日には「被爆者問題議員懇談会in長崎」が開催され、会長である参議院議員の水岡俊一さんや事務局長を務める山田勝彦さんなど4人の国会議員が長崎を訪れ、実際に「被爆体験者」とされているみなさんの意見やおもいを聞きました。
「被爆体験者」とされ、被爆者と認められない差別的な状況について、一刻も早い解決が必要です。原水禁は、政治的解決も含めたはたらきかけを、継続して行っていきます。
(4)被爆二世・三世の人権確立を求めるとりくみ
父母や祖父母の被爆体験を家族として身近に受け継ぎ、自ら核被害者としての権利を求め、核廃絶を訴えている被爆二世協の運動は、今後の原水禁運動の継承・発展にとっても重要です。被爆者の高年齢化が進む中、核兵器廃絶を実現させるための被爆の実相を語り継いでいく役割が、被爆二世・三世に期待されます。
被爆二世・三世は、被爆者援護法の枠外に置かれています。原爆被爆による放射線の遺伝的影響を否定できないなか、健康不安や健康被害、社会的偏見や差別などの人権侵害の状態に置かれてきました。被爆二世の全国組織である「全国被爆二世団体連絡協議会(全国被爆二世協)」は、国家補償と被爆二世への適用を明記した「被爆者援護法」の改正を国に対して要求してきました。
また、「被爆体験者」とともに、被爆二世・三世課題の解決にむけた被爆者問題議員懇談会を通して、問題性を明らかにし、被爆者援護法の適用を求めています。なお、3月8日に開催予定だった広島高裁での裁判日程は5月24日に延期になっています。
今後も続く被爆二世裁判の支援と被爆二世の課題解決にむけ、全国被爆二世協の運動と連携していくことが必要です。今後も続く被爆二世裁判の支援と被爆二世の課題解決にむけ、全国被爆二世協の運動と連携していくことが必要です。
(5)被曝労働者の権利確立を求めるとりくみ
原発労働は、従来から工事の下請け企業による雇用が中心で、雇用や労働環境の問題はなおざりにされてきました。被曝問題だけでなく、幾重にも重なる下請け企業構造の中で、労働者の基本的な権利が侵害される事例が起きていることが危惧されます。原発事故を起こした深い反省と謝罪を繰り返す東京電力は、こういった実態については請負企業側の問題であるとし把握もしていないことを明言しています。
8月から強行されている、事故を起こした福島第一原発の核燃料デブリにふれたALPS処理汚染水の海洋放出については、その作業中に誤って作業員が水を浴び、被曝する事故が発生しています。作業員の安全を確保することが、廃炉を進めるうえでは大前提になることは言うまでもありません。東京電力にその能力があるのかについて、信頼がおけない事態が続いています。
この間、被ばく労働者ネットワークや全国労働安全センターなど、関連する10団体と政府交渉を行ってきました。引き続き運動の連携を深め、被曝労働者の命と権利を守るとりくみを強化していきます。
(6)世界の核被害者(ヒバクシャ)との連帯を
原水禁運動は、国内の核被害者の支援・連帯はもとより、世界の核被害者(ヒバクシャ)との連帯を重要な課題として受け止め、とりくんできました。核の軍事利用や商業利用では、とりわけ核のレイシズムともいわれる差別と人種的偏見による人権抑圧の下で、先住民に核被害が押しつけられ続けてきました。原子力利用は、ウラン採掘の最初から放射性廃棄物処分の最後まで、放射能汚染と被曝をもたらします。原水禁は、米・仏などの核実験による被害者、特に近年では、ビキニの被災者、ウラン採掘現場での被害者、チェルノブイリの原発事故での被害者など、これまで多くの核被害者との連帯を深めてきました。
11月に開催された核兵器禁止条約第2回締約国会議において、第6条「被害者支援と環境修復」、第7条「国際協力と支援」が重要な議論の柱とされ、「国際信託基金」によって被害者の支援を行う方向性が確認されました。会議において原水禁から代表参加した高校生・大学生の発言と合わせて、マーシャル諸島の核被害についてとりくむ市民の発言もありました。
原水禁は、今後とも、差別と抑圧のきびしい現実の中でたたかっている世界中の核被害者(ヒバクシャ)と連帯し、ヒバクシャの人権と補償を確立し、核時代を終わらせるために運動の強化が求められています。特に、アメリカによるビキニ環礁での水爆実験から70年を一つの節目と捉え、現地との交流について再開をめざして準備を進めていきます。また、これまで継続してきた原水禁世界大会への参加を依頼するなど、核被害者との連帯をはかっていきます。
【とりくみ】
①原爆症認定制度の改善を求めます。被爆者の実態に則した制度と審査体制の構築に向けて、運動をすすめます。
②在外被爆者の支援や交流、制度・政策の改善・強化にとりくみます。
③在朝被爆者支援連絡会などと協力し、在朝被爆者問題の解決に向けてとりくみます。
④被爆体験者の再提訴裁判を支援します。
⑤健康不安の解消として現在実施されている健康診断に、ガン検診の追加など二世対策の充実をはかり、被爆二世を援護法の対象とするよう法制化に向けたとりくみを強化します。さらに健康診断などを被爆三世へ拡大するよう求めていきます。また、被爆者二世裁判を支援します。
⑥被爆認定地域の拡大と被爆者行政の充実・拡大をめざし、国への働きかけを強化します。
⑦被曝線量の規制強化を求めます。被曝労働者への援護連帯を強化します。
⑧被爆の実相を継承するとりくみをすすめます。「高校生1万人署名」、高校生平和大使などの若者による運動のとりくみに協力します。またDVD「君たちはゲンバクを見たか」のリニューアル版「核と人類は共存できない」の普及をはかります。
⑨世界のあらゆる核開発過程で生み出される核被害者との連携・連帯を強化します。
9.食・水・みどりをめぐるとりくみ
(1)食料・農業政策のとりくみ
コロナ禍に端を発した食料生産・流通の停滞、世界的な異常気象による干ばつなどに加え、長引くロシアとウクライナの戦争などの影響による世界的な食料価格の高騰や供給不足など、かつてない危機的状況にあります。
国連食料農業機関は全世界で8億人以上が深刻な食料不足状況にあると警告しています。また、国連機関(FAO、IFAD、UNICEF、WFP、WHO)によるレポートでは、「飢餓人口は依然としてコロナ前をはるかに上回っている」とされ、貧困や飢餓をなくすという、2030年までのSDGs(国連の持続可能な開発目標)の達成についても、危惧されています。
日本でも、食品価格の値上げが相次ぎ、今後も続くことは必至な状況です。農業生産でも、円安の影響も受け、輸入肥料や飼料価格が高止まりし、農業経営の継続が困難となっています。
近年、農業経営体や農業従事者は急速に減少し、農作物の作付面積は毎年、過去最低を更新しています。耕作放棄地も増加し、農業生産の基盤が崩壊しつつあります。また、食料自給率は38%(2022年度・カロリーベース)と、依然として先進国中で最低水準にあり、さらに、近年は中国の食料輸入が急増する中で、必要量が確保できない「買い負け」状況にもなっています。円安や生産・輸送コストの上昇で輸入農畜産物価格が大幅に上がる中、安定的な食の確保に向けた食料・農業政策の転換が必至です。
農水省は、食料安全保障のあり方を中心に、「食料・農業・農村基本法」の見直しを進めてきました。今通常国会へ提出する改正案には、日本が海外から農産物を安定的に確保できるよう「輸入相手国への投資促進や必要な施策を講じる」と明記する一方で、自給率向上や国内生産拡大への具体的対策は不明確です。全体的に「食料安全保障」が強調されていますが、農業や農村政策では新たな方向性が見えていません。「食糧安全保障」の根幹でもある食料自給率引き上げについては不十分なままです。
また、2022年から施行された、2050年を目標に、農薬や化学肥料を削減し、有機農業の拡大をめざす「みどりの食料システム法」も含め、今後の農林漁業および食品産業の持続的な発展にどうつながるかも注目していかなければなりません。
これまでの食料輸入を前提とした、規模拡大・効率化一辺倒の農政ではなく、食の安全や環境問題などに配慮した政策への転換が重要となっています。農民・消費者団体と協力し、食料自給率向上や所得補償制度の拡充、食品の安全性向上などの法制度確立と着実な実施を求めていく必要があります。また、食の安全や農林水産業の振興にむけた自治体の条例作りや、各地域での学校給食等を通じた食育も重要となっています。
2023年12月に開催した「第55回食とみどり、水を守る全国活動者会議」に続き、2024年の開催に向けて、実行委員会に参画し、協力していきます。
(2)通商交渉に対するとりくみ
2012年の第二次安倍政権以降、環太平洋経済連携協定(TPP11、2018年12月発効)、日本とヨーロッパ連合(EU)との経済連携協定(2019年2月発効)、日米二国間の貿易協定(2021年1月発効)、東アジアを中心とした地域的な包括的経済連携協定(RCEP、2022年1月発効)と、日本は次々と巨大な経済圏との通商協定を結んできました。
「メガFTA」と呼ばれるこうした協定により、日本は一挙に総自由化時代に突入しました。牛・豚肉をはじめ、輸入農畜産物の増加は国内農業に深刻な打撃を与えています。政府は、国内対策によって生産は減少せず、自給率も維持されるとしてきましたが、自給率の低下や離農の拡大を見れば、これは実態を無視した詭弁だったと言うしかありません。
「メガFTA」による市場開放政策は、「農業を成長産業にする」「農産物の輸出を拡大して攻めの農業を推進する」などと言いながら、実態は、自動車等の輸出促進、日本企業の対外進出を図るために、農業を犠牲にする政策であったことは明白です。
さらに、2023年11月には、米国が主導し、日本や東南アジア諸国、韓国、インドなど14か国が参加する新たな経済圏構想「インド太平洋経済枠組み」(IPEF)の首脳会合及び閣僚級会合が開催され、IPEFサプライチェーン協定の署名式が行われ、サプライチェーンのほか、貿易、クリーン経済、公正な経済の分野において、実質妥結となりました。これは、中国に対抗する戦略目的を持つもので、中国に貿易の多くを依存している日本の姿勢が問われています。
また、アメリカと日本との2か国間の本格的な貿易交渉によって、コメを含む農産品についての交渉が再燃する可能性があります。TPPの参加国も拡大しようとしており、多くの国は日本の農産物市場の拡大を狙っています。
これまでの通商交渉では、野党や市民の追及にもかかわらず、交渉経過や内容が明らかにされてきませんでした。今後、徹底した情報公開や市民との意見交換を求めていく必要があります。世界的にも行き過ぎたグローバリズムによる格差の拡大に対する声も広がっていることから、こうした問題も検討していく必要があります。
平和フォーラムは、「TPPプラスを許さない!全国共同行動」など、関係団体と連携をはかり学習会・集会、シンポジウムの開催や政府交渉などを進めます。
(3)食の安全などをめぐるとりくみ
通商交渉の動きは食に関しても大きな影響を与えるものです。2023年度から遺伝子組換え(GM)食品の表示制度が改定され、また、新しい遺伝子操作であるゲノム編集技術を用いた食品も流通しています。消費者団体ではゲノム編集食品の表示を求める活動を行っています。
一方、農薬の残留基準値も徐々に緩和され、輸入農産物の検査体制にも影響を与えています。アメリカなどでは、収穫直前に農薬を散布して作業の効率化を図る方法もとられ、農薬の残留が問題になっています。一方、日本は単位面積当たりの農薬の使用量が世界的にも多く、発がん性や環境への影響も指摘されています。消費者団体などから有機農産物の拡大や学校給食への導入を求める運動が広がりつつあります。
また、いわゆる「健康食品」については、不確実な宣伝・広告があふれています。平和フォーラムも参加する「食の安全・監視市民委員会」では、広告の規制などを求めています。とくに、「紅麹」問題発生によってその安全性が問題になっている「機能性表示食品」制度は、廃止を含む抜本的な見直しが必要です。現行制度では、安全の保障が届出事業者に任せられ、国が責任を負わない点でも情報の質・量の面で消費者に不利益が生じます。
さらに、全ての加工食品の重量割合1位の原材料の原産地表示が義務化されましたが、例えば、小麦の原産国が明記されないまま「小麦粉(国内製造)」と表示されていることや、3か国以上の外国産原材料使用の場合は単に「輸入」というおおくり表示であるなど、消費者が望んでいた表示とはかけ離れています。消費者の権利として正しくわかりやすい表示が求められています。
さらに、現在、日本では食品の有機フッ素化合物(PFAS)の残留基準が設定されていません。早急に基準設定に向けて運動する必要があります。
(4)水・森林・化学物質などのとりくみ
水問題については、合成洗剤などの化学物質の排出・移動量届出制度(PRTR制度)を活用した規制・削減や、化学的香料による健康被害の「香害」問題への早急な対策など、化学物質の総合的な管理・規制にむけた法制度や、有害物質に対する国際的な共通絵表示制度(GHS)の合成洗剤への適用などを求めて運動を展開していく必要があります。
とくに2021年にPRTR制度の指定物質に石けん成分が含まれようとしたことに対し、反対運動の結果、その方針を撤回させました。長年の運動の成果であり、改めて制度の意義を問い直すとともに、再度、同様の問題が起きないようとりくむ必要があります。
また、米軍基地などを発生源とする有機フッ素化合物(PFAS)による水汚染問題は、沖縄をはじめ全国に広がっています。早急に全国の実態調査と規制の強化を求めてとりくみを進めていく必要があります。
水の公共性と安全確保のため、今後も水循環基本法の理念の具体化や、「水道法改正」による水道事業民営化の動きを注視し、水道・下水道事業の公共・公営原則を守り発展させることが、引き続き重要な課題となっていることから、関係省庁要請など、必要な対策をすすめます。
世界的な森林の減少と劣化が進み、砂漠化や温暖化を加速させています。日本は世界有数の森林国でありながら、大量の木材輸入により、国内の木材自給率は低迷してきましたが、最近は、国産材の使用拡大施策などが図られています。
政府は2040年を見通した新たな「森林・林業基本計画」で、木材供給量を4割増とすることや、森林の二酸化炭素の吸収機能強化、公共建築物への木材活用促進などをめざすとしています。また、本格化している「森林環境譲与税」を活用した森林整備、担い手育成なども重要になっています。一方、さまざまな通商協定による木材貿易への影響を注視する必要があります。
今後も、温暖化防止の森林吸収源対策を含めた、森林・林業政策の推進にむけて、「森林・林業基本計画」の推進、林業労働力確保、地域材の利用対策、山村における定住の促進などを求めていくことが必要です。
【とりくみ】
①農林業政策に対し、食料自給率向上対策、直接所得補償制度の確立、地産地消の推進、環境保全対策、再生可能エネルギーを含む地域産業支援策などの政策実現を求めます。
②各地域で食品安全条例や食育(食農教育)推進条例づくり、学校給食に地場の農産物や米を使う運動、子どもや市民を中心としたアフリカ支援米作付け運動や森林・林業の視察・体験、農林産品フェスティバルなどを通じ、食料問題や農林水産業の多面的機能を訴える機会をつくっていきます。
③さまざまな通商交渉に対し、その情報開示を求め、問題点を明らかにするとともに、幅広い団体と連携を図り、集会や学習会などを開催していきます。
④輸入食品の安全性対策の徹底とともに、食品の安全規制緩和の動きに反対して、消費者団体などと運動を進めます。
⑤「食品表示制度」に対し、消費者のためになる表示のあり方を求めていきます。とくに、機能性表示食品制度については、廃止を含む抜本的見直しなどを求めていきます。
⑥「きれいな水といのちを守る全国連絡会」の事務局団体として活動を推進します。10月開催予定の「第37回きれいな水といのちを守る全国集会」の実行委員会に参画して、開催にむけてとりくみます。また、PFASなど水汚染問題等にむけたとりくみを進めます。
⑦関係団体と協力して、「森林・林業基本計画」で定めた森林整備の確実な推進、地産地消による国産材の利用拡大、木質バイオマスの推進などにとりくみます。
⑧温暖化防止の国内対策の推進を求め、企業などへの排出削減の義務づけや森林の整備など、削減効果のある具体的な政策を求めます。
⑨「第56回食とみどり、水を守る全国活動者会議」の実行委員会に参画して、開催にむけてとりくみます。
10.平和フォーラムの運動と組織の強化にむけたとりくみ
(1)平和フォーラムの運動の到達点と今後の課題
平和フォーラムは、総評労働運動の歴史を継承し、産別中央組織と運動組織の中央団体、および各都道府県組織の活動によって支えられてきました。また、2014年ごろから戦争法の廃止を求める運動の過程で、「戦争をさせない1000人委員会」、「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」、「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合」などの運動にとりくみ、活動の幅を広げてきました。これらの運動は、広範な市民と連携し社会の多数派形成の可能性を展望するものです。
しかしこの間のとりくみの中でも、地域間の温度差があることが明らかになっています。「総がかり行動実行委員会」のとりくみが中心となっている地域から、平和フォーラムの運動の枠内で活動している地域まで様ざまありますが、このことは、各県の地域事情、すなわち連合との関係性、立憲民主党や社民党との関係性や、さらには日本共産党やその影響下の運動組織との共闘のあり方に規定されているのが実情です。
2021年の衆議院選挙、2022年の参議院選挙の結果から、改憲勢力が両院で大きく3分の2を超えている現状を踏まえれば、今後改憲発議へと進むことは明らかであり、平和フォーラムの運動にとっても、その帰趨がもたらす意味は重大です。平和や人権、環境をめぐる諸政策の実現を可能とする政治を実現していくためには、具体的で効果的な運動の再構築と、それを支える組織の強化が必要です。
このため、以下の課題について、組織強化の具体化について機関会議などで討論を進めていきます。
(2)運動と組織の強化にむけたとりくみ
ⅰ)より広範な運動展開と社会の多数派をめざす活動
平和フォーラムのとりくんできた諸運動の到達点を踏まえ、政策実現のとりくみを進めるために政府との対抗関係を構築する必要があり、ナショナルセンターとしての連合にその役割を果たすことを期待しつつ、広範な運動の連携構築をめざします。
中央では、政府との対抗関係を構築するために、「戦争をさせない1000人委員会」、「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」、「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合」について、引き続き、とりくみを進めます。また、立憲民主党、社民党などと連携し、政府・各省・自治体等への対策を強化します。こうしたとりくみ全体を促進するため、研究者・研究団体、法律家、NPO・NGO、青年や女性団体などとの連携も強化します。
一方、平和フォーラムの地方組織においては、地域事情やさまざまな歴史が存在することを踏まえながらより広範な運動展開をめざしつつ、自らの基礎を固めるとりくみも重要です。このため、地方組織においては、それぞれの現在のとりくみを基礎として、地域事情に合った運動の展開をはかるとともに、ブロックごとのとりくみを重視し、運動を展開します。
ⅱ)平和フォーラム組織の強化・拡大
運動の継承を可能とするために、次代を担う人材の育成がすべての組織にとって重要な課題です。平和フォーラムの運動を若い世代に丁寧に伝えるなかで、意識的に若い世代の活動家づくりを進めます。このため、共闘の基礎を担う産別中央組織と中央団体とともに、次代を担う人材の育成にむけて、中長期を展望して対応を議論していきます。また、平和フォーラムの運動を担う、新たな仲間の獲得も重要です。運動のつながりの中から、さらなる組織拡大を追求していきます。
新型コロナウイルス感染症への対応を続けた中で、ZoomやYouTubeなどのさまざまな情報通信技術を活用するノウハウが蓄積されてきました。またSNS活用の重要性はさらに高まっており、積極的に活用していきます。しかしその際にも、新しい運動の担い手の結集の機会となるよう、意識しながらとりくみをすすめなければなりません。このために、運動の情報発信をより広く行い、とりくみの意義と目的が明確なものとなるよう努めます。
2023年は4回目になる「ピーススクール」を開催し、40人を超える参加者が、7つの課題とディベートに熱心にとりくみました。またこの3月には福島・茨城・東京で連続的なアピール行動を行う「フクシマ連帯キャラバン」も実施し、青年女性部を中心に若い世代の参加が期待されます。高校生平和大使の経験者が、高校卒業後にも運動に関わる方策の模索も開始しています。今年については、これら次代を担う人材の育成を意識的に進めていきます。
【とりくみ】
①機関運営について:
ア)平和フォーラムの運動の課題と目標を具現化するために、Zoom等も活用しながら、常任幹事会、運営委員会、原水禁常任執行委員会を開催します。また、各地方組織の課題、平和フォーラムの活動の共通目標の確認のため、各都道府県・中央団体責任者会議、全国活動者会議を開催し、討議を進めます。組織体制や運動づくりを進める際に、男女共同参画の視点は必須です。女性や若年層などが参画しやすい運営と環境づくりに工夫を重ね、常にジェンダーバランスに意識した運営を心がけます。
イ)首都圏における会議、イベントだけでなく、平和フォーラムの各都道府県組織との連携をはかるため、可能な限り平和フォーラムから、各地方ブロック会議に参加し情報交換を進めます。
②運動の拡大をめざすとりくみ:
ア)「戦争をさせない1000人委員会」、「戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会」、「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合」、「さようなら原発1000万人アクション」などを軸として、平和団体、市民団体、人権団体との連携を強化します。研究者、有識者との連携も強化します。
イ)制度・政策活動の充実にむけて、他団体、政党・議員との連携を強化し、政府・各省・地方自治体・関係企業などとの交渉力を強めます。また、政策課題に対応した立憲フォーラムをはじめとする議員団会議、議員懇談会との連携を強化します。
ウ)国際的平和団体、反核団体、市民団体、労働団体などと連帯し、国連や関係政府に働きかけると同時に国際連帯活動を強化します。とりわけ東アジアを重点とした関係強化を図ります。
エ)若い世代の活動家づくりを重点的に進めます。そのため、2024年10月18~20日、「ピーススクール」を開催します。
③情報の発信と集中、共有化について:
ア)インターネットやその他の通信手段で平和フォーラム・原水禁のとりくみに接する市民が増えており、インターネット等による発信力の強化が求められています。今後は、それぞれの機能を有効に活用し、一方的な情報発信にならないような工夫、情報の整理と蓄積などを行います。
イ)政策提言の発信や、パンフレットやブックレット、記録集の発行などをすすめます。
ウ)機関紙「ニュースペーパー」の定期発行を継続し、紙面の充実をはかるとともに、購読者の増加と活用機会の拡大に努めます。
④集会の開催、声明などの発信:
中央、地方の大衆的な集会の開催、署名活動、社会状況や政治的動向に対する見解や声明などの発信は、平和フォーラムの運動を可視化し、社会的な役割を拡大するために重要なとりくみです。政治情勢の変化によって起きるもろもろの事態に対応するため、適切なタイミングで声明等の発出に努めるとともに、運動の重点化、年中行事型運動の見直し、運動スタイルの多様化が必要です。参加しやすい環境づくりを念頭に置いて、見直しにとりくみます。
⑤財政基盤の確立と事務局体制の強化:
運動の前進と継続のため、引き続き財政基盤の確立と効率的な執行に努めます。また事務局を支える役職員の確保やスキルの向上を計画的に進めます。
以上