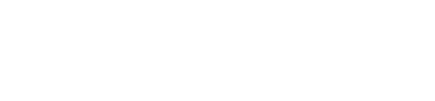憲法審査会 | 平和フォーラム
2025年04月25日
憲法審査会レポート No.53
2025年4月24日(木) 第217回国会(常会)
第5回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55744
※「はじめから再生」をクリックしてください
【マスコミ報道から】
野党、臨時国会「20日以内」に 衆院憲法審、召集期限を議論
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025042400953&g=pol
“衆院憲法審査会は24日、臨時国会の召集期限について議論した。立憲民主党など野党は召集要求があった場合、政府は「20日以内」に応じるとの期限を設けるよう求めた。自民、公明両党からは期限の設定に慎重な意見が出た。”
衆議院憲法審査会 臨時国会の召集期限で議論
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250424/k10014788341000.html
24日の衆議院憲法審査会で、立憲民主党の松尾明弘氏は、2017年の安倍政権当時、野党が臨時国会の召集を要求したものの、召集されたのが98日後だったケースなどを挙げ「明白な憲法違反であり、議会制民主主義に対する重大な問題だ」と指摘しました。”
臨時国会の召集「20日以内」の明記、与党は慎重姿勢 衆院憲法審
https://digital.asahi.com/articles/AST4S2VP7T4SUTFK00TM.html
“同条は少数派の国会議員の意見を国会に反映させることを目的としている。しかし、これに基づいて野党が召集を要求しても、2017年の安倍晋三内閣は約3カ月放置し、ようやく臨時国会を開いてもすぐに衆院を解散して実質的な審議をしなかった。”
“安倍内閣のケースでは野党議員が違憲訴訟を起こした。最高裁は憲法判断をせずに訴えを退けたが、内閣が召集の「義務」を負うと判決文に記した。”
憲法改正の「誘い水」になるのか 立民重視の「臨時国会召集期限」を議論 衆院憲法審
https://www.sankei.com/article/20250424-GVFAH53XPFLCPBZQQZR3XBJUDM/
“改憲勢力の一部には、野党第一党の要求に応えれば、憲法改正で協力を得られるのではないかという希望的観測がある。しかし、党内や支持層に護憲派を抱える立民の壁は依然として高く、「誘い水」になるのかは見通せない。”
【傍聴者の感想】
衆議院憲法審査会の傍聴は昨年以来で、ひさしぶりです。まず一見して、委員の構成も、そして雰囲気もだいぶん変わったように感じました。
今回の自由討議のテーマは臨時国会の召集期限でした。
最初に衆議院法制局から憲法53条後段「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」についての制定経緯や実例、学説・判例、各会派の主張についての説明があり、これが結構わかりやすい整理でした。
とくに違憲性が問われる例である2017年に行われた召集要求(を92日放置した挙句、開いた臨時国会を冒頭解散!)について、法制局長が「いわゆるモリカケ問題…」と説明していたのが印象的でした。
その後、各会派からそれぞれ発言していったのですが、改憲会派も(維新を除いて)これまでのような改憲一辺倒といった気色は薄れていました。
それもそのはず、上記の例も含め臨時国会召集要求を何度も踏みにじってきたのは当の自民党(や公明党)であり、そのくせ自民党が(野党時代の)2012年に作成した「憲法改正草案」には「20日以内の召集」を盛り込んでいたという矛盾をさらけ出してきたわけで、本件はどうにもやりにくいのでしょう。
自民党の上川陽子幹事は2018年に決定した「改憲4項目」が優先的テーマであって、「憲法改正草案」はもはや過去のものであるかのような口ぶりでした。
また、公明党の浜地雅一委員は憲法53条についての党としての統一見解はなく、今回の議論をフィードバックしたいと発言していました。
召集期限の問題を解消する方法が明文化の憲法改正なのか、あるいは国会法改正なのかが争点です。実際、2022年には立憲・維新・共産・有志・れ新による国会法の改正案(審議未了で廃案)が提出されており、そのいっぽう維新・国民・有志が2023年に改憲条文案として発表しています。
しかし、野党多数の現状にあって、国会法改正による問題解消がもっとも手っ取り早く実効的であり、このことから目を背けて改憲を叫び続ける一部会派にはあきれるほかありません。
きょうの発言のなかでは、立憲民主党の松尾明弘委員の、召集要求を無視するような憲法違反をふたたび起こさせないように、これまでの事例をしっかり調査することが憲法審査会の責務であるという主張が、いちばん腑に落ちました。
【国会議員から】松尾明弘さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会委員)
 本日テーマとなっております憲法53条後段は、臨時会の召集要求に対して内閣はその召集を決定しなければならないと定めており、これが法的義務であることは、学説上も争いはありません。さらに、2023年の最高裁判決においても、憲法53条後段が国会と内閣との間における権限の分配という観点からの規定であり、召集決定は法的義務であると判断されています。
本日テーマとなっております憲法53条後段は、臨時会の召集要求に対して内閣はその召集を決定しなければならないと定めており、これが法的義務であることは、学説上も争いはありません。さらに、2023年の最高裁判決においても、憲法53条後段が国会と内閣との間における権限の分配という観点からの規定であり、召集決定は法的義務であると判断されています。
しかし、実際には、憲法53条後段に基づく議員の4分の1以上による臨時会の召集要求があったにもかかわらず、不当に臨時会の召集が遅らせられる事例が多発しています。
具体的な例としては、2017年6月、森友、加計学園問題の真相解明のため、野党議員が憲法53条後段に基づいて臨時会の召集を求めました。それにもかかわらず、召集されたのは98日後で、その日に衆議院が解散され、参議院も同時に閉会することになりました。この召集は、実質的には憲法53条前段に基づく臨時会で、憲法53条後段に基づく臨時会の召集要求に対する拒否と言え、明白な憲法違反です。
このほかにも、2020年、21年、22年の3回にわたって、4分の1超の国会議員が臨時会の召集要求を行ったにもかかわらず、内閣が臨時会を召集したのは、それぞれ、47日後、80日後、46日後という長期間後であって、不当に召集を遅滞する憲法違反が繰り返されています。
憲法53条には召集期限は具体的に書かれていません。しかし、これは内閣に広範な裁量を認める趣旨ではありません。このことは、権力分立と人権保障の原理に立つ立憲主義の考え方からしても明らかです。
召集期限については、社会通念上合理的な期間とする見解や、召集手続のために必要な期間、すなわち国会開会の手続及び準備のために客観的に必要と見られる相当な期間内で、できるだけ早い期間とする、そういった見解が学説上有力であり、その期間を超えて内閣の裁量はないものと解されます。この見解は、三権分立の下、内閣と国会が牽制し合うことによって濫用を防ぎ、国民の権利を守るという憲法の理念にも合致するものです。
しばしば与党が述べる、召集の必要性は感じないという発言は、53条後段の要請を全く理解していないものです。53条後段は、内閣よりも議員の意思と判断を重視するものだからです。臨時会の権能は、内閣が提出する案件の審議に限られるものではなく、議員提出法案や質疑も可能ですから、内閣がそこに案件を提出する準備ができたかどうか、その他政治的な理由で召集の必要性や時期を決定することは許されません。
現在、憲法53条後段の召集義務に違反した場合であっても、政治的責任が追及され得るのみです。しかし、自民党によるこれまでの憲法違反に対して、原因の究明及び政治的責任の追及は不十分であったと言わざるを得ません。
憲法審査会の役割には、国会法102条の6において、憲法及びこれに密接に関係する基本法制の調査が職務に含まれていると明記されていることからも明らかなとおり、憲法改正をすべきかどうかを論じるだけではなくて、憲法違反問題を含む日本国憲法の施行、遵守の状況に関する調査を行うことも含まれています。よって、過去の不当な召集遅滞について、当時の内閣が召集をしなかった原因を究明し政治的責任を追及することは、当憲法審査会の責務であると考えています。
憲法審査会においては、過去の憲法違反に対する政治的責任の追及自体をまずは行うべきであって、それが済んだ後に、憲法53条後段を無視する内閣の不当な態度を正し、同様の憲法違反が繰り返されないために、召集期限を法定すべきかどうかを議論すべきと考えます。
この議論には、合理的期間を一定に法定することができるのかという点、そして、法定するとすれば何日程度とすべきなのかという二つの論点があります。
検討に当たり注目すべきは、2023年の最高裁判決における宇賀裁判官の反対意見です。ここでは、20日あれば十分と述べられています。これは憲法54条や地方自治法など他の法制度とも整合する数字です。
また、20日の理由として、2012年の自民党憲法改正草案が、憲法53条について、20日以内に臨時会を召集しなければならないとしていることも挙げられています。
なお、立憲民主党も、2022年に、他会派と併せて、国会法において召集期限を20日と明記する法案を提出しており、この意見とも符合するものです。
2017年を始め繰り返し生じている臨時会召集の大幅な遅れは、憲法53条の趣旨に明らかに反するものであり、立憲主義や議会制民主主義に対する重大な問題です。こうした経緯を踏まえれば、やはり何らかの立法的な手当ての必要性は否定できません。その具体的な方法については、国会法改正その他様々な選択肢があり得ると考えています。
いずれにせよ、先ほど申し上げたとおり、まずは、合理的期間とは何か、その基準を明確にするためにも、過去の憲法違反事例について、憲法審査会における徹底した原因究明と政治的責任の追及が必要です。それらを踏まえた上で、結論ありきではない建設的な議論が行われるべきことを申し述べ、私からの意見陳述といたします。
(憲法審査会での発言から)
2025年04月18日
憲法審査会レポート No.52
今週は参院憲法審査会が開催されました。いっぽう衆院憲法審査会は開催されず、17日の幹事懇談会の後に国民投票広報協議会規程についての意見交換会が行われています。
【参考】
【憲法審査会】国民投票広報協議会規程について。
https://yamahanaikuo.com/20250417k/
“(審査会の形で開催しなかったのはなぜ?)技術的・細目的な問題であること、そもそも何が論点となるかについて認識が共有されていないことなどから、審査会本体で扱っても議論が拡散すると考えられたからです。また、正式な会とすると、会派ごとに発言時間なども均等にしますから、柔軟な運営ができないことも理由です。どこかのタイミングで、議論の要旨については審査会に翻刻される予定です。”
2025年4月16日(水)第217回国会(常会)
第2回 参議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8458
【マスコミ報道から】
参院憲法審、緊急集会を議論 自・立、主張に違い
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025041600798&g=pol
“参院憲法審査会は16日、緊急事態における参院の「緊急集会」について議論した。自民党は緊急集会の機能を明確にするため、憲法改正による緊急事態条項の創設を主張。立憲民主党は、機能強化に必要な法整備を議論するよう唱えた。”
自民、緊急事態へ改憲主張 立民は法整備訴え、参院憲法審
https://www.47news.jp/12457337.html
“参院憲法審査会は16日、衆院解散後の緊急時に参院が国会権能を暫定的に代行する「参院の緊急集会」を巡り討議した。自民党は緊急集会の機能の明確化や、憲法改正による緊急事態条項の創設を主張した。立憲民主党は機能強化に向けた法整備を論議すべきだと訴えた。”
参院憲法審、緊急集会を討議 自民に衆参「統一見解」求める意見も
https://digital.asahi.com/articles/AST4J3C3PT4JUTFK00RM.html
“今月2日の憲法審に続き、自民党の佐藤正久・与党筆頭幹事は「(緊急集会の)権能は原則として国会の全てに及ぶ」と指摘。憲法が衆院に先議権を与える予算案も「対応可能」とした。立憲民主党の小沢雅仁氏も「衆院の優越事項を緊急集会の権能制限の根拠とするのは本末転倒だ」と同調した。”
参院憲法審、与党もさらなる議論を要求 緊急事態下の国会機能維持を巡る改憲も波高し
https://www.sankei.com/article/20250416-45SHEGQJEZMTJFI5AT7WL2NMEM/
“衆院憲法審で緊急事態下の国会機能を強化するための改憲論議が煮詰まる中、参院側の意見集約は困難が予想され、早期の憲法改正は見通せない状況だ。”
“衆院では最も実現に近いと評されてきた改憲項目だが、与党もさらなる議論を要求している「参院の壁」は高そうだ。”
【国会議員から】熊谷裕人さん(立憲民主党・参議院議員/憲法審査会幹事)
わが会派は、2023年6月7日の会派代表意見において、ナショナルエマージェンシーという大震災等の深刻な国家緊急事態をも想定した憲法制定時の立法事実、戦前の権力暴走の反省に基づく制度趣旨、一刻も早い総選挙の実施を必然とする平時への強力な復元力の仕組みなどを踏まえ、緊急集会は国民主権、国会中心主義、基本的人権の尊重、平和主義という憲法の基本原理に基づき、かつ、これらの諸原理を守り抜くための制度であり、良識の府である参議院が世界に誇るべき制度と評価してまいりました。
そして、平成26年6月11日の本審査会附帯決議にも明記されている法令解釈のルールに基づく論究によって、衆議院議員の任期満了時については、54条2項の類推適用により緊急集会は開催可能と解すべきこと、緊急集会で参議院議員が発議できる議案は総理大臣の示した案件に関連のあるものに限る現行の国会法の制約は妥当なものであること、また、緊急集会の権能については、国に緊急の必要があるときに国会の機能を一時的に代行するものとして、法律、予算など広く国会権限に属するものに及ぶ一方、衆議院の単独議決や緊急の必要性の観点から、憲法改正の発議、内閣不信任決議は認められず、総理大臣の指名は臨時代理制度が適用できないほどの人的被害が生じた場合には、法律上は認め得るものとの見解を示してまいりました。
特に、発議議案については、内閣による新案件の追加のほか、参議院が内閣に新案件の追加を促し、必要に応じて内閣に代替措置の検討も含めた説明責任を果たさせる国会法の改正による緊急集会の権能強化策の提言もいたしました。
他方、任期延長改憲の論拠である緊急集会、平時の制度、70日間限定、単純な二院制の例外説等に対しては、緊急集会の立法事実や根本趣旨、憲法54条1項の解散時の内閣居座り排除の趣旨、二院制の補完制度としての制度趣旨などを繰り返し示し、それこそが憲法が起草されたときの立法意思であると考えているところであります。
こうしたわが会派の見解は、4月2日の自民党・佐藤筆頭幹事が述べた自民党会派の見解とも基本的に整合するものと認識しています。また、任期延長改憲の根拠である選挙困難事態について、その70日超という長期性の定義要件が70日限定説を根拠とすることに異を唱えていることについても認識を同じくしていることには深い敬意を表します。
また、わが会派は昨年の常会で、東日本大震災の際の立法例などを踏まえた緊急集会を動かすための課題検証を通じて、緊急集会は制度面、運用面の双方において基本的な仕組みは整備されており、現状でも国民のために機能することが可能であるとの見解を示す一方で、いわゆる議員版BCPの策定、災害対策基本法などにおける衆議院の任期満了の際の緊急集会の対処の明確化の法改正などを提起してまいりました。
ここで、昨年6月の参議院改革協議会の下の選挙制度専門委員会の報告書の本文において、二院制における参議院の機能、役割として、災害対応について、緊急集会の機能の充実強化が明記されており、まさに緊急集会の活用は参議院のあり方論の中核論点と言うべき位置づけになっております。この意味において、緊急集会70日限定説などに依拠する任期延長改憲の議論は、わが参議院の自律への不当な干渉であると言わざるを得ません。
本審査会において、緊急集会において法の支配、立憲主義に基づく議論を徹底すること、並びに、今後改革協議会の議論に憲法論から貢献するためにも、緊急集会の機能強化とその必要な法整備、さらには選挙制度との連携も含めた運用改善等の議論を精力的に行っていくことを提言して、私の意見とさせていただきます。
(憲法審査会での発言から)
2025年04月11日
憲法審査会レポート No.51
2025年4月10日(木) 第217回国会(常会)
第4回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55685
※「はじめから再生」をクリックしてください
【マスコミ報道から】
衆院憲法審 憲法改正是非問う国民投票“偽情報拡散 対応必要”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250410/k10014775691000.html
“…憲法改正の是非を問う国民投票のあり方について意見が交わされ、SNS上での偽情報の拡散が、結果に影響を及ぼすおそれがあるとして何らかの対応が必要だという意見が与野党双方から出されました。”
自民、偽情報「罰則が論点」 国民投票巡り衆院憲法審
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025041000838&g=pol
“自民の寺田稔氏は「偽情報があらゆる場面でかなり増えている。国民投票でも罰則規定を備えるべきかが一つの論点になる」と述べた。立民の岡田悟氏は「表現の自由や政治活動の自由を制限しかねない」と表明。SNS事業者など参考人から意見を聴く必要があると訴えた。”
【参考】
【憲法審査会】ネットの適正利用、フェイクニュース対策について。
https://yamahanaikuo.com/20250410-k/
“偽・誤情報によって民主的なプロセスが歪められることは立憲民主制にとって脅威といっていいでしょう。
しかし、ある情報を偽である、誤っていると国家が判定することについては慎重であるべきとも考えられます。学問の自由に関するものですが、天皇機関説事件というのは、国家が特定の学説を「誤っている」として排斥を始めたことに端を発しています。”
【傍聴者の感想】
今回のテーマは、「国民投票法におけるネットの適正利用、特にフェイクニュース対策」でした。
AIを用いて個人の情報をプロファイリングすることやSNS等にフェイクニュースが拡散することで、私たちの言論空間において意見が極端化し、選挙の公正の観点からいえば言論環境の混沌化によって選挙権者が適切に選挙権を行使できるか、選挙結果や民主主義に多大な影響を与える懸念が生じるといった参考人の見解から話されました。
フェイクニュースによって選挙結果が左右されたり、世論形成に影響が出た事例としては、昨年の兵庫県知事選が最も端的な例でしょう。その中で、何が真実で何がフェイクなのかを見極めることは至難の業だといえます。言論の自由、表現の自由は順守されてしかるべきですが、だからといってデマや偽の情報を垂れ流すことで人々を混乱に陥れたり誹謗中傷するような事態は許されません。国民投票の場に限らず、フェイクニュースを見つけ次第それを規制し拡散されるのを防ぐことが重要だと思います。また、日進月歩で発達する情報通信技術に対応し、私たちはリテラシー教育を受け情報を的確に判断し批判する能力を備えていかねばなりません。
インターネットの出現によって、情報の発信は個人でもたやすく行うことができますが、それだけに情報の正確性、迅速性、客観性、公平性、信頼性を担保することは、マスメディアはもちろん私たち一般市民にも求められています。
国立国会図書館からの調査報告書では、諸外国・地域からのフェイクニュース対策について報告されましたが、有志の会からは公職選挙法といった現行法だけではフェイクニュースの規制は不十分との意見が出ました。一方で、共産党やれいわ新選組からの発言で、罰則規定や規制強化によって、国家権力による情報統制や改憲に有利な意見が多数派を占めることで恣意的な判断がなされる等のリスクもあり、より徹底した議論と検証が必要ではないかと感じました。
最後に、日本維新の会等から「外国勢力」からのサイバー攻撃という発言がしきりに出ていたのを、違和感を持って聴いていたことを付け加えておきます。
【国会議員から】岡田悟さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会委員)
 国民投票におけるフェイクニュース対策について、私どもの考えを申し上げます。
国民投票におけるフェイクニュース対策について、私どもの考えを申し上げます。
昨今の選挙では、SNS等において、虚偽情報や個人の誹謗中傷が大規模に拡散され、選挙結果を左右していると言わざるを得ない状況が生じています。また、諸外国では、自国に外交上有利となるよう、SNS等での投稿を組織的に行うことで、他国の世論形成に影響を及ぼそうとする動きがあります。
なお、今国会では、選挙戦でのポスターへの品位を求める公職選挙法の改正が実現をしました。SNS等の規制も議論となりましたが、附則によって、今後必要な措置を講ずるものとされました。選挙や政治活動でSNS等を単純に規制することは、表現の自由や政治活動の自由等を制限しかねないため、慎重な検討が求められているものと理解しています。
さて、私は、昨年十月の総選挙で兵庫7区から立候補をし、比例近畿ブロックで当選をしましたが、その直後、十一月に兵庫県知事選挙が行われました。選挙期間中や、その前後における齋藤元彦兵庫県知事による県職員へのパワハラ疑惑等の公益通報をめぐる混乱は、皆様もよく御存じのとおりと思います。とりわけ選挙戦においては、一連の問題の告発者の方や、この問題を追及していた元県議会議員の方にまつわる虚偽情報、誹謗中傷がSNSや動画投稿サイト等を通じて広く拡散をされました。
自ら命を絶たれた告発者の方は、個人であるにもかかわらず誹謗中傷にさらされ、元県議会議員の方もまた、今年一月に亡くなりました。自殺と見られています。元県議会議員の方は、生前、SNS等に端を発した誹謗中傷に大変苦慮していると私の知人に打ち明けていました。
そして、これらの情報源には、日本維新の会に所属をしていた別の県議会議員が立花孝志氏に提供した文書が含まれていました。選挙で選ばれた公職にある者がフェイクニュースの情報源となった事実は、極めて深刻に受け止めなくてはなりません。
では、こうした深刻な状況の中、憲法改正の国民投票を適切に行うことが可能でしょうか。これまでの憲法審での議論を踏まえつつ、その方法とルール作りについて検討をしました。
憲法審ではこれまで、国民投票広報協議会がファクトチェックに関与する手法が提案をされてきました。他方、広報協議会によるファクトチェックは、公権力による表現の自由への過度な介入になり得るとの懸念も示されてきました。これを踏まえれば、いかに虚偽情報であろうとも、脅迫や人命に関わるデマなど、犯罪となるものを除けば、これを制限したり削除したりすることは、実際には困難です。
そこで、特に大きく拡散をされ、世論に与える影響が大きい投稿等について、SNS事業者から情報提供を受け、広報協議会が付随的情報提供を行うといった形が考えられます。拡散された虚偽の投稿に対して広報協議会が把握している事実は何々ですなどの文言を表示することで、有権者へ注意を促します。表現の自由への過度な介入を回避しつつ、有権者により正確な情報をお示しをするとすれば、この程度が限界ではないでしょうか。
また、昨今の選挙戦では、いわゆるアテンションエコノミーを利用した収益化、SNS等で金銭を支払って虚偽情報や誹謗中傷を拡散させることが問題化しています。兵庫県知事選挙においては、業務のクラウドソーシングを仲介するサイト、クラウドワークスを通じて、事実ではないが、より感情に訴えやすいセンセーショナルな内容の切り抜き動画を作成する業務が発注され、受注者は自身の政治信条とは無関係に動画を作成して金銭を受け取っていたことが明らかになっています。これは公職選挙法をめぐる議論でも論点となっていますが、国民投票でのこうした収益化は、罰則を設けるなどして厳しく禁止をするべきでしょう。
もっとも、これらの方法でフェイクニュースの問題が十分に解決をできるとは考えておりません。虚偽情報の拡散のスピードと、これが定着をしてから説明を尽くして誤解を解くことの困難さは、国内外の多くの専門家が指摘をしているところですし、私自身も日々地元で経験をしています。
SNS等で既に生じているこれらの問題については、後ほど米山隆一委員からお話をいただきます。
また、縷々申し述べました国民投票の公平及び公正さを確保する方法を検討する中で、例えば、広報協議会とファクトチェック機関との連携の在り方、そして広報協議会とSNS事業者との連携の在り方など、より検討を深めるべき論点があるものと考えます。そのため、今後は、専門家やSNS事業者を参考人として招致をし、意見を伺う機会を設けることが適当であると考えます。
(憲法審査会での発言から)
【国会議員から】米山隆一さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会委員)
 私は、憲法投票における様々な広報協議会のようなファクトチェック機関等を前提とした上で、その実施に先立って、先ず、先ほど法制局からも話のあった通常の言論空間における健全性の確立の必要性について申し上げたいと思います。
私は、憲法投票における様々な広報協議会のようなファクトチェック機関等を前提とした上で、その実施に先立って、先ず、先ほど法制局からも話のあった通常の言論空間における健全性の確立の必要性について申し上げたいと思います。
現在のSNS上の言論空間は、偽情報や誹謗中傷があふれております。2020年にプロレスラーの木村花さんがネット上の誹謗中傷が原因で命を絶ち、2022年に侮辱罪の法定刑を「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」とする厳罰化が成されましたが効果なく、昨年の兵庫県知事選挙では、数々の偽情報が流された末に、誹謗中傷の標的となった兵庫県議会議員が命を絶つという痛ましい事件がございました。
私自身も昨年は、「論破王」ともてはやされたものとまったく同じ動画に、今年は「論破されて涙目」という真逆のタイトルがついて流布している状態で、要は偽情報・誹謗中傷を流す人にとって中身は無関係、それらしい動画に勝手な煽り文句と誹謗中傷を入れて動画サイトに置けば、面白がる人によって拡散され、少なからぬ人が命を絶つほどに傷つけられ、世論が大きく左右されるということが現在進行形で起こっているわけです。
このような状況で国論を二分する憲法改正の国民投票を行った場合、憲法改正の発議そのものについては、ファクトチェックや法規制等によって一定の適正化が図られたとしても、今度は、その賛否を問う活動をする人、今ここに御列席の各党の議員の方々を始め市民の方々までもが標的にされ、激しい偽情報や誹謗中傷にさらされ、それらによって投票結果が大きくゆがめられる事態が生じる可能性は極めて高いと思います。
我々が公正に形成された民意を適切に反映した憲法改正を行うには、国民投票におけるファクトチェック他の法規制のみならず、まず、今現になされているSNS上での偽情報や誹謗中傷に対し、憲法で保障される言論の自由の観点も考慮しつつ、刑法、情報流通プラットフォーム対処法等の諸法令を改正・整備し、適正な言論空間の確立をする必要があることを強く申し上げます。
今ほどの私の見解に対して、2020年にインターネットの誹謗中傷対策は侮辱罪の厳罰化で事足れりとして現在に至るまで不十分な対策しか打てていない自民党と、外国勢力からの介入に対しては非常に敏感な割に先の兵庫県知事選挙において誹謗中傷の原因となった真偽不明の情報の流布に加担した県議が所属しておられました日本維新の会に御意見を伺わせていただきます。
(憲法審査会での発言から)
2025年04月04日
憲法審査会レポート No.50
2025年4月2日(水)第217回国会(常会)
第1回 参議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8420
【マスコミ報道から】
参院憲法審査会 衆院側の“緊急集会 活動期間規定”発言に疑問
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250402/k10014768161000.html
“参議院憲法審査会が今の国会で初めて開かれ、大規模災害など緊急事態が発生した際の国会機能の維持に関連し、先週の衆議院の審査会で、参議院の緊急集会の活動期間を規定するような発言があったことに疑問を呈する意見などが出されました。”
参院憲法審、今国会初の討議 緊急時の国会機能論点に
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025040200850&g=pol
“自民党の佐藤正久氏は、憲法54条が定める参院の「緊急集会」について「(現行の)憲法において緊急事態に対応するための唯一の条項で、参院の重要な権能だ」と指摘。「緊急性があれば、権限行使の範囲を限定的、制約的に整理する必要はない」と主張した。”
憲法審の自民主張、衆参で「ちぐはぐ」 参院の緊急集会巡り
https://mainichi.jp/articles/20250402/k00/00m/010/173000c
“衆院側は緊急事態時に衆院議員が任期満了を迎えて不在となることを避けるため、議員任期延長を図る憲法改正を目指す。一方、参院側では自らの権限を抑制することへの否定的な意見が根強い。”
立民・小西洋之氏が自民の「ヒゲの隊長」を絶賛 衆院との微妙な距離が表面化 参院憲法審
https://www.sankei.com/article/20250402-BURNSXXVZNLL7AAAO33N4XVKPY/
“これまでも参院憲法審の議論は衆院に比べて遅れており、9日の次回定例日も幹事懇談会の開催にとどまり、討議は行われない見通しだ。”
【傍聴者の感想】
今年最初の参議院憲法審査会は、冒頭、欠員となっていた委員1人の選任を確認したのち、「憲法についての考え方」を各会派の代表が述べることから始まりました。
最初に自民党の佐藤正久議員は、これまで衆議院の自民党が参院の緊急集会の効力は70日間(解散から選挙まで40日、選挙から特別国会まで30日)に限られると主張してきたことにかかわり、これを明確に否定し、「緊急集会は現憲法の唯一の緊急事態条項として70日に限定すべきではない」とした上で、むしろ緊急集会の権能などについてあいまいな部分を憲法に明記する、緊急事態についての整理をはかることが必要という趣旨の主張をしました。
立憲民主党の辻元清美議員は、緊急時だから任期延長ではなく、緊急時でも選挙ができる強い制度作りこそが重要であること、また同性婚や優生保護法、夫婦別姓などで違憲判決が続いていることへの対応や、国民投票法の問題が優先されなければならないことを主張しました。
以下、公明、維新の会、国民民主、共産、れいわ、沖縄の風と発言が続き、その後、発言を希望する委員が意見を述べるという展開で進みました。
11人の委員が発言し、自民党議員は、合区解消、教育の充実、自衛隊明記を繰り返し、立憲野党からは、同性婚や夫婦別姓、インターネットの適正使用などについての意見が多く出されました。
参院は、参院の役割を高めるという認識が会派共通の土台としてあり、衆院のような稚拙で感情的な議論は比較的、控えられています。
違憲状態にある法律やその運用を是正する議論につなげていき、憲法審査会の本来の役割をはたしていってもらいたいと強く思います。
【国会議員から】辻元清美さん(立憲民主党・参議院議員/憲法審査会筆頭幹事)
 今年は、戦後80年に当たる年です。かつて日本は、全体主義と軍国主義という政府の過ちによる戦争で甚大な惨過がもたらされました。
今年は、戦後80年に当たる年です。かつて日本は、全体主義と軍国主義という政府の過ちによる戦争で甚大な惨過がもたらされました。
沖縄では4人に1人が亡くなり、私の父方の祖父もブーゲンビルで戦死しております。皆様の周辺にも犠牲者がいらっしゃるのではないでしょうか。
その反省の下、今日まで80年間のわが国の発展は、平和主義を掲げ、世界屈指の人権法典として優れた日本国憲法に基づくものと言えます。改めて、この節目の年に、憲法の意義について、石破総理は談話を閣議決定しないとおっしゃっていますので、本審査会で意義について議論してはいかがでしょうか。
さて、日本国憲法は、戦前戦後の内閣法制局長官を務められた金森徳次郎担当大臣や佐藤達夫先生などの法律家と先輩議員の懸命の努力によって制定されました。国会は二院制を採用していますが、元々、総司令部案では一院制でした。これに対して、日本側の強い意志により、現在の憲法の二院制になったという経緯があります。この経緯を見ても。押しつけ憲法ではないと言えます。日本国憲法第54条に、参議院の緊急集会が制定された経緯も戦争への反省に基づいたものと言えるでしょう。
憲法制定会議で、憲法担当の金森大臣は、戦前の緊急政令を認めないためにも参議院の緊急集会を設けた、さらには、非常の場合の暫定措置はやはり行政権ではなく国会が行うべきだと発言しています。また、大日本帝国憲法下、1941年2月に法律を改正して、1942年4月まで一年間選挙を延長し、その間に国民の信を問うことなく、1941年12月8日に無謀な日米開戦に突っ込み、何百万人もの犠牲者を出した歴史があります。この歴を踏まえるならば、安易に緊急事態条項の制定とか衆議院の任期延長とは言えないはずです。
参議院の緊急集会という制度は、災害時などだけではなく、後世の私たちが同じ過ちを繰り返さないために、戦争への歯止めとして憲法に組み込まれた仕組みという側面があります。戦後80年、憲法審査会の私たちがこれをしっかりと肝に銘じなければなりません。
さて、参議院では、昨年6月の参議院改革協議会の選挙制度専門委員会報告書で、緊急集会の機能の充実強化が明記されております。本審査会でもこれまで緊急集会の運用について充実した議論を行ってまいりましたが、機能強化や制度整備、選挙制度との関係などの議論を深めることは有意義であると考えます。
また、昨年、公明党の幹事からは、選挙困難事態の全国一斉選挙の必要性に対して、繰延べ投票でなぜいけないのか、衆議院議員の任期延長には民主的正統性の問題がある旨述べられ、問われるべきは、大災害時においてもできる限り選挙を行うことができる、災害に強い選挙制度をどう整えるかであるという旨の発言をされました。
戦前の反省からも、安易に任期延長を論じるのではなく、まずは、いかなる事態でも民主主義の源である選挙ができる制度の具体化の議論を深めるべきです。これこそ、立法府の私たちの役割ではないでしょうか。
また、国会法102条6に定められている憲法審査会の法的な任務として、憲法違反問題などの調査審議があります。3月25日の大阪高裁まで5つの高裁で違憲判決が出ている同性婚禁止、あるいは、2023年10月25日に最高裁は性同一障害の生殖能力に関する規定の違憲判決を出しました。さらに、選択的夫婦別姓、憲法53条の臨時国会の召集義務違反など、憲法問題として本審査会の任務としてしっかりと調査審議する必要があります。
さらには、国民投票について、テレビやネットのCM規制、ネット上のフェイク情報の対処など、さらには広報協議会のあり方について何ら解決されておらず、これら結論を得ない限り、国民投票の実施は困難と考えます。憲法21条の表現の自由との関係や、インターネット社会の民主主義のあり方についての検証と憲法論議も必要だと考えます。
最後に、緊急集会についての議論のあり方について一言申し上げます。
立憲民主党では、衆議院の憲法審査においてこのような発言をいたしております。参議院の緊急集会でできないことを前提として衆議院で議論を進めることは、参議院の自律に対する干渉ではないかと問題提起をいたしました。
緊急集会のあり方は参議院全体に関わる事項であり、参議院改革協議会などで広範な議論が必要です。参議院の憲法審査会だけで結論を出すことはできないばかりではなく、参議院を差しおいて衆議院の憲法審査でその機能などについて結論を出すような事項ではないということは、参議院憲法審査会の各党の合意がなされるものと存じます。念のためにこの点も申請して、発言を終わります。
(憲法審査会での発言から)
【国会議員から】打越さく良さん(立憲民主党・参議院議員/憲法審査会委員)
 憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うべき機関です(国会法第102条の6)。
憲法審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行うべき機関です(国会法第102条の6)。
従って、日本国憲法に違反すると主張されながら改正されず放置されている法律について調査を行うことも当審査会の責務です。
民法等において同性婚や選択的夫婦別姓が認められないことが憲法に違反しないかが争われ続けています。本年3月25日、大阪高裁は同性婚を法律婚の対象としない民法等の規定は、性的指向が同性に向く者の個人の尊厳を著しく損なうものであり、かつ、婚姻制度の利用の可否について性的指向による不合理な差別をするもので法の下の平等に反するとして、憲法14条1項及び24条2項に違反すると判断しました。これまで5つの高等裁判所全てが違憲と判断しています。なお、昨年12月13日の福岡高裁判決は、同性婚を認めないことが憲法13条にも違反すると断じました。
夫婦同氏規定については、今まで3回最高裁で判断されています。私が弁護団事務局長を務めた第一次夫婦別姓訴訟の最高裁判決では15人の裁判官のうち5人が違憲と判断しました。今まで合計35人の最高裁の裁判官のうち10人が夫婦同氏規定を違憲であると判断しています。芦部信喜の『憲法』第8版では「夫婦同氏強制を憲法違反だとする学説が多数である」と記述されるに至っています(144ページ)。
もとより司法判断があろうとなかろうと、違憲判断が確定しようとしていまいと、憲法上疑義のある法律を放置する立法府であってはなりません。
同性婚や選択的夫婦別姓は、反対の人に同性婚や夫婦別姓を強いるものではありません。導入しても、誰も不幸になりません。むしろ社会全体の幸福の総量は確実に増大します。
戦後、法令違憲の最高裁判断は、13件しかありませんが、うち6件がジェンダーや家族に関する規定であることは偶然でしょうか。今日あげた同性婚や選択的夫婦別姓もジェンダー、家族にかかわることです。このような状況では、立法府が、廃止された家制度に郷愁を感じている一部の方々に忖度していると疑われてしまいます。憲法が個人の尊厳を尊重し、平等を実現すべきとさし示していることが未だ実現できていません。家制度はとうにありません。憲法に添わないとの疑義を持たれる立法を放置せず改めるのが私たち立法府の責任であることを申し上げ、意見とします。
(憲法審査会での発言から)
【国会議員から】小西洋之さん(立憲民主党・参議院議員/憲法審査会委員)
 わが会派は、これまで任期延長改憲の理由である緊急集会、平時の制度、70日間限定、二院制の例外の主張について、戦後議会で確立し、2014年6月の本審査会附帯決議に明記の法令解釈のルール、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものを満たすのか、その論証の文書提出を求めてまいりましたが、いまだ提出はありません。
わが会派は、これまで任期延長改憲の理由である緊急集会、平時の制度、70日間限定、二院制の例外の主張について、戦後議会で確立し、2014年6月の本審査会附帯決議に明記の法令解釈のルール、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、論理的に確定されるべきものを満たすのか、その論証の文書提出を求めてまいりましたが、いまだ提出はありません。
一方、衆議院では、この法令解釈のルールが関知されることもなく、去る3月27日の衆議院憲法審では当方の指摘を受けて、衆議院法制局が、参議院憲法審では何度も議論されてきた緊急集会の立法事実の根幹、災害対処等に関するGHQとの交渉記録3ページ余りを初めて追加し、また一見学説紹介にように見える、平時の制度に過ぎないとの意見もありとの不可解な記述を削除するなどに至りました。
なお、この度衆院では54条1項の40、30日の規定が2項以下の緊急集会の開催期限を法的に制限するという連関構造説なるものが唱えられています。
しかし、これについては、54条1項の40、30日の規定が2項以下の緊急集会の開催期限を法的に制限するという連関構造説なるものが唱えられています。
しかし、これについては、54条の1項の40、30日は、比較法的にも解散時の内閣の居座り排除の規定、GHQとの議論でのナショナルエマージェンシーという深刻な国家緊急事態をも想定した立法事実、そして、条文技術的に現行の54条2項、3項に置かれたという立法経緯等に照らし、連関構造説なるものは法令解釈とは言えない暴論と考えます。このことは、長谷部、土井両教授も本審査会で明確に解釈論として無理があると答弁くださいました。
また、憲法制定議会の金森担当大臣の答弁においては、緊急集会は全体の改選期がある衆議院を定めたわが国の二院制において、国会制度の趣旨を徹底して実行する、すなわち衆議院不在の不便を補う合理的な制度として創設されたことが明確に説明されています。要するに、緊急集会は、両院同時活動が論理必然的に不可能な場合のあるわが国の二院制の機能を補う、つまり、二院制を補完するための制度であり、二院制の例外制度ではありません。衆参改憲派の主張は本末転倒極まりないものと言うほかありません。
なお、27日の衆議院憲法審では、金森大臣のこの説明答弁の中での解散後の70日は国会を開けない状況になるとの箇所を、70日間限定説の根拠としていますが、そうした解釈は金森大臣が丁寧に論じる二院制の補完機能という緊急集会の根本趣旨に反する典型的な言語道断の切り取り解釈です。
法令解釈のルールに基づくあるべき解釈論としては、金森大臣のどんなに精緻な憲法を定めても口実をつけこまれ、破壊される恐れが絶無とは断言し難いとの戦前の反省に基づく緊急集会採用の根本趣旨、さらには国会と国民の表裏一体化を確保する観点からは不便が起きることはやむを得ないと明確に衆議院議員の任期延長を憲法の制度設計として否定していること、さらには54条3項が有する地上最大の政治的パワーとも言うべき一刻も早い総選挙を実施させる復元力、レジリエンスとその後の衆議院の厳格な同意制度からは、70日限定説を法令解釈と認める余地はまったくあり得ません。
緊急集会について、法の支配、立憲主義、憲法の基本原理に基づく議論を求めつつ、先ほどの佐藤筆頭幹事の良識の府の参議院の矜持あふれる緊急集会の意見表明に深い敬意を表しつつ、私の意見とさせていただきます。
(憲法審査会での発言から)
2025年4月3日(木) 第217回国会(常会)
第3回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55650
※「はじめから再生」をクリックしてください
【マスコミ報道から】
衆院憲法審査会 憲法改正の国民投票 ネット広告に対策が必要
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250403/k10014768921000.html
“衆議院憲法審査会で、国民投票を行う際の広告のあり方について議論が行われ、与野党から、インターネット広告は有権者の冷静な判断に影響を及ぼすおそれがあるとして、ガイドラインの策定など対策が必要だという指摘が出されました。”
改憲CM規制で温度差 自民慎重、立民は議論必要 衆院憲法審査会
https://nordot.app/1280382114579678035
“自民党は政党間の申し合わせなどの措置を組み合わせれば公平性を保てるとして、規制強化に慎重な考えを表明。立憲民主党は資金量が投票行動に与える影響を懸念し、議論の必要性を訴えた。両党の立場には温度差が生じた。”
自民、改憲CMで規制強化に慎重 衆院憲法審で討議
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025040300936&g=pol
“立憲民主党の津村啓介氏は、事業者の自主規制には「大きな疑義」が生じていると指摘。さらに2015年に大阪市で行われた「大阪都構想」を巡る住民投票で、賛成派のCMが反対派の「約4倍の量だった」と述べ、規制議論の必要性を訴えた。”
党派超えた苦言も「引くつもりはない」裏方批判の立民新人 憲法審で「学説の捏造」発言
https://www.sankei.com/article/20250403-T5X73E5M7ZAGBEL7EXQY2RGJAM/
“藤原氏は3月27日の憲法審で、法制局の資料について「こまぎれ、ばらばらに学説が分類されている。学説の捏造といわれても仕方がない。改憲派の先生方を容易にミスリードし得るものだ」と発言した。”
【傍聴者の感想】
今回の憲法審査会は定時になっても始まらず、約10分遅れで開始されました。本日のテーマは「憲法改正国民投票法を巡る諸問題」で特に放送CM、ネットCMについて自由討議が行われました。
枝野会長から冒頭、前回の審査会において発言時間の割り当て等についての問題提起があり、割り当て時間と答弁時間の関係や質問にあたっての留意事項などが改めて確認されました。
そのなかで前回の審査会での事務方に対する「不適切発言」への注意がありました。立憲民主党の藤原規眞議員の発言に関するもののようです。
その後自由討議に入りました。
放送CMについて、現行の国民投票法では「投票日前2週間、勧誘CM禁止」を規定しています。一方でネットCMは法規制がありません。私は、これでは不公平ではないかと思いました。いっぽう、厳しい法規制をすると「表現の自由」との関連で問題かもしれませんし、しかしだからと言って自主規制にして好き勝手できる状態になってしまうのは、どうなのかと思ってしまいます。
そんなことを思いながら各議員の発言を聞いていた私は余計にわからなくなってしまいそうでしたが立憲民主党の吉田はるみ議員の「民意がお金で買われてはいけない」という発言で私の中のモヤモヤはスッキリした感じがしました。政治家の主張や政策を拡散する自由はお金で保障されてはいけないと声を大にして言いたくなりました。
私が今まで傍聴した憲法審査会は片手で数えられる程度ですが、今回は自分の理解が深まる経験があったことで、傍聴したなかでは初めて、次回の審査会はどのような議論がされるんだろうと、ワクワクした気持ちになりました。
【国会議員から】津村啓介さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会幹事)
 私たち立憲民主党は、憲法改正国民投票法につき、かねてより①憲法改正案に対する賛否の勧誘のための広告放送の全面禁止、②政党等による賛否の意見表明のための広告放送の全面禁止、③政党等によるインターネット有料広告の禁止などを具体的に提案してきました。
私たち立憲民主党は、憲法改正国民投票法につき、かねてより①憲法改正案に対する賛否の勧誘のための広告放送の全面禁止、②政党等による賛否の意見表明のための広告放送の全面禁止、③政党等によるインターネット有料広告の禁止などを具体的に提案してきました。
国民投票法の附則4条は、施行後3年を目途に「国民投票運動等のための広告放送およびインターネット等を利用する方法による有料広告の制限」について検討を加え、
必要な法制上の措置を講ずることを定めています。
立憲民主党は、なぜこの検討条項が附則に盛り込まれたのか、という原点を確認することからこの議論をスタートしたいと考えます。
もともと国民投票法が立案された際には、憲法改正の賛否を問う国民投票は、人間を選ぶ通常選挙とは大きく異なる性質を持つことが意識されていました。
公職選挙法は今から75年前、1950年に制定されて以来、社会環境の変化や情報技術の進歩に伴い、幾たびも改正されてきました。
しかし、国民投票に関しては、必ずしも公職選挙法と同様の立法事実が確認されえない場合も存在しえます。
そのため、①(有権者名簿の作成や投・開票に関する事務など)投票そのものに関するルールについては基本的に公職選挙法に準拠するものとしつつ、他方、②いわゆる運動に関するルールについては、ゼロベースで検討をしたうえで、必要最小限度のものとするという原則にのっとって立案された経緯があります。
放送CMについては、当初から禁止すべきとの議論がありました。
欧州の先行事例を俯瞰いたしますと、フランスでは国民投票については放送CMは全面的に禁止されています。イタリアも、地方局では一定の要件のもとに認められる場合があるものの、全国放送の放送CMは禁止。デンマークでも放送CM全面禁止、スイスではテレビのみならず、ラジオの放送CMも禁止されています。
なお2016年に実施されたイギリスのEU離脱、いわゆるブレクジットに関する国民投票に際しても、放送CMは全面禁止され、賛成派と反対派の双方に同じ量の放送枠を無償提供するルールが採用されました。
こうした世界的な潮流を受け、日本における国民投票法制定時にも、放送CMは禁止すべきとの見解がありました。
しかし、2006年6月の衆議院憲法調査特別委員会において、賛否の双方にイコールタイムの確保が可能かという趣旨の質問に対して、民放連の参考人が「放送CMについて自主規制はできるし、やらなければならない」との趣旨を発言されたことから、法的規制ではなく、自主規制で目的が達成可能との認識で現行法の仕組みが出来上がった経緯です。
ところが、2019年5月9日、衆議院憲法審査会の冒頭の意見表明において民放連の永原専務理事は、「…民放連としましては、昨年九月の理事会でCM量の自主規制は行わないという方針を決定して以来、国民投票運動の放送対応について進めてきた検討作業は、これで一区切りとなります。…昨年九月の理事会で、CM量に特化した自主規制は行わないと決定したわけでございます。……」と発言をされました。
ここにおいて、本件の議論の前提が大きく変わりました。
この問題が再燃したきっかけは、もう一つあります。
2015年に大阪市において行われた、大阪市を廃止して府と統合して特別区を設置する、いわゆる大阪都構想に関する第1回目の住民投票です。運動期間中、放送CMについて、賛成派が反対派の約4倍の量であったなどの指摘がなされました。
国民投票法制定時に述べられた民放連の自主規制表明には、既にこの時点で疑義が生じていたともいえます。
このように、国民投票法制定当時において前提とされていた民放連の対応に齟齬が生じたことに加え、必ずしも立法事実が確認できないとされていた放送CM規制の重要性、有効性が確認されたことから、改めて放送についてのCM規制について議論する必要性が生じたと思料いたします。
なお翻って、当憲法審査会での議論を眺めても、資金の多寡によって情報の差がつきやすいことへの懸念や、外国政府の介入の恐れ等を指摘する意見表明が国民民主党の玉木雄一郎議員や立憲民主党の奥野総一郎議員からなされてきたことは、先ほどの橘法制局長のご説明にもあるとおりです。
放送については他のメディアにはない特徴があります。免許制がとられていること、番組編集準則(放送法4条)が定められていることなどです。
なぜ放送についてはこのようなことが認められているのかについて、伝統的な見解は、①電波の有限性・希少性と、②社会的影響力の大きさから、特殊な規律があっても憲法違反ではないという説明をしてきました。
伝統的な理解に従えば、放送CMについては、規制の余地がより大きく存在すると考えられます。しかしながら、いわゆるネットCMについて規制をする根拠をどのように考えるかは、放送CMとは切り分けて考える必要があります。
この点は、本日この後ご発言される同僚議員の指摘に委ねたいと考えます。
最後に、当審査会において、放送規制の根拠やネットの規制の可能性について、学識経験者から最新の知見を拝聴する機会を設けていただくことを提案して、立憲民主党を代表しての私の意見とさせていただきます。
(憲法審査会での発言から)
【国会議員から】吉田晴美さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会委員)
最も大切なことは、民意がお金で買われてはならない、という点です。
ネットCM規制をする場合、コンテンツを規制することは「表現の自由」の観点から慎重な対応が必要です。一方、発信方法に関しては、バズれば儲かるという収益モデルがあり、問題を深堀する必要があります。
言論の自由、そして表現の自由は守るというスタンスを明確にした上で、議論させて頂きます。
ネットCMは、お金を出す広告主とSNSなどプラットフォーマーとの間での取引ですが、現実はすでにこのネットCMを超えた、いわば「隠れネットCM」ともいうべきものが存在しています。
ある学生の提案にはっと気づかされました。「政治に興味を持って欲しいなら、人気のあるインフルエンサーの人に発信してもらえばいい。」この場合、ある人が、インフルエンサーにお金を払って、特定の政治的主張を広めることが可能です。この場合、取引は個人間にとどまり、表に出てこない。支払われるお金の規模、そして実態は見えず闇の中になりかねません。
このような事態も起きています。一昨日投票が行われたアメリカのウィスコンシン州の州最高裁判事の選挙で、Xの所有者であるイーロン・マスク氏は支持しない判事に反対する請願書に署名した有権者2人に100万ドルの小切手を渡し、署名した人にも各100ドルを支払い、その総額は日本円で30億円を超えると報道されています。
政治的自由は、こうしたお金の影響力を断ち切ることで初めて担保されるのではないでしょうか。政治家の主張や政策を拡散する自由は保証されるべきです。しかしそれは、お金を介さずとも個々人の思いで支援し、共鳴する内容であれば拡散するはずです。
バズって再生回数を稼ぎ収益を得るというアテンションエコノミーは、2013年の公職選挙法改正の時点では想定できませんでした。中には誹謗中傷など人を傷つけ、自死にまで追いやってしまう事案も発生しています。政治・選挙を「稼ぐ材料」にしてはならない。政治や選挙関係のコンテンツの動画拡散は、広告料収入の適用外とすべきではないかと考えますが、各党のご見解を伺います。
(憲法審査会での発言から)
2025年03月28日
憲法審査会レポート No.49
2025年3月27日(木) 第217回国会(常会)
第2回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55630
※「はじめから再生」をクリックしてください
【マスコミ報道から】
衆議院憲法審査会 大規模災害などでの国会機能維持で議論
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250327/k10014762311000.html
“衆議院憲法審査会が開かれ、大規模災害などの緊急事態の際に、参議院の緊急集会で国会機能を維持する期間について自民党が最大70日程度と主張したのに対し、立憲民主党は期間を限定すべきではないという考えを示しました。”
緊急集会、自民「最大70日」=立民は期間限定に反対―衆院憲法審
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025032700894&g=pol
“憲法54条は、衆院解散時に「緊急の必要」がある場合は内閣が参院に緊急集会を求めることができると規定。開催期間については、解散から特別国会召集までの最大70日とする見解がある。”
衆院憲法審、期間・権能の見解に隔たり 参院の緊急集会
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA271B40X20C25A3000000/
“自民党は参院の緊急集会の開催期間は最大70日程度とすべきだと主張した。総選挙の実施が見通せない場合も妥当だと話した。立憲民主党は想定外の事態などを念頭に70日に限らないとの立場に立つ。”
衆院解散後の「緊急集会」で見解割れる…自民は「例外」、立民は反論 衆院憲法審査会
https://www.sankei.com/article/20250327-YPEYK4VNZBMPZOXOLSCSSRWRVU/
“自民の船田元氏は「安易に解釈を拡大するのは避けるべきだ」と述べ、70日を大幅に上回れば憲法の想定を大きく超えると懸念を示した。立民の武正公一氏は「緊急集会は参院のみに認められた独自機能だ」と指摘。緊急集会で対応できないことを前提にした議論は、参院への干渉との評価もあり得るとした。”
【参考】
衆院憲法審査会が緊急事態条項を3月27日に採決? 採決の予定は無い【ファクトチェック】
https://www.factcheckcenter.jp/fact-check/politics/false-emergency-clause-vote/
“2025年3月27日の衆院憲法審査会で緊急事態条項を採決しようとしているとの主張は誤り。3月27日は参議院の緊急集会について討議する予定だ。”
※右派のなかにも「緊急事態条項反対」を主張するグループがあり、そうした人びとの間で、SNSなどをつうじて「3月27日採決」との風説が流布していました。
【傍聴者の感想】
今国会2回目の衆議院憲法審査会は、枝野会長から進行の説明の後、衆議院法制局・衆議院憲法審査会事務局が提出した「『参議院の緊急集会』の射程に関する資料」の説明から始まりました。「一切の私見を挟まずに、客観的にご説明いたしました」といって法制局からの発言が終わると、場内に失笑が漏れていました。
憲法審査会の傍聴は、これまでたまたま参議院ばかりでしたので、初めての衆議院での傍聴となりました。過去の議論を見知る中で想像していたよりも盛り上がりに欠けていたというのが正直な感想です。「参議院の緊急集会」を念頭に発言が続いていましたが、「壊れたテープレコーダー」と揶揄されるように同じところを行ったり来たりしていました。その合間に言葉尻を捉えるような発言が挟まって時間が過ぎていってしまうような感じでした。
自民、立憲、維新…と各会派が順に発言していく中で、気になったのは維新の発言です。法制度設計について、これ見よがしに「大陸型」などの用語を使っていたことです。政治学の教科書にいくらでも書いてあるような言葉ですが、「もっともらしい」と感じられるということでしょうか。なんかすごい…と思わせることが、彼らのやり方なのだと再認識させられました。
実際に、日本が地震大国であることは疑いようもないことですし、自然災害に備えるということが主張されるのも理解が出来ます。でも、どうしてそれが憲法改正の話にまで及ぶのでしょうか。選挙が出来ないほどの事態を考えるのならば、なぜ原発再稼働なんて選択ができるのでしょう。やっていることと言っていることとの高低差に頭が痛くなりました。
【国会議員から】武正公一さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会筆頭幹事)
 前回、選挙困難事態に関する「立法事実」をテーマとしました。立憲民主党は、有権者の投票する権利の尊重並びに、選ばれる側の居座りを許さないという点から臨みました。本日のテーマ「参議院の緊急集会の射程」にも関係しますので、冒頭「選挙困難事態」に触れます。
前回、選挙困難事態に関する「立法事実」をテーマとしました。立憲民主党は、有権者の投票する権利の尊重並びに、選ばれる側の居座りを許さないという点から臨みました。本日のテーマ「参議院の緊急集会の射程」にも関係しますので、冒頭「選挙困難事態」に触れます。
北海道南西沖地震に際して壊滅状態の奥尻島で選挙は行われました。
東日本大震災の時に、福島県内の喜多方市議選、矢祭町長選、古殿町長選、玉川村長選、北塩原村議選、鮫川村議選では選挙が実施されました。
昨年9月の石川県豪雨災害直後、被災地石川3区も衆議院議員選挙が行われました。投票率は、輪島市で10%下がったものの、わが党の近藤和也衆議院議員など、選挙を経て復旧復興のために引き続き取り組んだことも事実です。
前回も、この場で申し上げたように、被災地の復旧復興のためにもできるだけ早く代表者を選ぶ必要があると考えます。
選挙実施が困難な場合は国政選挙でも繰り延べ投票で対応すべきと考えます。そして、国政選挙などでは「一体性」を憲法も要請はしていないこと。今仮に、東日本大震災と同じ規模の災害が衆議院議員選挙前に起きても8割以上の衆議院議員を選ぶことができることから、選挙困難時の立法事実とするのは難しいと前回立憲民主党議員より述べました。
取り組むべきは、いかに選挙困難時期にあっても選挙ができる体制を組むかです。
平時において、投票環境の整備が急務の課題です。選挙困難時を想定した「有権者名簿など選挙データのバックアップ体制」「インターネット投票」「郵便投票」の検討、拡充です。また、期日前投票所の拡充、共通投票所の実施などできることは今でもあるはずです。
特に、投票日に、指定された投票所以外にだれでも投票できる「共通投票所」は、令和6年衆院選時点で、15市、16町、6村の226ケ所の設置にとどまっています。災害時に選挙区を離れて投票所を設けるためにも、二重投票を防ぐ仕組みをもって各自治体が共通投票所を設置することは有効ではないでしょうか。
ちなみに、今、横浜市では各区内の投票所すべてを共通投票所にして、各投票所独自の有権者名簿を投票所間で共通化して無線で確認を行い二重投票を防ぐシステムづくりが進められていると聞いています。
そのうえで、憲法54条にいう緊急集会について述べます。
「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する」(42条)とされていて、いわゆる二院制を採用しています。
もともと1946年2月13日に連合国最高司令官総司令部(GHQ)が日本政府に対して提示した総司令部案(マッカーサー草案)では一院制とされていました。これに対して、日本側が二院制の必要性を求め、現在の憲法の二院制になったという経緯があります。
その二院制の機能や役割分担のレベルを超えて、制度としてまったく独自のものとして存在しているのが参議院の緊急集会制度(54条)です。
これは、緊急事態に際して大日本帝国憲法時代には天皇の緊急勅令(明治憲法8条)や緊急財政処分(明治憲法70条)で対処するとされていたものを、国会中心主義の貫徹という趣旨から、参議院の緊急集会をもって対応することとしたものです。
金森国務大臣が制憲議会で「戦前の緊急政令」を認めないためにも参議院の「緊急集会」を設けたと言っています。大日本国憲法下1941年2月に法律をして1942年4月まで1年間選挙を延期したうえ、1941年12月には日米開戦に踏み切ってしまった反省にも立っていると考えます。
諸外国の憲法には緊急事態に関する規定があるのに日本国憲法にはないという趣旨の発言もあったかと思いますが、各種文献でも、この緊急集会の制度は世界に類例を見ないものと評価されていることからもわかるように、他の国々とは違う形で制度設計していることから、他の国々と同様の規定を探せば日本国憲法に規定がないというのは当然のことで、「緊急事態に際して対処すべき規定があるか」という観点から検討すれば、緊急集会の条文がこれに当たる、というのは明らかだと考えられます。先人たちはすでに「想定外」の事態の規定を設けていたというわけです。
憲法54条についてはその趣旨に基づいて参議院の緊急集会を適切に開催してゆくべきと考えます。特に、緊急集会70日限定説をとらないということを前回も申し述べています。
ところで、衆議院・参議院は相互に独立して審議・議決を行う機関ですから、他の機関や他の院の干渉を排して行動できる、いわゆる自律権を持っています(58条1項・55条)。
所掌事項という言葉が適切かどうかわかりませんが、参議院の緊急集会というのは参議院にのみ認められた独自の権能であるといえます。
したがって、参議院が「緊急集会で対応できる」と判断する可能性のある事項について、衆議院側で「緊急集会では対応できない」という判断をすべきできないのはもちろんのこと、そもそも参議院の緊急集会では対応できないことを前提にして議論を進めることは参議院の自律に対する干渉という評価もありうるところであり、衆議院側としては慎むのが二院制の下でのエチケットであると考えます。
仮に参議院側で、「緊急集会では対応が困難である」という院の意思が示されることがあったとして、その時点ではじめて衆議院側での議論がスタートされるべきと考えます。
さらに、緊急集会の機能などについては、参議院議長のもとの参議院改革協議会では昨年6月の選挙制度専門委員会の答申を受けて、参議院の在り方論の柱項目の一つとして、「緊急集会の機能の充実強化」について今後具体的な議論を進めていくと伺っています。
今後、衆議院憲法審査会では任期延長改憲の議論を行うことが憲法論的のみならず政治的にも妥当なのか、各党各会派で参議院側ともよく議論していただくことを求めて、私の意見を終わります。
(憲法審査会での発言から)
2025年03月14日
憲法審査会レポート No.48
2025年3月13日(木) 第217回国会(常会)
第1回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55583
※「はじめから再生」をクリックしてください
【マスコミ報道から】
議員任期延長、自・立に溝 衆院憲法審、今国会初の討議
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025031300215&g=pol
“衆院憲法審査会は13日、今国会初の討議を行った。自然災害などの緊急事態で選挙が実施できない場合の国会議員の任期延長を巡り、自民党は「選挙困難事態」として憲法改正で対応する必要があると主張。一方、立憲民主党は選挙権の制限になると慎重な考えを示した。”
緊急時の議員任期延長を討議 今国会初めて、溝は埋まらず
https://nordot.app/1272758071879303356
“立民の山花郁夫氏は「一部地域の選挙が困難であることをもって、より多くの地域の選挙権を制限するのは明らかにバランスを欠いている」と反論。公選法改正などの検討を先行すべきだとし、現時点で立法事実は確認できないと結論付けた。”
衆議院憲法審査会 選挙の実施困難な事態想定し与野党が討議
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250313/k10014748721000.html
“自民党の船田元氏は東日本大震災を例に挙げ「選挙の実施が困難な事態に当たり、衆議院に被災地選出の議員がいない状況が生まれる。憲法を改正して議員任期を延長する制度を創設すべきだ」と主張しました。”
“日本維新の会、国民民主党、公明党も議員任期の延長に前向きな考えを示しました。”
衆院憲法審査会、今国会で初討議 「緊急事態条項」がテーマ
https://news.ntv.co.jp/category/politics/6cb135484306470786007eb166c149cd
“野党議員が衆議院憲法審査会の会長に就いたのは初めてですが、枝野会長は特別なコメントはせず、淡々と進行していました。”
“憲法改正の実現に向けて、自民党や日本維新の会は議論を加速させたい考えですが、会長の枝野氏は憲法改正に積極的ではない立憲民主党に所属するだけに、慎重に進めるものとみられています。”
【傍聴者の感想】
今国会で初めてとなる衆議院憲法審査会が開かれました。先の衆議院選挙で議席を伸ばした立憲民主党の議員が委員会室の席を埋める光景は、これまでの憲法審査会とは違う雰囲気を醸し出していました。
今回のテーマは、緊急時に選挙をすることができなくなって、国会機能を維持できなくなるような立法事実があるのかどうかという点でした。
はじめに、衆議院法制局の方が、論点やこれまでの議論のポイントを説明したうえで、各党会派からの自由討議となりました。
船田元議員(自民)、山花郁夫議員(立民)、浅野哲議員(国民)などは、テーマに沿ってこれまでの論点を補強する発言をしていたのですが、日本維新の会の馬場伸幸議員は、発言冒頭から枝野幸男審査会長の議事運営を執拗に批判したうえに、今の議論を打ち切り、有志の会と維新で出した緊急事態条項を踏まえた改正条文案の議論をすべきだと迫っていました。この条文案は自公と大差ないものじゃないかと少数与党の自民に秋波を送ったかと思うと、今の石破自民党には改憲に向けた意気込みがないとはっぱをかける始末です。
法制度についての議論はさておいて興味深かったのは、柴田勝之議員(立民)が公明党の平林晃議員に対し、参議院憲法審査会での公明党理事の発言内容について問い質したところです。平林議員は、同じ公明党の同僚議員に対して、「あれ」よばわりして異例の発言だとし、「参議院での公明党の発言は党として公式のものではない」と釈明に追われていました。選挙困難事態の立法事実をめぐって「選挙としての一体感」を強調していたわりには、公明党としての一体感はまるでないところを浮き彫りにしていました。
最後に、あまりにも粗雑でわかりやすい馬場伸幸議員の同盟者とも言うべき、有志の会の北神圭朗議員の発言についてコメントします。
選挙困難事態の立法事実についての議論で、大規模災害の被災地の声を代表する議員がいないのはまずいから、選挙困難事態の立法事実はあるんだという改憲派の議論の補強で、北神議員は極めて冷静な口調で、「議員は全体の代表者ではありますが、地元の声を反映させるということも一般的にはあるのです」と主張されていました。公務員は全体の奉仕者でしたよね。法制度の立法事実の議論をしているときに、一般的な、なあなあでそうなっている事実を持ち出して補強の議論になるのでしょうか。
【憲法学者から】飯島滋明さん(名古屋学院大学教授)
「国会議員任期延長改憲論」に「国民固有の権利」(憲法15条1項)を奪う正当性があるか
~2025年3月13日衆議院憲法審査会を傍聴して~
戦争をさせない1000人委員会「壊憲・改憲ウォッチ(49)」より転載
https://www.anti-war.info/watch/2503171/
2025年3月13日、衆議院憲法審査会を傍聴しました。
国会議員の任期延長改憲論をめぐり議論されましたが、議論の分析が以下になります。
①改憲5会派(自民党・公明党・日本維新の会・国民民主党・有志の会)からは主権者の権利である「選挙権」を奪う正当な事由が示されなかった
②改憲5会派は主権者の「国民固有の権利」である選挙権を軽視している
③議論が不十分
④改憲5会派が主張する「国会議員の任期延長改憲論」は「内閣と衆議院の居座りを許すゾンビ改憲草案」(れいわ新選組の大石あきこ議員発言)
【1】「国民固有の権利」(憲法15条1項)を奪う正当性があるか
日本国憲法では「国民主権」が基本原理とされており(憲法前文、1条)、国民主権の具体化として憲法15条1項では「選挙権」が「国民固有の権利」とされています。
改憲5会派が主張する「国会議員の任期延長改憲論」は、「選挙困難事態」と認定された際、国会議員の選挙を延期するという改憲論です。
改憲5会派は主権者の権利である「選挙権」を奪う改憲を主張していますが、「選挙権」という「主権者の権利」を奪う正当性があるのでしょうか?
れいわ新選組の大石あきこ議員は「自民の船田幹事と維新の馬場幹事に聞きたいんですけれども、選挙の一体性、選挙という国民固有の権利を奪うほどの正当性があるというのは憲法の何条に支えられているのでしょうか」と質問しました。
大石議員は「根拠条文は何条ですか」と聞いています。
にもかかわらず、日本維新の会の馬場伸幸議員は関係ない答弁を長々と発言し、「何条」という根拠条文を答えませんでした。
当然ながら大石議員は「答えになっていませんでした」と発言しました。
船田元自民党議員は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」という憲法43条1項を挙げました。
43条1項を挙げたことに大石議員は「憲法15条、国民がまず選挙で選んで始まるんだというところに対して、それを上回るような理屈でなかった」と発言しています。
れいわ新選組の大石議員は「私たちの選定と罷免は国民固有の権利であると憲法15条は言っています。任期延長はこの国民の権利を奪うものですから、それに足りる理屈が必要ですけれども、それは存在しません」と主張しています。
東日本大震災で選挙ができない地域があったことを例に挙げ、全国民の選挙権の行使の制限を主張する改憲5会派に対し、立憲民主党の山花郁夫議員も以下の発言をしています。
「一部地域で選挙を行うことが困難であることをもってより多くの地域の選挙権を制限するというのは、比較考量、比例原則の観点からも明らかにバランスを失している」。
日本共産党の赤嶺政賢議員も以下の発言をしています。
「日本国憲法は、主権者が国民に存することを宣言し、国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動することとしています。その下で、衆議院の任期を4年、参議院を6年と定めて3年ごとの半数改選とすることで、定期的な民意の反映と権力の民主的統制を求めています。そのためにも、いかなる場合であっても選挙権は絶対に保障されなければなりません。ましてや、国民の選挙権行使の機会を奪う場合をあらかじめ定めておくなどということが許されるはずがありません」。
2005年9月14日、最高裁判所は「在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件」で以下の判示をしています。
「国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないというべきである」。
立憲民主党、れいわ新選組、日本共産党が主張するように、選挙権は「主権者」の権利として極めて重要な権利です。
最高裁判所も、正当な事由もないのに選挙権の行使を制限することは許されないと判示しています。
しかし改憲5会派の議論からは、主権者の権利として重要な「選挙権」を制限するのが必要との説得的な主張がされませんでした。
「平等」という主張がまったく理由がないとまでは言えませんが、山花議員が主張するように、「比例原則」等を根拠としても、全国民の選挙権を一斉に奪う改憲論は正当ではありません。
改憲5会派は主権者の権利である「選挙権」を軽く見ています。
【2】議論が不十分
公明党ですが、衆議院の憲法審査会では議員任期延長改憲が必要と主張するのに対し、参議院では「衆議院の任期延長には民主的正統性の問題がある」旨(2023年6月7日参議院憲法審査会での公明党西田幹事)発言しています。
公明党が衆議院と参議院で異なる主張をしていることに対し、立憲民主党の柴田勝之議員は公明党にその整合性を質問しました。
この点に関しても公明党の回答は不十分でした。
『地平2024年12月号』73頁などで私は主張しましたが、2024年8月7日、自民党は国会議員の任期延長論議の前提となる「参議院の緊急集会」等について見解を変えました。
船田元氏は「選挙困難事態における選挙期日、議員任期延長の特例と前議員の職務権限行使については、自民、公明、維新、国民、有志の5会派において、ほぼ合意を得るに至っています」などと発言しました。
しかし議論は「不十分」「生煮え」であることが3月13日の審議でも明らかでした。
【3】ルールを守らない維新の問題点
2024年12月19日付の「壊憲・改憲ウォッチ47」で私は日本維新の会の「規範意識の欠如」も問題としました。
2025年3月13日の憲法審査会でも枝野幸男会長から「発言時間が終了しました。お約束はお守りください」と注意されても長々と発言を続けました。
馬場氏が発言を終えた後、枝野会長は再度、「お約束をお守りください」と馬場伸幸氏を注意しました。
当然の注意です。
最近でも2024年の兵庫県知事選挙に際し、非公開とされた百条委員会の音声を外部に提供するなど、日本維新の会の政治家には規範意識の欠如を感じることが多いですが、ルールを守らない馬場氏の対応にも「規範意識の欠如」を感じます。
内容的にも問題ですが、「規範意識の欠如」を感じる日本維新の会の政治家たちが憲法改正を主張するのを聞くと、彼ら・彼女たちが主張する改憲は危険との思いをますます強くします。
【4】「内閣と衆議院の居座りを許すゾンビ改憲草案」
上川陽子前外務大臣は「東日本大震災のような大規模災害が発生した場合、選挙運動ができると考えるのでしょうか。こうした場合、御自身が被災地でどのような選挙行動を行なうつもりなのか」などと立憲民主党に質問していました。
改憲が行われるのであれば、それはあくまで主権者である私たちのためであり、政治家のためであってはなりません。
選挙運動ができないことを改憲の理由に挙げた上川陽子発言を聞くと、自民党政治家は自分たちのために「議員任期延長改憲」を主張しているとの思いを強くします。
国会の機能維持のために国会議員の任期延長が必要だと改憲5会派は主張していますが、たとえば最近でも2024年11月の沖縄県北部豪雨災害、2025年2月の岩手県大船渡の山林火災に国会は本格的な対応をしてきたのでしょうか?
「緊急事態でも国会機能の維持が重要」などと発言していますが、改憲5会派は真剣に自然災害に対応しているのでしょうか?
法律で対応できないかどうかも十分に議論もしないのに憲法改正を主張するのでは、山花議員が主張したように、憲法改正の「立法事実」があると言えません。
2025年3月13日衆議院憲法審査会での改憲5会派の主張を前提としても、国会議員の任期延長改憲論は、選挙をしないで国会議員の地位に居座る改憲であり、「内閣と衆議院の居座りを許すゾンビ改憲草案」(2025年3月13日衆議院憲法審査会でのれいわ新選組大石あきこ議員の指摘)です。
【国会議員から】山花郁夫さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会幹事)
 憲法15条に選挙権についての規定がありますが、この選挙権は有権者団の構成員としての公務であるとともに、そのような公務に参与することを通じて国政に関する自己の意思を表明することができるという個人の主観的権利でもあるといういわゆる二元説が通説的見解です。そして、芦部教授も、「……選挙権がアメリカの判例・学説流にいえば、表現の自由と密接に関連し平等権保護条項等によって保障される『優越的権利』だということである」とされています(芦部信喜「参議院定数訴訟と立法府の裁量」『人権と憲法訴訟』243ページ(有斐閣・1994年))。この論文は、投票価値の平等に関するものではありますが、司法審査が行われる場合には「厳格な合理性」( strict rationality )基準によるべきとされています。
憲法15条に選挙権についての規定がありますが、この選挙権は有権者団の構成員としての公務であるとともに、そのような公務に参与することを通じて国政に関する自己の意思を表明することができるという個人の主観的権利でもあるといういわゆる二元説が通説的見解です。そして、芦部教授も、「……選挙権がアメリカの判例・学説流にいえば、表現の自由と密接に関連し平等権保護条項等によって保障される『優越的権利』だということである」とされています(芦部信喜「参議院定数訴訟と立法府の裁量」『人権と憲法訴訟』243ページ(有斐閣・1994年))。この論文は、投票価値の平等に関するものではありますが、司法審査が行われる場合には「厳格な合理性」( strict rationality )基準によるべきとされています。
ところで、憲法45条で衆議院議員については解散がなければ任期は4年、46条で参議院については任期は6年で3年ごとの半数改選が規定されています。15条と45条・46条をあわせて読めば、衆議院については最長で4年以内に、参議院についは3年ごとに代表者を選出することが選挙権の主観的権利の内容となっているということができます。
選挙困難事態において議員任期を延長するということは、ルールを変更するというだけでなく、選挙権を行使しうる時期について制限を加えることになります。その意味で、議員任期延長問題というのは、ルールと原理が交錯する問題ということができるでしょう。
さて、選挙困難事態の具体例として東日本大震災、阪神淡路大震災などが議論されていました。この2つのケースで特例法を制定して実施したのは、形式的には地方の首長、議員の任期は憲法上のものではなく法律上のものであることから、特例法によったものですが、より重要な点は、首長は当該地方公共団体の有権者から直接公選されるものであること、地方議会議員については一般に大選挙区制度がとられていることなどから、選挙そのものが定数全部にわたってなしえないという事情です。
これに対し、これら2つの震災は災害としては甚大なものであったことは間違いありませんが、衆議院議員が1人も選出できないというような事態ではないことが地方選挙の例とは大きく異なるということができます。
東日本大震災に関しては、仮にこのタイミングで総選挙があったとしても、8割強の議員の選出はできると試算されておりますところ、このようなケースで任期延長を行うということは、8割強の有権者の選挙権を行使しうる機会を制限する、延期することを意味しています。
選挙の一体性を損なうというご意見も出ていますが、民主制のプロセスそのものである選挙権の意義・法的性質からすると、全部について選挙権行使の機会を停止する・制限するよりも、繰延投票等の方法により選挙の時期をずらすということのほうが「より制限的でない他の選びうる手段」だと考えられます。
もっとも、この議論は法律の違憲審査の局面でありません。立法論・憲法改正論としては比較衡量論や比例原則に従って考えることが適切かもしれません。それにしても、一部地域で選挙を行うことが困難であることをもってより多くの地域の選挙権を制限するというのは比較衡量・比例原則の観点からも明らかにバランスを失しているといわざるをえないと思われます。
このことから、大規模災害のケースを立法事実として想定することが難しいと考えられます。
これに対して、感染症の全国的な蔓延が深刻な事態となった場合を想定すると、投票所で密になる、不要不急の外出を控えるなどの状況は一部地域だけでなく、日本全国において選挙が困難になる可能性はゼロではないかもしれません。
しかしこれも、現行の公職選挙法を前提に議論されている、つまり下位の規範である法律の規定を根拠に上位の規範である憲法の説明をしてしまっているように思われます。すなわち、投票日を定めて、入場券を郵送し、その場所に足を運び、自書で候補者の氏名を記入するというやり方を前提に選挙が実施できないという結論を出してしまっているのではないかということです。
憲法が上位の規範であり、その規範が求めていることが現行法で難しいということであれば、順序としては、公職選挙法の改正などにより憲法の求める価値を実現するのか立法府の役割であると考えます。
避難所、避難場所でも投票ができるようにする方法を模索することや、インターネット投票などの方法で大規模災害などの時でも公正な選挙が確保できるような仕組みを追求することなどを検討することが論理的に先行すべきことと考えられます。そのような手を尽くしたうえで、いかんともしがたい事態があるのだ、ということが確認されてはじめて、そのことが立法事実となるはずです。その意味で、現時点で私どもとしては立法事実が確認できない、と申し上げて意見表明といたします。
(憲法審査会での発言から)
2025年03月07日
憲法審査会レポート No.47
衆院憲法審査会、3月13日に開催へ
3月6日に開催された衆議院憲法審査会の幹事懇談会で、3月13日に今国会1回目の審査会を開催することが合意されました。なお、2回目については3月27日開催となるもようです。
【マスコミ報道から】
衆院憲法審 13日に開催 緊急事態での国会機能の維持など議論へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250306/k10014741281000.html
“衆議院憲法審査会の幹事懇談会で、与野党は今の国会で初めてとなる審査会を3月13日に開催し、緊急事態における国会機能の維持などをテーマに議論を行うことで合意しました。”
衆院憲法審、初討議は13日開催 参院予算委に配慮し延期
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA063J50W5A300C2000000/
“緊急時に選挙が困難になり国会機能が維持できなくなる立法事実があるかどうかを議論する。27日に「参院の緊急集会」をテーマに討議する日程も大筋で申し合わせた。”
“当初は6日の開催で一致していたが、参院予算委員会で石破茂首相と全閣僚が出席して2025年度予算案の審議が開かれていることに配慮して延期した。”
衆院憲法審は13日に先送り、予算案衆院通過も「参院へのマナー」 改憲派は主導権喪失
https://www.sankei.com/article/20250306-LS3BO5ONONIF5IHXVWAV6P4TMM/
“…衆院では参院の予算審議に先んじて憲法審を開催した前例もあり、少数与党に転落した自民党が憲法論議の主導権を失った影響が早くも露呈した形だ。”
“…4年の通常国会では衆院での予算審議の最中の2月10日に初回の憲法審が開かれた。幹事懇では改憲を重視する日本維新の会の馬場伸幸氏が「(参院の予算審議と衆院憲法審の開催とに)何の関係があるのか」と枝野氏を追及する場面もあったという。”
2024年11月08日
憲法審査会レポート No.45
衆院憲法審会長に枝野議員が就任の見込み
10月27日投開票の衆議院総選挙で、与党が過半数割れし、また改憲勢力も3分の2を割りました。この結果を受け、与野党の国対間で委員長ポストをめぐる協議が行われていましたが、憲法審査会の会長ポストが立憲民主党に割り当てられ、枝野幸男・衆議院議員が就任する見通しです。
この間行われてきたほぼ毎週の開催をはじめ、改憲発議を目的化した衆院憲法審査会のありさまに一定の歯止めがかかることが期待できますが、石破首相自身は強固な改憲派であり、今後の改憲をめぐる動向に対しては引き続きの警戒と注視が必要です。
(一部修正・追記しました)
【マスコミ報道から】
立民が衆院憲法審査会長ポストを確保
https://nordot.app/1227475408232284609
“衆院各派協議会は、憲法審査会の会長ポストを野党に割り当てることで合意した。立憲民主党が確保する。”
【速報】衆院の憲法審査会長に立憲・枝野幸男元代表が就任へ
https://www.fnn.jp/articles/-/784295
“衆院憲法審査会長は、立憲民主党が務めることになり、立憲は、枝野元代表を充てることを決めた。”
【参考】
改憲勢力が衆院の3分の2割り込み、改憲機運の後退必至…日本国憲法公布78年
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20241103-OYT1T50083/
“…衆院選で自公両党が過半数割れの「少数与党」に陥り、改憲に注力することは難しくなりそうだ。予算案や法案を成立させるためには野党の協力が欠かせず、「綱渡り」の国会運営が続くためだ。自公は議席の減少に伴い、憲法審の委員も少なくなる見通しで、自公主導で改憲議論を推進することも困難となることが予想される。”
憲法改正が「冬の時代」へ 改憲勢力後退、石破茂首相への不信感も根強く
https://www.sankei.com/article/20241028-KOIN6KRSXFKNZBLUPV45ZCUSIM/
“…国民民主の玉木雄一郎代表は28日、記者団に「自民は選挙で『改憲、改憲』と言っているが、本当にやる気があるのかどうか。もっとまじめに憲法改正に向き合っていただきたい」と強調。維新幹部は「自民は単独過半数も失った。寝言にしか聞こえない」と首相を突き放した。”
2024年06月28日
憲法審査会レポート No.44
衆院憲法審幹事懇の開催目論むも流会
衆院憲法審査会の森会長は閉会中審査開催に向けた幹事懇談会を、与野党筆頭幹事の合意ではなく職権をもって28日開催を決定しましたが、逢坂筆頭幹事をはじめ立憲民主党と共産党は欠席を表明、結局流会となりました。
25日には自民党役員会で岸田首相が「憲法は先送りできない課題の最たるものだ」などと発言してみたり、憲法改正実現本部のもとに衆参両院の議員による会議体の新設を決定するなどしています。
普通に考えれば、幹事懇を職権で強行することは今後の憲法審自体の開催にも悪影響を及ぼすだけであって、論外の行いです。岸田首相の発言や会議体新設云々もそうですが、パフォーマンスを繰り返すことで、なんとか求心力の維持に努めようとしているものと思われます。
自民党総裁選挙も控えていることから、今後もこうした「受け狙い」の動きが続くことが予想されます。警戒を緩めることなく、しっかりと注視していきましょう。
【参考】
衆院の憲法審査会幹事懇は開催できず 立憲や共産が欠席
https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000357126.html
“衆議院の憲法審査会は国会閉会中も憲法改正に向けた議論を進めるために幹事懇談会を開くことを決めましたが、立憲民主党や共産党が反発して欠席し開催できませんでした。”
憲法の政治利用/逢坂誠二 7849回
https://ohsaka.jp/15514.html
“まず閉会中の審議のあり方について、与野党国対で、十分な合意がないこと。国会での様々な与野党のやり取りは、最初に国対が大きな方向を決めます。それに従って各委員会の筆頭が協議します。今回、憲法審については、国体の方針が決まらない中での強行です。”
“こうした中では、筆頭間協議をしない、あるいはできないのですが、強引かつ一方的に要求を突きつけてきます。理不尽という他はありません。”
岸田首相「憲法、最たる課題」 保守派を意識、自民に温度差
https://www.47news.jp/11109216.html
“岸田文雄首相は25日の自民党役員会で「憲法は先送りできない課題の最たるものだ」と述べ、改正論議の前進を訴えた。9月の総裁選をにらみ、党内保守派へのアピールとみられる。ただ松山政司参院幹事長は記者会見で「衆参には意見の食い違いがある」と拙速な議論を警戒した。党内に温度差があるのが実情だ。”
自民 憲法改正に向け 衆参議員参加の新たな会議体 検討加速へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240626/k10014491981000.html
“…国会の憲法審査会の議論は衆議院と参議院で進捗(しんちょく)が異なることから、党の実現本部のもとに衆参両院の議員が参加する会議体を新たに設けて検討を加速させることを決めました。”