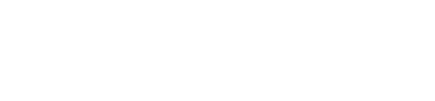憲法審査会レポート、2025年
2025年04月25日
憲法審査会レポート No.53
2025年4月24日(木) 第217回国会(常会)
第5回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55744
※「はじめから再生」をクリックしてください
【マスコミ報道から】
野党、臨時国会「20日以内」に 衆院憲法審、召集期限を議論
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025042400953&g=pol
“衆院憲法審査会は24日、臨時国会の召集期限について議論した。立憲民主党など野党は召集要求があった場合、政府は「20日以内」に応じるとの期限を設けるよう求めた。自民、公明両党からは期限の設定に慎重な意見が出た。”
衆議院憲法審査会 臨時国会の召集期限で議論
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250424/k10014788341000.html
24日の衆議院憲法審査会で、立憲民主党の松尾明弘氏は、2017年の安倍政権当時、野党が臨時国会の召集を要求したものの、召集されたのが98日後だったケースなどを挙げ「明白な憲法違反であり、議会制民主主義に対する重大な問題だ」と指摘しました。”
臨時国会の召集「20日以内」の明記、与党は慎重姿勢 衆院憲法審
https://digital.asahi.com/articles/AST4S2VP7T4SUTFK00TM.html
“同条は少数派の国会議員の意見を国会に反映させることを目的としている。しかし、これに基づいて野党が召集を要求しても、2017年の安倍晋三内閣は約3カ月放置し、ようやく臨時国会を開いてもすぐに衆院を解散して実質的な審議をしなかった。”
“安倍内閣のケースでは野党議員が違憲訴訟を起こした。最高裁は憲法判断をせずに訴えを退けたが、内閣が召集の「義務」を負うと判決文に記した。”
憲法改正の「誘い水」になるのか 立民重視の「臨時国会召集期限」を議論 衆院憲法審
https://www.sankei.com/article/20250424-GVFAH53XPFLCPBZQQZR3XBJUDM/
“改憲勢力の一部には、野党第一党の要求に応えれば、憲法改正で協力を得られるのではないかという希望的観測がある。しかし、党内や支持層に護憲派を抱える立民の壁は依然として高く、「誘い水」になるのかは見通せない。”
【傍聴者の感想】
衆議院憲法審査会の傍聴は昨年以来で、ひさしぶりです。まず一見して、委員の構成も、そして雰囲気もだいぶん変わったように感じました。
今回の自由討議のテーマは臨時国会の召集期限でした。
最初に衆議院法制局から憲法53条後段「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」についての制定経緯や実例、学説・判例、各会派の主張についての説明があり、これが結構わかりやすい整理でした。
とくに違憲性が問われる例である2017年に行われた召集要求(を92日放置した挙句、開いた臨時国会を冒頭解散!)について、法制局長が「いわゆるモリカケ問題…」と説明していたのが印象的でした。
その後、各会派からそれぞれ発言していったのですが、改憲会派も(維新を除いて)これまでのような改憲一辺倒といった気色は薄れていました。
それもそのはず、上記の例も含め臨時国会召集要求を何度も踏みにじってきたのは当の自民党(や公明党)であり、そのくせ自民党が(野党時代の)2012年に作成した「憲法改正草案」には「20日以内の召集」を盛り込んでいたという矛盾をさらけ出してきたわけで、本件はどうにもやりにくいのでしょう。
自民党の上川陽子幹事は2018年に決定した「改憲4項目」が優先的テーマであって、「憲法改正草案」はもはや過去のものであるかのような口ぶりでした。
また、公明党の浜地雅一委員は憲法53条についての党としての統一見解はなく、今回の議論をフィードバックしたいと発言していました。
召集期限の問題を解消する方法が明文化の憲法改正なのか、あるいは国会法改正なのかが争点です。実際、2022年には立憲・維新・共産・有志・れ新による国会法の改正案(審議未了で廃案)が提出されており、そのいっぽう維新・国民・有志が2023年に改憲条文案として発表しています。
しかし、野党多数の現状にあって、国会法改正による問題解消がもっとも手っ取り早く実効的であり、このことから目を背けて改憲を叫び続ける一部会派にはあきれるほかありません。
きょうの発言のなかでは、立憲民主党の松尾明弘委員の、召集要求を無視するような憲法違反をふたたび起こさせないように、これまでの事例をしっかり調査することが憲法審査会の責務であるという主張が、いちばん腑に落ちました。
【国会議員から】松尾明弘さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会委員)
 本日テーマとなっております憲法53条後段は、臨時会の召集要求に対して内閣はその召集を決定しなければならないと定めており、これが法的義務であることは、学説上も争いはありません。さらに、2023年の最高裁判決においても、憲法53条後段が国会と内閣との間における権限の分配という観点からの規定であり、召集決定は法的義務であると判断されています。
本日テーマとなっております憲法53条後段は、臨時会の召集要求に対して内閣はその召集を決定しなければならないと定めており、これが法的義務であることは、学説上も争いはありません。さらに、2023年の最高裁判決においても、憲法53条後段が国会と内閣との間における権限の分配という観点からの規定であり、召集決定は法的義務であると判断されています。
しかし、実際には、憲法53条後段に基づく議員の4分の1以上による臨時会の召集要求があったにもかかわらず、不当に臨時会の召集が遅らせられる事例が多発しています。
具体的な例としては、2017年6月、森友、加計学園問題の真相解明のため、野党議員が憲法53条後段に基づいて臨時会の召集を求めました。それにもかかわらず、召集されたのは98日後で、その日に衆議院が解散され、参議院も同時に閉会することになりました。この召集は、実質的には憲法53条前段に基づく臨時会で、憲法53条後段に基づく臨時会の召集要求に対する拒否と言え、明白な憲法違反です。
このほかにも、2020年、21年、22年の3回にわたって、4分の1超の国会議員が臨時会の召集要求を行ったにもかかわらず、内閣が臨時会を召集したのは、それぞれ、47日後、80日後、46日後という長期間後であって、不当に召集を遅滞する憲法違反が繰り返されています。
憲法53条には召集期限は具体的に書かれていません。しかし、これは内閣に広範な裁量を認める趣旨ではありません。このことは、権力分立と人権保障の原理に立つ立憲主義の考え方からしても明らかです。
召集期限については、社会通念上合理的な期間とする見解や、召集手続のために必要な期間、すなわち国会開会の手続及び準備のために客観的に必要と見られる相当な期間内で、できるだけ早い期間とする、そういった見解が学説上有力であり、その期間を超えて内閣の裁量はないものと解されます。この見解は、三権分立の下、内閣と国会が牽制し合うことによって濫用を防ぎ、国民の権利を守るという憲法の理念にも合致するものです。
しばしば与党が述べる、召集の必要性は感じないという発言は、53条後段の要請を全く理解していないものです。53条後段は、内閣よりも議員の意思と判断を重視するものだからです。臨時会の権能は、内閣が提出する案件の審議に限られるものではなく、議員提出法案や質疑も可能ですから、内閣がそこに案件を提出する準備ができたかどうか、その他政治的な理由で召集の必要性や時期を決定することは許されません。
現在、憲法53条後段の召集義務に違反した場合であっても、政治的責任が追及され得るのみです。しかし、自民党によるこれまでの憲法違反に対して、原因の究明及び政治的責任の追及は不十分であったと言わざるを得ません。
憲法審査会の役割には、国会法102条の6において、憲法及びこれに密接に関係する基本法制の調査が職務に含まれていると明記されていることからも明らかなとおり、憲法改正をすべきかどうかを論じるだけではなくて、憲法違反問題を含む日本国憲法の施行、遵守の状況に関する調査を行うことも含まれています。よって、過去の不当な召集遅滞について、当時の内閣が召集をしなかった原因を究明し政治的責任を追及することは、当憲法審査会の責務であると考えています。
憲法審査会においては、過去の憲法違反に対する政治的責任の追及自体をまずは行うべきであって、それが済んだ後に、憲法53条後段を無視する内閣の不当な態度を正し、同様の憲法違反が繰り返されないために、召集期限を法定すべきかどうかを議論すべきと考えます。
この議論には、合理的期間を一定に法定することができるのかという点、そして、法定するとすれば何日程度とすべきなのかという二つの論点があります。
検討に当たり注目すべきは、2023年の最高裁判決における宇賀裁判官の反対意見です。ここでは、20日あれば十分と述べられています。これは憲法54条や地方自治法など他の法制度とも整合する数字です。
また、20日の理由として、2012年の自民党憲法改正草案が、憲法53条について、20日以内に臨時会を召集しなければならないとしていることも挙げられています。
なお、立憲民主党も、2022年に、他会派と併せて、国会法において召集期限を20日と明記する法案を提出しており、この意見とも符合するものです。
2017年を始め繰り返し生じている臨時会召集の大幅な遅れは、憲法53条の趣旨に明らかに反するものであり、立憲主義や議会制民主主義に対する重大な問題です。こうした経緯を踏まえれば、やはり何らかの立法的な手当ての必要性は否定できません。その具体的な方法については、国会法改正その他様々な選択肢があり得ると考えています。
いずれにせよ、先ほど申し上げたとおり、まずは、合理的期間とは何か、その基準を明確にするためにも、過去の憲法違反事例について、憲法審査会における徹底した原因究明と政治的責任の追及が必要です。それらを踏まえた上で、結論ありきではない建設的な議論が行われるべきことを申し述べ、私からの意見陳述といたします。
(憲法審査会での発言から)