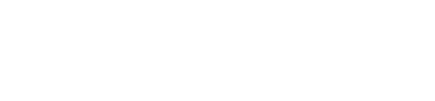憲法審査会レポート、2025年
2025年03月28日
憲法審査会レポート No.49
2025年3月27日(木) 第217回国会(常会)
第2回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55630
※「はじめから再生」をクリックしてください
【マスコミ報道から】
衆議院憲法審査会 大規模災害などでの国会機能維持で議論
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250327/k10014762311000.html
“衆議院憲法審査会が開かれ、大規模災害などの緊急事態の際に、参議院の緊急集会で国会機能を維持する期間について自民党が最大70日程度と主張したのに対し、立憲民主党は期間を限定すべきではないという考えを示しました。”
緊急集会、自民「最大70日」=立民は期間限定に反対―衆院憲法審
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025032700894&g=pol
“憲法54条は、衆院解散時に「緊急の必要」がある場合は内閣が参院に緊急集会を求めることができると規定。開催期間については、解散から特別国会召集までの最大70日とする見解がある。”
衆院憲法審、期間・権能の見解に隔たり 参院の緊急集会
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA271B40X20C25A3000000/
“自民党は参院の緊急集会の開催期間は最大70日程度とすべきだと主張した。総選挙の実施が見通せない場合も妥当だと話した。立憲民主党は想定外の事態などを念頭に70日に限らないとの立場に立つ。”
衆院解散後の「緊急集会」で見解割れる…自民は「例外」、立民は反論 衆院憲法審査会
https://www.sankei.com/article/20250327-YPEYK4VNZBMPZOXOLSCSSRWRVU/
“自民の船田元氏は「安易に解釈を拡大するのは避けるべきだ」と述べ、70日を大幅に上回れば憲法の想定を大きく超えると懸念を示した。立民の武正公一氏は「緊急集会は参院のみに認められた独自機能だ」と指摘。緊急集会で対応できないことを前提にした議論は、参院への干渉との評価もあり得るとした。”
【参考】
衆院憲法審査会が緊急事態条項を3月27日に採決? 採決の予定は無い【ファクトチェック】
https://www.factcheckcenter.jp/fact-check/politics/false-emergency-clause-vote/
“2025年3月27日の衆院憲法審査会で緊急事態条項を採決しようとしているとの主張は誤り。3月27日は参議院の緊急集会について討議する予定だ。”
※右派のなかにも「緊急事態条項反対」を主張するグループがあり、そうした人びとの間で、SNSなどをつうじて「3月27日採決」との風説が流布していました。
【傍聴者の感想】
今国会2回目の衆議院憲法審査会は、枝野会長から進行の説明の後、衆議院法制局・衆議院憲法審査会事務局が提出した「『参議院の緊急集会』の射程に関する資料」の説明から始まりました。「一切の私見を挟まずに、客観的にご説明いたしました」といって法制局からの発言が終わると、場内に失笑が漏れていました。
憲法審査会の傍聴は、これまでたまたま参議院ばかりでしたので、初めての衆議院での傍聴となりました。過去の議論を見知る中で想像していたよりも盛り上がりに欠けていたというのが正直な感想です。「参議院の緊急集会」を念頭に発言が続いていましたが、「壊れたテープレコーダー」と揶揄されるように同じところを行ったり来たりしていました。その合間に言葉尻を捉えるような発言が挟まって時間が過ぎていってしまうような感じでした。
自民、立憲、維新…と各会派が順に発言していく中で、気になったのは維新の発言です。法制度設計について、これ見よがしに「大陸型」などの用語を使っていたことです。政治学の教科書にいくらでも書いてあるような言葉ですが、「もっともらしい」と感じられるということでしょうか。なんかすごい…と思わせることが、彼らのやり方なのだと再認識させられました。
実際に、日本が地震大国であることは疑いようもないことですし、自然災害に備えるということが主張されるのも理解が出来ます。でも、どうしてそれが憲法改正の話にまで及ぶのでしょうか。選挙が出来ないほどの事態を考えるのならば、なぜ原発再稼働なんて選択ができるのでしょう。やっていることと言っていることとの高低差に頭が痛くなりました。
【国会議員から】武正公一さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会筆頭幹事)
 前回、選挙困難事態に関する「立法事実」をテーマとしました。立憲民主党は、有権者の投票する権利の尊重並びに、選ばれる側の居座りを許さないという点から臨みました。本日のテーマ「参議院の緊急集会の射程」にも関係しますので、冒頭「選挙困難事態」に触れます。
前回、選挙困難事態に関する「立法事実」をテーマとしました。立憲民主党は、有権者の投票する権利の尊重並びに、選ばれる側の居座りを許さないという点から臨みました。本日のテーマ「参議院の緊急集会の射程」にも関係しますので、冒頭「選挙困難事態」に触れます。
北海道南西沖地震に際して壊滅状態の奥尻島で選挙は行われました。
東日本大震災の時に、福島県内の喜多方市議選、矢祭町長選、古殿町長選、玉川村長選、北塩原村議選、鮫川村議選では選挙が実施されました。
昨年9月の石川県豪雨災害直後、被災地石川3区も衆議院議員選挙が行われました。投票率は、輪島市で10%下がったものの、わが党の近藤和也衆議院議員など、選挙を経て復旧復興のために引き続き取り組んだことも事実です。
前回も、この場で申し上げたように、被災地の復旧復興のためにもできるだけ早く代表者を選ぶ必要があると考えます。
選挙実施が困難な場合は国政選挙でも繰り延べ投票で対応すべきと考えます。そして、国政選挙などでは「一体性」を憲法も要請はしていないこと。今仮に、東日本大震災と同じ規模の災害が衆議院議員選挙前に起きても8割以上の衆議院議員を選ぶことができることから、選挙困難時の立法事実とするのは難しいと前回立憲民主党議員より述べました。
取り組むべきは、いかに選挙困難時期にあっても選挙ができる体制を組むかです。
平時において、投票環境の整備が急務の課題です。選挙困難時を想定した「有権者名簿など選挙データのバックアップ体制」「インターネット投票」「郵便投票」の検討、拡充です。また、期日前投票所の拡充、共通投票所の実施などできることは今でもあるはずです。
特に、投票日に、指定された投票所以外にだれでも投票できる「共通投票所」は、令和6年衆院選時点で、15市、16町、6村の226ケ所の設置にとどまっています。災害時に選挙区を離れて投票所を設けるためにも、二重投票を防ぐ仕組みをもって各自治体が共通投票所を設置することは有効ではないでしょうか。
ちなみに、今、横浜市では各区内の投票所すべてを共通投票所にして、各投票所独自の有権者名簿を投票所間で共通化して無線で確認を行い二重投票を防ぐシステムづくりが進められていると聞いています。
そのうえで、憲法54条にいう緊急集会について述べます。
「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する」(42条)とされていて、いわゆる二院制を採用しています。
もともと1946年2月13日に連合国最高司令官総司令部(GHQ)が日本政府に対して提示した総司令部案(マッカーサー草案)では一院制とされていました。これに対して、日本側が二院制の必要性を求め、現在の憲法の二院制になったという経緯があります。
その二院制の機能や役割分担のレベルを超えて、制度としてまったく独自のものとして存在しているのが参議院の緊急集会制度(54条)です。
これは、緊急事態に際して大日本帝国憲法時代には天皇の緊急勅令(明治憲法8条)や緊急財政処分(明治憲法70条)で対処するとされていたものを、国会中心主義の貫徹という趣旨から、参議院の緊急集会をもって対応することとしたものです。
金森国務大臣が制憲議会で「戦前の緊急政令」を認めないためにも参議院の「緊急集会」を設けたと言っています。大日本国憲法下1941年2月に法律をして1942年4月まで1年間選挙を延期したうえ、1941年12月には日米開戦に踏み切ってしまった反省にも立っていると考えます。
諸外国の憲法には緊急事態に関する規定があるのに日本国憲法にはないという趣旨の発言もあったかと思いますが、各種文献でも、この緊急集会の制度は世界に類例を見ないものと評価されていることからもわかるように、他の国々とは違う形で制度設計していることから、他の国々と同様の規定を探せば日本国憲法に規定がないというのは当然のことで、「緊急事態に際して対処すべき規定があるか」という観点から検討すれば、緊急集会の条文がこれに当たる、というのは明らかだと考えられます。先人たちはすでに「想定外」の事態の規定を設けていたというわけです。
憲法54条についてはその趣旨に基づいて参議院の緊急集会を適切に開催してゆくべきと考えます。特に、緊急集会70日限定説をとらないということを前回も申し述べています。
ところで、衆議院・参議院は相互に独立して審議・議決を行う機関ですから、他の機関や他の院の干渉を排して行動できる、いわゆる自律権を持っています(58条1項・55条)。
所掌事項という言葉が適切かどうかわかりませんが、参議院の緊急集会というのは参議院にのみ認められた独自の権能であるといえます。
したがって、参議院が「緊急集会で対応できる」と判断する可能性のある事項について、衆議院側で「緊急集会では対応できない」という判断をすべきできないのはもちろんのこと、そもそも参議院の緊急集会では対応できないことを前提にして議論を進めることは参議院の自律に対する干渉という評価もありうるところであり、衆議院側としては慎むのが二院制の下でのエチケットであると考えます。
仮に参議院側で、「緊急集会では対応が困難である」という院の意思が示されることがあったとして、その時点ではじめて衆議院側での議論がスタートされるべきと考えます。
さらに、緊急集会の機能などについては、参議院議長のもとの参議院改革協議会では昨年6月の選挙制度専門委員会の答申を受けて、参議院の在り方論の柱項目の一つとして、「緊急集会の機能の充実強化」について今後具体的な議論を進めていくと伺っています。
今後、衆議院憲法審査会では任期延長改憲の議論を行うことが憲法論的のみならず政治的にも妥当なのか、各党各会派で参議院側ともよく議論していただくことを求めて、私の意見を終わります。
(憲法審査会での発言から)