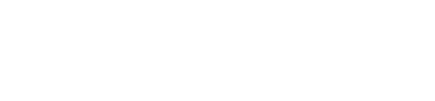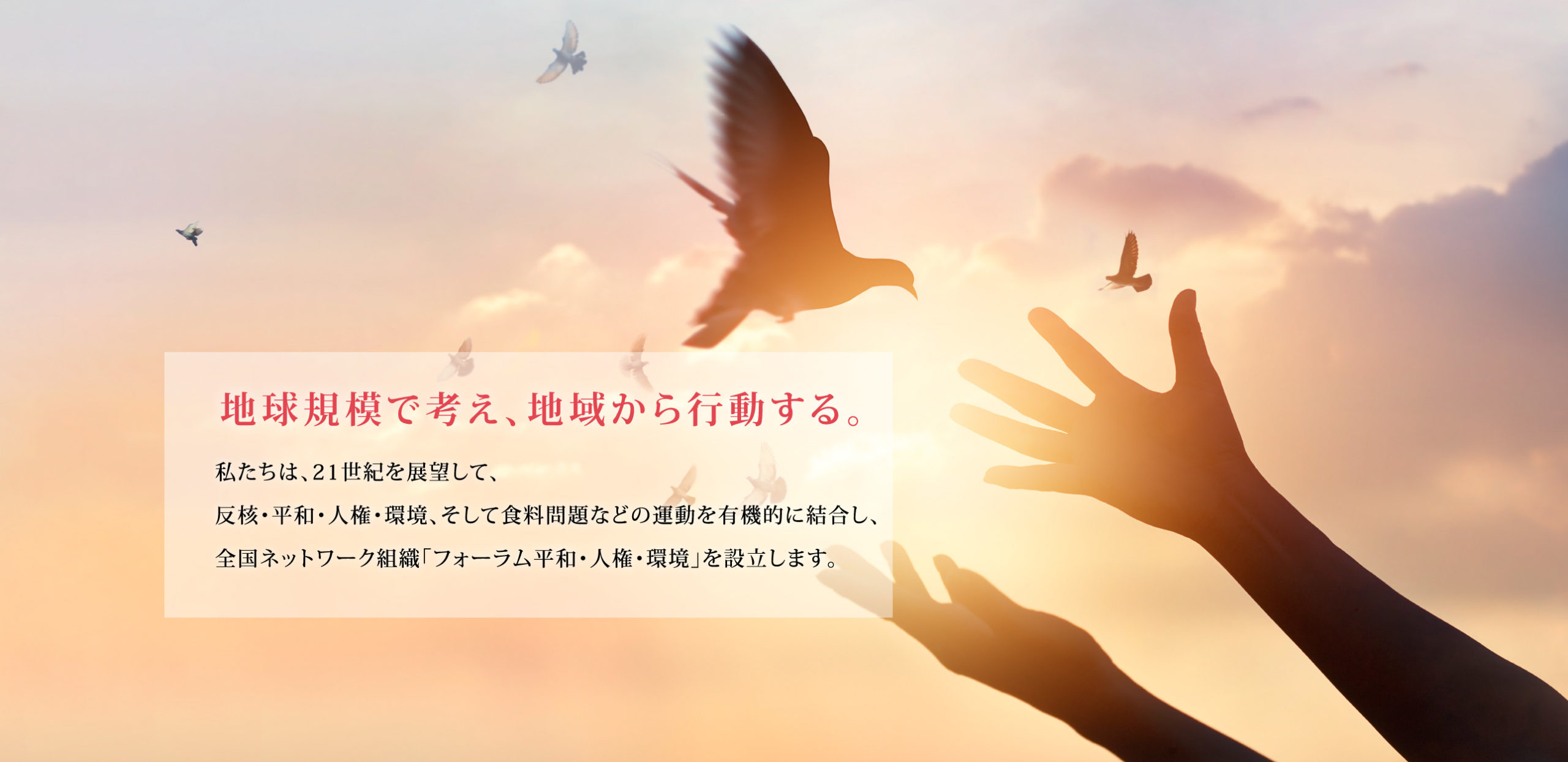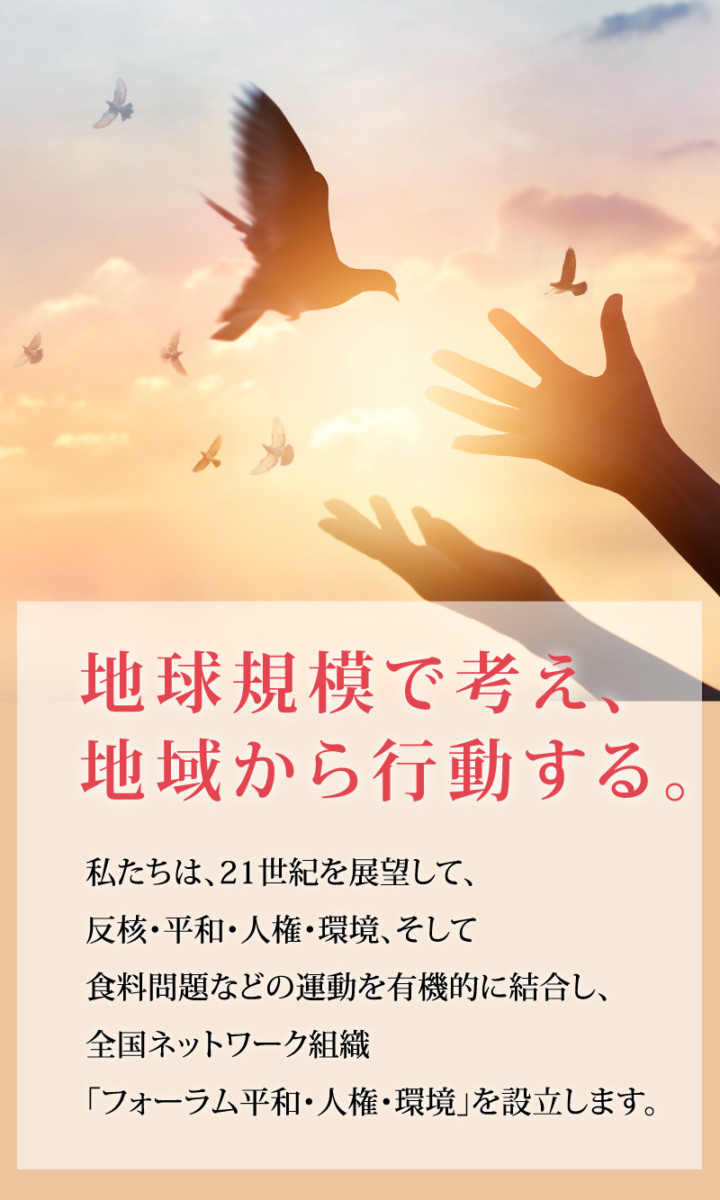新着情報
 日弁連/足利事件の録音テープから分かる取調べの実態~今こそ取調べの可視化の実現を
日弁連/足利事件の録音テープから分かる取調べの実態~今こそ取調べの可視化の実現を
取調べの可視化を含む刑事訴訟法改正案は、すでに参議院で二度も可決されており、また、マニフェストに可視化実現を掲げた民主党は衆議院総選挙も勝利し、2009年9月に鳩山新政権が誕生しました。法務大臣に就任した千葉景子参議院議員は、9月16日の大臣就任記者会見において、取調べの可視化を実現することを明言しました。しかし、その後の法務省の動きは鈍く、今次通常国会での提出法案とされていません。そのなかで、実現に向けた動きを強めようと、1月28日には、国会内で「取り調べの全面可視化を実現する議員連盟」(会長・川内博史衆院国土交通委員長)の設立総会が開かれます。 足利事件などのえん罪事件の発覚によ
 国内人権機関と選択議定書の実現を求める共同行動(人権共同行動)院内集会
国内人権機関と選択議定書の実現を求める共同行動(人権共同行動)院内集会
日本では公権力による人権侵害・差別や私人間の人権侵害・差別などが日々起きています。これまで人権NGOはそれぞれの立場から、こうした人権侵害・差別事象を根絶し、また人権を侵害され、差別された個人やマイノリティの権利を救済するため、1.政府から独立した国内人権機関の設置と、2.各選択議定書の批准等を求めてきました。 2009年9月の政権交代により誕生した鳩山新政権で法務大臣に就任した千葉景子参議院議員は、9月16日の大臣就任記者会見において、人権救済機関の設置、個人通報制度の受諾、取り調べの可視化を実現することを明言しました。「この発言をひとつの契機として、積年の課題を何とか実現できないか」と関
世界的な経済の新自由主義・グローバリゼーションの動きに対して、戦争も、搾取も、抑圧も、環境破壊もない「もう一つの世界は可能だ」を合い言葉に、国際的な社会運動団体などが結集して、2001年以来毎年、「世界社会フォーラム」(WSF)がブラジルやアフリカ等で開かれ、毎回数万人が参加しています。 今年のWSFは、各国・各地域で1月下旬を中心に各国で開催する形で行われることになり、東京では1月24日に、千代田区「韓国YMCA」を会場に、食と農、貧困、ジェンダー、労働、温暖化問題などの様々な問題について、全日にわたって分科会や全体会等が行われ、市民など約300人が参加しました。 このうち、平和
朝鮮人強制連行真相調査団は、1月23日、2010年全国協議会・東日本を東京文京区の朝鮮出版会館で開催し、約50名が参加しました。協議会では、2007年から開催されてきた「在日朝鮮人歴史・人権週間」などのとりくみを中心に報告・討議・交流しました。埼玉(曹洞宗全国布教師養成講演・フィールドワークなどさまざまなイベント開催について)、栃木(足尾朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑建立のための活動などのとりくみと2010年度の目標)、群馬(「記憶反省そして友好」追悼碑前集会などのとりくみ)、神奈川(2009在日朝鮮人歴史・人権週間東日本集会のとりくみ報告)、真相究明クラブ(朝鮮大学校朝鮮人強制連行
2010年01月23日
 日弁連/2010日本の人権を国際標準に。-今こそ、個人通報制度実現を!大集会
日弁連/2010日本の人権を国際標準に。-今こそ、個人通報制度実現を!大集会
2009年9月の政権交代により、各人権条約の個人通報制度の実現を公約に掲げた政党が政権与党となり、個人通報制度実現の期待が一気に高まっています。この機をとらえ、広く市民、NGO、国会議員などが手を繋ぎ、新政権に個人通報制度の早期実現を求めようと、1月15日、東京・日比谷公会堂で日本弁護士連合会主催の「2010日本の人権を国際標準に。-今こそ、個人通報制度実現を!大集会」が開催されました。 集会は、宮崎誠日弁連会長の開会あいさつにつづいて、参加した政党代表・国会議員として、民主党の松岡とおる参議院議員、公明党の漆原良夫衆議院議員、社会民主党党首で
日本が締結している自由権規約、女性差別撤廃条約、人種差別撤廃条約及び拷問等禁止条約には、さまざまな人権保障条項があります。個人通報制度とは、これらの人権が侵害されているにも拘わらず、最高裁判所でも人権救済が実現しない場合、被害者個人等が各人権条約の定める国際機関に通報し、救済を求める制度です。この個人通報制度を実現するためには、各条約の人権保障条項について個人通報制度を定めている選択議定書等を批准するなどの手続が必要です。 残念ながら、最高裁判所をはじめとして日本の裁判所は、これらの人権保障条項の適用について積極的とはいえず、せっかく締結した各条約の人権保障条項が十分に活かされていません。各
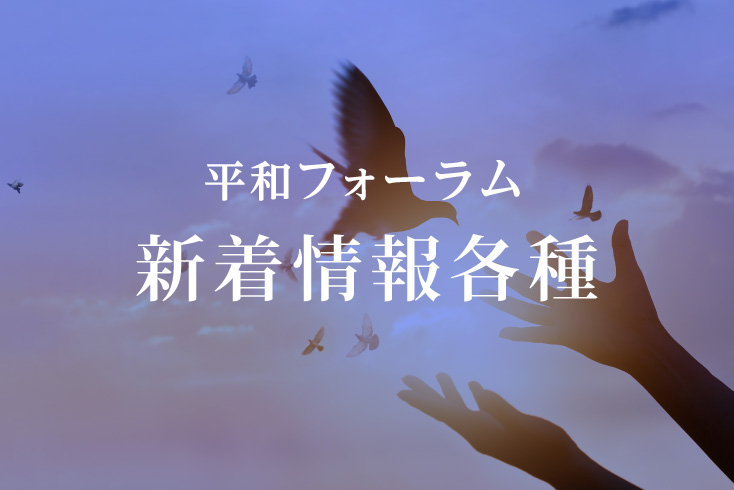 集会案内/1月24日「世界社会フォーラム2010首都圏」食と農問題分科会のご案内
集会案内/1月24日「世界社会フォーラム2010首都圏」食と農問題分科会のご案内
1月24日に東京「韓国YMCA」で開かれる「世界社会フォーラム2010首都圏」では、平和フォーラムは食と農問題の分科会を開きます。ここに、山形の「山びこ学校」で有名な佐藤籐三郎さんをお呼びして、「村はどう変わったか」の講演を受けます。さらに、現場の報告を受けながら、「農と食のこれから」を参加者全員で討論します。多くの方の参加をお待ちしています。世界社会フォーラム 首都圏/WSF2010 in TOKYO食と農問題の分科会★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 農と食の現場から"もうひとつの道"を探る─山形から佐藤籐三郎さん(山びこ学校)を招いて─★☆★☆★☆