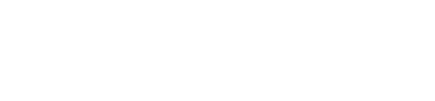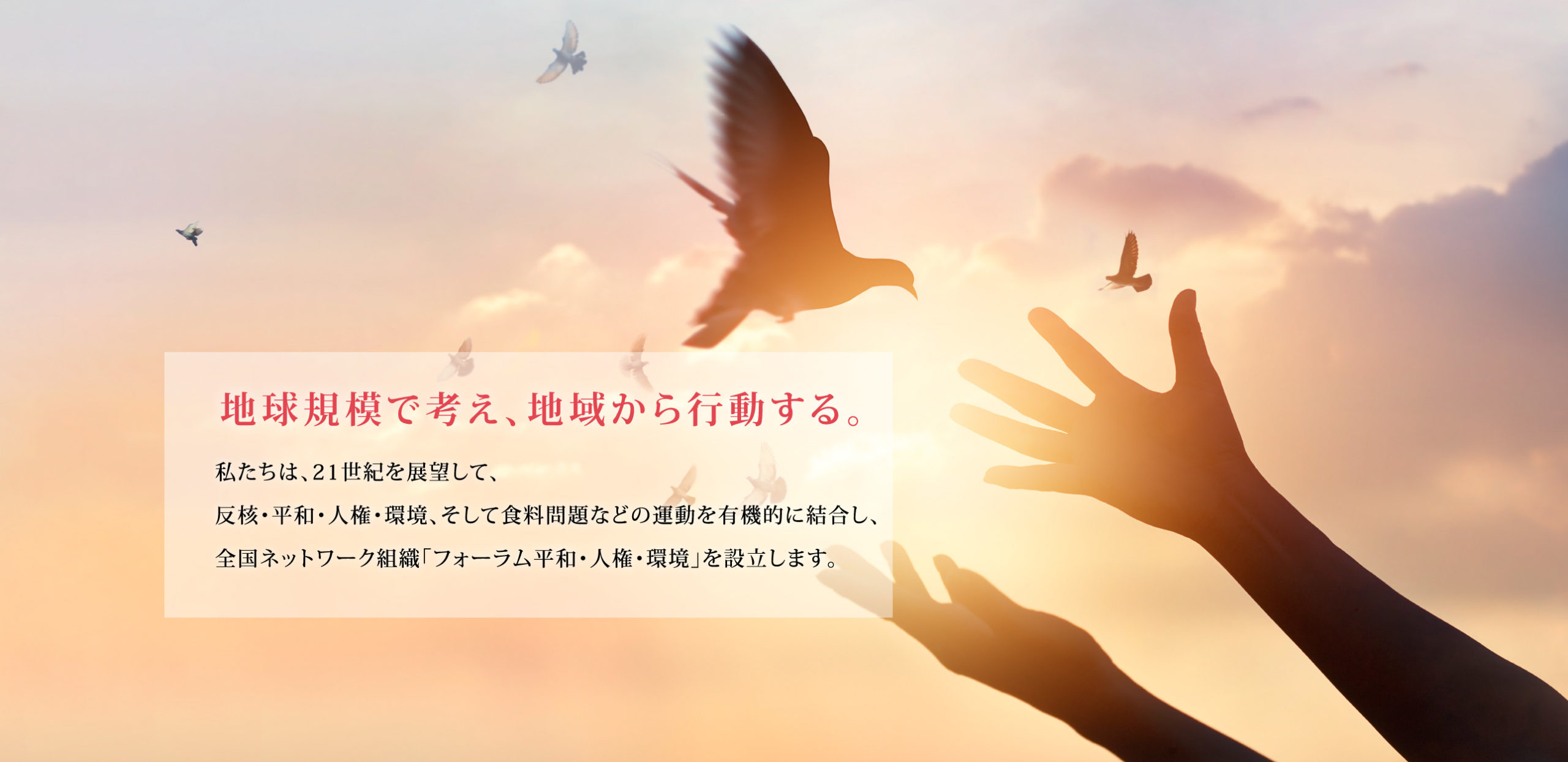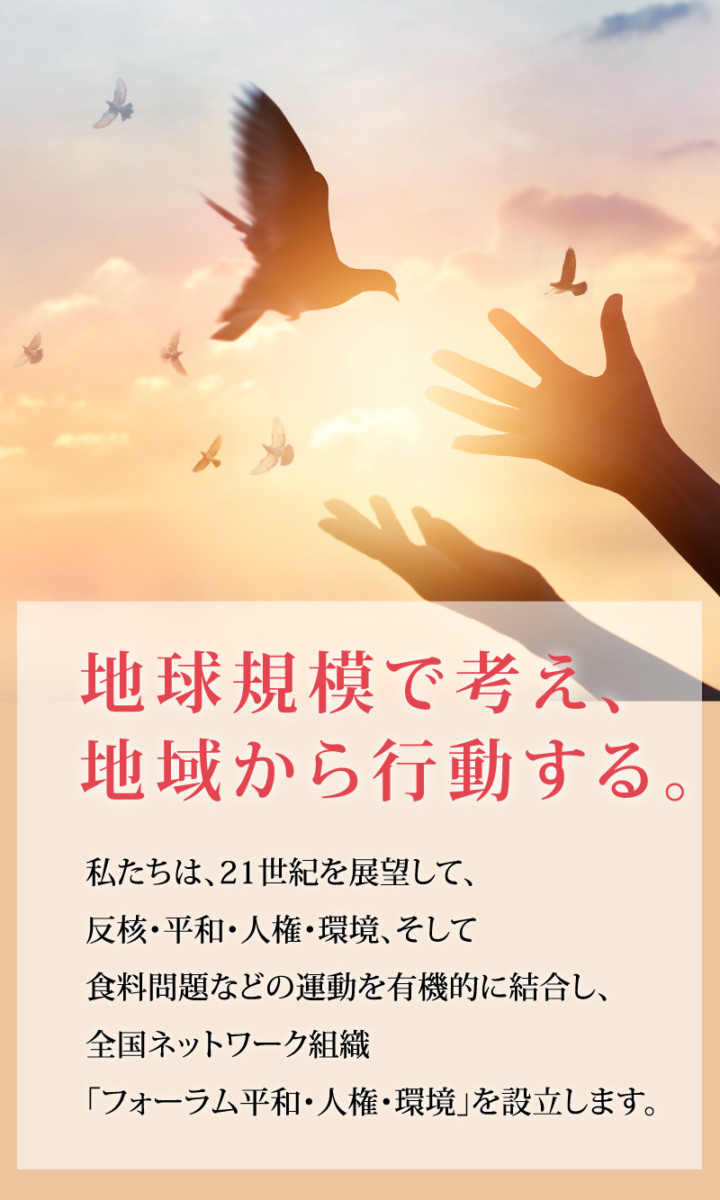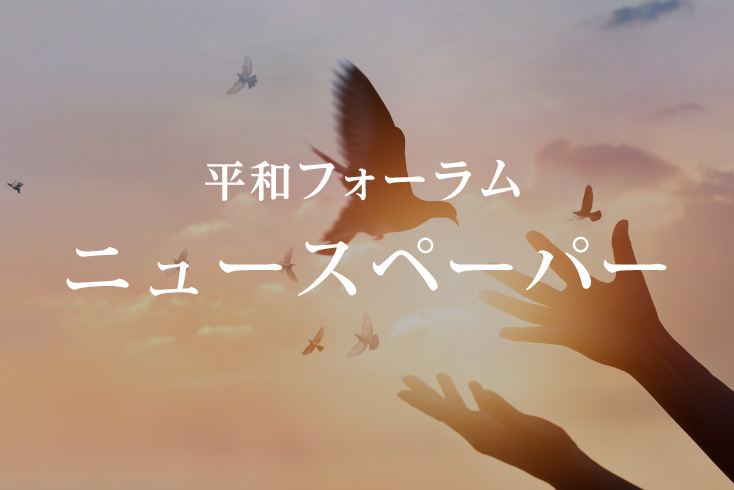新着情報
 報告 カンボジアへ支援米20トン送る 震災被災地にも6000キロ
報告 カンボジアへ支援米20トン送る 震災被災地にも6000キロ
平和フォーラムは毎年、全国でアジア・アフリカ支援米を作付けして、マリ共和国やカンボジアに送る「アジア・アフリカ支援米運動」を行っています。4月12日には、カンボジアに向けて20711キロのお米を送りました。すでにマリ共和国へは23926キロを送っており、総計44637キロとなりました。 今年はカンボジア向け支援米を集約する時に、東日本大震災が発生し、東北各県などからの支援米の輸送が出来なくなりました。そのため、急遽、約6000キロについては、被災地への救援米として活用されることになり、それぞれ避難先などに届けられました。 そのため、例年に比べて少ない支援米になりましたが、カ
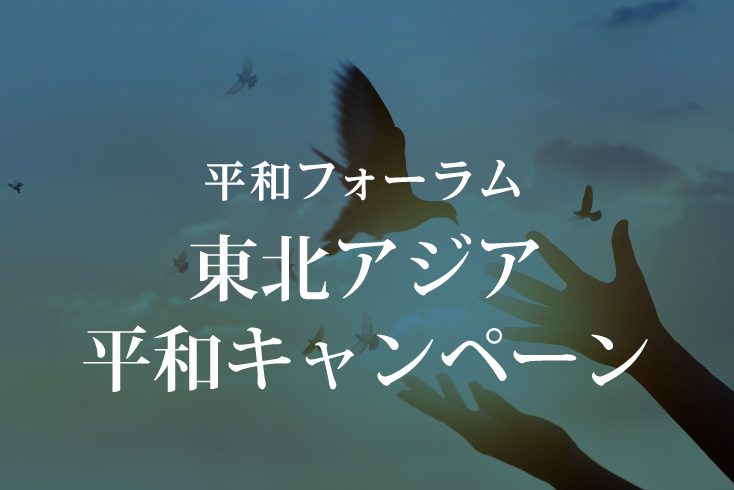 「朝鮮人強制労働被害者補償立法の実現を求める要請署名」について
「朝鮮人強制労働被害者補償立法の実現を求める要請署名」について
1990年代より戦時中の強制労働被害者が日本政府・企業に対し謝罪と補償を求めて起こした訴訟の支援を続けてきた各地のグループの連絡組織「強制連行・企業責任追及裁判全国ネットワーク」は、被害者の訴えを拒む政府と政府の言い分をそのまま追認し請求を棄却する判決を重ねる司法の壁に直面しながらも、戦後66年、被害者は高齢化し、亡くなる被害者もあとを絶たないなかで、一日も早く被害者の救済、名誉回復を図るため、戦後補償=過去の清算は被害者のためだけではなく、日本の未来への投資であり、東アジアの平和構築のための基盤整備でもあるとして、朝鮮人強制労働被害者補償立法の実現を提起し、署名を開始しました。平和フォーラ
2011年04月11日
 福島原発情報・特報便No.4 上関原発工事中止に! 原発依存からかじを切れ
福島原発情報・特報便No.4 上関原発工事中止に! 原発依存からかじを切れ
http://www.peace-forum.com/gensuikin/fukushima_tokuhouNo.4.pdf
2011年04月01日
3月11日、東日本を未曾有の大震災が襲いました。誰もが想像したことのない日本の観測史上最大の震災です。不幸なことに、東京電力福島第一原子力発電所において、地震と津波によって「緊急炉心冷却装置」が作動せず、原子炉の爆発やメルトダウンが予想される深刻な事態に陥っています。原子炉を中心に20キロ圏内には避難命令が出され、被曝者も確認されています。これまで政府や電力会社は、日本の原発は安全であると主張してきました。しかし、今回の事故は極めて重大であり、原発の安全性がいかに脆弱なものであるかを露呈しています。 今回の津波は「想定外」の事態であったと思われます。これまで事故のたびに、原発の安全性につ
2011年04月01日
未曾有の大災害に襲われた福島第一原発、一日も早い収束を インタビューシリーズ 全日本農民組合連合会会長 斉藤孝一さんに聞く 世界一危険な普天間基地を閉鎖させよう(伊波洋一前宜野湾市長) 有害化学物質の多くが合成洗剤の成分 世界の核兵器の状況を考える(1) 各地からのメッセージ「青森」 本の紹介「ザイニチ魂」 投稿「祝島自然エネルギー100%プロジェクトがスタート」 「破綻したプルトニウム利用」─政策転換への提言 東日本大震災犠牲者の方々に心から哀悼を表するとともに、被災者のみなさまにお見舞い申し上げます 3月11日、14時46分ころ発生した「東日本大震災」は、日本の観測史上最大規模の巨大