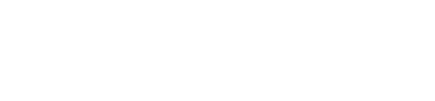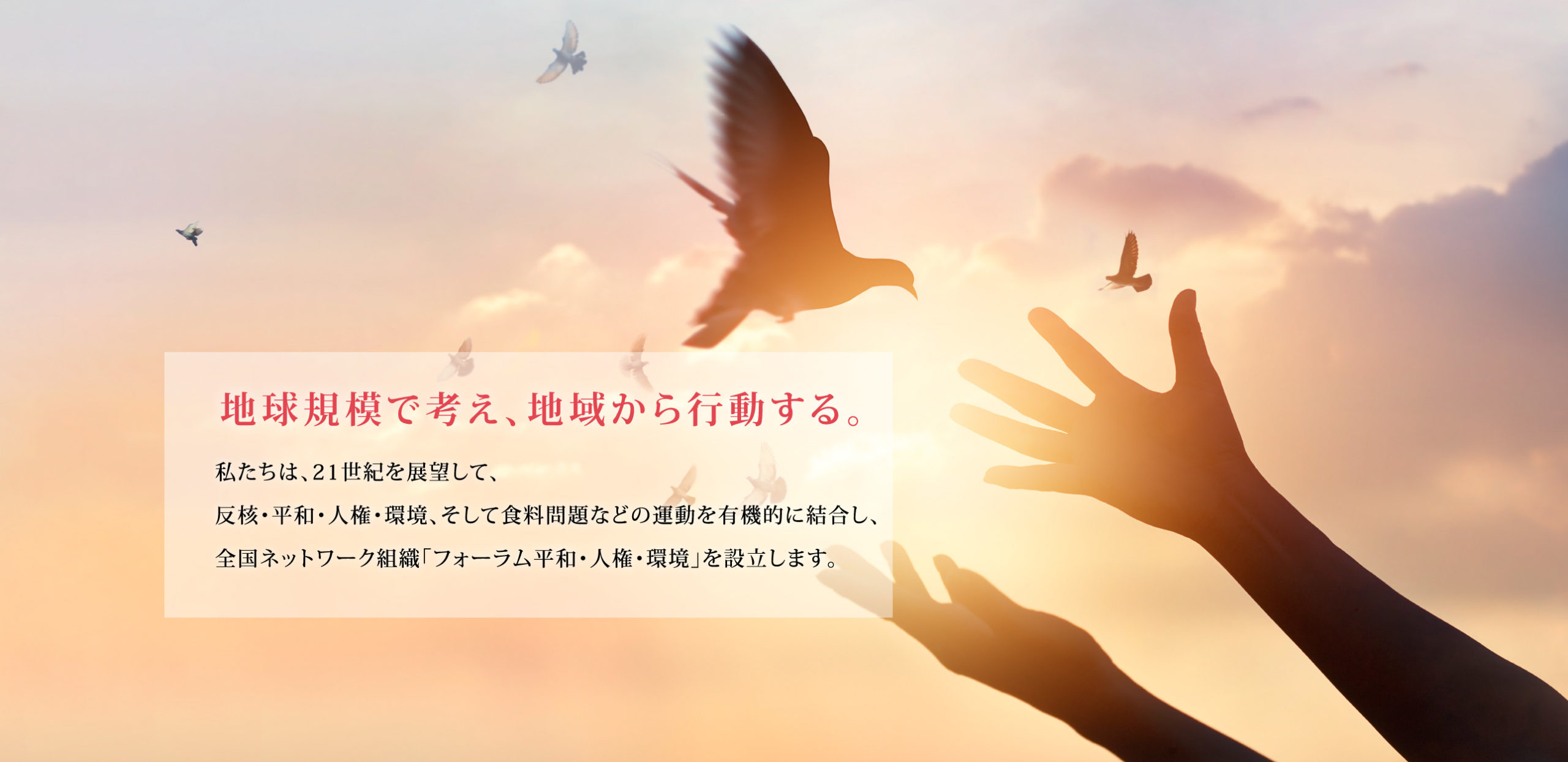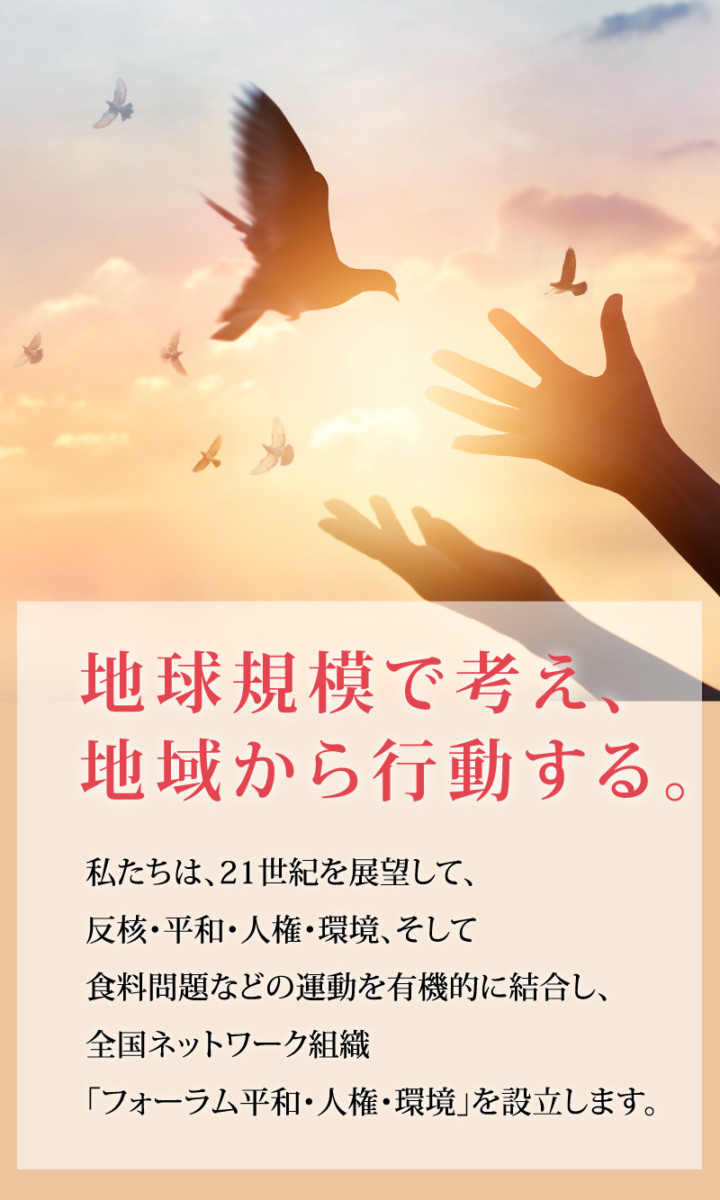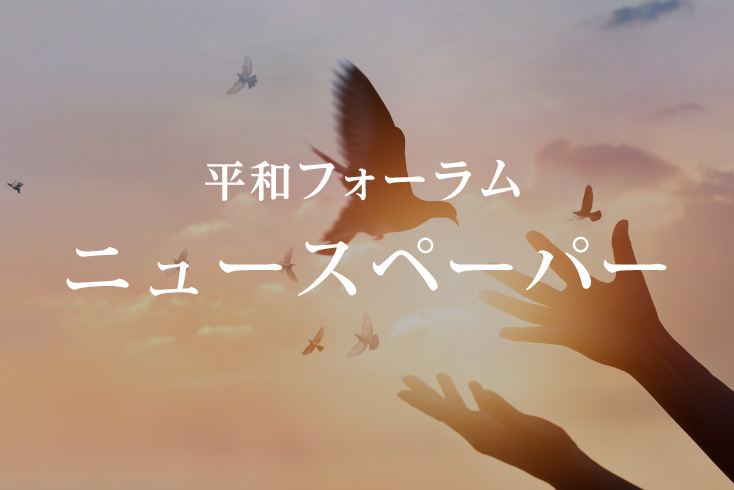新着情報
インタビューシリーズ 全オリジン労働組合協議会 議長 本間正史さん オリジン電気労働組合 書記長 関上哲生さんに聞く 首相が「最重要課題」とする問題への憲法的視点 政権交代でどう変わる食料・農業政策 さらなる困難な状況に直面する福島 日本の再処理・プルトニウム抽出が国際問題化 米原子力規制委が攻撃部隊を使った原発警備演習 外国人労働者の権利を訴えて「マーチ・イン・マーチ」 各地の活動紹介 神奈川平和運動センター 清水澄子さんを悼む つながろうフクシマ!さようなら原発大行動 平和フォーラムは毎年2月11日、戦前の「紀元節」を「建国記念の日」としていることに異議を唱え、集会を行って
2月28日~3月1日、平和フォーラムは全国150名の参加者のもと静岡市で全国活動者会議を開催しました。 28日は、福山真劫代表の主催者あいさつ、「2013年度の運動と組織の方針について」の藤本泰成事務局長の提起を受け、青森、愛媛、北海道などからの報告、愛敬浩二名古屋大学教授の講演「総選挙後の政治状況と改憲動向」を受け、質疑・討論しました。1日も山形、宮城、栃木、福島、神奈川、静岡、新潟、石川、福井、鹿児島、沖縄の各地からの報告とともに富山、三重、石川、愛知、新潟、全農林からの質問と意見を受け討論しました。これらは平和フォーラムが4月24日に予定している第15回総会の議案方針に活
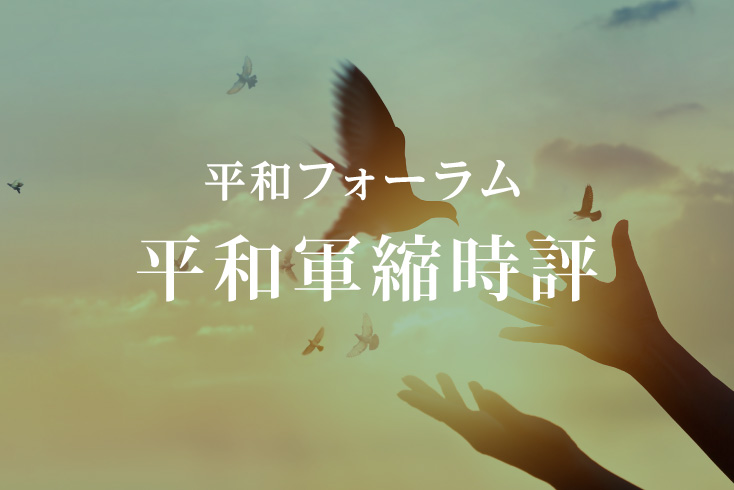 平和軍縮時評2月号 「集団的自衛権」議論は憲法改悪への序章―安倍タカ派政権の本質は対米追従 田巻一彦
平和軍縮時評2月号 「集団的自衛権」議論は憲法改悪への序章―安倍タカ派政権の本質は対米追従 田巻一彦
2月28日、安倍首相は「施政方針演説」で防衛、安全保障政策の骨格を示した。草稿から抜粋しよう。 「6. 原則に基づく外交・安全保障 … 私の外交は、『戦略的な外交』、『普遍的価値を重視する外交』、そして国益を守る『主張する外交』が基本です。 … その基軸となるのは、やはり日米同盟です。 … 日米安保体制には、抑止力という大切な公共財があります。これを高めるために、我が国は更なる役割を果たしてまいります。 … 北朝鮮が核実験を強行したことは、断じて容認できません。拉致、核、ミサイルの諸懸案の包括的な解決に向けて具体的な行動を取るよう、北朝鮮に強く求めます。 … 尖閣諸島が日本固有
 250人参加し「東アジアの平和と友好に向けた課題-『建国記念の日』を考える2.11集会」
250人参加し「東アジアの平和と友好に向けた課題-『建国記念の日』を考える2.11集会」
平和フォーラムは例年2月11日、戦前の「紀元節」を「建国記念の日」としていることに異議を唱え、集会を行っています。戦後の日本は、自民党内閣のもとで、東アジアとの関係、とくに歴史認識については繰り返し問題が引き起こされてきました。民主党政権下では韓国併合100年で植民地支配についての菅首相談話などの前進面もありましたが、竹島や尖閣諸島などの「領土問題」での近隣諸国との対立と東アジアの緊張状態は強まりました。昨年末の総選挙の結果、河野談話や村山談話をを否定し、教科書の「近隣諸国条項」の見直しをも主張する安倍晋三を首班とする政権が誕生しました。近隣アジア諸国
2013年02月11日
「障害を持ったことで、底上げされている気分。私は誰かを感動させるために、生きているんじゃない」。12月25日付の朝日新聞で「生きる 光と音のない生-目と耳の力失った女子大生-」という記事にあった言葉だ。「そもそも生きるって、自分って、なんだろう?(中略)私ってポンコツじゃないか、と」と自問する彼女の回りに集まった友人の中で、彼女を入れたつきあい方の「場のルールがいつの間にかできた」という。共生の社会のあり方が見えてくる。 この記事を読みながら、子どもの日の記憶がよみがえった。故郷北海道の小さな農村で、土蔵が燃える火事があり若い女性が焼死した。亡くなった女性は、精神疾患を病み、その土蔵の中
2013年02月01日
インタビューシリーズ 医師・チェルノブイリ・ヒバクシャ救援関西 振津かつみさんに聞く 求めるものは平和・社会民主主義・脱原発 オスプレイ配備と米軍機低空飛行訓練を止めるために 消費者のためになる食品表示法を 「脱原発法案」の再提出で国会論戦を 脱原発国ドイツのもう一つの顔は「乾式貯蔵先進国」 韓国大統領選挙の結果が意味するもの 各地の活動紹介 愛媛県平和運動センター 本の紹介「ほうしゃせん きらきら きらいだよ」 「つながろうフクシマ!さようなら原発大行動」 沖縄県宜野湾市の海浜公園で12月23日、「オスプレイ配備撤回!米兵による凶悪事件糾弾!怒りの御万人(うまんちゅ)大行動」が