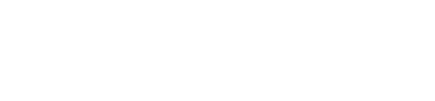2024年、平和軍縮時評
2024年12月31日
中東政治を展望する~シリア・ガザ情勢と第二次トランプ政権
役重善洋
アサド政権崩壊をどう捉えるか
12月8日、シリアのアサド政権が崩壊した。トルコ保護下のイドリブを拠点にしていた、元アル・カーイダのメンバーであるアフマド・シャラア率いるシャーム解放機構(HTS)を主力とした反体制派が11月27日に反転攻勢を政府軍に仕掛けてからわずか12日後のことである。
アサド父子による50年以上にわたる独裁支配のあっけない終焉の背景には、いうまでもなく、アサド政権と同盟関係にあったロシアとイランがそれぞれ対ウクライナ戦争と「対イスラエル戦争」で手一杯の状態にあり、シリア情勢の急変に対応する余力を持っていなかったという事情があった。イランが支援するレバノンのヒズブッラーが、最高幹部暗殺という痛手を経てイスラエルと停戦合意をした直後に反体制派の攻勢が始まったということが、状況の因果関係を物語っている。シリア反体制派の攻勢は、イスラエルによるシリア政府軍拠点への空爆という援護があってはじめて成功したものであった。
それでは、この間の「抵抗の枢軸」の決定的敗北状況をどのように捉えるべきだろうか。一つ確実に言えることは、二項対立的に物事を捉えるべきではないということである。中東・アラブ地域の現実は、反米/親米で色分けすることを拒む流動性や重層性を多分に含んでいる。湾岸戦争時、シリアが多国籍軍に参加したことはその顕著な一例である。今回、アサド政権を打倒したシャーム解放機構がアル・カーイダにルーツをもつ組織であることもやはり象徴的である。同組織は米国によってテロ組織指定されたままであるが、そもそもアル・カーイダの出自であるアフガニスタンのムジャヒディーンを訓練していたのが米国であったことを忘れてはなるまい。
このような複層的状況を把握する上で、中東・イスラーム地域における世俗(非宗派)主義とイスラーム主義との相克を意識しておくことは大変重要である。もともとオスマン帝国領内の東アラブ地域の一部であったシリアは第一次世界大戦後、フランスの委任統治下に置かれた。その際に多数派であるスンニ派イスラーム教徒を抑え込む役回りである軍人・警察官に多く採用されたのが少数宗派のアラウィ派であった。英国支配の正当性は、建前上、民族自決の原則にもとづく「アラブの独立」を支援することにあるとされ、オスマン帝国期の宗派コミュニティによる非領域的自治を単位とするイスラーム統治の理念は否定された。
第二次世界大戦後のアラブ諸国の独立運動は、この世俗的・非宗派的な民族主義というフレームを引き継ぐものであった。植民地時代のアラウィ派優遇は、独立後のシリア軍における同派の影響力を不釣り合いに大きなものとし、アサド父子の独裁を生み出すことになった。
この経緯は、シーア派が多数派のイラクでスンニ派アラブを基盤とし、世俗的アラブ民族主義を掲げたフセイン政権が生まれた経緯と構造的に似ている。世俗的ナショナリズムは、反植民地主義運動の理念を枠づけつつも、植民地支配を通じた西欧モデルの押し付けという性格を克服し切れたとは言えない。その限りにおいて、イラクとシリアをまたがるかたちで生まれたイスラーム国(IS)などのイスラーム主義勢力は、反植民地主義的性格を有しているといっても良い。しかし、実際のところ、これらの勢力は、米国やイスラエル、トルコ等による、この地域をめぐる利権抗争、とりわけ民族主義勢力に対抗するための一つのコマとして利用されてきた。100年前に、多民族的イスラーム統治システムを切り崩すために欧米植民地主義のコマとして利用されたアラブ民族主義が、現代においてはイスラーム主義に取って代わったと言うこともできるだろう。
アル・カーイダ等の排外主義的性格の強い急進的イスラーム主義は、歴史的には欧米キリスト教のミッショナリー運動などによりイスラーム的価値が脅かされているという危機意識の中から生まれてきた側面が強く、多宗派・多民族世界を前提としたコスモポリタンなイスラーム本来の歴史的在り方とは大きく異なる。世俗主義もイスラーム主義も、軍事主義を伴った画一的なアイデンティティ集団への志向を見直さない限り、多層的な中東の社会状況と軋轢を来たさざるを得ない。世俗主義かイスラーム主義かの二者択一ではなく、この地域の多様な人びとの合意プロセスこそが重視されるべきである。
シリア暫定政権を当面率いることとなるシャラア氏は、新憲法の起草に3年、選挙実施に4年はかかると言っている。その際、シリアが抱える少数宗派と少数民族をいかに包含するのか、また、周辺地域情勢、とりわけイスラエルのパレスチナ人に対する民族浄化政策に対し、いかなる倫理的姿勢を示すのか、さらには、そうした方針決定に際し、いかに大国の介入から自律した包含的な民主的プロセスを確保するのかといったことが、この地域全体の今後の展開にとって決定的な意味をもつことになるであろう。
シリア政変のガザ情勢への影響
次にシリア政変がガザ情勢に及ぼす影響について考えたい。アサド政権崩壊については、「西側ブロック」対「中露ブロック」という地政学的観点から、否定的であれ肯定的であれ、パレスチナ側の敗北状況の証左として捉える論調を多くみかけるが、そうした冷戦的指向を引きずった二項対立的把握ではこの地域の政治を見誤ることになる。ハマースは、シリア内戦に際し、反体制勢力支持の立場に立ち、10年近くの間、シリアおよびイランとの関係は冷却化していた。2022年に両国との関係回復をするものの、それはあくまでも戦略的なものであったと考えるべきであろう。そのことは、ハマースが、アサド政権崩壊の翌日には、自由と正義を求め闘ってきたシリア民衆を称える声明を出したことからも伺える。
2023年10月7日の「アル・アクサ―の洪水」作戦は、イランやヒズブッラーを対イスラエル戦争に巻き込むことで優位な停戦交渉に持ち込めるという計算もあったと考えられる。しかし、ヒズブッラーの対イスラエル攻撃は一貫して及び腰であり、イランの動きも極めて受け身的であった。結果的には、イスラエルの反撃によりナスラッラー書記長以下幹部を一斉に殺害されるなど、ヒズブッラーは極めて大きな損害を被り、アサド政権崩壊によりイランからの武器補給ルートも断たれた。そうした意味でハマースを含めた「抵抗の枢軸」がこの間大打撃を受けたことは間違いない。
しかし、そのような中東の政治バランスの激変が、パレスチナ人に対して不利に働くだけと考えるべきではない。15か月におよぶイスラエル軍の非道と、それを一方的に支持する西側諸国の欺瞞、それらを目の前にして何ら行動を起こすことができないアラブ・イスラーム諸国の政治状況は、この地域の人びとに大きなフラストレーションを与えている。そのような中で起きたシリアの政変に衝撃を受けたのはイランだけではない。シリアの新たな統治者としてイスラーム主義者が現れたことは、とりわけ、イスラーム主義勢力を弾圧してきたエジプトやヨルダンにおいて強く警戒されている。
イスラエルの両隣のエジプトやヨルダンは、米国の圧力により、イスラエルに批判的な圧倒的国内世論を押さえ同国との平和条約を結んでいる。そのため、ガザ情勢を受け高まっている反イスラエル世論は容易に政府批判に結びつく。加えて、エジプトは、イエメンのフーシ派による紅海通過船舶への攻撃によるスエズ運河通行料収入の激減を被っている。化石燃料資源を産出しないヨルダンは、エネルギー価格の高止まりによって、やはり大きな経済的損失を受けている。このような状況で、イスラエルに融和的な姿勢を両国政府が取ることは大きなリスクとなる。とりわけ、ヨルダンは国民の半数以上がパレスチナ難民であり、また、エルサレムの聖地ハラム・シャリーフの保護者という地位を対イスラエル和平合意で保障されているにも関わらず、トランプ政権のエルサレム首都承認やイスラエルの極右や軍による聖地における挑発的暴力によってその威信を傷つけられてきたという背景もある。そもそも国際情勢の風向き次第では権威主義体制をいとも簡単に崩壊させることができるという実例が白昼堂々と示されたことは、親米か反米かという色分けにかかわらず、この地域のすべての為政者に緊張を与えている。自ら統治の正当性を民衆に対して改めて示す必要性を課されたアラブの指導者は、これ以上の地域情勢の不安定化を望まず、パレスチナ問題の公正な解決に向けて、少なくとも表向きは、より強い態度で臨むことにならざるを得ない。
第二次トランプ政権の下で中東はどうなるか?
次に、第二次トランプ政権がガザ情勢に及ぼす影響について考えてみたい。第一次トランプ政権の取った中東政策は、パレスチナ人にとって破壊的ともいえるものであった。エルサレムのイスラエルの首都としての承認、ゴラン高原の併合承認、西岸地区イスラエル入植地の併合を含む「世紀のディール」の提案、イスラエルとUAE・バハレーン等アラブ諸国との(パレスチナ問題についての条件付けのない)国交正常化等々。これらの動きを阻止するためのイニシアチブを何ら取れなかったパレスチナ自治政府への失望が、パレスチナ民衆のハマースに対する相対的評価を押し上げたと言える。これまでの歴史的な経緯や国際法上の議論との整合性を軽視するトランプの姿勢はおそらく第二次政権においても変わらないものと思われる。「米国第一主義」を掲げ、自国の利益の最大化を目指す「ディーラー」としての行動様式も基本的に変わらないであろう。
とりわけ、中東における米軍の展開を縮小し、中国包囲網の強化に重心を移すとみられるトランプ政権が最も力を注ぐと考えられるのは、2020年の「アブラハム合意」の拡大である。しかしながら、前節で述べた分析を踏まえるならば、第1期トランプ政権においても、バイデン政権においても、遂に達成できなかったイスラエルとサウジアラビアとの国交正常化は、パレスチナ問題に関する何らかの「手打ち」を実現しないことには、実現は難しい。その無理筋を押し通すための最大の取引材料は、「世紀のディール」ですでに明らかにされている通り、湾岸産油諸国のオイルマネーである。すなわち、ガザの復興や西岸地区の自立的経済発展を阻止し、パレスチナ人の対外依存を永続化するという、長年イスラエルが考え、実践してきた計画を湾岸産油諸国の協力の下で現実化しようとしている。中東問題担当特使に、UAEなど湾岸諸国と取引のある富豪スティーブ・ウィトコフを指名したのも、その方向性を追求するためだと考えられる。
その際、バイデン政権の4年間における国際環境の大きな変化は、必然的に第一次トランプ政権の中東政策とは異なるバランス感覚でのアプローチを追及することにならざるを得ないのではないか。この間の重要な変化として、①「抵抗の枢軸」の弱体化および中露との連携強化、②中国の仲介を通じたよるイラン・サウジ関係の改善、③イスラエルの極端な右傾化、といった新たなファクターがこの4年の間に生じてきた。ここに共通するのは、中東地域における国家指導者の全般的な威信低下と相互依存関係の増加であり、この傾向は、トランプ政権の「ディール」にとって両義的な意味を持つ。第一期トランプ政権の取ったイランに対する「最大の圧力」政策が、同国の中国・ロシアへの依存を強め、結果的に中国包囲網の構築という大目標に逆行することになってきた経緯をすでにトランプは知っているはずである。第二次トランプ政権にも、マルコ・ルビオのような親イスラエル派が配置されることになっているが、その主眼は対中国経済戦争であって、第一次のときのような、ジョン・ボルトンやマイク・ポンペオのような好戦的なネオコン有力者は目立たない。とはいえ、第一期においてエルサレムの首都承認を宣言したトランプが、この問題について、宗教右翼が一大勢力となっているイスラエルに妥協を強いることができるかどうかは極めて疑わしい。他方、サウジやヨルダンにとってエルサレム問題に関する妥協は、アラブ・イスラーム世界の文脈において自らの統治者としての正当性に決定的な傷をつけることを意味し、到底受け入れられるものではない。
トランプ政権が、第一期の経験から、中東地域に安定をもたらそうとするならば、力にものを言わせた「ディール」では逆効果になるということを少しでも学習していることを期待したい。いずれにせよ、この問題に関して米国が決定的なイニシアチブを発揮できる可能性はますます小さくなりつつあると言わざるを得ない。トランプはそのことにこそ気付くべきである。注目すべき指標は、重層的な構造変化の中で米国とイスラエルの軍需産業の相互依存関係をどこまで低減できるか、ということである。そのためには、結局迂遠な話のようではあるが、兵器の需要を減らす、つまり紛争ではなく外交による諸問題の解決に全地球規模で取り組む以外に道はない。米国の対イスラエル武器援助が減額されれば、それに応じて、必然的にイスラエルはパレスチナ人との何らかの共存を視野に入れざるを得なくなるであろう。