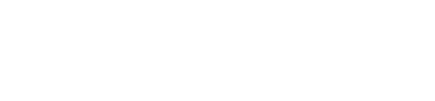12月, 2024 | 平和フォーラム
2024年12月31日
中東政治を展望する~シリア・ガザ情勢と第二次トランプ政権
役重善洋
アサド政権崩壊をどう捉えるか
12月8日、シリアのアサド政権が崩壊した。トルコ保護下のイドリブを拠点にしていた、元アル・カーイダのメンバーであるアフマド・シャラア率いるシャーム解放機構(HTS)を主力とした反体制派が11月27日に反転攻勢を政府軍に仕掛けてからわずか12日後のことである。
アサド父子による50年以上にわたる独裁支配のあっけない終焉の背景には、いうまでもなく、アサド政権と同盟関係にあったロシアとイランがそれぞれ対ウクライナ戦争と「対イスラエル戦争」で手一杯の状態にあり、シリア情勢の急変に対応する余力を持っていなかったという事情があった。イランが支援するレバノンのヒズブッラーが、最高幹部暗殺という痛手を経てイスラエルと停戦合意をした直後に反体制派の攻勢が始まったということが、状況の因果関係を物語っている。シリア反体制派の攻勢は、イスラエルによるシリア政府軍拠点への空爆という援護があってはじめて成功したものであった。
それでは、この間の「抵抗の枢軸」の決定的敗北状況をどのように捉えるべきだろうか。一つ確実に言えることは、二項対立的に物事を捉えるべきではないということである。中東・アラブ地域の現実は、反米/親米で色分けすることを拒む流動性や重層性を多分に含んでいる。湾岸戦争時、シリアが多国籍軍に参加したことはその顕著な一例である。今回、アサド政権を打倒したシャーム解放機構がアル・カーイダにルーツをもつ組織であることもやはり象徴的である。同組織は米国によってテロ組織指定されたままであるが、そもそもアル・カーイダの出自であるアフガニスタンのムジャヒディーンを訓練していたのが米国であったことを忘れてはなるまい。
このような複層的状況を把握する上で、中東・イスラーム地域における世俗(非宗派)主義とイスラーム主義との相克を意識しておくことは大変重要である。もともとオスマン帝国領内の東アラブ地域の一部であったシリアは第一次世界大戦後、フランスの委任統治下に置かれた。その際に多数派であるスンニ派イスラーム教徒を抑え込む役回りである軍人・警察官に多く採用されたのが少数宗派のアラウィ派であった。英国支配の正当性は、建前上、民族自決の原則にもとづく「アラブの独立」を支援することにあるとされ、オスマン帝国期の宗派コミュニティによる非領域的自治を単位とするイスラーム統治の理念は否定された。
第二次世界大戦後のアラブ諸国の独立運動は、この世俗的・非宗派的な民族主義というフレームを引き継ぐものであった。植民地時代のアラウィ派優遇は、独立後のシリア軍における同派の影響力を不釣り合いに大きなものとし、アサド父子の独裁を生み出すことになった。
この経緯は、シーア派が多数派のイラクでスンニ派アラブを基盤とし、世俗的アラブ民族主義を掲げたフセイン政権が生まれた経緯と構造的に似ている。世俗的ナショナリズムは、反植民地主義運動の理念を枠づけつつも、植民地支配を通じた西欧モデルの押し付けという性格を克服し切れたとは言えない。その限りにおいて、イラクとシリアをまたがるかたちで生まれたイスラーム国(IS)などのイスラーム主義勢力は、反植民地主義的性格を有しているといっても良い。しかし、実際のところ、これらの勢力は、米国やイスラエル、トルコ等による、この地域をめぐる利権抗争、とりわけ民族主義勢力に対抗するための一つのコマとして利用されてきた。100年前に、多民族的イスラーム統治システムを切り崩すために欧米植民地主義のコマとして利用されたアラブ民族主義が、現代においてはイスラーム主義に取って代わったと言うこともできるだろう。
アル・カーイダ等の排外主義的性格の強い急進的イスラーム主義は、歴史的には欧米キリスト教のミッショナリー運動などによりイスラーム的価値が脅かされているという危機意識の中から生まれてきた側面が強く、多宗派・多民族世界を前提としたコスモポリタンなイスラーム本来の歴史的在り方とは大きく異なる。世俗主義もイスラーム主義も、軍事主義を伴った画一的なアイデンティティ集団への志向を見直さない限り、多層的な中東の社会状況と軋轢を来たさざるを得ない。世俗主義かイスラーム主義かの二者択一ではなく、この地域の多様な人びとの合意プロセスこそが重視されるべきである。
シリア暫定政権を当面率いることとなるシャラア氏は、新憲法の起草に3年、選挙実施に4年はかかると言っている。その際、シリアが抱える少数宗派と少数民族をいかに包含するのか、また、周辺地域情勢、とりわけイスラエルのパレスチナ人に対する民族浄化政策に対し、いかなる倫理的姿勢を示すのか、さらには、そうした方針決定に際し、いかに大国の介入から自律した包含的な民主的プロセスを確保するのかといったことが、この地域全体の今後の展開にとって決定的な意味をもつことになるであろう。
シリア政変のガザ情勢への影響
次にシリア政変がガザ情勢に及ぼす影響について考えたい。アサド政権崩壊については、「西側ブロック」対「中露ブロック」という地政学的観点から、否定的であれ肯定的であれ、パレスチナ側の敗北状況の証左として捉える論調を多くみかけるが、そうした冷戦的指向を引きずった二項対立的把握ではこの地域の政治を見誤ることになる。ハマースは、シリア内戦に際し、反体制勢力支持の立場に立ち、10年近くの間、シリアおよびイランとの関係は冷却化していた。2022年に両国との関係回復をするものの、それはあくまでも戦略的なものであったと考えるべきであろう。そのことは、ハマースが、アサド政権崩壊の翌日には、自由と正義を求め闘ってきたシリア民衆を称える声明を出したことからも伺える。
2023年10月7日の「アル・アクサ―の洪水」作戦は、イランやヒズブッラーを対イスラエル戦争に巻き込むことで優位な停戦交渉に持ち込めるという計算もあったと考えられる。しかし、ヒズブッラーの対イスラエル攻撃は一貫して及び腰であり、イランの動きも極めて受け身的であった。結果的には、イスラエルの反撃によりナスラッラー書記長以下幹部を一斉に殺害されるなど、ヒズブッラーは極めて大きな損害を被り、アサド政権崩壊によりイランからの武器補給ルートも断たれた。そうした意味でハマースを含めた「抵抗の枢軸」がこの間大打撃を受けたことは間違いない。
しかし、そのような中東の政治バランスの激変が、パレスチナ人に対して不利に働くだけと考えるべきではない。15か月におよぶイスラエル軍の非道と、それを一方的に支持する西側諸国の欺瞞、それらを目の前にして何ら行動を起こすことができないアラブ・イスラーム諸国の政治状況は、この地域の人びとに大きなフラストレーションを与えている。そのような中で起きたシリアの政変に衝撃を受けたのはイランだけではない。シリアの新たな統治者としてイスラーム主義者が現れたことは、とりわけ、イスラーム主義勢力を弾圧してきたエジプトやヨルダンにおいて強く警戒されている。
イスラエルの両隣のエジプトやヨルダンは、米国の圧力により、イスラエルに批判的な圧倒的国内世論を押さえ同国との平和条約を結んでいる。そのため、ガザ情勢を受け高まっている反イスラエル世論は容易に政府批判に結びつく。加えて、エジプトは、イエメンのフーシ派による紅海通過船舶への攻撃によるスエズ運河通行料収入の激減を被っている。化石燃料資源を産出しないヨルダンは、エネルギー価格の高止まりによって、やはり大きな経済的損失を受けている。このような状況で、イスラエルに融和的な姿勢を両国政府が取ることは大きなリスクとなる。とりわけ、ヨルダンは国民の半数以上がパレスチナ難民であり、また、エルサレムの聖地ハラム・シャリーフの保護者という地位を対イスラエル和平合意で保障されているにも関わらず、トランプ政権のエルサレム首都承認やイスラエルの極右や軍による聖地における挑発的暴力によってその威信を傷つけられてきたという背景もある。そもそも国際情勢の風向き次第では権威主義体制をいとも簡単に崩壊させることができるという実例が白昼堂々と示されたことは、親米か反米かという色分けにかかわらず、この地域のすべての為政者に緊張を与えている。自ら統治の正当性を民衆に対して改めて示す必要性を課されたアラブの指導者は、これ以上の地域情勢の不安定化を望まず、パレスチナ問題の公正な解決に向けて、少なくとも表向きは、より強い態度で臨むことにならざるを得ない。
第二次トランプ政権の下で中東はどうなるか?
次に、第二次トランプ政権がガザ情勢に及ぼす影響について考えてみたい。第一次トランプ政権の取った中東政策は、パレスチナ人にとって破壊的ともいえるものであった。エルサレムのイスラエルの首都としての承認、ゴラン高原の併合承認、西岸地区イスラエル入植地の併合を含む「世紀のディール」の提案、イスラエルとUAE・バハレーン等アラブ諸国との(パレスチナ問題についての条件付けのない)国交正常化等々。これらの動きを阻止するためのイニシアチブを何ら取れなかったパレスチナ自治政府への失望が、パレスチナ民衆のハマースに対する相対的評価を押し上げたと言える。これまでの歴史的な経緯や国際法上の議論との整合性を軽視するトランプの姿勢はおそらく第二次政権においても変わらないものと思われる。「米国第一主義」を掲げ、自国の利益の最大化を目指す「ディーラー」としての行動様式も基本的に変わらないであろう。
とりわけ、中東における米軍の展開を縮小し、中国包囲網の強化に重心を移すとみられるトランプ政権が最も力を注ぐと考えられるのは、2020年の「アブラハム合意」の拡大である。しかしながら、前節で述べた分析を踏まえるならば、第1期トランプ政権においても、バイデン政権においても、遂に達成できなかったイスラエルとサウジアラビアとの国交正常化は、パレスチナ問題に関する何らかの「手打ち」を実現しないことには、実現は難しい。その無理筋を押し通すための最大の取引材料は、「世紀のディール」ですでに明らかにされている通り、湾岸産油諸国のオイルマネーである。すなわち、ガザの復興や西岸地区の自立的経済発展を阻止し、パレスチナ人の対外依存を永続化するという、長年イスラエルが考え、実践してきた計画を湾岸産油諸国の協力の下で現実化しようとしている。中東問題担当特使に、UAEなど湾岸諸国と取引のある富豪スティーブ・ウィトコフを指名したのも、その方向性を追求するためだと考えられる。
その際、バイデン政権の4年間における国際環境の大きな変化は、必然的に第一次トランプ政権の中東政策とは異なるバランス感覚でのアプローチを追及することにならざるを得ないのではないか。この間の重要な変化として、①「抵抗の枢軸」の弱体化および中露との連携強化、②中国の仲介を通じたよるイラン・サウジ関係の改善、③イスラエルの極端な右傾化、といった新たなファクターがこの4年の間に生じてきた。ここに共通するのは、中東地域における国家指導者の全般的な威信低下と相互依存関係の増加であり、この傾向は、トランプ政権の「ディール」にとって両義的な意味を持つ。第一期トランプ政権の取ったイランに対する「最大の圧力」政策が、同国の中国・ロシアへの依存を強め、結果的に中国包囲網の構築という大目標に逆行することになってきた経緯をすでにトランプは知っているはずである。第二次トランプ政権にも、マルコ・ルビオのような親イスラエル派が配置されることになっているが、その主眼は対中国経済戦争であって、第一次のときのような、ジョン・ボルトンやマイク・ポンペオのような好戦的なネオコン有力者は目立たない。とはいえ、第一期においてエルサレムの首都承認を宣言したトランプが、この問題について、宗教右翼が一大勢力となっているイスラエルに妥協を強いることができるかどうかは極めて疑わしい。他方、サウジやヨルダンにとってエルサレム問題に関する妥協は、アラブ・イスラーム世界の文脈において自らの統治者としての正当性に決定的な傷をつけることを意味し、到底受け入れられるものではない。
トランプ政権が、第一期の経験から、中東地域に安定をもたらそうとするならば、力にものを言わせた「ディール」では逆効果になるということを少しでも学習していることを期待したい。いずれにせよ、この問題に関して米国が決定的なイニシアチブを発揮できる可能性はますます小さくなりつつあると言わざるを得ない。トランプはそのことにこそ気付くべきである。注目すべき指標は、重層的な構造変化の中で米国とイスラエルの軍需産業の相互依存関係をどこまで低減できるか、ということである。そのためには、結局迂遠な話のようではあるが、兵器の需要を減らす、つまり紛争ではなく外交による諸問題の解決に全地球規模で取り組む以外に道はない。米国の対イスラエル武器援助が減額されれば、それに応じて、必然的にイスラエルはパレスチナ人との何らかの共存を視野に入れざるを得なくなるであろう。
2024年12月23日
ニュースペーパーNews Paper 2024.12
12月号もくじ
ニュースペーパーNews Paper2024.12
表紙 普天間基地と沖縄の海/民間空港・港湾の軍事利用
*「日米地位協定」について
ジャーナリスト 布施祐仁さんに聞く
*与野党伯仲の政治状況を選択した有権者
*きれいな水といのちを守る第37回全国集会報告
*2024年ピーススクール開催報告とこれから
*ハンセン病の悲劇と歴史を記憶
*本の紹介「鎌田慧セレクション-現代の記憶-1 冤罪を追う」鎌田慧・著
2024年12月20日
憲法審査会レポート No.46
12月19日、今臨時国会初となる衆議院憲法審査会が開催されました。なお、国会会期は小幅延長のうえ、24日までとなっていますので、現状では衆参ともに今後の開催の予定はありません。
※追記:12月24日、閉会にあたっての手続きのため、衆議院憲法審査会が数分のみ開催されています。
2024年12月19日(木) 第216回国会(臨時会)
第1回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55448
※「はじめから再生」をクリックしてください
【会議録】
※公開され次第追加します(おおむね2週間後になります)
【マスコミ報道から】
衆院憲法審、自・立に溝 枝野会長下で初の討議
https://nordot.app/1242315946075243501
“衆院憲法審査会は19日、立憲民主党の枝野幸男会長の下で初の本格的な討議を行った。自民党は憲法改正の優先テーマとして緊急事態時の国会議員任期延長を主張。立憲民主党はテレビCMなどを規制するため国民投票法の改正が最優先課題だと反論し、与野党第1党の立場の違いが改めて浮き彫りとなった。”
衆院憲法審査会 枝野審査会長のもと初討議
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241219/k10014672491000.html
“19日の討議は「今後の議論の進め方」がテーマで、与党側の筆頭幹事を務める自民党の船田 元経済企画庁長官は、緊急時の政府の権限や国会のルールを定める「緊急事態条項」に関連して国会議員の任期延長を最優先に議論を進めるべきだと主張しました。”
“そのうえで「韓国の非常戒厳を引き合いに『緊急事態条項は乱用のおそれがある』と言われるが、政治活動を禁止したり報道や集会を規制したりするものとは性質が異なる」と述べました。”
緊急事態条項、自民「優先を」 立民、選挙妨害巡る議論提起―衆院憲法審
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024121900117&g=pol
“自民の船田元氏は、大規模災害など緊急時に国会機能を維持する「緊急事態条項」の論点整理が既に行われていると指摘。「これを発射台とし、優先的に議論を進めていくべきだ」と訴えた。公明、日本維新の会、国民民主の各党も同調した。”
野党会長のもと初の憲法審査会、最優先課題に改憲派は「緊急事態条項」 一方、立憲「国民投票法」
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1627375
“…立憲民主党は選挙妨害の問題や表現の自由の保障に関わる国民投票法の改正を最優先課題として掲げたうえで、内閣の衆院解散権を制約するなど国家権力を抑制するための仕組み作りを議論すべきだと主張しました。”
【傍聴者の感想】
枝野会長のもとでの初めての憲法審査会が開催されました。冒頭、幹事などの事務的な確認を行ったうえで、これまでの経過の復習として、「憲法審における憲法論議の経過」について、衆議院法制局から説明されました。これを20分ほど行い、その後は憲法審の進め方についてすべての会派(8会派)から意見表明、その後任意に発言を求め、6人の委員が他会派への質問という形で発言しました。
自民党は改憲4項目のうち、緊急事態、選挙困難事態、議員任期延長について優先したい旨を述べ、あわせて改憲手続法についても速やかな検討をすべきとしました。他の改憲4会派も同様の趣旨を表明しました。これに対して立憲民主党は、改憲手続法は最優先課題としつつ、選挙運動の自由と表現の自由、恣意的な解散の抑制、臨時国会の召集期限、同性婚、政治資金の自由など様々な課題があり、議論を深めるべきとしました。れいわ、共産党は、憲法を変える議論ではなく、現実を変えることに注力すべきとの主張をしました。
発言の内容や方向性にこれまでの憲法審との大きな変化は感じられず、ただ全体的に改憲手続法への言及が多く、課題意識も会派による対立的な違いは少ないことから、この課題が大きくなるのかなという感じがしました。
会長を立憲民主党から選出されたほか、会派別の委員の構成比も変わりましたが、会派の数自体は変わらず、委員全体の過半数が改憲派であることには変わりはありません。憲法審で具体的にどういう議論がされているのか、どういう問題があるのかを、丁寧に市民に伝えていくとりくみが今後も必要であることをあらためて痛感しました。
【憲法学者から】飯島滋明さん(名古屋学院大学教授)
2024年12月19日衆議院憲法審査会について
戦争をさせない1000人委員会ウェブサイト「壊憲・改憲ウォッチ(47)」より転載
https://www.anti-war.info/watch/2501041/
【1】はじめに
2024年12月19日、衆議院では憲法審査会が開催されました。
この原稿、2025年1月1日に書いています。
率直な感想として、この原稿を書いている最中に「ため息」が出ました。
改憲5会派の改憲論、あまりにも憲法の理解に欠け、支離滅裂だからです。
たとえば日本維新の会の馬場伸幸議員、「立憲主義、民主主義の根幹には国民主権があります」と発言しています。
「民主主義の根幹には国民主権がある」とはどういうことでしょうか?
自民党は、自党の過去の立場に矛盾する発言すら平然と行います。
船田元議員が「平成24年の自民党の憲法草案でございます。この扱いにつきましては、確かに自民党の中でのオーソライズはしたものでございますが、その後、様々な検討を行いましたところ、この24年の草案については、ある意味では歴史的文章として凍結をしている」と発言した時、他会派の議員たちは「失笑」していました。
一方、2024年10月の衆議院選挙後、憲法審査会の委員や構成が変わり、好ましい傾向も出ています。
ちょっと長くなりますが、ここでは憲法審査会の問題点と今後の指針に言及します。
【2】日本維新の会の問題点
(1)馬場伸幸前日本維新の会代表の支離滅裂な憲法理解
日本維新の会の馬場伸幸議員は、「立憲主義、民主主義の根幹には国民主権があります」と発言しています。
「民主主義の根幹には国民主権がある」とはどういうことしょうか? 馬場議員にはぜひ、「民主主義」と「国民主権」の関係について説明してほしいです。
樋口陽一東京大学名誉教授は、「国民主権」と「立憲主義」は緊張関係にある旨主張していますし、私もそう理解しています。
「国民主権」の実現で個人の権利・自由が全く侵害されないのであれば、国家権力を拘束する「立憲主義」は必要ないからです。
「立憲主義……の根幹には国民主権がある」と発言した馬場議員、「立憲主義」と「国民主権」の関係をどう捉えているのでしょうか?
馬場伸幸議員は「憲法を国民の手に取り戻すときです」とも発言していますが、国民全体が改憲を真剣に求めているわけではありません。
国民全体が求めてもいないのに政治家が自分たちの政治目的を達成する口実として「国民意志」を援用することこそ、「国民主権」濫用の危険性として憲法学界でも警戒されてきたことです。
(2)中山太郎氏の神髄とは
憲法審査会で議論をするのであれば、実際の憲法問題を真剣に議論すべきです。
ところがいつものように、馬場伸幸議員は今回も憲法審査会で執拗に自民党、立憲民主党、共産党批判をしていました。
「弟子だった私が中山方式の神髄をはっきり申し上げます」と馬場伸幸議員は発言していましたが、中山太郎議員は自分と異なる立場の人たちを執拗に批判してきたのでしょうか?
「静ひつな環境の下で大所高所からの議論を行なうべき」(12月19日の橘幸信衆議院法制局長の紹介)というのが「中山方式」の神髄であれば、憲法審査会で他党批判をしつこく繰り返す馬場氏の対応、「中山方式」と相容れるのでしょうか?
「年末年始の閉会中も審査会を適時開いて、議論を前に進めようではありませんか」と馬場氏は発言していますが、憲法審査会で執拗に他党批判を繰り返すのであれば、憲法審査会の開催は必要ありません。
(3)規範意識の欠如
1巡目の自由討議に関しては、幹事会の協議に基づいて発言は各会派一名ずつで7分以内、時間を経過したらブザーを鳴らすとしていました。
発言時に馬場伸幸議員はブザーを鳴らされましたが、急いで発言をまとめることなく、延々と発言を続けました。
幹事会の協議に基づき、2巡目は他党に対する質問とされていました。
ところが同じく日本維新の会の阿部圭史議員は他党への質問をしないで自己の主張を続けました。
ルールを守らない阿部圭史議員に枝野幸男会長は注意しました。
今回の憲法審査会でも馬場伸幸議員、阿部圭史議員の対応に規範意識の欠如を感じました。
【3】自民党の立場について
2024年12月に韓国で非常戒厳が発動され、その危険性が危惧されていることに関し、船田元議員は以下の発言をしています。
「韓国で発出されました戒厳令、非常戒厳、これを引き合いに、緊急事態条項には濫用のおそれがあり、憲法に緊急事態条項を設けるべきではないと言われることもしばしがばございますが、韓国の戒厳令と我々が行っている議論とは全く別物と考えています」。
具体的にどう違うのか。船田議員は以下の発言をしています。
「我々が議論している、いわゆる議員任期延長を中心とした緊急事態条項は、いかなる緊急時であっても国会機能を維持し、国民の生命、身体、財産を守るために法律の制定や予算の議決ができるようにするための仕組みをつくっていこうというものであります。韓国の戒厳令のように政治活動を禁止したり報道や集会を規制したりするといったものとは全く性質が異なります」。
上記の発言、今までの自民党の対応からすれば「虚偽」と言わざるを得ません。
2025年1月1日に自民党憲法改正実現本部のHPで確認しましたが、「憲法改正実現本部は〔2024年〕9月2日、選挙困難事態における国会議員の任期特例に加え、早急に取り組むべき憲法改正の重要なテーマとして確認した、自衛隊明記と緊急政令に関する論点整理を取りまとめました」とされています。
ここでいう自民党の「緊急政令」こそ、韓国の「非常戒厳」と同様の危険性をもたらす改憲論です。
【4】有志の会北神圭朗議員の発言について
北神議員は以下の発言をしています。
「韓国憲法第77条5項には、国会が在籍議員の過半数の賛成により戒厳の解除を要求したときは、大統領はこれを解除しなければならないと規定されています。大統領の非常戒厳に対する手続が明記されていたからこそ、国会はこれにのっとって非常戒厳の解除をすぐに行うことができたのです。このことを踏まえれば、緊急時に行政権の暴走を牽制する仕組みを憲法に明記することこそが、国会中心の民主主義を守ることにつながるのではないでしょうか」。
れいわ新選組の櫛淵万里議員は緊急事態条項創設の改憲論について、「事実と異なる国会答弁を118回も行った総理大臣さえいました。憲法を無視し、国会にうそをつく日本で緊急事態条項のルールが守られるなど、空絵事でしかありません」と批判しています。
櫛淵議員の発言に北神議員は説得力をもって反論できるのでしょうか?
国会の解除手続があったから濫用されなかったと北神議員は述べていますが、そもそも解除手続が明記されていたのは、非常戒厳の濫用を防止するためです。
時の政権による濫用の危険性を回避するためには、緊急事態条項自体を憲法に導入しない方が適切ではないでしょうか?
「緊急時に行政権の暴走を牽制する仕組みを憲法に明記することこそが、国会中心の民主主義を守ることにつながるのではないでしょうか」と北神議員は発言していますが、そのような目的から、憲法に緊急事態条項を設けず、「参議院の緊急集会」で対応すると帝国議会憲法改正委員会で金森徳次郎大臣が答弁していた意義を理解する必要があります。
【5】公明党の「環境権」の主張について
公明党の濱地雅一議員は「環境権」の議論もすべきと発言しました。
ただ、スペインで訴訟が乱発されたことを口実にして、「環境権等につきましては、国民の主観的権利ということではなく、「国は」で始まる、国に対する責務を課すような規定でなければならない」と発言しています。
公明党が主張する「環境権」に関する改憲論、市民に権利を保障することを目的にしていないことを念頭に置く必要があります。
【6】憲法審査会では何を議論すべきか
今まで紹介したように、改憲5会派の改憲論議は支離滅裂、自党の立場とすら異なる主張を公然と行うなど、大問題です。
一方、立憲民主党、れいわ新選組、共産党は国会法102条の6を根拠に「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制」の調査の必要性を主張しました。
立憲民主党の武正公一議員は「同性婚の法制化」等の議論の必要性を主張しました。
れいわ新選組の櫛渕万里議員は、「憲法25条1項に、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあります。しかし、それができていない。憲法審査会では、このように現行の憲法規定が遵守されていない問題を徹底的に議論すべきでしょう。現行憲法さえ守れない者たちに憲法改正を論じる資格は一切ありません」と主張しています。
「30年にわたる不況、コロナ、そして物価高の三重苦で国民が苦しむ中」、憲法25条が実現されていない現実こそ徹底的に議論すべきという櫛淵議員の発言、極めて大切です。
日本共産党の赤嶺政賢議員も沖縄の基地問題に加え、「同性婚や選択的夫婦別姓、学費や教育費の無償化、貧困と格差、えん罪と再審請求、外国人の人権など、全てが憲法問題です。憲法の原則に逆行し、踏みにじられている政治と社会の実態を放置することは許されません。私たちは、政治家は憲法を変える議論ではなく憲法に反した現実を変えるための議論をすべき」と主張をしています。
憲法審査会で議論すべきは、人々のいのちと暮らしを守ることを目的とする憲法の理念を活かす政治が行われているのか、そうした議論です。
憲法審査会を開催するのであれば、国会法102条の6に基づく政治の実態を議論すべきと私たち市民も強く主張することが重要です。
【7】選挙を視野に入れて
2024年の通常国会まで、議員数の圧倒的違いから、衆議院憲法審査会は改憲5会派による強行的な主張・対応がまかり通っていました。
しかし2024年12月19日の衆議院憲法審査会、議論の状況が変わっていました。
とりわけ立憲民主党、れいわ新選組、日本共産党の委員が国会法102条の6を根拠とする憲法実態の調査を力強く主張したこと、米山議員の発言のように、企業・団体献金と憲法の関係について憲法審査会で追及できる環境が生じたことは、私たちのいのちと暮らし、生活をよくするためには極めて有益な変化です。
衆議院憲法審査会がこうした状況になったのは、2024年10月の衆議院選挙で改憲会派が議席を減らす一方、立憲民主党が議席を増やし、共産党に加えてれいわ新選組も憲法審査会で発言できるようになったからです。
支離滅裂な改憲論議が「国権の最高機関」である国会で幅を利かせ、国民・市民の平和とくらしを脅かす改憲にむけた動きを阻止するためにも、2025年の参議院選挙、さらに次の衆議院選挙でも「ジゴクイコウ」(自民、国民、維新、公明)といわれる改憲会派の議席を増やさないとりくみが必須です。
2024年12月03日
第61回護憲大会・分科会報告
第1分科会「非核・安全保障」
冒頭、本分科会講師である畠山澄子さん(ピースボート共同代表)の呼びかけで、アイスブレイク「サイレント」を行いました。参加者が声を出さずに、誕生日順に並びました。その後、誕生日が近い人たちで3人前後のグループをつくり、自己紹介しあいました。和やかな雰囲気で進み、参加者同士のコミュニケーションを図ることができました。
続いて、「次の世代のこととは誰のことをさすのか」をテーマに、グループ別ディスカッションにとりくみました。
・当時を経験した人以外はみんな次の世代である。
・学校で平和教育をしているが、子どもたちや保護者の理解があまりないように感じる。
・何かあれば耳を傾けるが、基本的には関心がない。「8月6日」、「9日」について知らない人も多い。当事者意識にはなりにくい。
・長崎では、資料館に行くことも多く、関心が高い。
・北海道では、原発には意識があるが、核兵器となると意識が下がっているように感じる。
・イベントとしての学習ではなく、普段からの学ぶことが大切。自分たちの未来に関わることだという意識をもって学んでほしい。
・自分が親になったときに、「8月6日」のことを語り継ぐことができるのか。日本人ならもってほしい視点だと思う。広島や長崎は登校日であることから、継承しやすいが、そのような日がない地域では、空気が違う。修学旅行で行くことも減っている。
そのうえで、畠山さんからの「核兵器のない世界のために私たちができること」と題しての講演、質疑応答がありました。
・グローバル学者という表現があった。国際・インターナショナルと言っていたが、グローバルと言われるようになってきた。この差とは何なのか。運動の一つ一つはインターナショナルになるのではないか。
(畠山)インターナショナルは、国家間の枠組みという意味で、使っている。グローバルは、被爆者という視点で考えると、アメリカやインドでも被害者がいる。国家としての枠組みではない場合には、グローバルを使う。国家ではなく、個人という意味合いが強い。経済や市場としての意味合いが強いのも理解はできる。
・労働組合も負け続けているが、続けている。平和運動も組合運動もつながっているように感じた。
(畠山)必ずしも為政者としての立場になる必要はなく、こうなってほしいという思いをもつことはできる。それを政治家と一緒に考えていくことが必要である。私たちが生きていくうえで、どういうことがよくて、どういうことがダメなのかを考え、人生が侵されたということに声をあげることは大事な一歩である。
・国連とは国家の集まりである。また、NGOが必ず発言している。核兵器禁止条約にも市民団体が直接国の集まりに対しても、発言することができ、力関係に変化がみられる。しかし、核兵器を作った国が発言力を高めている面もある。その点はどのように考えるのか。
(畠山)代議制が100%機能しているのであれば、私たちの出番は必要ないのかもしれない。しかし、そのような機能を果たすのは難しい。国の場で漏れてしまう意見を市民の声として、届けることは大切である。
残念ながら、5大国の力は大きいと思う。しかし、核兵器禁止条約の広がりが怖いと思っているのも事実である。フランスは植民地であった国に圧力をかけている。本当に効力がない場合は、このような圧力は必要ない。しかし、核兵器禁止条約に批准した国の力が強まれば、5大国の地位も変わってくるという心配も感じているのではないか。
・トランプ大統領の再選があった。トランプ政権についてはどのように考えているのか。
(畠山)アメリカ政治は専門ではないが、結果はもちろん受け止めるしかない。4年すればひっくり返る可能性がある国である。国際的な枠組みが壊れないような手立てを打っていく必要はある。具体的にいうことはできないが、気候変動などの枠組みから抜けるというようなこともあった。日本にも言えることだが、トランプに入れた人は理解できないというのではなく、理解するために努力する必要もある。何が真実か分からない中で、投票している。分からないというのではなく、お互いが向き合う姿勢が求められる。そのような学生もいるが、対話の場は必要である。トランプ政権は対岸の火事と思うべきではない。
最後に、谷事務局長が以下のようにまとめました。
何ができるのかということを考えながら話を聞いていた。日本被団協のみなさんがノーベル平和賞をとったが、今から何をすべきなのかを考えなければならない。責任は増している。日ごろのみなさんの運動で展開していくため、私たちもみなさんに対してどのような言葉をかけるべきか考えていく。
当たり前を変えていくのは私たちの力である。長い時間をかけて、とりくみをすすめていく必要がある。憲法にも書かれている。私の未来をどう選択すべきなのかを憲法理念のもとに考え、行動していく。今日はまず事実を知る。事実を知ることは想像力を高めることにつながる。今後の展開をみなさんとともに、模索していきたい。
第2分科会「軍拡・基地強化」
米兵による性被害当事者であり、米兵犯罪対策の活動をされているキャサリン・ジェーン・フィッシャーさんから日米地位協定の改定の必要性について提起を受けました。
ジェーンさんはオーストラリア出身で1980年代から日本を拠点に40年以上活動されており、モデルや歌手としてテレビに出演されていたこともある方です。ジェーンさんは2002年に神奈川県横須賀市で米兵から性的暴行を受けた上、警察から屈辱的な取り調べを受けPTSDを発症されました。その後、民事訴訟で勝訴したものの、加害者の米兵は2002年に帰国し所在不明となり賠償金は支払われませんでした。
しかし、ジェーンさんは泣き寝入りすることなく、加害者の元米兵を自力で見つけ出し、米国で訴訟を起こし勝訴しました。ジェーンさんは「日本では性犯罪を起こした米兵が刑事でも民事でも責任を取らずに済まされているケースが多いために事件が繰り返されている。日米地位協定には日本法令の『尊重』と規定されているが、米兵による性犯罪を防ぐためにはこれを『順守』とし、日本においては日本の法を守らせ、犯罪が起こったときには日本の法で裁けるようにしないといけない。加害者が守られる今の地位協定はおかしい」と訴えました。
続いて名古屋学院大学教授の飯島滋明さんから、日米地位協定の問題点と、裁判権放棄密約についての解説がありました。
地位協定により、米兵等について日本側の捜査・取調べ・公判等の刑事裁判権は著しく制限されていることに加えて、「裁判権放棄密約」があることから、米兵による性犯罪の多くが不起訴となっているという問題提起がされました。「裁判権放棄密約」とは1953年に日米間で交わされた「日本にとって著しく重要と考えられる事件以外については第1次裁判権を行使つもりがない」という密約です。解説の最後に飯島教授は、国を守るのであれば、憲法改正ではなく、一度も改定されていない日米地位協定を改定すべきだと訴えました。
参加者からは「地位協定の問題は米軍基地があるところではリアルなものとしてとらえられるが、基地がないところでは問題としてとらえられていない。どのように連帯していくかが課題」「基地がないところにおいては防衛費、税金の使い方といったことから問題をとらえることで日本全体の問題として基地問題に取り組めるのではないか」といった意見が出されました。
ジェーンさんは最後に、「自身の被害の体験を話すのは今でもPTSDの発作がでるほどつらいことだが、自身の経験を伝えることで、より多くの人が社会の問題としてとらえ、そしてみんなで声をあげることができれば、日米地位協定を必ず変えられると信じて活動している」と話されました。
ジェーンさんは米兵を憎んではいない、憎いのは犯罪だと話されました。つまり差別と偏見になってはいけないということだと思います。対等な関係でありたいということだと思います。そういった意味でも不平等な日米地位協定は改定が必要なのだと感じました。
第3分科会「人権課題」
師岡康子さん(弁護士)から、「包括的反差別法制定に向けて~人種差別撤廃を中心に」と題しての講演、問題提起を受けました。
日本における差別として国籍民族差別が現在もあり、日本で同じように生活している外国籍住民はマイノリティであり、マジョリティとの生活の違いから差別を受けている現状があります。日本で生活する外国籍住民は、住民として納税義務などを果たしているにもかかわらず、地方参政権を認められていないことや、改正入管法からもわかるように国の政策自体が日本で生活する外国人を認めておらず、共に暮らすではなく管理していると言う日本の現実があります。そのため、職が限定されたり、高校無償化の対象外など、何世代に渡り日本で生活していても不平等な対応となっており声をあげることも難しい状況です。自分の本来の名前を隠して日本名で生活することを選択する人もいるなど、アイデンティティが問われています。
日本国憲法第14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と差別が禁止されているにもかかわらず、差別は無くなっていません。また、日本には国際人権基準である差別禁止法や国内人権機関、個人通報制度が無く、国際的にも遅れている状況です。
罰則規定が盛り込まれた先進的条例である、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」が制定された川崎市では、ヘイトスピーチやヘイトデモが無くなり成果が出ています。他方で、川崎市でヘイトスピーチを繰り返し行っていた人たちが今度は、埼玉県の川口や蕨市でクルド人に対してヘイトスピーチを行っている状況です。
国際基準に合致した差別禁止規定が盛り込まれた人種差別撤廃法の実現にむけ取り組む必要があり、外国人人権法連絡会が作成したモデル案が紹介され、各地方からも声をあげることが重要であることも示されました。
参加者からは活発な質疑や討論が行われ包括的反差別法の必要性や複合差別や人権課題について共有されました。先進的事例を取り入れ、各地でできることを広げていくこと、議員への働きかけなどはマジョリティが取り組むべきであり、各自治体で条例制定を進め国を動かし法制定へとつなげることが重要です。
最後に講師から、人種差別撤廃条約に日本は加入している以上、条約を守らなければならないこと。また、知らないから行う無意識の差別があり、学習や教育の必要性が高まっており、教育現場での取り組みが重要になること。これらの課題を解決するために、各自治体での人種差別撤廃にむけて条例制定の取り組みを進めましょう。とお話し頂きました。
第4分科会「歴史認識」
弁護士の内田雅敏さんが問題提起として、「靖國問題」と題して講演しました。靖國神社を巡る誤解を解くとして、戦没者追悼式に対して批判があるのではなく、批判の焦点は、靖國神社という場所での追悼にあり、靖國神社が持つ「大東亜戦争史観」や「アジア植民地解放史観」といった聖戦史観が、追悼の場所としてふさわしくないなどと話された他、戦後、靖國神社は国家機関から宗教法人に転じたにも関わらず、戦没者の魂を独占し続けること、特攻や戦後の戦死者への扱いも遺族や国際社会からの反発を招いていることなど、歴史や宗教、政治など様々な視点から、靖國神社の問題を指摘しました。
次に、関東大震災朝鮮人虐殺犠牲者追悼と責任追及の実行委員会の藤本泰成さんが、「関東大震災の朝鮮人虐殺について」と題して報告しました。1923年に発生した関東大震災と同時に起こった朝鮮人虐殺について、軍隊・警察が中心となって、朝鮮人が火をつけた、井戸に毒を投げた等、流言がばらまかれたことにより、虐殺が起こった。虐殺の本質は、「朝鮮人への迫害」だと指摘した。また、虐殺が起こったにも関わらず、それを認めない日本政府や東京都知事の対応を批判しました。
質疑では5人の参加者が、「東京裁判における天皇の戦争責任について」、「史実を捏造されないためには」、「政党が偏見・差別をなくしていけるのか」など質問。講師から、「東京裁判の問題は色々あるが、最高責任者の1人である天皇が訴追されなかったということは一番大きな問題」「自国の歴史を権力者側がどう書くか。見る側によって歴史は変わる。向こうとこちらでお互い話し合いながら作り上げることが大事」、「個別に議員はいる。そうした議員を大切にし、私たちからコミットしていかなければならない」などと回答がありました。
まとめとして、藤本さんからは、「アメリカが世界の中で、特にこの東アジアで何をしてきたかしっかり見つめ直す。そして、単に批判するだけではなく、アジアの平和のために何が必要なのか。この日本における差別という、この植民地主義というものを払拭していって、そしてアジアの中でもっときちんと対話をして、色々なことができる社会を作らないといけない」などと述べました。
内田さんからは、「日本はかなり問題があるけれど、中国の今の独裁体制にも問題がある。それはそれで批判していかなくてはいけない。中国に『以民促官(いみんそくかん)』という言葉がある。民をもって官を促し、政治を変える。日中共同声明では、4つのことを約束した。それを活用せずに、ミサイルがとか、一戦交える覚悟だとか、それは外交でも何でもない」などと述べました。
第5分科会「憲法を学ぶ」
本分科会への参加者は、護憲大会に初めて参加したという方が多数を占めていました。本分科会の趣旨を全体で共有し、憲法の基本をみんなで学ぶ場にしていきたいという、分科会の方向性をまず確認しました。
その後、日本体育大学教授の清水雅彦さんに、「憲法の基本を学ぶ」の演題で講演をいただきました。
講演の概要は以下の通りです。
公務員や教員は試験で憲法を学ぶが、その他の民間のかたは憲法を学ぶ機会が少ない。条文の丸暗記で教育ができたと思うのは間違いで、憲法をどう解釈していくのかが大切である。
18世紀のフランスをはじめとして近代市民革命が起こった。近代市民革命前までは暴力・神話(天皇は神の子であるなど神話をつくって人を支配した)によって「人が支配」していた。革命後、国家がおこなってきた悪事を防ぐために「憲法」をつくり、「法の支配」となった。
「日本国憲法」を見てみると、国家の統治規定(天皇・戦争の放棄・国会・内閣・地方自治法など)と人権規定(国民の権利及び義務)がある。人権規定が多い印象があるかもしれないが、実際は大部分が統治規定である。人権を守るために統治規定がある。国は国家権力制限規範として戦争・軍隊に対する重みを感じるべきである。
憲法第81条の違憲審査制は、多数派が間違ったら裁判所が是正するためのものである。日本ではなかなか裁判所が違憲審査を出さない。内閣が最高裁の裁判官の人事権を握っているため、長期政権が続くと裁判所も与党よりになる。この違憲審査制が機能していないのは裁判官だけでなく、最高裁の人事権が内閣にあることも考えて選挙にいっているかという国民の責任も大きい。
また、日本国憲法はどのような憲法なのかということにも言及されました。
形式的には戦前の大日本帝国憲法の改正憲法であるが、実質的には新憲法である。戦争に負けたことによって、市民革命などを経ず、近代憲法(18世紀市民革命語の自由権保障)と現代憲法(20世紀以降の社会権保障)の特徴を持つ憲法を手にすることができたのが日本。しかしながら、日本国憲法は、天皇制という封建制の遺物を残した資本主義憲法であるという課題ももっている。
君が代の「細石」の意味を理解しているか。君が代の歌詞の意味を正確に教えないのが問題。子どもに歌詞の意味を教えた上で、判断させるようにすべきである。元号についても、大化から令和まで、その意味を理解しているか。元号を発案した中国も現在は元号を使用していない。国際化の現状、元号は不便なので西暦を使用すべきである。
人権については、高校生の校則問題にもふれ、学生服・セーラー服は軍服からきていることを知った上で、なぜ制服をなぜ着ないといけないのかということ疑問をもつことも大切である。また、メタボ規制によって一律の基準で健康を押し付け、個人の健康問題に介入することにも疑問を感じる。
労働者の権利は組合組織率の低下によって政策に反映されなくなっている。日本は有給休暇の取得率が低い。正規労働者の労働時間も欧米に比べて大幅に多い。日本は労働組合の組織率が低いため労働者の意見を政策に反映できていなが、欧米は労働組合の意見を反映した政党が政権を取ることで、労働者の意見を政策に反映できている。
改憲の動きについても、明文改憲はとまっていても、防衛費の増額等の実質改憲が進む危険性があることには注意が必要である。
労働者に支えられた政党が政権をとっている欧米をモデルにし、労働組合の強化と労働組合が政党を支え、労働者の声を届けることが大切である。労働組合での憲法学習をこれから広げていくべきであるとまとめられた。
休憩時間を挟んで、質疑・応答・討論に入りました。参加者から積極的に発言があり、活発な議論が展開されました。
天皇制・日の丸・君が代問題については、地道な草の根運動を続けていくことの大切さと、現行制度に対して疑問をもつことの重要性も確認されました。
憲法と地方自治の関係についても議論が展開された。戦前は地方自治が認められていなかったが、戦後、反省をもとに憲法で地方自治が認められるようになった。沖縄の民意は基地移設反対なのだから、国も尊重していくべきとの指摘がありました。
元号の使用について、西暦も宗教の関係があって現場では疑問に思うところがあるとの発言がありました。清水さんから、西暦はキリスト教と結びついているので相応しいとは思わないが、元号は日本でしか通用しないのでふさわしくない。世界で通用する暦という意味で西暦を使用していくべきとの回答がありました。
現地に行って本物に出会い、本質を学ぶことや本を読むことを敬遠する人が増えており、「HOW TO」をもとめる現状への懸念についても発言がありました。
清水さんからは、私たちが忖度せず進んでいく姿を次の世代に見せていくべきであり、コスパ・タイパを重視する現代社会において、新聞をはじめとする活字を読んでない人が多くなっている。活字を読んでいない人は表現ができない。活字を読むという文化を広げ、表現できる人材を育てていってほしいとの発言がありました。
本分科会参加者には労働組合関係者が多いと思われますが、「憲法学習」を労働組合でしていく必要性を改めて考えさせられました。私たちが憲法を生かすことができていない今、改めて憲法を学び、生かしていくためのとりくみが必要があります。なぜ、どうしてを考えることの大切さに立ち返り、自分自身で知ること・学ぶこと、草の根運動に生かしていきたいと、運営委員がまとめて締めくくりました。