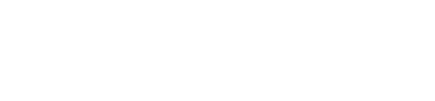6月, 2024 | 平和フォーラム
2024年06月30日
生物多様性から見た上関『使用済み核燃料中間貯蔵施設』計画―海洋保護区での港湾・防波堤建設や埋立て・浚渫はあり得ない―
湯浅一郎
2022年11月28日、中国電力(以下、中電)の上関原発建設の埋立て免許の延長申請に対して、山口県知事は公有水面埋立て免許期限を2027年6月まで延長する3回目の承認を行った。同時に山口県は、中電に対し原子炉の設置許可が出て、原発本体の着工時期が見通せない間は埋立てをしないようにとの条件を付している。いずれにせよ上関原発建設計画はくすぶったままである。
さらに2023年8月2日、中電は、今度は関電の苦境を救う一助として、使っていない上関町の所有地での「使用済み核燃料中間貯蔵施設」の立地調査を表明した。再処理工場の稼働が全く見通しが立たないことなどで核燃料サイクルが破綻している中で原発再稼働を推進するというあまりにも愚かな国の方針のつじつま合わせのために、極めて不当な政策が出てきたのである。しかし、そんなことのために、かけがえのない自然と生物多様性を壊すわけにはいかない。海洋保護区での港湾・防波堤建設や埋立て・浚渫は生物多様性の保全の観点からみてありえない計画であることを明らかにする。
1.100%海洋保護区で囲まれた中電所有地
2024年6月26日、山口県議会において中島光雄議員が「公開されている共89号(長島西部)、共84号(長島中部)(令和6年(2024年)1月1日更新)の図のすべての海域が共同漁業権を有していると考えてよいのか」との質問を行った。これに対し、山口県は「共同漁業権共第84号と共第89号の漁場図で示している全ての海域について、現在、共同漁業権が免許されています」と答弁した。
山口県HPに掲載されている共同漁業権第89号の海域図を図1(注1)に示す。私は、この図を見たとき、長島西端の田ノ浦沖の上関原発の埋立て予定地が含まれる海域との境界が示されていないことに疑問を持った。田ノ浦の海域については、2000年4月27日、四代や上関漁協と中電との間で漁業補償契約書(注2)が取り交わされ、田ノ浦沖と取水口用の2か所の海域は「漁業権消滅区域」とされている(図2)。しかし、図1に、図2で示した「漁業権消滅区域」との境界がないということは、漁業補償海域にも共同漁業権があるということなのかという疑問があった。 中島県議の質問に対する山口県の答弁は、この疑問に関して「今も共同漁業権がある」という回答を与えている。田ノ浦沖は、漁業補償がなされて漁業権が放棄されたようになっているが、なぜ共同漁業権はあるのか? 漁業法で、漁業権は「漁業を営む権利」と定義されており、漁業者が免許申請をしてきた場合には、県知事としては「漁業の免許」を半ば自動的に出しているということなのではないか?
いずれにせよ、この事実は中間貯蔵施設や上関原発計画に関して極めて重要である。これにより、中電所有地が面する海は、すべて生物多様性の保全という目的を持った海洋保護区であることになるからである。背景は以下である。
2010年、名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議において、2020年に向けて生物多様性を保全し、回復するための国際合意として20項目にのぼる「愛知目標」が採択された。その第11項目は「2020年までに沿岸の10%を海洋保護区にする」としている。これを受けて環境省は、2011年5月、「我が国における海洋保護区の設定の在り方について」(注3)なる文書で海洋保護区を以下のように定義した。
「海洋生態系の健全な構造と機能を支える生物多様性の保全及び生態系サービスの持続可能な利用を目的として、利用形態を考慮し、法律又はその他の効果的な手法により管理される明確に特定された区域」
この定義に基づき、環境省は、2020年予定の第15回生物多様性条約締約国会議に向け、いくつかの法的な枠組みで持続的に利用できるような海域を保護区とする作業を進めた。コロナ禍でやや遅れたが2021年8月の環境省の資料(注4)には、その結果が以下のように示されている。
①自然景観の保護等;自然公園(自然公園法):優れた自然の風景地保護と利用の増進。
②自然環境又は生物の生息・生育場の保護等;
・自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域(自然環境保全法):保全が特に必要な優れた自然環境を保全する
・鳥獣保護区(鳥獣保護管理法):鳥獣の保護
③水産動植物の保護培養等
・保護水面(水産資源保護法):水産動植物の保護培養。
・沿岸水産資源開発区域、指定海域(海洋水産資源開発促進法) 水産動植物の増殖及び養殖を計画的に推進するための措置等により海洋水産資源の開発及び利用の合理化を促進
・共同漁業権区域(漁業法) 漁業生産力の発展(水産動植物の保護培養、持続的な利用の確保等)等
つまり日本では、愛知目標の「海の10%を海洋保護区にする」を、自然公園法、自然環境保全法、鳥獣保護管理法、水産資源保護法、海洋水産資源開発促進法、漁業法など既存の法律に基づいて作られている「特定の区域」を、そのまま海洋保護区として選定することで対応したのである。この中で最も面積が広いのが共同漁業権区域である。これによりほぼ90%の瀬戸内海はすでに海洋保護区になっている。日本全国で言うと、このかたちで8.3%の日本の周りの水域が海洋保護区に指定され、国連にも報告されている。
しかし、漁業者を初め市民に、ほとんどこの認識はない。かく言う私自身が、昨年10月まで明確には認識していなかった。このような事態が起きている背景には、環境省や各県が、愛知目標に対応した海洋保護区が決まっていて、瀬戸内海では共同漁業権区域が切れ目なく張り巡らされている関係で、海辺から普通に見ている海はほとんど海洋保護区であることを市民に知らせようとしていないことに起因している。
いずれにせよ以上から分かるように共同漁業権区域は海洋保護区とされているわけである。ここで、冒頭で示した山口県議会における中島県議の質問に対する山口県の答弁が生きてくる。つまり上関の中電所有地が面する海には共同漁業権が存在し、結果として100%海洋保護区になっているということになる。
2.上関の海は「生物多様性の観点から重要度の高い海域」の一つ
一方、生物多様性からの評価については、環境省が2016年に抽出している既存の『生物多様性の観点から重要度の高い海域』の沿岸域270海域があり、瀬戸内海には57海域がある(注5)。これらは、以下の8つの抽出基準を基に評価されている。
1.唯一性または希少性、2.種の生活史における重要性、3.絶滅危惧種、4.脆弱性、感受性または低回復性、5.生物学的生産性、 6.生物学的多様性、7.高い自然性の保持、 8.典型性、代表性
その270海域には、原発予定地や立地点が含まれる。中でも上関原発予定地である田ノ浦海岸は「長島・祝島周辺」と名付けられた「海域番号13708」の中心に位置している(図3参照)。
環境省によれば、この海域には、先に見た抽出の基準ごとに以下の特徴がある。
・基準2(生活史における重要性);[哺乳類]スナメリ、[鳥類]コアジサシ(営巣)、[魚類]イカナゴ(産卵場)、ヒラメ(産卵場)、マダイ(産卵場)、[甲殻類等]カブトガニ、[頭足類]マダコ。
・基準3(絶滅危惧種):[鳥類]コアジサシ、[維管束植物]ヒロハマツナ。
・基準7(自然性):[甲殻類等]カブトガニ、[維管束植物]ウラギク、ヒロハマツナ、フクド。
そして特徴として「祝島と長島を隔てる水道はタイの漁場として有名であり、スナメリやカンムリウミスズメが目撃されている。岩礁海岸ではガラモ場が非常によく発達しており、生産性も高い。宇和島ではオオミズナギドリの繁殖地が見つかっている。」「護岸のない自然海岸が多く、瀬戸内海のかつての生物多様性を色濃く残す場所である」としている。270海域の中でも生物多様性の豊かさという点ではトップクラスなのである。
加えて先に1.で見たように田ノ浦海岸を初め中電所有地が面する海はすべて海洋保護区とされている。そうなれば、まずは既に行われている山口県知事の田ノ浦沖に関する埋立て承認は、生物多様性の保全を目的とした海洋保護区を埋めることを承認するというあり得ない行為であり、「生物多様性基本法に照らして法的な瑕疵がある」ことになり、撤回されねばならないことは明らかである。1982年、地元自治体の誘致で始まった上関原発計画の海面埋め立てに関する山口県知事の埋立て認可は、生物多様性国家戦略の閣議決定、及び愛知目標に対応して海洋保護区が選定されているという新たな文脈の中で、その不当性が浮かび上がっている。
3. 海洋保護区での法的規制は無く、国家戦略に照らした検証プロセスは存在しない
しかるに海洋保護区に選定されていたり、生物多様性国家戦略があるから自動的に開発は止まるわけではない。環境省は、設定した海洋保護区の生物多様性を保持するための指針や法的規制については何も定めていない。「各所管省庁がそれぞれの制度の目的に応じてその目的達成に必要な規制を設けており、それらの適切な運用を通じて、海洋保護区を管理していくことが重要である」としているだけである。つまり、せいぜい当該の法制度の運用によって管理していくとしているだけなのである。「海洋保護区」と称しただけで、それが実効的に有効になるための措置を取ろうとしていないのである。しかし、海洋保護区と称した以上、その目的に照らして「生物多様性の保全に逆行する行為は禁止する」との規制をかけるべきである。
生物多様性国家戦略に照らして事業の妥当性を検証するプロセスはできておらず、環境省は、「国家戦略は、生物の保全、及び持続可能な利用に関する基本的な計画である」としつつも、「個別具体的な事業について言及しているものではない」としている。これでは、生物多様性国家戦略を閣議決定し、2030年までに「陸と海の30%以上を保護区にする」などとしていても、生物多様性の低下を抑えることは全くおぼつかない。
20世紀末、人類は、このまま生物多様性を破壊していけば自らも含めて破滅への道であることに危機感を抱き、1992年、リオデジャネイロ(ブラジル)での地球サミットで生物多様性条約と気候変動枠組み条約をセットで採択した。しかし30年間の努力にもかかわらず事態の改善は見えていない。この状況を打開すべく2022年12月19日、生物多様性条約第15回締約国会議(モントリオール)は、生物多様性の維持・回復に関する「昆明(クンミン)・モントリオール生物多様性枠組み」に合意した。2050年までの長期ビジョン「自然と共生する世界」と、そのため2030年までに「陸と海の少なくとも30%を保護区にする」など23目標を盛り込んでいる。これを受け日本政府は、2023年3月31日、「生物多様性国家戦略2023-2030-ネーチャーポジテイブ実現に向けたロードマップ」を閣議決定した。これらの文書の底流には「今までどおりから脱却」し、「社会、経済、政治、技術など横断的な社会変革」をめざすとの基本理念を掲げ、その具体化のため昆明・モントリオール枠組みに即して2030年までに「陸と海の30%以上を保護区にする」など25の行動目標を盛り込んだ。これらにより政府は、生物多様性条約の新たな世界目標、及び生物多様性国家戦略に基づいて国のすべての政策を検証せねばならない義務を負うことになったはずなのである。にも拘わらず個別具体的な事業で生物多様性の損失をもたらすとしか考えられない要素があっても、何一つ対応しようとしていないのである。
この状況下では市民が問題点を提起し、海洋保護区での港湾建設やましてや埋立てなどはあり得ないとの世論を作り、自治体や政府のありようを変えていく活動を強めていくしかない。
ちなみに全国17か所の原子力サイトで、泊、東通、女川、福島、東海、浜岡、志賀、敦賀、美浜、大飯、高浜、島根の各原発も「重要度の高い海」に面している。共同漁業権に基づく海洋保護区との位置関係などを含め生物多様性国家戦略に照らしての検証が求められる。例えば浜岡原発は「駿河湾西域・御前崎・遠州灘周辺」(海域番号12901)、敦賀・美浜・大飯・高浜の4原発は「若狭湾」(海域番号16301)という名の重要度の高い海域内にある。前者は「大井川河口から遠州灘の海岸はアカウミガメの産卵地」であり、御前崎のウミガメ及びその産卵地が天然記念物指定されている。後者ではヤナギムシガレイ、マダイ、ヒラメなど多くの魚種の産卵場がある。こうした場に核分裂性物質を大量に保管する工場があり、稼働すれば膨大な温排水を放出することの意味が問われるべきであろう。
(注)
1)共89号区域図https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/169136.pdf
2)漁業補償契約書(2000年4月27日)。
http://www.kumamoto84.sakura.ne.jp/Kaminoseki/000427hoshoukeiyakusho.pdf
3)「我が国における海洋保護区の設定の在り方について」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/dai8/siryou3.pdf
4)令和3年度 第1回 民間取組等と連携した自然環境保全の在り方に関する検討会、資料3。https://www.env.go.jp/content/900489164.pdf
5)環瀬戸内海会議HP。
https://www.setonaikai-japan.net/00kansetonaikaikaigi/301topics/topics301.html
2024年06月28日
【平和フォーラム声明】繰り返される米兵による女性への暴力・暴行事件に強く抗議する
平和フォーラムは6月28日付で、以下の声明を発表しましたので、お知らせします。
繰り返される米兵による女性への暴力・暴行事件に強く抗議する
昨年12月、嘉手納基地所属の空軍兵士が沖縄本島中部の公園で声をかけた16歳未満の女性を誘拐して米軍基地外の自宅に連れ込み、性的暴行におよぶ許しがたい事件が発生した。
事件当日の女性の家族からの110番通報をもとに沖縄県警による捜査が行われ、今年3月27日に起訴に至った。起訴を受けて外務省はエマニュエル駐日米大使に綱紀粛正と再発防止の徹底を申し入れたが、他方で沖縄県には何の連絡もしなかった。このため、沖縄県は6月25日に報道があるまで、起訴から3カ月が経ってもこの事件を把握できないままだった。これについて、林官房長官は「関係者のプライバシーへの配慮」「捜査公判への影響の有無を考慮」したと釈明し、外務省の報道官も「常に関係各所への連絡通報が必要だとは考えていない」と述べている。しかし、県民の生命や安全を守る責務を負う沖縄県に通報がないことは重大な問題であり、日本政府や外務省は「被害者のプライバシー」に配慮したのではなく、6月16日に投開票が行われた県議会議員選挙や6月23日の「慰霊の日」の岸田首相の訪沖といった政治日程を踏まえて沖縄県内で事件への抗議の声が高まることを恐れたのではないか。また、これまでの辺野古新基地建設をめぐる国と県の対立が影響を及ぼしたことも否めない。
起訴により日米地位協定にもとづいていったん日本側に引き渡された被告の米兵の身柄は、現在は保釈によりふたたび米軍基地内へと移されている。6月25日の報道によりこの事件が発覚した後、27日に沖縄県庁を訪れた米第18航空団のエバンス司令官は被告について「裁判期間中は基地の外へ出られないよう関係者に指示し、パスポートも差し押さえている」と報告しているが、米軍基地内での米軍による身柄確保は過去に米兵が引き起こした犯罪事件を振り返ると、証拠隠滅や逃亡の懸念がぬぐい切れない。そもそも在日米軍基地内では日本当局による出入国審査が行われておらず、パスポートを取り上げることが被告の逃亡を防ぐ有効な手段であることを意味しない。しかも、エバンス司令官とドル駐沖縄米国総領事は県庁を訪れた際に「遺憾の意」は表明したものの、被害者や県民への謝罪の意志は示さなかった。
沖縄では、今回の事件にとどまらず、米兵による女性に対する暴行、暴力事件が相次いでいる。1972年の復帰後、2023年までの51年間で沖縄県内における米軍構成員(軍人、軍属、家族)の刑法犯による摘発は6235件、摘発者は6124人にものぼり、うち殺人、強盗、放火、不同意性交など「凶悪犯」の摘発は586件、759人をしめている。日本政府に県民、国民の安全や尊厳を守る姿勢が欠如しているなか、日米地位協定の下で犯罪を起こした米兵が適正に処罰されないこと、被害者への補償がなされないことも深刻な問題である。とくに不同意性交については被害者の多くが泣き寝入りを強いられており、表面化している摘発件数は氷山の一角に過ぎない。
今年に入ってからも米軍構成員の刑法犯による摘発は28件、34人にのぼり、うち「凶悪犯」は5件、4人を占めている。5月に20歳代の海兵隊員が女性に性的暴行を加え、抵抗した女性にけがを負わせて逃亡した後、通報を受けた県警に米軍基地外で不同意性交致傷の疑いで逮捕された。6月3日には海兵隊の大尉が飲酒したうえで交際相手の女性に暴行して全治日数不詳の打撲を負わせ、傷害の疑いで現行犯逮捕された。
さらに、4月には海兵隊員が県内のコンビニエンスストアでナイフを店員につきつけて現金約13万円を奪った強盗事件が発生した。6月9日深夜には北谷町のホテルで泥酔した海兵隊の少尉がホテルの備品を破壊して器物損壊で逮捕され、さらに22日早朝には北中城村で基準値の約3倍の酒気を帯びた状態で乗用車を運転した陸軍兵士が逮捕された。一般の兵士ばかりか将校までが事件・事故を繰り返すなど、米軍の規律の崩壊はますます深刻になっていると言わざるを得ない。
「綱紀粛正」「再発防止の徹底」では、米兵の犯罪はなくならないことは明らかである。新基地建設を阻止し、さらに沖縄から米軍基地をなくすこと以外に安心・安全な生活を実現する途はない。12月に発生した米兵による未成年の女性への性的暴行事件と日本政府・外務省の情報隠しに対し、これまでに浦添市議会、那覇市議会、北中城村議会で抗議決議が可決されている。平和フォーラムは相次ぐ米兵による女性に対する暴力事件、暴行事件に最大限の怒りをもって抗議し、沖縄の仲間たちとの連帯を強めつつ、米軍基地の撤去に向けたたたかいのいっそうの強化を決意し、全国に呼びかける。
2024年6月28日
フォーラム平和・人権・環境
共同代表 染 裕之
共同代表 丹野 久
2024年06月28日
憲法審査会レポート No.44
衆院憲法審幹事懇の開催目論むも流会
衆院憲法審査会の森会長は閉会中審査開催に向けた幹事懇談会を、与野党筆頭幹事の合意ではなく職権をもって28日開催を決定しましたが、逢坂筆頭幹事をはじめ立憲民主党と共産党は欠席を表明、結局流会となりました。
25日には自民党役員会で岸田首相が「憲法は先送りできない課題の最たるものだ」などと発言してみたり、憲法改正実現本部のもとに衆参両院の議員による会議体の新設を決定するなどしています。
普通に考えれば、幹事懇を職権で強行することは今後の憲法審自体の開催にも悪影響を及ぼすだけであって、論外の行いです。岸田首相の発言や会議体新設云々もそうですが、パフォーマンスを繰り返すことで、なんとか求心力の維持に努めようとしているものと思われます。
自民党総裁選挙も控えていることから、今後もこうした「受け狙い」の動きが続くことが予想されます。警戒を緩めることなく、しっかりと注視していきましょう。
【参考】
衆院の憲法審査会幹事懇は開催できず 立憲や共産が欠席
https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000357126.html
“衆議院の憲法審査会は国会閉会中も憲法改正に向けた議論を進めるために幹事懇談会を開くことを決めましたが、立憲民主党や共産党が反発して欠席し開催できませんでした。”
憲法の政治利用/逢坂誠二 7849回
https://ohsaka.jp/15514.html
“まず閉会中の審議のあり方について、与野党国対で、十分な合意がないこと。国会での様々な与野党のやり取りは、最初に国対が大きな方向を決めます。それに従って各委員会の筆頭が協議します。今回、憲法審については、国体の方針が決まらない中での強行です。”
“こうした中では、筆頭間協議をしない、あるいはできないのですが、強引かつ一方的に要求を突きつけてきます。理不尽という他はありません。”
岸田首相「憲法、最たる課題」 保守派を意識、自民に温度差
https://www.47news.jp/11109216.html
“岸田文雄首相は25日の自民党役員会で「憲法は先送りできない課題の最たるものだ」と述べ、改正論議の前進を訴えた。9月の総裁選をにらみ、党内保守派へのアピールとみられる。ただ松山政司参院幹事長は記者会見で「衆参には意見の食い違いがある」と拙速な議論を警戒した。党内に温度差があるのが実情だ。”
自民 憲法改正に向け 衆参議員参加の新たな会議体 検討加速へ
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240626/k10014491981000.html
“…国会の憲法審査会の議論は衆議院と参議院で進捗(しんちょく)が異なることから、党の実現本部のもとに衆参両院の議員が参加する会議体を新たに設けて検討を加速させることを決めました。”
2024年06月24日
【平和フォーラム声明】第213回通常国会閉会にあたって
平和フォーラムは6月24日付で、以下の声明を発表しましたので、お知らせします。
第213回通常国会閉会にあたって
23日に閉会した第213回通常国会は、自民党派閥の政治資金パーティー券収入による裏金づくりに国民の厳しい目が向けられる中、多くの問題法案が横暴な数の力により成立した。
政治への不信感を払しょくすると、岸田首相が意気込んだ政治資金規正法改正は、野党が求めた企業・団体献金の禁止は行われず、政治資金を監視する第三者機関の具体像も不明なままである。積み残された課題は今後の与野党協議に委ねられるが、議論の場さえ決まっていない。自民党議員からは「国会が閉会すればこの問題は終わり」と幕引きを目論む声も聞かれ、長期政権の緩みと驕りが端的に現れている。
1)憲法審査会について
第213回通常国会の最終局面の6月19日、岸田政権初となる党首討論が行われた。
立憲民主党・泉代表が、国民の政治不信を招いた岸田首相の責任を糾したことに対し、岸田首相は「(御党も)憲法改正について責任ある対応をお願いしたい。具体的な改正起案について議論を始めるよう協力をお願いしたい。」と応じた。憲法を守るべき国務大臣の長たる内閣総理大臣が、国会の党首討論の場で憲法改正に言及するなど決して許されるものではない。
参院憲法審査会は、緊急時における参院の緊急集会のあり方について議論が重ねられている一方、衆院憲法審査会では緊急事態条項の創設および議員任期の延長について、「議論は出尽くした。発議の条文化に着手するべき」と、改憲ありきの主張が改憲推進会派から主張されるなど、衆参の議論内容や温度差が明らかになっている。
13日、“首相、任期中の改憲断念”と報じられたが、衆院の改憲推進会派からは国会閉会中審査を求める意見が出されていることから、引き続き憲法審査会の動向を注視する必要がある。
2)防衛装備移転三原則の運用指針改定、次期戦闘機の第三国への輸出可能決定について
国家安全保障会議および閣議決定で防衛装備移転三原則の運用指針が改定されたことを踏まえ、日英伊共同開発の次期戦闘機の第三国への輸出を可能とすることが閣議決定された。
日本国憲法の平和主義を逸脱し、国際紛争を助長する恐れがある決定は、日本にとって取り返しのつかない選択となりかねない。軍需産業の存在感が強まれば、政治への影響力も大きくなり、さらなる武器輸出推進の声につながることも懸念される。
3)重要経済安保情報保護法について
経済安全保障上の機密情報を扱う民間人らを身辺調査する、適正評価制度の導入を柱とした重要経済安保情報保護法が成立した。
重要経済安保情報の漏洩は処罰の対象となるが、情報の範囲が不明確であるため様々な問題が生じ得る。適性評価については、本人の同意を得て実施するとされているが、同意しなければ人事考課や給与査定等で不利益を受ける可能性も否定できない。
公布から1年以内の同法の全面施行までに、同法の運用基準等の策定に向けた検討が始まり、パブリックコメントも実施されると言われている。同法の抜本的な見直しを求めつつ、同法による悪影響が最小限となるための具体的な方策が必要となる。
4)地方自治法の一部改正
感染症や災害など重大な事態が発生した場合に、国の自治体への指示権を拡大する地方自治法の一部改正が成立したが、指示権が発動できる基準が曖昧である。国会の承認も不要で、政府の閣議決定だけで指示権を行使できる。地方自治に対する国の不当な介入につながり、国と地方は対等とする地方分権改革に逆行し、上意下達的に国の考えに地方を従わせるものである。
問題点が明らかになるにつれて反対や批判の声は全国にひろがった。憲法をも逸脱する重大な問題を含んだ法案が、わずかな審議によって採決・成立が強行されたことに満腔の怒りをもって抗議する。
5)民法改正(共同親権の導入)について
法律の成立により離婚後も父母が共同で親権を持つことが可能になる。これまでは父母の一方だけに親権が認められていたが、話し合って共同親権にするか、どちらかの単独親権とするかを選ぶことが可能となり、合意できない時は家庭裁判所が決めるとされている。
配偶者からの暴力(DV)や子どもへの虐待がある場合、親権の行使を理由に接点が生まれ、被害が続く可能性が生じる。その結果、子どもに不利益が及ぶことが危惧される。子どもの利益が損なわれないような運用が行われなければならない。
6)自衛隊法の改正について
陸海空の各自衛隊を一元的に指揮する、常設の「統合作戦司令部」を設置することを盛り込んだ改正自衛隊法などが成立した。
4月の岸田首相のアメリカ訪問の共同声明では、「自衛隊と米軍の間の相互運用性及び計画策定の強化を可能にするため」、「それぞれの指揮・統制の枠組みを向上させる」としている。
自衛隊を一元的に指揮する「統合作戦司令部」の創設は、米軍の指揮下に自衛隊が組み込まれ、先制攻撃の一翼を担うことになる危険性をもつ。こうしたアメリカ追従の「岸田大軍拡」に対して、ストップをかけるたたかいを本格化させなければならない。
7)出入国管理法の改正について
出入国管理法改正案と外国人技能実習法改正案が成立した。
技能実習の在留資格を廃止し、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格である「育成就労」の創設を主としているが、永住許可制度の適正化を理由として、税金や社会保険料を支払わない場合に永住許可を取り消せる規定が設けられるなど、外国人差別を助長する重大な問題を抱えた内容である。
税の滞納等へのペナルティは日本人と同様に扱うべきである。国籍や人種などで差別されない、真の多文化・共生社会の実現こそ求められている。
8)食料供給困難事態対策法について
異常気象や紛争などの影響で、米や小麦、畜産物など重要な食料が不足した場合への対応を盛り込んだ新たな法律が成立した。
食料が大幅に不足する予兆があった場合、内閣総理大臣をトップとする対策本部を設置し、関係する事業者に生産や出荷などに関する計画の提出や変更を指示できるとしているが、計画を提出しない事業者には20万円以下の罰金を科すことに懸念が残る。
(まとめ)
憲法前文には「国政は国民の厳粛な信託によるもの」と謳われている。「国民の厳粛な信託」とは、衆院の資料によると「国民からの信託に背かないように権力を行使する責任を負う」と説明されている。「国民の厳粛な信託」による政治とあまりにもかけ離れた、口先だけの政権運営を続ける自公政権には一刻も早く退陣してもらわなければならない。
抜け穴だらけで中途半端な政治資金規正法改正は、国民の政治不信をさらに高めただけである。かかる政治状況を招いた自民党政治を糾弾するとともに、一刻も早く国民の信を問うための衆院の解散・総選挙を強く求める。
第213回通常国会の閉会にあたって、平和フォーラムは生活者の視点で、国民が主役となる政治を取り戻すために、引き続き国会対策や大衆運動の展開を追求することを表明する。
2024年6月23日
フォーラム平和・人権・環境
共同代表 染 裕之
共同代表 丹野 久
2024年06月24日
ニュースペーパーNews Paper 2024.6
6月号もくじ
ニュースペーパーNews Paper2024.6
表紙 「朝鮮学校差別に反対するNGO 第1回国際連帯ハンマダン」
*戦没者遺骨をふるさとへ、家族のもとへ帰すために
沖縄戦遺骨収集ボランティア 具志堅隆松さんに聞く
*原水禁世界大会に向けて
*2023年、2024年と続く入管法改悪にNO!
*「機能性表示食品制度」について
*地方自治法改正に反対する
*本の紹介「火山鳥」(全7巻) 金石範 著
*決意も新たに!平和F・原水禁 スタッフ一丸となって
2024年06月21日
憲法審査会レポート No.43
国会は23日に閉会、閉会中審査開催要求の動きも
今通常国会は延長せず、このまま閉会する見込みです。
19日に行われた党首討論では、岸田首相は立憲民主党の泉代表に対し、衆院憲法審査会の「定例日」の木曜日が翌20日であることを引き合いに出しつつ、条文案起草作業への協力を求めましたが、憲法審査会の開催は現場の(幹事間の)判断であり「総理がするような質問ではない」と断じられています。
「岸田首相の自民党総裁任期中の改憲」という目標はひとまず潰えましたが、それでもなお自民党や公明党などからは、閉会中審査開催を求めていく意向が語られています。
しかし、裏金にまみれてきた自分たちの政治腐敗の有様は棚に上げながら、憲法に手をつけようなどとは、言語道断です。こうした動きを許さないために、引き続きの注視を呼びかけます。
【参考】
立民、首相の改憲発言に反発 党首討論で条文化を呼びかけ
https://nordot.app/1176727387321582189
“衆院憲法審査会で野党筆頭幹事を務める立憲民主党の逢坂誠二氏は…「(岸田首相が)憲法審の運営に口を出したことは極めて遺憾だ」と記者団に述べた。”
“21日の衆院憲法審幹事会で、与党筆頭幹事を務める自民の中谷元氏は23日の国会閉会後も憲法審を開くよう提案したが継続協議となった。”
憲法審、閉会中も開催を 自民
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024062000924&g=pol
“自民党の憲法改正実現本部は20日、党本部で会合を開き、今国会の閉会後に衆参両院の憲法審査会の閉会中審査を開催するよう野党側に求めていくことを決めた。”
憲法改正 公明 北側副代表“条文案の作成へ閉会中審査を”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240620/k10014486841000.html
“…公明党の北側副代表は大規模災害をはじめとした緊急事態への対応は衆議院憲法審査会で議論が尽くされているとして、条文案の作成に向けて閉会中審査を行うべきだという考えを示しました。”
国会閉会へ…自民不記載事件で改憲論議進まず 「閉会中審査」が焦点
https://www.sankei.com/article/20240620-7CA6CWAV7NLK3JVXLHOD5XTNMU/
“今後、閉会中審査が実現しなければ、改憲を党是に掲げる自民の信頼は地に落ちかねない。”
“自民の「政治とカネ」が招いた改憲論議の遅れを取り戻すべく、維新や国民民主などは閉会中審査の開催を要求。自民も20日の会合で閉会中審査を求めていくことを確認した。”
ブックレット『その改憲、ちょっと待った! 憲法審査会は今』、好評発売中!
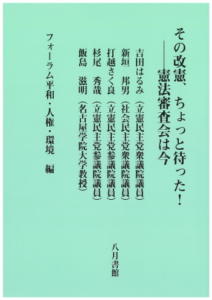 改憲をめぐる正念場!
改憲をめぐる正念場!
憲法審査会の現状を把握するために、ぜひ本書のご活用をお願いします。
本書は全国書店でお買い求めになれます。
著者:吉田はるみ(立憲民主党・衆議院議員)
新垣邦男(社会民主党・衆議院議員)
打越さく良(立憲民主党・参議院議員)
杉尾秀哉(立憲民主党・参議院議員)
飯島滋明(名古屋学院大学教授)
編集:フォーラム平和・人権・環境
発売:八月書館
内容:A5判並製・76ページ
定価:本体900円+税
2024年06月14日
憲法審査会レポート No.42
岸田首相の自民党総裁任期中の改憲は事実上不可能に
今国会は会期延長がないまま、23日に閉会するとみられています。そうなると、日程的には憲法審査会の「定例日」は衆参それぞれ残り1回ですが、19日の党首討論後の不信任案提出も検討されていることから、開催されるかは流動的です。
今国会中に改憲条文案作成が進まなかったことで、このかん岸田首相が掲げてきた「自民党総裁任期中の改憲」それ自体が、現実的には不可能になったわけですが、今後も閉会中審査などを強行してくる可能性も十分ありますので、動向を注意深く監視していく必要があります。
【参考】
(社説)憲法審査会 丁寧な合意形成優先を
https://digital.asahi.com/articles/DA3S15956355.html
“自民は5月末の衆院憲法審で、賛同する公明党、日本維新の会、国民民主党、無所属議員らの「有志の会」を加えた、「5会派のみで検討したい」と表明した。”
“前身の憲法調査会時代から続いてきた、党派を超えた合意形成の重視という原点をないがしろにするものだ。さすがに、その後、自民内でも慎重論が相次ぎ、反対会派も含めた「全会派の参加」をめざす方向に転じたようだが、「改憲ありき」で突き進めば禍根を残すだけだろう。”
自民、改憲原案の今国会提出見送りへ 首相、総裁任期中の実現を断念
https://mainichi.jp/articles/20240611/k00/00m/010/296000c
“自民の衆院側には会期末ぎりぎりまで改正原案の提出を模索する動きもあるが、厳しい情勢だ。4党1会派で条文を作成する方針を確認した上で、国会閉会後に作業を進める案などが検討されている。”
首相、任期中の改憲を断念 自民原案、今国会の提出見送り
https://www.47news.jp/11049501.html
“原案提出の見送りで国会発議の見通しは立たなくなり、目標達成は断念せざるを得ない状況となった。”
“中谷氏は13日の衆院憲法審で、論点整理を示す見通しだ。「個人的発言」との位置付けにとどめ、改憲原案や要綱案の提出は見送る。”
2024年6月12日(水) 第213回国会(常会)
第5回 参議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8056
【会議録】
※公開され次第追加します(おおむね2週間後になります)
【マスコミ報道から】
国民投票運動規制で平行線 自民「自由」、立民「支出上限を」
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024061200900&g=pol
“参院憲法審査会は12日、憲法改正が発議された際の「国民投票運動」をテーマに討議を行った。自民党は原則として自由とすることを主張。立憲民主党は資金力の差が結果に影響を及ぼさないよう支出上限の設定を求めた。”
【傍聴者の感想】
今日の参議院憲法審査会で印象的だった話は投票率の話でした。国民投票法について、例え実施されたとしても現状の低投票率のなか、果たして「過半数」とみなされてもいいものか、という指摘を沖縄の風、高良鉄美議員がしていました。投票率を50%だと仮定すると、その過半数はもともとの主権者の25%ということになります。
世論調査において、「憲法改正」の必要性を感じている市民は決して多くありません。そのような中で国民投票を強行して実施したところで、投票率が上がることは考えにくいと言えます。そもそも、投票率が高くなるなら良いという問題ではないことは、もちろんのことだとして、議論の観点として、納得する部分がありました。
憲法審査会の意見にもあったように、まずすべきことは政治への期待を回復させることにあるように思います。今の大きな課題である投票率が低いという事実にこそ、各議員は向き合うべきです。政治の信頼回復は喫緊の課題です。
参議院は衆議院と違い、論点の整理であるとか原案のとりまとめであるとかといった話にはなっていません。二院制が確固たるものとして確立されている限り、それぞれの議論がそれぞれに存在することは当たり前のことです。自民党議員からは衆議院から送られてきた場合の審議を速やかに行うべきという発言が相次ぎました。
国民投票に関わるCM規制等についての意見が今回の主な内容でした。「公平・公正」について各党からさまざまな意見が出ていましたが、主権者に正しい情報が偏りなく届けられることが重要であるとも述べられていました。憲法にかかわらず常日頃からの情報公開について、透明性が求められていることは言うまでもありません。
「どうせ」「またか」とあきらめることなく、政治は私たちのくらしに直結する重要な存在であることを繰り返し訴えていきたいと思います。
なお、今回傍聴していたなかで、改憲派の特定の政党の意見表明に合わせて遅れて入り、終わると出ていった20人を超す男性グループの動きが異様に感じました。特定の政党の発言のみを傍聴し、全員が一矢乱れぬ整列のまま退場する姿は、思わず何事かと目を引く瞬間でした。
【国会議員から】辻元清美さん(立憲民主党・参議院議員/憲法審査会幹事)
 国民投票法の改正と広報協議会の在り方について、会派を代表して発言をいたします。
国民投票法の改正と広報協議会の在り方について、会派を代表して発言をいたします。
私からは、特に令和3年改正附則4条2号の検討条項に規定されております国民投票の公平及び公正を確保するための事項について意見を述べます。
まず、第2号のイのテレビCMとネットCMの制限についてですが、国民投票法は、テレビCMについてのみ勧誘広告の投票日前2週間の禁止の制限を設け、ネットCMについては何ら制限がございません。しかも、私も立法に関わった国民投票法制定からはや17年が経過し、制定当時と比べ、いわゆるネット社会は著しく進歩、進化、拡大しております。
博報堂の研究所の調査、2023年によりますと、1日当たりの接触時間、ネットは、パソコン、タブレット、スマホ合計すると256分、スマホ単独でも152分。テレビの135分をはるかに上回っております。また、電通の調査によると、2023年の広告費も、ネットは3兆3,330億円であり、テレビの1兆7,347億円を上回っております。
このような現状を踏まえますと、国民投票法制定時のテレビCM中心の制度は社会の実情と完全にそごを来しており、ネットCMについてテレビCMと同様に何らかの法規制は必要になると考えます。というのは、テレビは2週間は禁止と決めておりますので、ネットをどうするか、これは検討事項として重要だと思われます。
立憲民主党は、政党等によるネットCMを禁止し、その他のものによるネットCMについてはネット広告事業者にCM掲載基準の策定等の努力義務を課す国民投票法改正案をまとめています。
次に、第2号のハのインターネットの適正な利用の確保についてですが、例えば、ゼレンスキー大統領が市民らに投降を呼びかける内容の偽動画とか、アメリカ国防総省の近くで爆発が起きたかのように見せかけた偽動画とか、岸田総理大臣が卑わいな言葉で語りかけているように見せかける偽動画など、世界でも我が国でもいわゆるフェイクニュースが大変問題になっております。フェイク情報によって国民投票の判断が狂わせられることは決してあってはなりません。ネットの適正利用の確保は喫緊の課題と言えます。
立憲民主党は、ネットで国民投票運動等をする際のメールアドレスの表示義務、広報協議会によるネットの適正利用のためのガイドラインの作成などが必要だと考えております。さらに、フェイクニュース対策として、広報協議会による客観的かつ中立的な情報の積極的な提供、広報協議会とファクトチェック団体との連携、国民投票についてネット検索した際には広報協議会の情報が表示されるようにすることなども積極的に検討するべきです。
次に、第2号ロの資金規制についてです。
ネット社会の進展と弊害などを踏まえて、資金力の多寡による公平性への悪影響を検討し、必要な法的措置を検討する必要があると考えます。
立憲民主党は、国民投票運動等の支出上限の設定、収支報告書の提出などが必要と考えています。立法府として、時代の変化に即して、国民投票の在り方と広報協議会の役割を再検討しなければならない時期に来ていると考えております。
最後に、国民投票法制定時、民放連はテレビCMの自主規制を行うと国会に約束をし、これ、私もこの目の前でそういう発言を聞いております。平成26年の参議院附帯決議第19項もそれを前提とした規定になっています。テレビCMについて、民放連の対応がその後どのような変遷、結論となっているのかについて事務局に説明を求め、国民投票法などの改正なくして改憲発議はあり得ないと申し上げ、私の意見を終わります。
(加賀谷ちひろ・参院憲法審事務局長)
平成30年9月に民放連が量的自主規制はしない旨を表明し、その後、先ほど御説明申し上げました配付資料の22ページ、23ページに掲載の考え方等が公表されました。
令和4年4月の衆議院憲法審査会においては、参考人の民放連専務理事より、自主規制について、量を全く考慮しないわけではなく、あらゆることを総合判断する旨の答弁がされております。
(憲法審査会での発言から)
2024年6月13日(木) 第213回国会(常会)
第10回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55299
※「はじめから再生」をクリックしてください
【会議録】
※公開され次第追加します(おおむね2週間後になります)
【マスコミ報道から】
自民、改憲の論点整理提示 緊急事態時に国会議員任期延長
https://www.47news.jp/11053217.html
“自民党の中谷元氏は13日の衆院憲法審査会で、緊急事態時の国会議員任期延長に関する論点整理を提示した。改憲条文案作成の土台との位置付け。立憲民主党が条文化に反対していることを踏まえ「個人的メモ」にとどめた。”
衆院憲法審査会 自民 緊急事態での議員任期延長で条文案作成を
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240613/k10014479771000.html
“中谷氏は「今後、これをもとに条文化を進めたい。審査会で憲法改正の原案を作り国会に提出して3分の2以上の賛成をもらう必要がある」と述べ、各党に協力を呼びかけました。”
“その上で、今月23日の会期末で今の国会が閉会したあとも閉会中審査を行うべきだという考えを示しました。”
衆院憲法審、自民が国会機能維持の論点整理を発表
https://www.sankei.com/article/20240613-WTQ632ZY7JIARMOIH6XLYBVX4A/
“自民党は13日の衆院憲法審査会で、選挙困難時に国会議員の任期延長を可能にする憲法改正案の「たたき台」となる論点整理を提示した。必要性を共有する公明党や日本維新の会、国民民主党など5党派で調整した上で取りまとめられた。今国会の会期末が23日に迫っており、憲法改正の機運を盛り上げる狙いがある。”
【傍聴者の感想】
冒頭、この間の討論を踏まえた「中谷の個人的メモ」なるコピーが配布されました。そこには、「選挙困難事態」として「自然災害」「感染症まん延」「武力攻撃」「テロ・内乱」に加えて「その他これらに匹敵する事態」が挙げられています。
これらの想定はいずれも「ためにする」ものです。まず、「自然災害」については、そもそも合理化で自治体や企業の体力がそがれて大規模災害に対応できなくなっている状況が問題です。被災した鉄道の線路が何年も放置されたり、道路・水道・電力といったインフラの復旧が進まなかったり、あるいは劣悪な環境の避難所での長期間の生活に象徴される日本の災害行政の後進性や無策を放置したままでは、いくら大規模災害時に「国会機能が維持」されたとしても、復旧・復興に何らかの役割を果たせるはずがありません。そもそも福島では原発事故の発生から13年が経っても多くの人々が避難生活の継続を強いられています。原発が動き続けている限りは大規模災害時の被害は大きくなり、そして長期化するばかりです。国会議員の任期延長の前に脱原発が必要です。
「感染症まん延」についても、2020年以降の3年間の政府による「コロナ対策」が適切、適当だったのかの検証がないままになっています。国会議員の任期を云々する前に、子どもたちの「休校」や、「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」が本当に感染防止に適当だったのか、社会や生活への影響はどうだったのかなど、振り返るべき点があるはずです。
「武力攻撃」は、今回の討論で共産党の赤嶺議員が指摘していたように平和的な外交で回避すべきものです。「武力攻撃」を受けるような事態を招いた国会議員の任期の延長など市民にとっては悪夢そのものです。さっさと退任・引退してもらうしかありません。日本が「テロ」の標的になるような事態についての国会議員の責任についても同様でしょう。
「内乱」を「選挙困難事態」の口実にするのは、そもそも国会議員が自国民を信頼していないことの表れだと感じます。もし「内乱」が実際に起きたとしても、それは逆に市民による政治への極度の不信の延長線上にあるはずですから、こちらもとっとと国会議員など退任すべきであり、任期の延長など不要です。さっさと選挙を実施すべきです。
【国会議員から】逢坂誠二さん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会幹事)
 先週、憲法五十三条に関し発言がありました。憲法五十三条には、いつまでに臨時国会を召集しなければならないのかの期限の定めがありません。我々は、この期限は法律で定めることができるとの認識の下、臨時国会の召集期限を定める国会法の改正案を、日本維新の会など五党一会派共同で衆議院に提出をしました。
先週、憲法五十三条に関し発言がありました。憲法五十三条には、いつまでに臨時国会を召集しなければならないのかの期限の定めがありません。我々は、この期限は法律で定めることができるとの認識の下、臨時国会の召集期限を定める国会法の改正案を、日本維新の会など五党一会派共同で衆議院に提出をしました。
一方、この期限の定めについては、先週、玉木委員が指摘されましたとおり、憲法で定めるべきとの考えもあります。この指摘も踏まえ、法律でよいのか、憲法でよいのか、この点について、今後更に議論を深めたいと考えております。
次に、国民投票に関し、憲法審査会事務局にお尋ねします。
国民投票法に関連し、今後、法律、規程の制定、改正など、どのような法整備が必要となるのか、お知らせいただきたいと思います。
(橘幸信・衆院法制局長)
国民投票実施のための法整備としては、まず挙げられるのは、令和三年の国民投票法改正案、いわゆる七項目案の改正法附則四条に規定されております二つの事項、すなわち、一つ、投票環境整備に関する事項と、二つ、国民投票の公平公正の確保に関する事項、これらについて検討し、その結果、法整備が必要と判断された場合には、そのための措置を講ずることが想定されております。
もう一つ、国民投票実施のために最低限必要な法整備としては、憲法改正の発議がなされた場合に国会に設置される国民投票広報協議会に関する諸規程の整備が挙げられます。
国民投票法において具体的に明示されている規程としては、広報協議会とその事務局の組織に関する広報協議会規程と事務局規程、そして広報協議会が行う放送CMや新聞広告等に関する広報実施規程、この三つのものがあります。
なお、これらの規程の整備に併せて、その事務局職員を国会職員に追加するための国会職員法や国会職員育児休業法などの法律改正も必要となるかと存じます。
これらの法改正や規程の整備、これは、衆議院の憲法審査会のみで議論し決定するものではなく、別の場での議論や決定が必要なものがあるというふうに承知をしておりますが、これらの法改正や規程の整備に関し必要な手続とはどのようなものか、事務局としての見解をお示しください。
(橘法制局長)
まず、国民投票法や国会職員法等といった法律の改正につきましては、通常の議員立法の立案、審議手続と変わるところはございません。その法案の所管については、国会法第百二条の六の規定によりまして、国民投票法改正案は憲法審査会、本審査会の所管となりますが、国会職員法等の改正案につきましては議院運営委員会との御協議が必要となるかと存じます。
次に、広報協議会に関する諸規程につきましては、両院の議長が協議して定める、いわゆる両院議長協議決定と呼ばれる法形式で定めることとされております。これは、原則として、両院の議長がそれぞれの議院運営委員会又はその理事会に諮って定めることとされているものでございます。したがいまして、これらの規程の制定に当たっては、衆参の憲法審査会の間での御協議、そしてそれぞれの議院運営委員会との調整、これが必要となってくるものと思料いたします。
なお、この両院議長協議決定は、通常の法律案の制定手続とは異なり、衆議院と参議院が先議、後議の関係に立つものではございません。それぞれの議院で同一の案文を決定し、それを両院議長が決裁するという手続になってくる点にも御留意が必要かと存じます。
それでは次に、常々私が指摘しております災害に強い選挙の確立については総務大臣や政治改革特別委員長に、また、あらゆる場面における国会機能の維持強化については議院運営委員長に、これらの検討について憲法審査会としてお願いすべきではないかと考えております。今後、これらの点に関しても議論を深めてまいりたいと思います。
(憲法審査会での発言から)
2024年06月07日
憲法審査会レポート No.41
今週は衆議院憲法審査会のみの開催でした。
衆院憲法審をめぐっては、先週、自民党の中谷元・与党筆頭幹事から改憲条文案の起草作業のための幹事懇談会開催の提案がありましたが、4日に撤回されました。政治資金規正法改正案をめぐる審議日程への影響を避ける思惑だと指摘されています。
また、自民党の衆参国対委員長からは、条文案の起草作業より法案審議を優先すべきだ、岸田首相の自民党総裁任期中の改憲は難しい、といった表明が相次ぎました。
しかしいっぽう、起草委員会設置の強行、あるいは閉会中審査の開催などもじゅうぶん考えられることから、参院国対間の会談では立憲民主党が審議拒否の姿勢を示してけん制しています。いずれにせよ会期末に向け山場が続きますので、引き続きの警戒を呼びかけます。
【参考】
自民、憲法審幹事懇の開催を撤回 国会日程への影響避けたか
https://nordot.app/1170270347119952172
“自民党は、憲法改正条文案の起草作業を行う場として提案していた衆院憲法審査会幹事懇談会の4日開催を取り下げた。自民関係者が3日、明らかにした。衆院で政治資金規正法改正案の質疑が大詰めを迎えており、国会日程への影響を避けた可能性がある。”
首相の自民総裁任期中の改憲「厳しい」 浜田靖一国対委員長が言及 規制法への影響懸念か
https://www.sankei.com/article/20240605-4TFOEC6GIVOA3MHOVQ4P36O6NY/
“秋までに憲法を改正するためには今国会の会期末(23日)までに憲法改正を発議する必要があるとされていた中、衆院憲法審査会では自民が主張した改憲原案を協議する起草委員会の設置が一向に進まず、参院憲法審の議論も停滞している。”
“…自民は改憲案、もしくはその前段階の「要綱」を党意思決定機関の総務会に諮ることにとどめる案を含め、対応を協議する構えだ。”
「政権延命に憲法使ってはならない」 改憲勢力での条文案に慎重論
https://digital.asahi.com/articles/ASS653T9VS65UTFK00SM.html
“自民党は5日、憲法改正実現本部を開き、岸田文雄首相が掲げる総裁任期中(今年9月まで)の改憲のあり方について意見を交わした。”
“改憲に前向きな各党各会派による「緊急事態条項」創設の条文案づくりを念頭に、「自民には改憲を実現する責任がある」といった声が上がったが、強硬姿勢への慎重論も根強く、今後の進め方について結論は出なかったという。”
改憲作業強行なら全法案審議拒否 参院立民国対委員長、自民に伝達
https://nordot.app/1171354140554740657
“立憲民主党の斎藤嘉隆参院国対委員長は6日、自民党の石井準一参院国対委員長と会談し、自民が改憲案の条文化作業を強行する場合、参院側では政治資金規正法改正案を含め全ての法案審議に応じられないと伝えた。”
2024年6月6日(木) 第213回国会(常会)
第9回 衆議院憲法審査会
【アーカイブ動画】
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55291
※「はじめから再生」をクリックしてください
【会議録】
※公開され次第追加します(おおむね2週間後になります)
【マスコミ報道から】
衆院憲法審査会 自民“条文案を” 立民“総裁任期関係ない”
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240606/k10014472711000.html
“衆議院憲法審査会で、自民党は大規模災害など緊急事態の対応をめぐる憲法改正の条文案の作成に入るよう重ねて提案しました。これに対し立憲民主党は岸田総理大臣が自民党総裁の任期中に改正を実現したいとしていることと審査会の議論は関係がないと主張しました。”
自民、改めて幹事懇開催提案 緊急事態条項巡り 衆院憲法審
https://mainichi.jp/articles/20240606/k00/00m/010/207000c
“自民党の中谷元・与党筆頭幹事は憲法改正の条文案を起草する場として、全会派が参加する幹事懇談会の開催を改めて提案した。国会閉会中に議論を続けたい意向も示した。”
岸田文雄首相は、9月までの党総裁任期中の憲法改正に意欲を示すが、今月23日の国会会期末までの憲法審の定例日はこの日を除いて2日のみ。”
自民、改憲論点を提示方針 立民は国民投票法改正を優先
https://nordot.app/1171281886035755620
“自民党は選挙困難事態の国会機能維持を巡り、条文案作成の土台となる論点整理と基本的な考え方を示す方針を表明した。起草作業を行う場として反対党派も含めた幹事懇談会の開催を改めて提案した。”
“立民の本庄知史氏は広告規制やネットの適正利用などの課題が残されているとして「今の状況でいくら条文化作業をしても国民投票の実施は見通せない。議論の順序が全くあべこべだ」と批判した。”
改憲発議へ論点整理 自民提案に立民慎重
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024060600828&g=pol
“自民の中谷元氏は「条文イメージ作成の土台となるような論点整理を示したい」と主張。国民民主党の玉木雄一郎代表も「覚悟を決めて戦略的に取り組んでほしい」と述べた。”
“これに対し、立民の本庄知史氏は、岸田文雄首相(自民総裁)が9月までの総裁任期中の改憲を掲げていることに触れ、「総裁任期と憲法改正に一体何の関係があるのか」とけん制した。”
【傍聴者の感想】
今回の審査会は、国民投票法(改憲手続法)および緊急事態の考え方を中心に自由討議が行われました。
改憲手続法については、各会派から、放送広告の資金規制、ネット広告をめぐる課題、ファクトチェックの問題、外国からの関与の規制、国民投票広報協議会の役割、投票用紙の記載の仕方など様々な課題が提起されました。維新、国民、有志の3会派の議論は改憲を急ぐ立場からのものですが、ある意味具体的で、真っ当な指摘も多いと感じました。
しかし例えば、インターネット社会におけるフェイクへの対応やプラットフォーマーの規制、様々な経済活動における外国資本への向き合い方などは、すでに現在の社会課題になっており、改憲議論があろうとなかろうと新たなルール作りに政治が努力をしなければならない課題です。
改憲手続法の不備を正していくことはもちろん必要ですが、それ以前に政府や国会がやるべきことは多く、いざことに挑もうとして課題を洗ったら日ごろのさぼりが浮き彫りになった、そんな印象を持ちました。
選挙を延期する(議員任期を延長する)期間や範囲、参院緊急集会との関連がもう一つの課題でした。各会派が自分たちの問題意識を主張しあうという点は今までとあまり変わりませんが、他会派を攻撃するという場面はほとんどなく、会派間のあるいは委員間の質疑応答という場面が従来より増えたという印象を持ちました。
議論の仕方としては望ましいことかもしれませんが、これをもって熟議を尽くしたと言えるほどの内容ではないことは、傍聴者として報告しておきたいと思います。
国会の会期末も近いことから、条文案が作成されないことに国民、維新からは強い口調での自民党への批判がされ、自民党の中谷筆頭幹事は「(国会)閉会中の開催」にも言及しました。改憲派は少しでも具体的な実績を積み上げたいということでしょうが、改憲理由事実の基本的な認識の一致すらできていないこと、手続法にも相当の課題があること、加えて政治資金で自民党の信頼は大きく失墜していることをふまえれば、発議などできないはずです。
しかしあらゆる常識が通用しないのが現政権ですので、今後も厳しい監視と、適時の反撃をし続けることが必要です。
【憲法学者から】飯島滋明さん(名古屋学院大学教授)
いま、沖縄大学での内地留学のために沖縄に滞在しているので常に憲法審査会は傍聴できません。ただ、6月6日は衆議院憲法審査会を傍聴しました。憲法審査会の議論を聞いていると、改憲を主張する政治家たちには「憲法の基本理念」と「立憲主義」が定着していないのとの思いを持ちました。いろいろ問題がありますが、紙幅の関係で以下の指摘をします。
(1)議論は煮詰まっていません
2023年11月30日衆議院憲法審査会で公明党北側一雄議員は「議論は相当に詰まっていることは間違いないというふうに思うんですね」などと発言し、立憲民主党抜きの改憲条文案作成を進める意向を示唆しました。しかし「選挙困難事態」に関して日本維新の会は憲法裁判所の事後審査、国民民主党は最高裁判所の事後審査、自民党は裁判所の関与不要という立場にたっています。法を専門にする人からすれば、こうした状況で「議論が煮詰まった」とは考えないでしょう。こうした見解の相違一つとっても、「議論は相当に詰まっている」という北川議員の認識は「間違い」です。
(2)玉木雄一郎議員のフェイクに関する発言
玉木雄一郎議員は「今の自民党の9条改正案によって、違憲論がすべて解消され、自衛隊の権限が大きく拡大し、新たにできることが増え、パワーアップした自衛隊が搭乗するかのような説明も、これもフェイクです」と発言しました。憲法改正国民投票でも「フェイクニュースへの法的対応」は必要です。フェイク対策がなされないのであれば改憲の国民投票は「デマから生まれた憲法改正」になる危険性があり、正当化できません。ただ、玉木議員が紹介した見解は「フェイク」ではありません。自衛隊が憲法に明記されれば自衛隊を「憲法違反」とは言えなくなりますし、「徴兵制」「民間人の戦地派遣」も憲法的にも正当化されます。「自衛のために自衛隊を保持する」等の文言で自衛隊が憲法に明記されれば、安保法制の内容を超える「全面的な集団的自衛権」の行使も可能になる可能性があり、「自衛隊の権限が大きく拡大」します。自分の意見と相容れない見解を「フェイク」とする玉木議員の発想は民主政国家では極めて危険です。
(3)「社会学的代表」から議員任期延長改憲を正当化する公明党大口善徳議員
大口善徳議員は「全国民の代表の要請は選挙の一体性の原則とリンクしている」と発言しました。憲法43条1項の「全国民の代表」はフランス憲法学でいう「半代表」、大口議員が引用した芦部信喜先生の教科書では「社会学的代表」とされています。ただ、公明党議員たちが「社会学的代表」としての議員活動をしてきたと言えるのでしょうか? 「社会学的代表」とは、「議会は建前として人民の意思(民意)をできるだけ正確に反映して代弁すべきだという、直接民主制的な要素を加味した代表の考え方」とされます。特定秘密保護法、安保法制、原発再稼働、マイナンバー制度の強行導入等でも、公明党は国民意志に反する政治に加わってきたようにしか私には見えません。「国民の意思と代表者の意思の事実上の類似を重視するという社会学的代表の考え方」から、「全国津々浦々の全国民の多様な意思をできる限り公正かつ忠実に、いわばその縮図のように国会に反映させることを要請する憲法上の原理」とも大口議員は発言しています。「全国津々浦々の全国民の多様な意思」などと言っていますが、たとえば米軍人の犯罪や軍事訓練等で大変な思いをしてきた沖縄県民、辺野古新基地建設に反対する沖縄県民の民意に公明党は耳を傾けてきたのでしょうか? 辺野古新基地建設の代執行を強行した斉藤鉄夫国土交通大臣は公明党所属議員です。
公明党大口善徳議員は芦部先生の「社会学的代表」に関する見解を引用して、国会議員の任期延長改憲論を主張します。それこそ芦部先生の見解に依れば、「国民主権原理」は憲法改正の限界とされます。投票権は国民主権を実現するための権利であり、投票権を剥奪する改憲は「国民主権」を空洞化する危険性があります。芦部先生の教科書をきちんと読めば、憲法43条1項の「全国民の代表」を根拠に、選挙もしないで国会議員が地位に居座ることを可能にする「国会議員の任期延長改憲論」が正当化されるとの結論は出ないはずです。公明党大口善徳議員は、国民意志を代弁する政治をしてこなかった公明党の実態を踏まえないことに加え、極めて不正確な憲法論を展開しています。
最後に、改正政治資金規正法をめぐる自民党・公明党・日本維新の会の対応を見れば、やはり国会議員の任期延長改憲は国会議員の利益を守るための「保身」「居座り」を認める改憲になるとの思いを持ちました。
(4)国会議員の保身のためになる国会議員任期延長改憲論
本来であれば国会議員を辞職、あるいは逮捕・起訴されてもおかしくない裏金問題を起こしながら、再び悪質な裏金問題を起こさせない政治資金規正法の改正をしなかった自民党や公明党。「改正政治資金規正法」では企業・団体献金は禁止されず、政策活動費も温存されました。「身を切る改革」と口先では調子のよいパフォーマンス的発言をしながら自民党にすり寄り、日本維新の会派「改正政治資金規正法」に賛成しました。政治家の利権を温存する「改正政治資金規正法」に賛成した自民党・公明党・日本維新の会が国会議員の任期延長改憲論を主張するのをみると、さまざまな口実を設け、選挙もしないで国会議員に居座る改憲を主張しているとの思いを強くしました。
選挙もしないで国会議員に居座るための改憲、みなさんは賛成しますか?
【国会議員から】本庄さとしさん(立憲民主党・衆議院議員/憲法審査会幹事)
 本日の議題の前に、前回、前々回と、国民民主党の玉木委員からたくさんご質問をいただいていますので、その回答から始めたいと思います。
本日の議題の前に、前回、前々回と、国民民主党の玉木委員からたくさんご質問をいただいていますので、その回答から始めたいと思います。
第一に、長期かつ広範に選挙が実施できない選挙困難事態において、選挙管理委員会が繰延投票の選挙期日(投票日)を正しく定めることが可能か、また、繰延は何日間までなら可能か、とのお尋ねがありました。
まず、公職選挙法第57条第1項において、天災等により、投票所で投票ができないときは、都道府県の選管は、直ちに繰延投票とする旨を告示し、更に定めた期日を少なくとも投票2日前に告示しなければならないとされています。
つまり、選挙期日の繰延と繰延後の期日は、玉木委員がおっしゃるように同時に判断、決定される必要はなく、発災時と投票前の2段階で判断され、決定されるということです。したがって、選挙困難事態であっても、選管が別の選挙期日を正しく定めることは十分可能であると考えます。
その上で、繰延投票は、公選法上、何日以内に行われなければならないという定めはありませんが、都道府県の選管が投票を適正に行わせることが可能であると判断した時点で、更に期日を定めて投票を行わせるものとされています。
憲法上、何日間まで繰延可能かは一概には言えませんが、例えば、公選法第33条の2により、衆議院議員の補欠選挙では、任期満了にかかる場合は最長で1年間、任期満了にかからない場合でも最長で7カ月強、欠員が生じ得ることを想定しています。したがって、憲法上も、少なくとも7カ月強ないし1年は、繰延投票が認められるものと解せられます。
第二に、繰延投票では、期日前投票や選挙運動が公示日から繰延された投票日まで長期間可能となり、かつ、その間、選管は職員被災で機能しないのではないか、とのお尋ねがありました。
まず、期日前投票については、公選法第48条の2第3項において、天災等により、期日前投票所で投票ができないときは、期日前投票所を開かず、又は閉じるものとされています。したがって、天災等による繰延投票の場合には、必然的に期日前投票もできないと考えられます。
他方、繰延投票における選挙運動期間については、これは玉木委員ご指摘の通り、公選法第129条により、公示日から繰延投票の期日の前日まで選挙運動ができると解されており、この点は私も制度上の不備だと思います。ただ、これは法律改正事項であり、憲法改正事項ではありません。
被災地の選管は職員も被災していて機能しないとのご指摘は、1993年の北海道南西沖地震の際に予定通り衆議院総選挙が実施された奥尻町の例などもあり、一概には言えませんが、仮に、ご指摘のようなことがあれば、繰延投票によって対応するものと考えます。
第三に、繰延投票によって、憲法違反の可能性のある議員不在の状況を生み出す判断を選管に委ねることの是非について、お尋ねがありました。
選挙期日が議員任期内に公示されていれば、その後の繰延投票によって、選挙期日が任期を超えたとしても、そのことが直ちに憲法違反であるとは言えません。したがって、選管に繰延投票の判断を委ねるとしても、問題があるとは考えていません。
最後に、いわゆる「スーパー緊急集会」創設の場合の憲法改正の要否について、お尋ねがありました。
まず、参議院の緊急集会が70日超を想定していないとの見解には、根拠がありません。衆議院の解散から40日以内の総選挙実施、その後30日以内の国会召集を憲法が義務付けているのは、時の政権が衆議院を解散したまま恣意的に総選挙を実施しない、国会を召集しないといった権力濫用を防止するためであり、選挙困難事態のような緊急事態を前提としたものではありません。
また、緊急集会が有する権能の範囲は、憲法第54条第2項の規定により、「国に緊急の必要がある」と内閣が判断し、提案された案件である限り、法律の制定や予算の議決、更には条約の締結の承認についても別段の制約はないと解されています。
したがって、「スーパー緊急集会」なるものは「創設」するまでもなく、憲法改正の必要もないと考えます。なお、議員任期延長とは異なり、後日正当に選挙された衆議院の同意を必要とすることで、緊急時から通常時への復元力(レジリエンス)も確保されており、制度的バランスも取れていると考えています。
最後に、本日の議題である国民投票法に触れて、私の発言を終えたいと思います。
ご存じのとおり、岸田総理は自身の自民党総裁任期中の憲法改正を掲げています。維新の会や国民民主党もこれに同調し、総裁任期中の憲法改正を求めています。しかし、総裁任期と憲法改正に一体何の関係があるのでしょうか。この審査会の中でも、合理的に説明できる議員はいないと思います。
岸田総裁の任期は今年9月30日です。しかし、それより先に期限が来るのが、国民投票法の附則第4条に規定された諸課題です。この期限は、目途ではありますが、9月18日です。岸田総理が掲げる政治日程と、法律に明記された期限と、どちらが優先されるべきかは論を俟ちません。
かねて私たちが最優先課題としてきた附則第4条第2項、放送CM、ネットCM、資金規制、ネット等の適正利用、更には、広報協議会規程、事務局規程、広報実施規程など、国民投票法及び手続き上の課題は依然として残されたままです。
今の状況では、いくら条文化作業や改正発議をしても、国民投票の実施は見通せません。議論の順序が全くアベコベです。まず附則第4条について議論を深め、結論を得ることを提案します。森会長、ご検討をお願いします。私からは以上です。
(憲法審査会での発言から)
ブックレット『その改憲、ちょっと待った! 憲法審査会は今』、好評発売中!
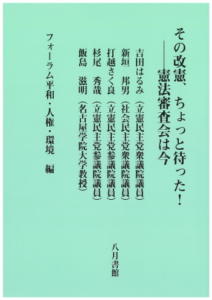 改憲をめぐる正念場!
改憲をめぐる正念場!
憲法審査会の現状を把握するために、ぜひ本書のご活用をお願いします。
本書は全国書店でお買い求めになれます。